
「採用活動で面接にかかる時間が足りない」「応募者との日程調整やフィードバックに追われてしまう」「面接官ごとに評価がバラつき、公平な判断が難しい」──そんな悩みを抱えている採用担当者の方は多いのではないでしょうか。
面接代行サービスは、こうした課題を解決するために面接業務を外部に委託できる仕組みであり、業務負担の軽減や採用プロセスの効率化、面接の質向上に大きく貢献します。
本記事では、面接代行サービスの具体的な内容や導入によって得られるメリット・デメリット、そしてサービス選定の重要なポイントを詳しく解説します。
「効率的に、かつ質の高い採用活動を実現したい」と考える方は、ぜひ最後までご覧ください。
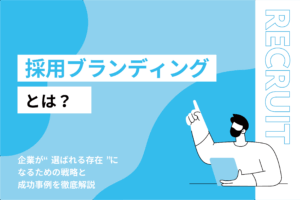
Index
面接代行サービスの概要
面接代行サービスとは、企業の採用活動における面接業務を外部の専門業者に委託する仕組みです。単に面接の代理を行うだけでなく、応募者との日程調整や事前の評価基準策定、フィードバックの提供など幅広い業務をサポートします。こうしたサービスは、採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)の一部として提供されるケースも多く、採用プロセス全体の効率化を目的としています。
面接代行サービスとは
面接代行サービスは、オンライン・対面のいずれの形式でも対応可能で、応募受付や書類選考、面接実施からレポート作成までを外部のプロに委ねることができます。これにより企業は、採用担当者が抱える膨大な業務を軽減し、戦略的な採用活動や人材計画にリソースを集中できるようになります。
また、専門業者による迅速な対応は応募者の離脱防止に繋がり、結果として採用単価の削減や内定承諾率の向上にも効果を発揮します。面接は採用プロセスの中でも最も重要なフェーズの一つであり、質の高い面接を継続的に実施することで、企業と応募者のミスマッチを減らし、入社後の定着率改善にも寄与するでしょう。
面接代行サービスが注目される背景
面接代行サービスが近年注目を集めている背景には、人材不足の深刻化と採用活動の複雑化があります。特にITエンジニアや専門職では求人倍率が10倍を超えるケースもあり、多くの企業が優秀な人材の確保に苦戦しています。こうした売り手市場では、応募から内定までのスピードが競争力を左右するため、選考プロセスの迅速化が欠かせません。
さらに、通年採用やオンライン面接の普及により、採用担当者の業務量は増加の一途をたどっています。面接1件あたりに必要な時間は準備や評価、フィードバックまで含めると平均4〜5時間にも及び、担当者の負担は非常に大きいものです。その結果、本来注力すべき採用戦略や候補者との関係構築にリソースを割けないという課題が生じています。
また、社内で面接を実施する場合、面接官ごとの経験値やスキルによって評価基準にばらつきが生じ、公平性を担保しにくいという問題もあります。このような状況を背景に、外部のプロによる面接代行サービスを活用し、効率性と面接の質を両立させようとする企業が増えているのです。
面接代行サービスが提供する業務内容
面接代行サービスは、面接の代行にとどまらず、採用活動の初期段階から最終評価までを幅広くサポートします。主な業務内容は以下の通りです。
- 採用ターゲットの明確化・評価基準の策定
企業が求める人物像や確認すべきポイントを整理し、公平かつ一貫した評価を行える体制を整えます。 - 面接・面談の実施
オンライン面接や対面面接に加え、カジュアル面談、集団面接、グループディスカッションなど幅広い形式に対応可能です。 - 事務業務の代行
応募受付、面接日程の調整、書類選考、人材紹介会社との連携など、採用に関わる事務作業を一括して委託できます。 - レポーティングと分析
面接後には候補者ごとの評価や強み・課題をまとめたレポートを提出。企業は面接に同席しなくても採用判断に必要な情報を把握できます。 - 付加的なサポート
面接官向けのトレーニングや、採用ターゲットに応じた質問設計の支援など、採用活動全体の質を向上させる取り組みも提供されます。
このように、面接代行サービスは単なる「面接の外注」ではなく、採用活動全体を最適化するパートナーとして企業を支援します。
面接代行サービス導入のメリット
面接代行サービスを導入することで、企業は採用活動における大きな負担を軽減し、効率的で質の高い採用を実現できます。特に以下の4つのメリットは多くの企業に共通して効果をもたらしています。
- 面接業務の工数削減
- 採用プロセスの迅速化
- 面接品質と評価基準の向上
- 採用ノウハウの蓄積
次のセクションでは、これらのメリットを一つずつ詳しく解説していきます。
面接業務の工数削減
面接代行サービスを導入する大きなメリットの一つが、面接業務にかかる工数の大幅削減です。面接は単に候補者と話す時間だけでなく、日程調整、面接準備、合否連絡、レポート作成といった多くの付随業務を伴います。これらを全て社内で対応すると、1件あたり平均4〜5時間もの工数が必要になると言われています。
特に大量採用を行う企業や人手不足の企業では、この負担は非常に大きなものです。面接代行を活用すれば、こうしたノンコア業務を外部に委託でき、採用担当者は戦略立案や人材育成といったより本質的な業務にリソースを集中させることが可能になります。実際に導入した企業の中には、採用工数を約60〜75%削減できた事例も報告されています。
採用プロセスの迅速化
現代の採用市場は売り手優位で、応募者は複数の企業に同時並行で応募するのが一般的です。そのため、応募から内定までのスピードが遅いと、優秀な人材が他社へ流れてしまうリスクが高まります。実際に「選考期間が長い企業は辞退されやすい」という調査結果もあるほどです。
面接代行サービスを利用すれば、応募受付から面接設定、実施、合否連絡までをスムーズに進めることができます。特に即日面接や短期間での内定出しといったフローを組むことも可能なため、候補者を待たせることなく迅速に選考を進められます。
結果として、応募者の離脱率を抑え、内定承諾率を向上させることができるのです。スピード感のある採用プロセスは企業の信頼感にもつながり、競合他社との差別化要因となるでしょう。
面接品質と評価基準の向上
自社で面接を行う場合、面接官の経験やスキルの差によって評価にばらつきが生じることは少なくありません。その結果、候補者によって選考の公平性が損なわれたり、採用ミスマッチにつながるリスクが発生します。
面接代行サービスでは、まず企業が求める人物像や評価基準を明確に言語化し、それに基づいた統一された評価シートや質問項目を設計します。これにより、属人化を防ぎ、常に一貫性のある面接を実施することが可能になります。
さらに、代行を担当するのは採用に特化したプロの面接官です。彼らは候補者の能力や適性を的確に見極めるスキルを持ち、法的リスクを回避するための知識も備えています。こうした専門性によって、採用のミスマッチを減らし、質の高い人材を確保できる確率が高まります。
加えて、応募者にとってもプロによる面接は「整備された選考プロセス」という印象を与え、企業への信頼感を高めます。結果的に、内定率や入社率の向上にもつながるでしょう。
採用ノウハウの蓄積
面接代行サービスを導入することは、単なる業務委託にとどまらず、自社の採用ノウハウを高める機会にもなります。代行会社は多様な業界や職種の採用を支援してきた実績を持ち、その知見を企業に還元してくれます。
例えば、採用ターゲットの明確化や評価基準の策定を行う過程では、プロの視点から具体的な質問内容や評価ポイントについてアドバイスを受けることができます。また、自社の社員が面接に同席することで、候補者の本質を見抜く質問技術や評価の観点を直接学ぶことも可能です。
さらに、面接後に提供されるフィードバックレポートには、候補者の評価結果だけでなく、面接プロセス改善のヒントや有効な質問事例なども含まれる場合があります。こうした知見を蓄積していくことで、自社の採用担当者のスキルが磨かれ、将来的には質の高い面接を内製化できる体制を築くことができるのです。
面接代行サービス導入のデメリットと注意点
面接代行サービスは多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。事前に把握しておくことで、導入後のトラブルを防ぎ、サービスを最大限に活用することができます。主なデメリットは以下の通りです。
- 応募者との関係構築が難しくなる
- 委託コストが発生する
- 自社の魅力を十分に伝えにくい
次のセクションでは、これらのデメリットを一つずつ詳しく解説していきます。
応募者との関係構築の難しさ
面接代行サービスを利用する際に最も懸念されるのが、候補者との直接的な接点が減ることです。自社で面接を行う場合は、担当者や現場社員が候補者と複数回接触し、細やかなコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことができます。しかし代行サービスを利用すると、面接の多くを外部の専門家が担うため、企業としての魅力やカルチャーを候補者に十分に伝えにくくなる可能性があります。
特に、候補者にとって面接官の印象は「企業そのものの印象」と結びつきやすいものです。外部面接官の対応次第では志望度が大きく変わってしまうこともあるため、慎重な配慮が求められます。
この課題を解消するためには、面接代行会社に対して自社の事業内容や企業文化をしっかり共有し、応募者に伝えてほしいメッセージを事前にすり合わせておくことが重要です。さらに、最終面接や内定者フォローは必ず自社で行うなど、応募者と企業が直接関わる機会を意識的に設けることで、関係構築の不足を補うことができます。
委託コストの発生
面接代行サービスの導入では、外部委託費用が必ず発生します。料金体系は主に次の3種類に分けられます。
| 料金体系 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 月額固定型 | 一定額で契約期間中の業務を包括的に依頼できる | 業務量が少ない時でもコストは変わらない |
| 従量課金型 | 面接件数や業務量に応じて費用が発生 | 案件数が増えると想定以上にコストが膨らむ可能性あり |
| 成功報酬型 | 採用が決定した場合にのみ費用が発生 | 単価が高めに設定される傾向がある |
費用の相場は以下の通りです。
- 新卒採用代行:月額50〜70万円程度
- 中途採用代行:月額10〜70万円程度
ただし、これはあくまで目安であり、依頼範囲や会社規模によって変動します。費用を抑えるためには、「自社で対応できる業務」と「外注すべき業務」を切り分けることが重要です。例えば日程調整や候補者連絡のみを代行に任せ、最終面接は自社で行うといった工夫で費用対効果を高められます。
自社の魅力伝達の課題
面接代行サービスを利用する際の大きな懸念のひとつが、自社の魅力を十分に候補者に伝えきれない可能性です。外部の面接官が面接を行うため、企業文化や職場の雰囲気、社員同士の関係性といった「言葉では伝えにくい魅力」が候補者に伝わりにくくなります。
例えば、自社で面接を行う場合は、現場社員や採用担当者が具体的なエピソードや職場の雰囲気を直接共有できるため、候補者は企業理解を深めやすくなります。しかし、代行面接官にはどうしても限界があり、候補者が入社後に「想像していた環境と違う」と感じるリスクが残ります。
この課題を解決するには、以下のような工夫が有効です。
- 事前共有を徹底する
企業のビジョン・事業内容・社風・求める人物像を面接代行会社に詳細に共有し、質問や説明に反映してもらう。 - 直接接点を組み込む
最終面接や内定者フォローは必ず自社担当者が行い、候補者が直接企業を感じられる機会を確保する。 - 補完的な情報提供
面接後に企業紹介資料や採用サイト、社員インタビュー動画などを候補者に案内し、自社の魅力を多角的に伝える。
こうした取り組みによって、外部委託による情報伝達の弱点を補い、候補者に「ここで働きたい」と思ってもらえる可能性を高められます。
面接代行サービスの活用が適している企業
面接代行サービスはどの企業にも有効ですが、特に以下のような課題を抱える企業にとって大きな効果を発揮します。
- 採用担当者のマンパワー不足
少人数体制で採用を進めている企業では、面接に割ける時間が限られています。代行を活用することでリソース不足を補い、安定した採用活動を実現できます。 - 選考スピードの遅延
応募から内定までに時間がかかり、優秀な人材を他社に取られてしまうケースが多い企業に適しています。代行を利用すればスピーディーな対応が可能になります。 - 面接品質のばらつき
面接官の経験やスキルによって評価が偏る傾向がある場合、統一基準を用いる代行サービスは有効です。公平で一貫性のある選考を実現できます。
つまり、「効率性」と「質」の両立が課題となっている企業にとって、面接代行サービスは非常に有効な選択肢となります。
面接代行サービスの選定ポイント
面接代行サービスは数多くの企業が提供しており、サービス範囲や得意分野も大きく異なります。導入を成功させるためには、自社の採用課題やニーズに合致するサービスを見極めることが不可欠です。特に以下の3つの観点を重視すると良いでしょう。
- 対応可能な業務範囲の確認
- 情報共有体制の確認
- 実績と専門性の確認
次のセクションからは、これらの選定ポイントについて順番に詳しく解説します。
対応可能な業務範囲の確認
面接代行サービスを選ぶ際に最初に確認すべきなのは、どこまでの業務を委託できるかという点です。代行会社ごとに対応範囲は大きく異なり、単に「面接を実施するだけ」のケースもあれば、採用戦略の策定から内定者フォローまで包括的に支援するケースもあります。
具体的には、以下のような業務が含まれるかをチェックしておくと安心です。
- 採用ターゲットの策定、評価基準の設定
- 書類選考・応募受付・日程調整などの事務作業
- オンライン面接・対面面接・集団面接・カジュアル面談など多様な形式への対応
- 面接後のフィードバックやレポーティング
- 内定者フォローや面接官トレーニングなどの付加サービス
また、自社が採用したい人材の属性に合わせて、新卒採用・中途採用・アルバイト採用など契約形態に対応できるかも重要な確認事項です。最初に業務範囲を明確化しておくことで、導入後の「思っていたサービスと違う」というミスマッチを防ぐことができます。
情報共有体制の確認
面接代行サービスを導入する際に欠かせないのが、企業と代行会社との間でどれだけスムーズに情報共有できるかです。採用はスピードと精度が求められる業務であり、情報の遅延や不足があると採用判断の質に直結します。
特に確認しておきたいのは次のポイントです。
- 面接の進捗状況や候補者の評価がリアルタイムで共有されるか
- 面接後に提供されるレポートの内容・詳細度・更新頻度
- 候補者の強み・課題・懸念点が具体的にフィードバックされるか
- 緊急時の連絡体制や利用できる情報共有ツール(チャット・クラウド管理システム等)の有無
これらが整っているサービスを選ぶことで、自社が面接に同席しなくても候補者の状況を正確に把握できるようになります。また、情報の透明性が高いほど意思決定もスムーズになり、安心して採用業務を委託することが可能です。
実績と専門性の確認
面接代行サービスを選定するうえで最も信頼性を判断しやすい指標のひとつが、導入実績と専門性です。豊富な実績を持つ会社は、多様な業界・職種の採用支援を行ってきた経験があり、その知見を活かして質の高いサービスを提供できる可能性が高いといえます。
特に確認しておきたいのは以下のポイントです。
- 自社と近い業界・職種での支援実績があるか
- どのような規模(中小企業・大手企業)の案件に対応してきたか
- 担当する面接官の経歴や専門スキルが明示されているか
- 過去の導入事例やクライアントの声が公開されているか
例えば、ITエンジニア採用に特化した会社や、製造業の採用に強い会社など、業界に精通しているサービスを選べば、候補者の適性を的確に見極められる可能性が高まります。また、プロの面接官が在籍しているかどうかも重要な判断基準です。専門性を持つ面接官が対応することで、企業にとっても候補者にとっても納得度の高い採用活動が実現できるでしょう。
まとめ
面接代行サービスは、採用担当者の業務負担を軽減し、選考スピードの向上や面接品質の統一といった効果をもたらす有効な仕組みです。特に人材不足や採用競争が激化する現在においては、そのニーズはますます高まっています。
一方で、応募者との関係構築の難しさや委託コスト、自社の魅力伝達といった課題もあるため、導入にあたっては慎重な検討が必要です。成功のポイントは、自社の採用課題を明確にしたうえで、業務範囲・情報共有体制・実績と専門性を持つパートナーを選ぶことにあります。
採用活動は「人材を確保すること」だけでなく、「企業の未来をつくる大切なプロセス」です。効率と質の両立を図りながら、自社にとって最適な採用体制を築いていきましょう。
採用活動を強化したい企業様へ
株式会社Piic(ピーク)では、採用ブランディングや採用サイト制作、ピッチ資料作成などの採用クリエイティブを通じて、企業の採用力強化を支援しています。単なるデザインや代行業務ではなく、企業の「らしさ」を言語化し、候補者に響く表現で発信することにこだわっています。
「採用活動を始めたいが、どこから手を付けてよいか分からない」「応募者に自社の魅力をうまく伝えられない」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。








