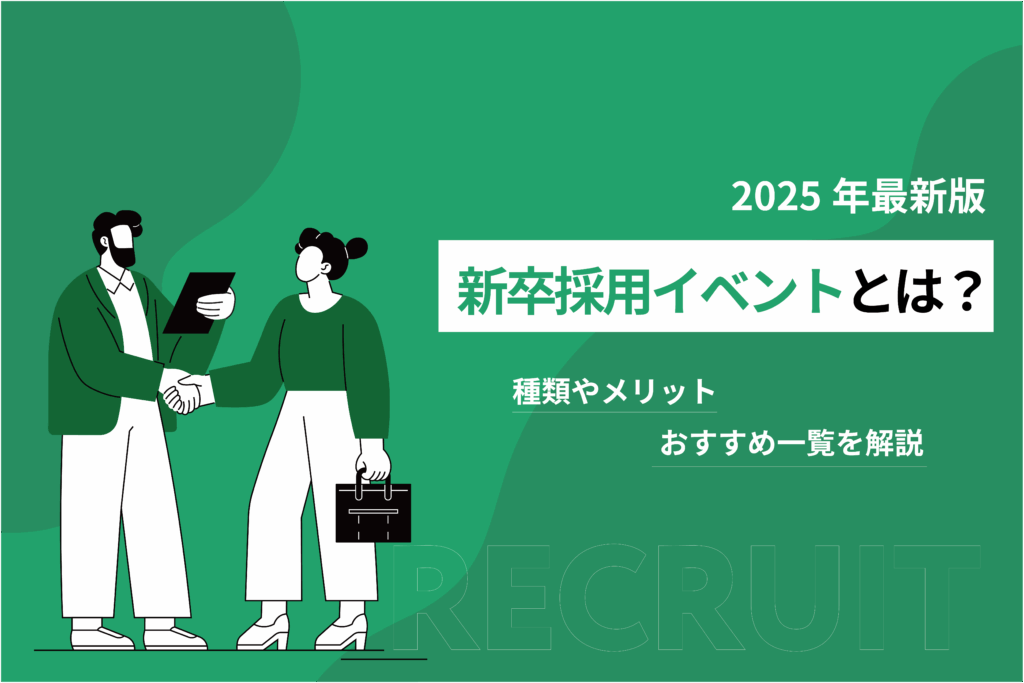
新卒の採用活動において、多くの企業が取り入れている採用イベントとは、学生と企業が直接出会う貴重な機会です。
この記事では、採用イベントの基本的な種類から、参加することで得られる企業側のメリット、さらにはおすすめのサービス一覧まで、幅広く情報を網羅しています。
自社の採用課題を解決し、最適な人材と出会うためのヒントとしてご活用ください。

Index
-
新卒採用イベントとは?
-
新卒採用イベントを活用する4つのメリット
-
直接コミュニケーションが取れる
-
企業の認知度向上に貢献する
-
ターゲットの学生層に絞ってアプローチできる
-
イベント後の選考へスムーズに誘導できる
-
新卒採用イベントで注意すべき3つのデメリット
-
企画や出展に時間とコストが発生する
-
想定通りの学生が集まらない可能性がある
-
イベントでの対応が企業イメージに直結する
-
【目的別】新卒採用イベントの主な種類と特徴
-
多くの学生に会える「合同企業説明会」
-
特定の学生に特化した「業界・属性別イベント」
-
相互理解を深める「マッチングイベント」
-
企業理解を促進する「セミナー・ワークショップ」
-
【比較】採用イベントの規模による違い
-
大規模イベントのメリットと注意点
-
中・小規模イベントのメリットと注意点
-
【厳選】おすすめの新卒採用イベントサービス一覧
-
幅広い学生にアプローチできる総合型イベント
-
特定のターゲット層に出会える特化型イベント
-
学生との深い交流が可能なマッチング型イベント
-
採用イベントを成功に導くための3つのポイント
-
採用したい人物像とイベントの目的を明確にする
-
学生の心をつかむ魅力的なコンテンツを準備する
-
イベント参加後のフォローアップ体制を整える
-
よくあるご質問
-
Q1. 採用イベントの出展費用はどのくらいかかりますか?
-
Q2. オンラインイベントと対面イベント、どちらが良いですか?
-
Q4. 学生にブースに来てもらうためのコツはありますか?
-
Q5. イベント後の学生へのアプローチで気をつけることは何ですか?
-
まとめ
新卒採用イベントとは?

新卒採用イベントとは、企業が採用候補者となる学生と直接コミュニケーションを取るために開催される催し全般を指します。
大規模な会場に多数の企業が集まる合同企業説明会が代表的ですが、特定の業界や職種に特化した小規模なものや、オンライン上で開催される形式も増えました。
企業にとっては、自社の魅力や事業内容を多くの学生に直接伝え、認知度を向上させる絶好の機会です。
一方、学生にとっても、Webサイトや資料だけでは分からない企業の雰囲気を感じ取ったり、気軽に質問したりできる貴重な場となります。
採用活動の初期段階における母集団形成から、内定承諾前の意欲向上まで、様々な目的で活用される手法です。
新卒採用イベントを活用する4つのメリット

採用イベントの活用は、企業側にとって多くの利点をもたらします。
ナビサイトなどテキスト中心の採用活動だけでは得られない、対面ならではの価値が存在します。
学生と直接触れ合うことで、自社の魅力をより深く伝え、採用のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
ここでは、採用イベントが持つ具体的な4つのメリットについて掘り下げていきます。
直接コミュニケーションが取れる
採用イベント最大のメリットは、学生と直接対話できる点にあります。
企業のウェブサイトや採用パンフレットだけでは伝えきれない、社風や働く社員のリアルな雰囲気を肌で感じてもらえます。
学生が抱く細かな疑問や不安に対して、その場で社員が直接回答することで、企業への理解を深め、信頼関係を築くきっかけになります。
学生からの素朴な質問の中に、自社の魅力や課題を再発見するヒントが隠されていることも少なくありません。
このような双方向のコミュニケーションを通じて、学生の入社意欲を高め、自社にマッチする人材かどうかを初期段階で見極めることが可能になります。
企業の認知度向上に貢献する
特に、まだ世間的な知名度が高くないBtoB企業や中小企業にとって、採用イベントは自社を知ってもらうための有効な手段です。
多くの学生が訪れるイベントに出展することで、これまで自社の存在を知らなかった層にもアプローチできます。
ブースの装飾や配布する資料を工夫すれば、学生の印象に残りやすくなります。
たとえその場で選考に進まなかったとしても、イベントをきっかけに企業名や事業内容を覚えてもらうことで、将来的な顧客になったり、別の機会に再会したりする可能性も生まれます。
継続的にイベントへ参加することは、採用市場における企業のブランディング活動としても機能します。
ターゲットの学生層に絞ってアプローチできる
近年、採用イベントは多様化しており、特定のターゲット層に特化したものが数多く開催されています。
例えば、エンジニア職を志望する学生だけを集めたイベントや、理系学生限定、高専生向けといった専門性の高いイベントがあります。
また、コンサル業界や特定の業界を志望する学生に特化した企画も人気です。
こうしたイベントに参加することで、自社が求めるスキルや志向性を持った学生に効率良く出会うことができます。
不特定多数の学生にアプローチするよりも、採用のミスマッチが起こりにくく、より質の高い母集団形成が期待できるでしょう。
採用活動の時間とコストを最適化する上でも非常に有効な手法です。
イベント後の選考へスムーズに誘導できる
採用イベントは、学生との接点を作るだけでなく、その後の選考プロセスへつなげるための重要なステップです。
イベント中にブースを訪れた学生や、自社の説明に熱心に耳を傾けてくれた学生に対して、その場で特別選考ルートの案内や、インターンシップへの参加を促すことができます。
連絡先を記入してもらうアンケートを実施し、後日改めて個別に連絡を取る方法も効果的です。
学生の興味や関心が高い状態のうちに次のアクションを提示することで、選考への参加率を高めることが可能です。
イベントで得た手応えを具体的な応募者数の増加につなげるための、スムーズな動線設計が重要になります。
新卒採用イベントで注意すべき3つのデメリット

採用イベントは多くのメリットがある一方で、時間やコスト、当日の運営など、事前に考慮しておくべき点も存在します。
これらのデメリットを理解し、対策を講じなければ、期待した成果が得られない可能性もあります。
イベント参加を成功させるためにも、注意すべきポイントをしっかりと把握しておきましょう。
企画や出展に時間とコストが発生する
採用イベントへの参加には、時間とコストがかかります。
出展料だけでも数万円から数百万円と、イベントの規模によって費用は大きく異なります。
それに加えて、ブースを目立たせるための装飾、学生に配布するパンフレットやノベルティグッズの制作費、当日対応する社員の人件費なども必要です。
また、どのようなコンセプトで学生にアピールするのかという企画段階から、当日の運営シミュレーション、事後のフォローアップまで、採用担当者は多くの時間を費やします。
これらのリソースを投入しても、必ずしも成果に結びつくとは限らない点が、一つのデメリットと言えます。
想定通りの学生が集まらない可能性がある
多くの学生との出会いを期待してイベントに参加しても、必ずしも自社が求めるターゲット層の学生がブースを訪れるとは限りません。
イベント全体の集客力が低かったり、参加学生の属性が自社の求める人物像と異なっていたりする場合があります。
特に大規模な合同説明会では、有名企業や人気企業に学生が集中し、自社のブースにはほとんど人が来ないという事態も起こり得ます。
イベントの企画内容や過去の開催実績、主催者側の集客方法などを事前に十分に調査し、自社の目的に合致しているかを慎重に見極める必要があります。
イベントでの対応が企業イメージに直結する
学生は、イベント会場での企業の振る舞いを非常によく見ています。
ブースで対応する採用担当者や社員の態度は、そのまま企業イメージとして学生にインプットされます。
例えば、担当者の態度が横柄だったり、質問に対して曖昧な回答しかできなかったりすると、学生は企業に対してマイナスの印象を抱いてしまうでしょう。
その印象は、SNSなどを通じて瞬く間に拡散されるリスクもはらんでいます。
イベントは自社の魅力をアピールする場であると同時に、一つのミスが企業の評判を損ねかねない場でもあることを、採用担当者は肝に銘じておくべきです。
【目的別】新卒採用イベントの主な種類と特徴

採用イベントと一口に言っても、その形式や規模は様々です。
自社の採用における目的、例えば「まずは多くの学生に社名を知ってもらいたい」のか、「特定のスキルを持つ学生と深く話したい」のかによって、選ぶべきイベントの種類は異なります。
- 合同企業説明会
- 業界・属性別イベント
- マッチングイベント
- セミナー・ワークショップ
ここでは、以上の代表的なイベントの種類とその特徴を目的別に整理して紹介します。
多くの学生に会える「合同企業説明会」
合同企業説明会は、大規模な会場に数百社の企業と数千人の学生が集まる、最も一般的な採用イベントです。
マイナビやリクナビといった大手就職情報会社が主催するものが有名で、企業の知名度向上や、幅広い学生層へのアプローチによる母集団形成を目的とする場合に適しています。
多くの学生と一度に接点を持てるメリットがある一方で、一社あたりの説明時間が短く、学生一人ひとりと深くコミュニケーションを取ることは難しい側面もあります。
他の多くの企業の中に埋もれてしまわないよう、ブースの装飾や呼び込みなどで学生の注意を引く工夫が求められます。
特定の学生に特化した「業界・属性別イベント」
特定の業界や学生の属性に絞って開催されるのが、業界・属性別イベントです。
例えば、IT業界、介護・保険業界といった業界特化型や、スタートアップ企業だけを集めたイベントがあります。
また、理系学生や体育会系学生、特定のスキルを持つ学生など、属性でターゲットを絞ったものも存在します。
こうしたイベントは、参加する学生の志向性やスキルセットが明確であるため、企業は自社の求める人材に効率的に出会うことが可能です。
ミスマッチが少なく、より質の高いコミュニケーションが期待できるため、専門職の採用や、特定の価値観を持つ人材を求める場合に有効な手段となります。
相互理解を深める「マッチングイベント」
マッチングイベントは、企業と学生がより深いレベルで相互理解を図ることを目的とした、比較的小規模なイベントです。
座談会形式でじっくり話したり、グループディスカッションや簡単なワークショップを行ったりすることで、学生の個性や思考力、コミュニケーション能力などを多角的に見ることができます。
学生側も、企業の雰囲気をよりリアルに感じ取り、自分の価値観と合うかどうかを判断しやすくなります。
近年では、学生が企業にプレゼンテーションを行う「逆求人型」のマッチングイベントも増えており、企業側が知らなかった優秀な学生を発見する機会にもなっています。
企業理解を促進する「セミナー・ワークショップ」
自社単独、または数社合同で、特定のテーマについて深く掘り下げる形式のイベントです。
業界の動向や自社の事業内容について詳しく解説するセミナーや、実際の業務に近い内容を体験してもらうワークショップなどがあります。
例えば、課題解決型のワークショップは、学生の論理的思考力やチームワークを見る上で有効です。
面白いテーマやユニークな内容の企画は学生の参加意欲を高め、企業への興味関心を強く惹きつけます。
単なる説明会よりも、学生の能動的な参加を促すことで、企業文化や仕事のやりがいへの深い理解を促進し、入社後のギャップを減らす効果が期待できます。
【比較】採用イベントの規模による違い

採用イベントを選ぶ際には、規模も重要な判断基準となります。数千人規模の学生が参加する大規模なものから、数十人程度のアットホームなものまで様々です。企業の知名度や採用目標人数、特に中小企業にとっては、自社の状況に合わせて適切な規模のイベントを選択することが、採用成功の鍵を握ります。
大規模イベントのメリットと注意点
大規模イベントの最大のメリットは、圧倒的な数の学生と接点を持てることです。
対面形式だけでなく、近年ではオンラインでの開催も増えており、全国の学生にアプローチすることが可能です。
企業の認知度を一気に高めたい場合や、できるだけ多くの母集団を形成したい場合に適しています。
一方で、注意点としては、競合となる多数の企業も出展しているため、自社のブースが埋もれてしまう可能性があります。
学生一人ひとりと話せる時間も限られてしまいがちで、深いコミュニケーションを取るのが難しい側面もあります。
学生の目を引くためのブース装飾や、簡潔で魅力的なプレゼンテーションの準備が不可欠です。
中・小規模イベントのメリットと注意点
中小規模イベントのメリットは、参加する学生一人ひとりとじっくり向き合える点です。
学生との距離が近いため、リラックスした雰囲気の中で対話しやすく、企業の魅力や働く人の人柄を深く伝えることができます。
学生からの質問にも丁寧に答える時間が確保でき、志望度を高めやすいのが特徴です。
一方で、イベント自体の集客力が大規模なものに比べて劣るため、出会える学生の数は限られます。
また、イベントのテーマが自社の求める人物像と合致しているかを、より慎重に見極める必要があります。
質の高いコミュニケーションを重視し、確実な採用につなげたい場合に適した選択肢と言えるでしょう。
【厳選】おすすめの新卒採用イベントサービス一覧

ここでは、多くの企業が活用している新卒採用イベントサービスを、タイプ別に分けて紹介します。
それぞれのサービスに特徴があり、参加費用も様々です。
中には無料で参加できる公的なイベントもありますので、自社の採用戦略や予算に合わせて、最適なサービスを見つけるための参考にしてください。
幅広い学生にアプローチできる総合型イベント
多くの学生にまずは自社を知ってもらいたいという場合に最適なのが総合型のイベントです。
代表的なものとしてリクナビやマイナビといった大手就職情報サイトが主催する大規模合同企業説明会が挙げられます。
全国の主要都市で開催され文系理系を問わず多様な学生が参加するのが特徴です。
また厚生労働省の委託事業として各都道府県の労働局やハローワークが主催する新卒者向けの就職フェアも無料で参加できる場合が多く地域に根差した採用活動を行いたい企業にとって有益な選択肢となります。
幅広い層の学生と接点を持ち母集団を形成する第一歩として活用できます。
特定のターゲット層に出会える特化型イベント
専門的なスキルを持つ人材や特定の志向性を持つ学生を求める場合には、特化型のイベントが効果的です。
例えば、ITエンジニア志望者のみを対象とした技術イベント、体育会系学生に特化した就職イベント、グローバルなキャリアに関心のある学生が集まるイベントなど、その種類は多岐にわたります。
これらのイベントは、新卒採用だけでなく中途採用の領域で実績のある企業が運営しているケースも多く、質の高いマッチングが期待できます。
自社の採用要件が明確な場合、総合型イベントよりも効率的にターゲット層へアプローチすることが可能です。
学生との深い交流が可能なマッチング型イベント
学生の人柄や潜在能力をじっくり見極めたい、相互理解を深めた上で採用したいと考える企業には、マッチング型のイベントがおすすめです。
「逆求人」として知られる、学生が企業にアピールする形式のイベントや、少人数での座談会・グループディスカッションを中心としたイベントがこれにあたります。
事前に学生のプロフィールを確認した上で参加できるサービスもあり、効率的な面談が可能です。
ソニーのような大手企業も、特定の職種ではこうしたイベントを活用して専門性の高い学生と交流を図っています。
学生との対話を通じて、自社の魅力を深く伝え、入社意欲を高めるのに適しています。
採用イベントを成功に導くための3つのポイント

採用イベントは、ただ参加するだけでは十分な成果を得られません。
事前の準備から当日の運営、そして事後のフォローアップまで、一連の流れを戦略的に設計することが成功の鍵となります。
ここでは、イベントの効果を最大化するために押さえておきたい3つの重要なポイントを解説します。
採用したい人物像とイベントの目的を明確にする
イベントに参加する前に、まず「どのような学生を採用したいのか」という人物像(ペルソナ)を具体的に定義することが不可欠です。
求めるスキル、価値観、人柄などを明確にすることで、参加すべきイベントの種類や、そこで伝えるべきメッセージが決まります。
次に、今回のイベント参加の目的をはっきりさせましょう。
目的が「認知度向上」なのか、「特定の専門性を持つ学生との接触」なのかによって、当日のブース運営の方法や目標とすべき学生との対話人数も変わってきます。
この二つが明確であれば、イベントの効果測定もしやすくなり、次回の改善につなげられます。
学生の心をつかむ魅力的なコンテンツを準備する
多くの企業がブースを構える中で、学生に足を止めてもらうためには、魅力的なコンテンツの準備が欠かせません。
パンフレットやノベルティグッズはもちろん、ブースのデザインやキャッチコピーも重要な要素です。
一方的な会社説明に終始するのではなく、若手社員との座談会を設けたり、仕事内容がイメージできる簡単なワークショップを実施したりと、学生が参加しやすい工夫を取り入れましょう。
また、社員の働く様子やオフィスの雰囲気が伝わる紹介ムービーを上映するのも効果的です。
学生の記憶に残り、興味を持ってもらえるような、自社ならではのコンテンツを用意することが他社との差別化につながります。
イベント参加後のフォローアップ体制を整える
採用イベントは、学生と接触して終わりではありません。
むしろ、その後のフォローアップこそが採用成功を左右します。
イベントで接触した学生に対し、できるだけ早くお礼のメールを送ったり、次のステップとなる限定セミナーや個別面談の案内を送付したりすることが重要です。
連絡先を交換したものの、その後のアプローチが遅れると、学生の関心は他の企業に移ってしまいます。
誰が、いつ、どのような方法でフォローするのか、事前に体制を整えておきましょう。
迅速で丁寧な対応は、学生の志望度を高め、スムーズな選考プロセスへの移行を促進します。
よくあるご質問
Q1. 採用イベントの出展費用はどのくらいかかりますか?
A1.イベントの規模や種類、出展プランによって大きく異なります。
小規模なもので数万円から、大手就職サイトが主催する大規模な合同説明会では数十万~数百万円かかる場合もあります。
ブースの装飾やパンフレット制作費などの別途費用も考慮する必要があります。
Q2. オンラインイベントと対面イベント、どちらが良いですか?
A2. それぞれにメリットがあります。
オンラインは場所の制約がなく、遠方の学生にもアプローチしやすいのが利点です。
対面は、企業の雰囲気や社員の人柄を直接伝えやすく、学生との深いコミュニケーションが期待できます。
採用ターゲットや目的に合わせて選ぶのが良いでしょう。
Q3. イベント当日に必要な持ち物は何ですか?
A3. 必須なのは、会社案内パンフレット、配布用のノベルティ、ブースを装飾するポスターや備品です。
また、学生の連絡先を記録するためのアンケート用紙や筆記用具、名刺、呼び込みに使う看板なども準備しておくとスムーズです。
Q4. 学生にブースに来てもらうためのコツはありますか?
A4. まず、ブースのデザインやキャッチコピーで学生の興味を引くことが重要です。
また、ブース前でただ待つのではなく、積極的に学生に声をかけることも効果的です。
若手社員が楽しそうに話している雰囲気を作ることも、学生が立ち寄りやすい空気感につながります。
Q5. イベント後の学生へのアプローチで気をつけることは何ですか?
A5. スピードが最も重要です。
イベント終了後、できれば当日中、遅くとも翌日にはお礼のメールを送りましょう。
その際、画一的な内容ではなく、イベントで話した内容に少し触れるなど、個別感を出すとより効果的です。
次のステップへの案内も明確に提示することが大切です。
まとめ
新卒採用イベントは、企業と学生が直接出会い、相互理解を深めるための重要な採用手法です。
合同説明会から特化型イベント、マッチングイベントまで、その種類は多岐にわたります。
自社の採用目的やターゲットとする学生像を明確にし、最適なイベントを選択することが成功の鍵となります。
東京や大阪、名古屋、福岡といった主要都市をはじめ、北海道の札幌から広島、沖縄まで、全国各地で様々なイベントが開催されています。
本記事で紹介したメリットや注意点を参考に、自社の採用戦略に採用イベントを効果的に組み込んでください。
イベントでの印象を“応募”につなげる採用パンフレット。
Piicでは、配布用パンフレットや会社案内、採用ピッチ資料など、イベント後のアクションを生むクリエイティブをトータルで制作しています。
まずは無料相談で、自社に最適な構成とデザインをご提案します。








