
採用LPとは、求職者の応募意欲を高めることに特化した一枚のWebページを指します。
一般的な採用サイトとは異なり、特定のターゲットに響くメッセージと魅力的なデザインで、直接応募へと導くことを目的としています。
この記事では、採用LPの基礎知識から、参考にしたいデザイン事例、具体的な作り方、費用相場まで、企業の採用担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。

Index
-
採用LPとは?求職者の応募意欲を高める一枚のWebページ
-
採用LPと採用サイトの目的と役割の違い
-
採用LPを導入する4つのメリット
-
特定のターゲットに響くメッセージを届けられる
-
短期間・低コストでの制作が可能になる
-
スマートフォンユーザーにもアプローチしやすい
-
効果測定と改善がスピーディーに行える
-
採用LPを作成する際の注意点
-
掲載できる情報量には限りがある
-
応募までのスムーズな導線設計が求められる
-
公開後の継続的な分析と改善が必要になる
-
【業種別】参考にしたい採用LPのデザイン事例
-
IT・Web業界の先進的なデザイン事例
-
クリエイティブ業界の個性的なデザイン事例
-
サービス・接客業の温かみが伝わるデザイン事例
-
メーカー・製造業の技術力がわかるデザイン事例
-
成果につながる採用LPの作り方4ステップ
-
Step1:誰に何を伝えるか?採用ターゲットを明確にする
-
Step2:何を載せるか?LPの構成とコンテンツを設計する
-
Step3:どう見せるか?求職者の心をつかむデザインを作成する
-
Step4:どう届けるか?Web広告などでの集客方法を計画する
-
採用LPの効果を最大化させる3つのポイント
-
最初の3秒で惹きつけるファーストビューを意識する
-
自社の魅力や社風がリアルに伝わる写真や動画を活用する
-
応募フォームは入力項目を最小限にして離脱を防ぐ
-
採用LPの制作にかかる費用相場はどれくらい?
-
よくあるご質問
-
Q1:採用LPの制作期間はどれくらいですか?
-
Q2:採用LPと採用サイト、どちらを作るべきですか?
-
Q3:公開後の運用では何をすればよいですか?
-
Q4:スマートフォン対応は必須ですか?
-
Q5:制作会社を選ぶ際のポイントは何ですか?
-
まとめ
採用LPとは?求職者の応募意欲を高める一枚のWebページ
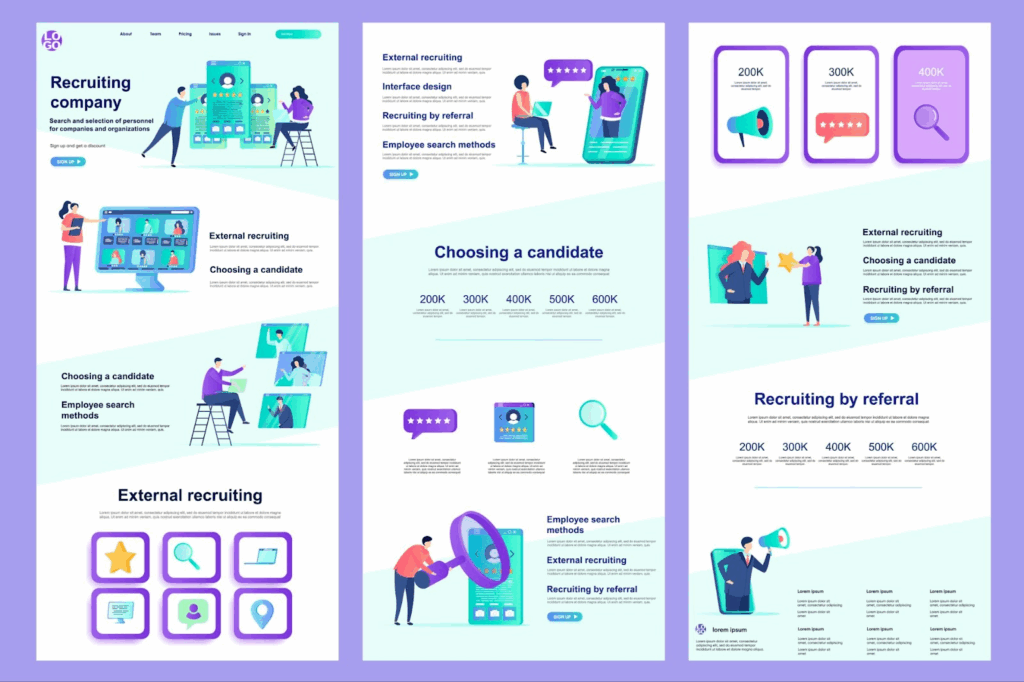
採用LPとは、LandingPage(ランディングページ)の略で、求職者に特定の行動(主に応募)を促すことに特化した、縦長の単一Webページのことです。
検索エンジンやWeb広告などを経由して訪れた求職者に対して、企業の魅力や仕事のやりがいをストーリー仕立てで伝え、最終的に応募フォームへと誘導する役割を担います。
多様な情報を網羅的に掲載する採用サイトとは異なり、採用LPは特定の職種やターゲットに絞ったメッセージを発信することで、より深く応募意欲を喚起します。
採用LPと採用サイトの目的と役割の違い
採用LPと採用サイトは、目的と役割に明確な違いがあります。
採用LPの主な目的は、特定のターゲット層からの「応募獲得」です。
エンジニアやデザイナーなど、限定した職種の求職者に向けたメッセージを1ページに集約し、迷わず応募まで進んでもらうための構成になっています。
一方、採用サイトは、企業全体の採用情報を網羅的に提供し、求職者に企業理解を深めてもらうことが目的です。
新卒、中途、職種ごとの情報、企業理念、福利厚生など、複数のページで構成され、求職者が知りたい情報へ自由にアクセスできる点が特徴です。
採用LPを導入する4つのメリット
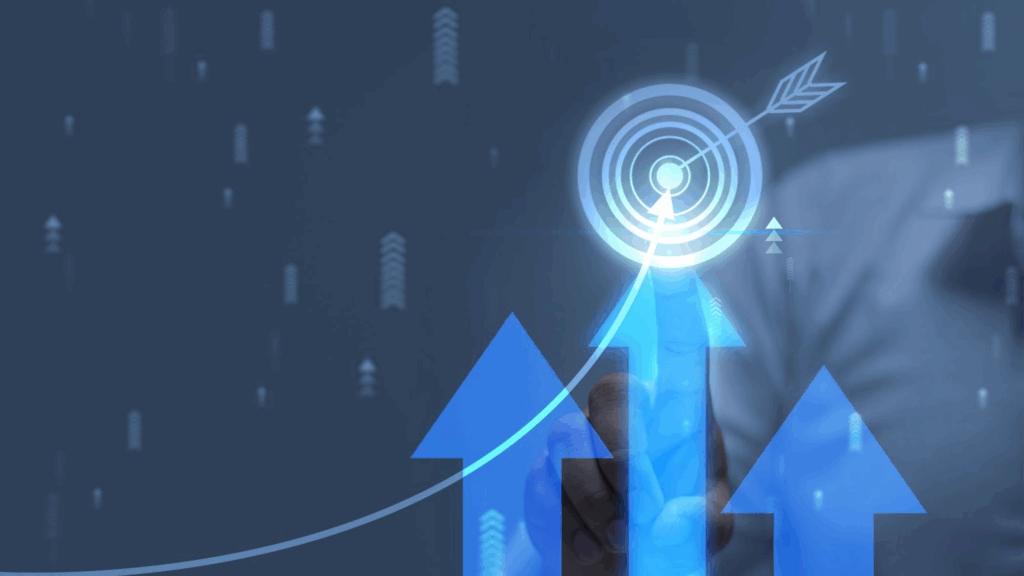
採用活動において採用LPを活用することには、多くの利点が存在します。
採用サイトのような網羅的な情報を提供する採用ページとは異なり、特定のターゲットに深く訴求できるため、ミスマッチの防止や応募の質の向上につながります。
また、制作期間やコストを抑えつつ、効果測定を行いやすい点も大きな魅力です。
ここでは、採用LPを導入することで得られる具体的な4つのメリットを解説します。
特定のターゲットに響くメッセージを届けられる
採用LPは、特定のターゲット層に絞ったメッセージを訴求することに長けています。
例えば、ハイスキルなエンジニアを対象とした中途採用LPであれば、使用する技術スタックや開発環境の魅力を前面に押し出すことが可能です。
また、第二新卒向けであれば、キャリアパスや研修制度の手厚さをアピールするなど、ターゲットが最も知りたい情報や刺さるキーワードを厳選して構成できます。
一般的な採用サイトでは伝えきれない、特定の層に向けた深いメッセージを届けることで、理想とする人材からの応募を効果的に集められます。
短期間・低コストでの制作が可能になる
採用LPは、複数のページで構成される大規模な採用サイトと比較して、短期間かつ低コストで制作できる点が大きなメリットです。
掲載する情報を1ページに集約するため、企画やデザイン、開発にかかる工数が少なく済みます。
特定の職種を急いで募集したい場合や、期間限定のキャンペーンを実施する際に、スピーディーに対応できる機動力は大きな武器になります。
採用ページ全体の制作予算が限られている場合でも、まずは特定のターゲットに向けたLPから始めることで、効率的に採用活動を進めることが可能です。
スマートフォンユーザーにもアプローチしやすい
現代の求職活動において、スマートフォンでの情報収集は主流となっています。
採用LPの縦にスクロールしていくシンプルな構造は、スマートフォンの画面サイズと非常に相性が良く、ユーザーにとってストレスの少ない閲覧体験を提供できます。
複雑なページ遷移がないため、求職者は隙間時間でも手軽に情報を読み進めることが可能です。
スマートフォンに最適化されたデザインと構成にすることで、モバイルユーザーの離脱を防ぎ、応募へのハードルを下げられます。
この手軽さが、多忙な求職者にも効果的にアプローチできる採用ページの強みとなります。
効果測定と改善がスピーディーに行える
採用LPは、公開後の効果測定と改善がしやすいメリットを持っています。
アクセス解析ツールを導入することで、ページの閲覧数、滞在時間、離脱率、応募ボタンのクリック率といった具体的なデータを容易に取得できます。
これらのデータを分析し、「キャッチコピーを変えたら反応がどう変わるか」「写真を変えたら離脱率が下がるか」といった仮説を立て、ABテストなどを実施することで、採用ページの成果を継続的に高めていくことが可能です。
このPDCAサイクルを高速で回せる点が、採用LPの大きな強みです。
採用LPを作成する際の注意点
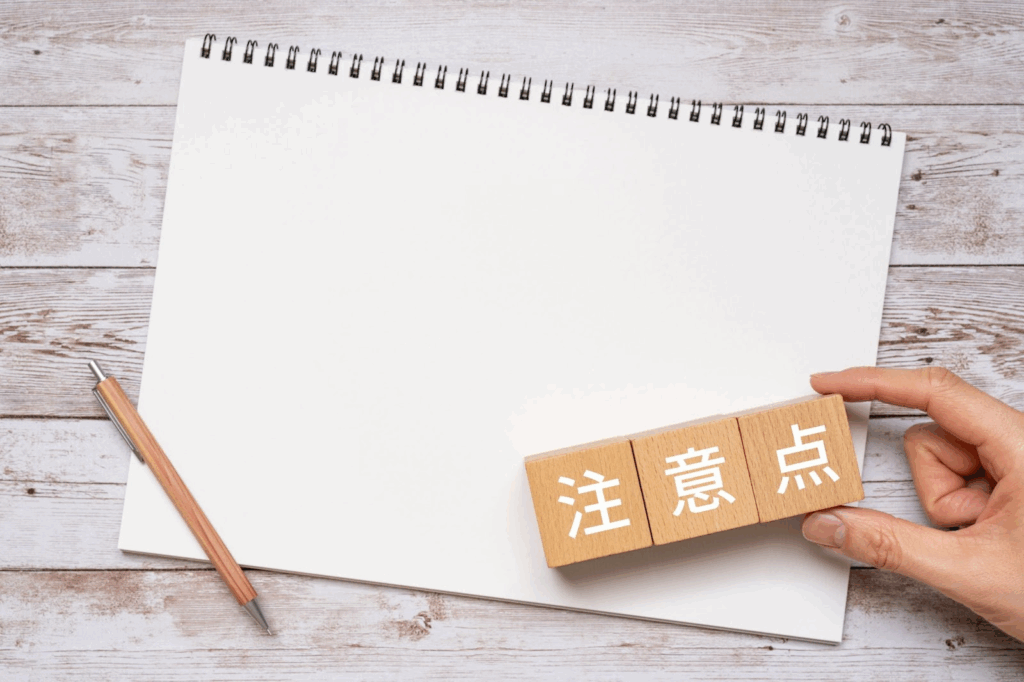
採用LPは効果的な採用手法ですが、その特性を理解せずに作成すると期待した成果を得られない場合があります。
メリットだけでなく、注意すべき点を事前に把握しておくことが重要です。
情報量の制限や、ユーザーを迷わせない導線設計など、採用ページならではのポイントが存在します。
ここでは、採用LPを作成する上で特に気をつけるべき3つの注意点を解説します。
掲載できる情報量には限りがある
採用LPは1枚のページで情報を伝える構成のため、掲載できる情報量には限界があります。
企業の歴史から福利厚生、全ての職種紹介まで網羅的に伝えようとすると、ページが長くなりすぎてしまい、かえって求職者の離脱を招く原因になりかねません。
そのため、採用ページに掲載する情報は、設定したターゲットに「何を一番伝えたいか」という観点で、優先順位をつけて厳選する必要があります。
最も重要なメッセージに絞り込み、簡潔で分かりやすいコンテンツを心がけることが、応募につながるLPの要点です。
応募までのスムーズな導線設計が求められる
採用LPの最終目的は、ページを訪れた求職者に応募してもらうことです。
そのためには、ページを読み進めたユーザーが迷うことなく、自然な流れで応募フォームまでたどり着けるような導線設計が不可欠です。
例えば、「応募はこちら」といったCTA(CallToAction)ボタンをページ内の適切な位置に複数配置したり、ボタンの色やデザインを目立たせたりする工夫が求められます。
求職者の興味や関心が高まったタイミングを逃さずに行動を促すことが、採用ページの成果を大きく左右します。
公開後の継続的な分析と改善が必要になる
採用LPは一度公開したら終わりではありません。
むしろ、公開してからが本当のスタートと言えます。
アクセス解析ツールを用いて、どの部分がよく読まれているか、どこで離脱しているか、応募率はどのくらいかといったデータを定期的に分析することが重要です。
その結果を基に、キャッチコピーの変更、写真の差し替え、構成の順番の入れ替えなど、細かな改善を繰り返していく必要があります。
この継続的な分析と改善のサイクルを回すことで、採用ページのパフォーマンスを最大化できます。
【業種別】参考にしたい採用LPのデザイン事例

自社の採用LPを制作する際、他社の成功事例からヒントを得ることは非常に有効です。
特に、業種によってターゲットとなる求職者の属性や響くメッセージが異なるため、同業種の事例は良い参考になります。
ここでは、さまざまな業種のデザイン事例を取り上げ、それぞれの特徴や工夫のポイントを解説します。
これから作成するLPのデザインの方向性を考える上で、ぜひ役立ててください。
IT・Web業界の先進的なデザイン事例
IT・Web業界の採用LPは、企業の技術力や先進性を視覚的に訴えかけるデザインが特徴です。
例えば、情報過多を避け、無駄を削ぎ落としたミニマルなレイアウトや、コーポレートカラーを基調としたスタイリッシュな配色が多く見られます。これにより、洗練された印象を与え、先進的な企業文化を表現できます。
また、動きのあるアニメーションやパララックス効果(スクロール差分効果)などを取り入れ、ユーザーに視覚的な驚きを与えることで、技術力の高さをアピールするケースも少なくありません。
このようなインタラクティブな要素は、求職者のエンゲージメントを高め、記憶に残る採用体験を提供します。 コンテンツとしては、開発環境や使用技術、エンジニアのインタビューなどを掲載し、専門職の求職者が求める具体的な情報を提供する構成が参考になります。
例えば、世界中で利用されている音楽ストリーミングサービスであるSpotifyの採用LPも、そのブランドイメージを損なわない洗練されたデザインと、同社の技術や文化を伝えるコンテンツが魅力です。このような先進的なデザインは、技術志向の強い求職者にとって魅力的に映り、応募への意欲を高める重要な要素となります。
クリエイティブ業界の個性的なデザイン事例
広告代理店やデザイン事務所など、クリエイティブ業界の採用LPは、企業の独自性や世界観を強く打ち出したデザインが目立ちます。常識にとらわれない大胆なレイアウトや、インパクトのある写真・イラストを大きく使用することで、求職者の感性に直接訴えかける工夫がされています。動画をメインコンテンツにしたり、インタラクティビティを取り入れたりと、クリエイティビティを存分に発揮した事例も豊富です。
例えば、TikTokクリエイターを募集しているReno Agencyの採用LPは、TikTokのアイコンの色味に似た色が全体に使われており、どのような職種を募集しているかが一目でわかるデザインです。このような企業の個性を強く表現することで、同じ価値観を持つ人材を引き寄せることを目的としたデザインは、大いに参考になります。 また、情報過多を避け、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインや、コーポレートカラーを基調としたスタイリッシュな配色が多く見られるのも特徴です。動きのあるアニメーションやパララックス効果(スクロール差分効果)などを取り入れ、ユーザーに視覚的な驚きを与えることで、技術力の高さをアピールするケースも少なくありません。
このようなインタラクティブな要素は、求職者のエンゲージメントを高め、記憶に残る採用体験を提供します。デザインは単に見た目を良くするだけでなく、企業の文化や働き方を表現する重要な要素となるため、自社の魅力を最大限に引き出すためのデザインを検討することが成功への鍵です。
サービス・接客業の温かみが伝わるデザイン事例
サービス・接客業の採用LPでは、企業の温かい雰囲気や「人」の魅力を伝えるデザインが非常に重要です。求職者が「ここで働きたい」と感じるような、親しみやすく温かみのある印象をデザインで演出することが成功の鍵となります。
例えば、株式会社塚田農場の採用LPは、店舗の活気ある様子やスタッフの笑顔を前面に出したデザインで、温かい社風を効果的に伝えています。暖色系の配色や手書き風のフォントを使用することで、視覚的に安心感や親しみやすさを与えるデザインは、特にサービス業において応募を後押しする上で参考になります。
さらに、実際に働くスタッフのインタビューや、入社後のキャリアパスなどを掲載することで、仕事のやりがいやチームワークの良さを具体的に示すコンテンツも有効です。例えば、社員が語る「仕事の面白い点」や「お客様との感動エピソード」などを盛り込むことで、求職者は入社後の自分の姿を想像しやすくなります。温かい雰囲気だけでなく、具体的なキャリア形成のイメージを示すことで、長期的に働きたいという意欲も高まることでしょう。
このようなデザインは、求職者に企業の一員として働く自分を想像させ、応募への意欲を高める重要な要素となります。また、研修制度や福利厚生に関する情報を分かりやすく提示することも、求職者の安心感につながります。
メーカー・製造業の技術力がわかるデザイン事例
メーカーや製造業の採用LPでは、企業の持つ高い技術力や製品へのこだわり、そして事業の安定性を効果的に伝えるデザインが非常に重要です。求職者に対して、モノづくりの現場のスケール感や専門性をアピールするために、製品が作られる工場の写真や精密な部品の画像を効果的に使用することが求められます。
特に、青やグレーを基調とした配色を採用することで、誠実さや信頼性を表現するデザインは、求職者に安心感を与え、企業の安定した基盤を印象付けます。 さらに、第一線で活躍する技術者のインタビューや、製品開発の裏側にあるストーリーを紹介することも有効です。これにより、仕事への誇りや社会への貢献度を具体的に伝え、求職者の共感を呼ぶデザインは、企業の魅力を最大限に引き出す参考となるでしょう。
例えば、グローバルに展開する電子部品メーカーであるオムロン(OMRON)のような企業は、先進的な技術力を前面に出したデザインを採用しています。精密なものづくりへの情熱や、社会を支える技術の重要性を視覚的に表現することで、企業の信頼性を高め、優秀な人材の獲得に繋げています。このように、技術力を明確に示し、企業の信頼性を構築するデザインは、メーカー・製造業の採用活動において欠かせない要素です。
成果につながる採用LPの作り方4ステップ
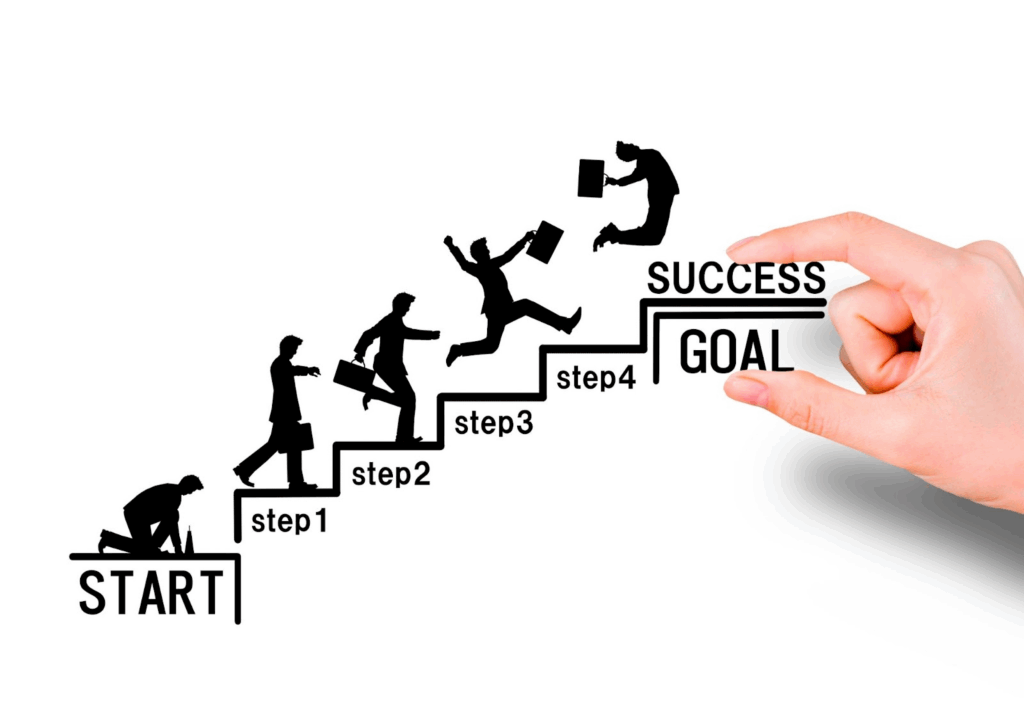
採用LPを制作する際には、やみくもに着手するのではなく、戦略的な手順を踏むことが成功への鍵となります。
ターゲットを明確にすることから始まり、構成の設計、デザインの作成、そして集客方法の計画まで、一連の流れを理解しておくことが重要です。
・Step1:誰に何を伝えるか?採用ターゲットを明確にする
・Step2:何を載せるか?LPの構成とコンテンツを設計する
・Step3:どう見せるか?求職者の心をつかむデザインを作成する
・Step4:どう届けるか?Web広告などでの集客方法を計画する
この4つのステップを丁寧に進めることで、求職者の心に響き、着実に応募につながる質の高い採用ページが完成します。
Step1:誰に何を伝えるか?採用ターゲットを明確にする
採用LP制作の最初のステップは、採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に設定することです。
年齢、性別、経験、スキル、価値観、情報収集の方法などを細かく定義します。
例えば、即戦力となるエンジニアを求める中途採用LPであれば、「30代前半、Webアプリケーション開発経験5年以上、新しい技術の習得に意欲的」といった具体的なペルソナを描きます。
ターゲットが明確になることで、その人物に響くキャッチコピーやコンテンツ、デザインの方向性が定まり、メッセージの精度が格段に高まります。
Step2:何を載せるか?LPの構成とコンテンツを設計する
ターゲットが明確になったら、次にLP全体の構成と掲載するコンテンツを設計します。
求職者がページを読み進める中で、どのように興味を持ち、最終的に応募したくなるかというストーリーを意識することが重要です。
一般的には、
①課題提起(こんな悩みはありませんか?)
②魅力的なオファー(キャッチコピー)
③共感・信頼(社員の声、実績)
④具体的な仕事内容
⑤募集要項
⑥応募フォーム
という流れが基本です。
各セクションでターゲットに最も伝えたいメッセージを考え、採用ページに掲載するテキストや写真、動画などの具体的なコンテンツを準備します。
Step3:どう見せるか?求職者の心をつかむデザインを作成する
構成とコンテンツが決まったら、それらを視覚的に表現するデザインを作成します。
デザインは、企業のブランドイメージを伝え、求職者の感情に訴えかける重要な要素です。
ターゲットの年齢層や職種に合わせて、配色、フォント、写真のトーンなどを決定します。
例えば、若手向けなら明るくポップなデザイン、専門職向けなら知的で信頼感のあるデザインといった方向性が考えられます。
単に見た目が美しいだけでなく、情報が読みやすく、応募ボタンがどこにあるか直感的にわかるような、使いやすさ(UI/UX)も考慮したデザインが求められます。
Step4:どう届けるか?Web広告などでの集客方法を計画する
魅力的な採用LPが完成しても、求職者に見てもらえなければ意味がありません。
そのため、LPを公開する前に、どのようにしてターゲットにページを届けるかという集客方法を計画しておく必要があります。
主な方法としては、特定のキーワードで検索したユーザーに表示するリスティング広告、SNS上でターゲットを絞って配信するSNS広告、求人検索エンジンや転職サイトからの誘導などが挙げられます。
ターゲットが普段利用している媒体を見極め、予算に応じて最適な集客手段を組み合わせ、安定的に採用ページへアクセスを集める仕組みを構築します。
採用LPの効果を最大化させる3つのポイント
採用LPを制作するだけでなく、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
求職者の心を一瞬でつかむ工夫や、企業の魅力をリアルに伝える手法を取り入れることで、応募率は大きく変わります。
作り方のステップに加えて、これから紹介する3つのポイントを意識すれば、より成果の出る採用ページを実現できるはずです。
最初の3秒で惹きつけるファーストビューを意識する
Webサイトを訪れたユーザーは、最初の3秒でそのページを読み進めるかどうかを判断すると言われています。
この最初に表示される画面領域「ファーストビュー」が、採用LPの成否を分ける最も重要な要素です。
ターゲットの心に突き刺さるキャッチコピーと、仕事の魅力や理想の働き方が一目で伝わる魅力的な画像を配置することが不可欠です。
ここで「自分のための求人かもしれない」と直感的に思わせるデザインにできなければ、ユーザーはすぐにページを閉じてしまいます。
伝えたいことを詰め込みすぎず、最も重要なメッセージに絞って訴求します。
自社の魅力や社風がリアルに伝わる写真や動画を活用する
テキストだけでは伝えきれない職場の雰囲気や、社員の活き活きとした表情は、写真や動画を活用することでリアルに伝えられます。
プロが撮影した綺麗な写真だけでなく、社員同士の自然なコミュニケーションが垣間見えるスナップショットや、オフィス紹介のショート動画などを掲載すると、求職者は働く姿を具体的にイメージしやすくなります。
実際に働く人々の姿を見せることは、安心感や親近感につながり、応募への心理的なハードルを下げます。
このリアルさが、他の採用ページとの差別化にもつながります。
応募フォームは入力項目を最小限にして離脱を防ぐ
せっかく採用LPを最後まで読んでもらい、応募意欲が高まっても、応募フォームの入力項目が多すぎると、面倒に感じて途中で離脱してしまう求職者は少なくありません。
この「フォーム落ち」を防ぐためには、入力項目を必要最小限に絞ることが極めて重要です。
まずは氏名、メールアドレス、電話番号といった、最初の連絡に必要な情報だけを求めるように設計します。
詳細な職務経歴などは、その後の選考過程でヒアリングすれば問題ありません。
入力の手間をできる限り減らすことが、応募完了率を高めるための最後の鍵となります。
採用LPの制作にかかる費用相場はどれくらい?

採用LPの制作費用は、制作会社、フリーランス、自社制作といった方法、LPの構成、デザインのクオリティ、盛り込む機能によって大きく変動します。
一般的な相場としては、テンプレートを活用した簡易的な採用ページであれば10万円~30万円程度、オリジナルのデザインでコンテンツ制作まで依頼する場合は30万円~60万円程度が目安となります。
さらに、動画制作や複雑なアニメーションなどを加える場合は、100万円以上になることもあります。
複数の制作会社から見積もりを取り、費用と内容を比較検討することが重要です。
よくあるご質問
Q1:採用LPの制作期間はどれくらいですか?
A1:LPの構成やデザインの複雑さによりますが、一般的には企画・構成からデザイン、コーディング、公開まで含めて1.5ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。原稿や写真素材が事前に揃っている場合は、より短期間での制作も可能です。
Q2:採用LPと採用サイト、どちらを作るべきですか?
A2:募集する職種やターゲットによります。特定の職種(例:エンジニア)を急募したい、特定の層(例:第二新卒)に強くアピールしたい場合は採用LPが効果的です。一方で、複数の職種を同時に募集し、企業全体の情報を伝えたい場合は採用サイトが適しています。両方を連携させて活用するのも有効な手段です。
Q3:公開後の運用では何をすればよいですか?
A3:主にWeb広告の運用と、効果測定に基づくLPの改善(LPO)を行います。広告の費用対効果を分析し、より効率的な集客を目指します。また、LPのアクセスデータ(閲覧数、離脱率、応募率など)を分析し、キャッチコピーやデザインを修正して、より成果が出るように改善を繰り返します。
Q4:スマートフォン対応は必須ですか?
A4:はい、必須です。現在の求職者の多くはスマートフォンで情報収集を行うため、スマートフォンで見た際に表示が崩れたり、文字が小さくて読みにくかったりすると、それだけで離脱の原因になります。レスポンシブデザインなどを用いて、必ずスマートフォンに最適化してください。
Q5:制作会社を選ぶ際のポイントは何ですか?
A5:採用分野でのLP制作実績が豊富かどうかを確認することが重要です。採用市場のトレンドや求職者の心理を理解している会社を選ぶことで、より効果的なLPが期待できます。また、デザインのクオリティだけでなく、公開後の運用サポートや改善提案まで行ってくれるかどうかも選定のポイントになります。
まとめ
採用LPとは、特定のターゲットに狙いを定め、応募というゴールに向けて一直線に誘導するための強力な採用ツールです。一般的な採用サイトとは異なり、1ページに情報を凝縮することで、メッセージがぶれることなく求職者の心に深く響かせることができます。
制作においては、ターゲットの明確化から構成設計、デザイン、そして集客戦略までを一貫して考える必要があります。公開後も継続的にデータを分析し、改善を繰り返すことで、その効果はさらに高まります。採用競争が激化する現代において、採用LPは自社の魅力を効果的に伝え、求める人材を獲得するための有効な選択肢です。
Piicでは、ターゲット設計から構成・デザイン、公開後の改善提案までを一貫してサポートし、貴社に最適な採用LPを制作いたします。
「採用LPを作りたい」「自社の魅力をもっと伝えたい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。








