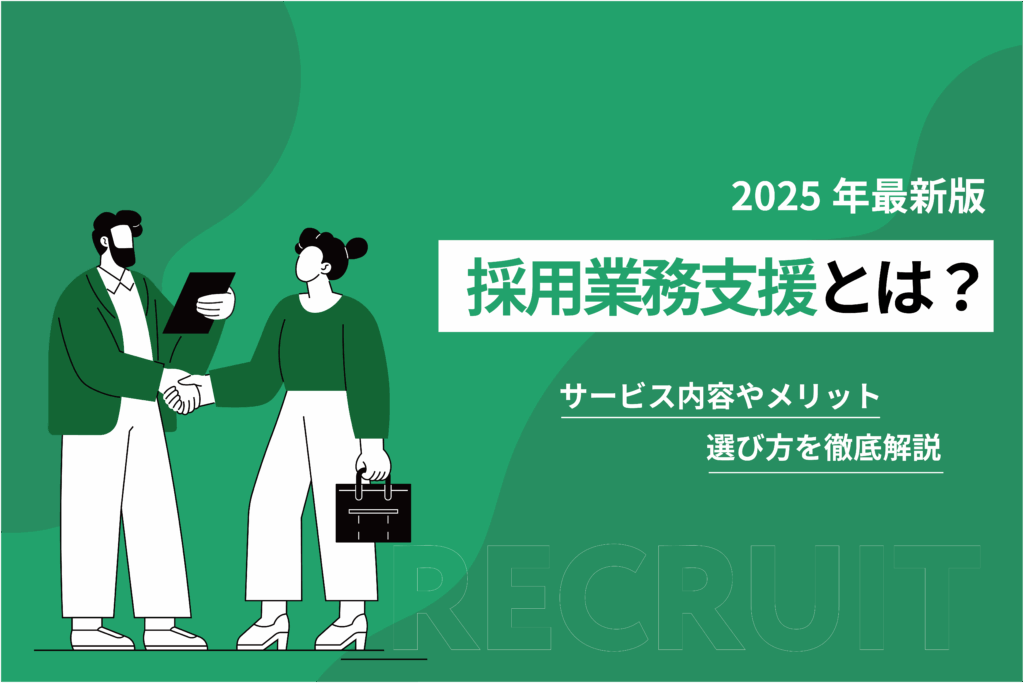
企業の成長に不可欠な人材採用ですが、多くの企業で人事担当者のリソース不足やノウハウの欠如といった課題が聞かれます。
採用業務支援サービスは、このような採用に関する悩みを解決し、企業の採用活動を成功に導くためのパートナーです。
この記事では、採用業務支援の基本的な内容から、具体的なサービス、メリット、そして自社に合ったサービスの選び方まで、網羅的に解説します。

Index
-
採用課題を解決する外部委託サービス【採用業務支援】
-
採用代行(RPO)や人材紹介との違い
-
依頼できる具体的な業務内容
-
採用戦略の立案・設計
-
候補者を集める母集団形成
-
書類選考から面接までの選考プロセス
-
内定者の承諾率を高めるフォロー
-
入社後の定着を促すオンボーディング支援
-
採用業務支援サービスを導入する3つのメリット
-
【採用力の強化】採用のプロの知見を活用
-
【コア業務に集中できる】人事担当者の工数を減らせる
-
【コストの削減】採用活動にかかるトータルな費用を抑えられる
-
導入前に知っておきたい採用業務支援の注意点
-
採用に関するノウハウが自社に蓄積されにくい
-
委託先との情報共有にコミュニケーションコストがかかる
-
認識のズレが採用のミスマッチを引き起こす可能性がある
-
【目的別】採用業務支援サービスの主な種類
-
幅広い業務をまとめて依頼できる「総合型」
-
採用戦略の策定から支援する「コンサルティング型」
-
スカウト業務など特定業務に特化した「専門型」
-
失敗しない採用業務支援サービスの選び方4つのポイント
-
自社の採用課題とサービスの得意分野が合っているか確認する
-
依頼したい業務をカバーしているか支援範囲を確かめる
-
料金体系が予算や採用計画に見合っているか検討する
-
自社と似た業界や職種での支援実績があるか調べる
-
採用業務支援サービスを最大限に活用するためのコツ
-
サービス会社に任せきりにせず協働体制を築く
-
委託する業務範囲と責任の所在を明確にする
-
定期的なミーティングで進捗と課題を共有する
-
よくあるご質問
-
Q1. 料金の相場はどのくらいですか?
-
Q2. どのくらいの期間から利用できますか?
-
Q3. 地方の企業の採用でも対応可能ですか?
-
Q4. 採用の機密情報は守られますか?
-
Q5. 導入までのおおまかな流れを教えてください。
-
まとめ
採用課題を解決する外部委託サービス【採用業務支援】

採用業務支援とは、企業の採用活動に関わる業務を外部の専門企業が代行またはサポートするサービス全般を指します。
採用支援サービスとは、単なる人材紹介に留まらず、採用戦略の立案から応募者の管理、面接調整、内定者フォローまで、採用プロセスの一部または全てをアウトソーシングできるのが特徴です。
人手不足やノウハウ不足に悩む人事部門の課題を解決し、より効率的で質の高い採用活動を実現するために活用されています。
採用代行(RPO)や人材紹介との違い
採用業務支援は、採用代行(RPO)とほぼ同義で使われることが多く、採用プロセス全体を包括的に支援します。
これに対して人材紹介は、企業が求める人材を探し出して紹介することに特化したサービスです。
採用が成功した場合に成果報酬を支払うのが一般的で、候補者を見つけるまでが主な役割となります。
また、派遣は企業に労働力を提供するサービスであり、雇用契約は派遣会社と結ばれます。
採用業務支援が自社の社員を採用するための活動をサポートするのに対し、派遣は必要な時に必要なスキルを持つ人材を外部から調達する点で目的が異なります。
依頼できる具体的な業務内容

採用業務支援サービスは、採用活動における一連のプロセスを幅広くカバーします。
具体的には、どのような人材をどうやって採用するかという戦略部分から、実際に応募者を集め、選考し、入社後の定着を促すところまで、企業のニーズに合わせて必要な業務を切り出して依頼することが可能です。
これにより、自社の弱点を補強し、採用活動全体の質を高めることができます。
採用戦略の立案・設計
どのような人材が自社に必要なのかを定義するペルソナ設計や、採用目標人数の設定、最適な採用チャネルの選定、選考フローの構築といった、採用活動の根幹となる戦略部分から支援を受けられます。
自社の経営計画や事業戦略をヒアリングした上で、専門的な知見を持つプロが客観的な視点からアドバイスを提供します。
採用に関する漠然とした悩みも、相談を通じて具体的な課題へと落とし込み、効果的な打ち手を計画することが可能です。
これにより、場当たり的な採用ではなく、一貫性のある戦略に基づいた採用活動を展開できます。
候補者を集める母集団形成
採用戦略に基づいて、実際に候補者を集めるための活動を代行します。
具体的には、求職者に響く求人広告の作成と各媒体への出稿管理、企業のデータベースに眠る候補者の掘り起こし、ダイレクトリクルーティングにおけるスカウトメールの文面作成や送信作業などが挙げられます。
また、複数の人材紹介エージェントとのやり取りを一本化し、効率的に候補者情報を集めることも可能です。
専門家が最新の市場動向を踏まえて最適なリクルート手法を駆使するため、自社だけで行うよりも質の高い母集団を効率的に形成することが期待できます。
書類選考から面接までの選考プロセス
応募があった候補者の書類を、あらかじめ定めた採用要件に基づいてスクリーニングする業務を委託できます。
また、候補者や面接官との連絡を取り、面接日程を調整するといった煩雑な事務作業も任せられます。
企業によっては、一次面接自体を代行してもらうことも可能です。
面接代行では、候補者のスキルや経験、人柄などを客観的な基準で評価し、レポートを提出します。
これにより、人事担当者は評価の高い候補者との最終面接に集中でき、選考プロセス全体の効率化と質の向上を図れます。
内定者の承諾率を高めるフォロー
優秀な人材を確保するためには、内定を出した後のフォローが極めて重要です。
内定者の入社意欲を維持し、内定辞退を防ぐための様々な施策を支援します。
例えば、内定者との定期的なコミュニケーションや、個別面談の設定、内定者懇親会の企画・運営、入社にあたっての疑問や不安を解消するための窓口業務などを代行します。
採用MAツールなどを活用し、内定者一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなフォローを行うことで、企業へのエンゲージメントを高め、最終的な入社へとつなげます。
入社後の定着を促すオンボーディング支援
採用は、人材が入社して終わりではありません。
入社した社員が早期に組織に馴染み、能力を発揮して定着するためのオンボーディングプログラムの設計や実施も支援の対象です。
具体的には、新入社員向けの研修コンテンツの企画・作成や、先輩社員が新人をサポートするメンター制度の導入支援、入社後の定期的なフォローアップ面談の実施などが含まれます。
こうした入社後の手厚いサポート体制を構築することで、新入社員のエンゲージメントを高め、早期離職のリスクを低減させます。
採用業務支援サービスを導入する3つのメリット

採用業務支援サービス、特に専門性が求められる中途採用支援サービスなどを活用することで、企業は多くのメリットを得られます。
採用のプロフェッショナルが持つ知識やノウハウを活用できるだけでなく、社内のリソース配分を最適化し、結果としてコスト削減にもつながる可能性があります。
ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく見ていきます。
【採用力の強化】採用のプロの知見を活用
採用業務支援会社は、数多くの企業の採用を支援してきた実績から、豊富な知識とノウハウを蓄積しています。
最新の採用市場の動向や、効果的な求人媒体の選定、候補者の心に響くアプローチ方法など、専門家ならではの知見を活用することが可能です。
これにより、自社だけでは気づけなかった採用活動の課題を発見し、改善策を実行できます。
結果として、採用の質とスピードが向上し、これまでアプローチできなかった優秀な人材の獲得も期待でき、企業全体の採用力が底上げされます。
【コア業務に集中できる】人事担当者の工数を減らせる
採用活動には、応募者との日程調整や合否連絡、データ入力といった、時間がかかる一方で定型的なノンコア業務が数多く存在します。
これらの業務を外部へ業務委託することで、人事担当者は大幅な工数削減を実現できます。
その結果、創出された時間を採用戦略の立案や、候補者の魅力を引き出す面接、入社後の活躍を見据えた制度設計といった、企業の将来に直結する重要なコア業務に集中させることが可能となります。
これにより、より戦略的で質の高い人事活動が展開できます。
【コストの削減】採用活動にかかるトータルな費用を抑えられる
採用担当者を一人新たに正社員として雇用する場合、給与や社会保険料、教育コストなど多額の費用が発生します。
特に採用活動が特定の時期に集中する企業では、年間を通じて人件費を払い続けるのは非効率な場合もあります。
採用業務支援サービスやフリーランスの採用担当者を活用すれば、必要な期間だけ専門家の力を借りることができ、人件費を変動費化できます。
また、採用プロセスの効率化によって求人広告費の無駄がなくなったり、採用期間が短縮されたりすることで、採用活動にかかる全体のコスト抑制が期待できます。
導入前に知っておきたい採用業務支援の注意点

採用業務支援サービスの導入は多くのメリットをもたらしますが、注意すべき点も存在します。
「採用支援とは」何かを正しく理解し、単なる業務の丸投げにならないよう、デメリットも把握した上で検討することが重要です。
ここでは、導入後に後悔しないために、事前に知っておきたい3つの注意点を解説します。
これらの点を考慮し、対策を講じることで、サービスをより効果的に活用できます。
採用に関するノウハウが自社に蓄積されにくい
採用業務の大部分を外部に委託すると、採用活動の具体的なプロセスや判断基準、成功事例や失敗から得られる学びといった貴重なノウハウが、自社の資産として蓄積されにくいという側面があります。
委託先に任せきりの状態が続くと、将来的に契約を終了した際に、自社だけで採用活動を遂行する力が弱まってしまう可能性があります。
これを防ぐためには、定期的な報告会で詳細なデータや活動内容の共有を求め、意思決定のプロセスに関与するなど、主体的に採用活動へ関わり続ける姿勢が求められます。
委託先との情報共有にコミュニケーションコストがかかる
外部のパートナーと円滑に業務を進めるためには、密な情報共有が欠かせません。
自社の事業内容や企業文化、求める人物像、採用の進捗状況などを正確に伝え、常に認識を合わせておく必要があります。
そのため、定期的なミーティングの設定や、日々の連絡、資料の作成といったコミュニケーションに、一定の時間と労力がかかります。
このコミュニケーションを怠ると、認識のズレが生じてしまい、思うような成果が得られない原因にもなりかねません。
導入前に、どのような体制で連携していくのかを具体的にすり合わせておくことが重要です。
認識のズレが採用のミスマッチを引き起こす可能性がある
委託先の担当者が、自社の事業内容や社風、本当に求める人物像を深く理解できていない場合、採用のミスマッチが起こるリスクがあります。
例えば、書類上のスキルや経歴だけで候補者を判断し、自社のカルチャーに合わない人材を通過させてしまうケースです。
こうした認識のズレからミスマッチな人材を採用してしまうと、早期離職につながり、結果的に採用コストが無駄になってしまいます。
これを防ぐには、サービス開始時に時間をかけて自社の理念や文化を共有し、選考基準を具体的にすり合わせる作業が不可欠です。
【目的別】採用業務支援サービスの主な種類

採用業務支援サービスは多岐にわたり、企業の採用課題や求める支援内容に応じて最適なサービスを選ぶことが重要です。主なサービスには、採用代行(RPO)、採用コンサルティング、人材紹介、人材派遣、求人広告媒体、採用システム・ツール導入支援などがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況と照らし合わせてみましょう。
【採用代行(RPO)】
採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、採用業務の一部または全てを外部の専門業者に委託するサービスです。履歴書・職務経歴書の確認、面接日程調整、応募者対応などの事務作業から、採用戦略の立案、求人広告掲載の代行、スカウトメール配信、面接代行、内定者フォロー、入社後研修の企画まで、幅広い業務を依頼できます。採用担当者の業務負担を軽減し、採用活動の効率化や採用の質の向上に貢献します。
【採用コンサルティング】
採用コンサルティングは、企業が抱える採用課題に対し、専門的な知見とノウハウに基づいて採用戦略の立案から実行までをサポートするサービスです。採用計画の策定、ターゲット人材の明確化、母集団形成、選考プロセスの設計、面接官トレーニング、内定者フォロー、入社後の定着支援など、採用活動全般において専門的なアドバイスやサポートを受けられます。採用市場の最新トレンドを把握し、自社に合った最適な採用戦略を立てる上で有効です。
【人材紹介】
人材紹介サービスは、企業と求職者のマッチングを行うサービスです。企業は求める人材の要件を伝え、人材紹介会社が保有するデータベースの中から条件に合う求職者を紹介します。採用が決定した場合に紹介手数料が発生する成功報酬型のケースが多いのが特徴です。自社では見つけにくい専門性の高い人材や、非公開求人を通じて質の高い人材に出会える可能性があります。
【人材派遣】
人材派遣サービスは、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ企業に派遣するサービスです。派遣社員の雇用元は人材派遣会社であり、給与支払い、社会保険などの労務管理は派遣会社が行います。急な欠員補充や一時的な業務量の増加に対応できるほか、専門的なスキルを持つ人材を必要な期間だけ活用したい場合に有効です。
【求人広告媒体】
求人広告媒体は、企業が求人情報を掲載し、広く求職者を募るためのサービスです。総合型の転職サイト、特定の業界や職種に特化した専門サイト、アルバイト・パート向けの媒体など、様々な種類があります。求人検索エンジンやダイレクトリクルーティング型の媒体も含まれます。掲載方法も多様で、掲載課金型や成果報酬型などがあります。
【採用システム・ツール導入支援】
採用システム・ツール導入支援は、採用活動の効率化や効果向上を目的としたシステムの導入をサポートするサービスです。採用管理システム(ATS)は、求人情報、応募者情報、選考状況などを一元管理し、採用業務の効率化を促進します。その他、Web面接ツール、適性検査ツール、リファラル採用ツールなども含まれます。これらのツールを導入することで、採用担当者の負担軽減やデータに基づいた採用戦略の立案が可能になります。
幅広い業務をまとめて依頼できる「総合型」
採用戦略の立案から母集団形成、選考プロセスの運用、内定者フォロー、入社後のオンボーディングまで、採用活動に関わる一連の業務をワンストップで依頼できるタイプです。
採用部門の立ち上げフェーズにある企業や、採用担当者のリソースが全体的に不足している企業に向いています。
窓口が一つにまとまるため、複数の業者とやり取りする手間が省け、採用活動全体を効率的に管理できるのが大きなメリットです。
包括的なサポートにより、採用プロセスの全体最適化を図りたい場合に適しています。
採用戦略の策定から支援する「コンサルティング型」
採用活動における最上流工程である、採用戦略の立案や採用ブランディングの構築、採用すべき人物像の設計などを中心に支援するサービスです。
「採用がうまくいかない根本的な原因がわからない」「自社に合った採用手法を見つけたい」といった、より戦略的な課題を抱える企業に適しています。
専門家の客観的な視点から自社の採用活動を分析してもらい、データに基づいた具体的な改善策の提案を受けられます。
実務の代行よりも、まず課題解決の方向性を定めたい場合に有効です。
スカウト業務など特定業務に特化した「専門型」
ダイレクトリクルーティングのスカウトメール送信だけ手が回らない、面接の日程調整業務を効率化したい、求人広告の運用をプロに任せたいなど、特定の業務に絞って支援を提供するサービスです。
採用活動における課題が明確で、ピンポイントでリソースを補強したい場合に非常に有効です。
必要な業務だけを切り出して依頼できるため、コストを比較的安価に抑えられるのが特徴です。
自社の採用体制の弱点を補う形で柔軟に活用できるため、多くの企業にとって利用しやすい選択肢となります。
失敗しない採用業務支援サービスの選び方4つのポイント

数多く存在する採用業務支援サービスの中から、自社に最適な一社を見つけ出すことは、採用成功のための重要な第一歩です。
サービスの知名度や料金だけで安易に決めてしまうと、期待した効果が得られないこともあります。
ここでは、自社の採用課題を解決し、信頼できるパートナーを選ぶために、必ず確認しておきたい4つのポイントを紹介します。
- 自社の採用課題とサービスの得意分野が合っているか確認する
- 依頼したい業務をカバーしているか支援範囲を確かめる
- 料金体系が予算や採用計画に見合っているか検討する
- 自社と似た業界や職種での支援実績があるか調べる
これらの視点を持って、複数のサービスを比較検討することが重要です。
自社の採用課題とサービスの得意分野が合っているか確認する
まず、自社が抱える採用課題を具体的に洗い出すことから始めます。
応募者の数が足りない、優秀な人材からの応募が少ない、内定を出しても辞退されてしまうなど、課題によって有効な打ち手は異なります。
その上で、検討しているサービスが自社の課題解決を得意としているかを確認します。
例えば、エンジニア採用に強みを持つサービス、新卒採用のノウハウが豊富なサービスなど、各社には得意分野があります。
自社の課題とサービスの強みが一致しているかどうかが、選定における最も重要なポイントです。
依頼したい業務をカバーしているか支援範囲を確かめる
サービスによって、対応可能な業務の範囲は大きく異なります。
戦略立案のような上流工程からサポートしてくれるのか、それとも日程調整などの事務作業が中心なのか、事前にしっかりと確認する必要があります。
自社が「どこからどこまで」の業務を委託したいのかを明確にし、そのニーズを満たすサービスを選びましょう。
契約後に「この業務は範囲外だった」といった認識の齟齬が生まれないよう、見積もりや提案の段階で、支援範囲の詳細について具体的にすり合わせておくことが大切です。
料金体系が予算や採用計画に見合っているか検討する
料金体系は主に、毎月定額の費用が発生する「月額固定型」と、採用成功時に費用を支払う「成果報酬型」があります。
月額固定型は、依頼する業務量が多い場合にコストパフォーマンスが良くなる傾向があり、成果報酬型は初期費用を抑えたい場合に適しています。
自社の採用人数や採用にかける期間、そして確保している予算を考慮し、どちらの料金体系が合っているかを慎重に判断します。
基本料金のほかにオプション料金が発生するケースもあるため、最終的にかかる費用の総額を事前に確認しておくことが重要です。
自社と似た業界や職種での支援実績があるか調べる
採用のノウハウや有効なアプローチ方法は、業界や職種によって大きく異なります。
そのため、自社と同じ業界や、採用したい職種での支援実績が豊富なサービスを選ぶことを推奨します。
実績が豊富であれば、その分野における採用市場の動向や候補者の特性を熟知している可能性が高く、より効果的なサポートが期待できます。
サービスの公式サイトに掲載されている導入事例をチェックしたり、商談の際に具体的な実績について質問したりして、自社との親和性を確認しましょう。
採用業務支援サービスを最大限に活用するためのコツ

優れた採用業務支援サービスを導入したとしても、ただ業務を丸投げするだけではその効果を十分に引き出すことはできません。
サービスを最大限に活用し、採用活動を成功に導くためには、委託する企業側の主体的な関わり方が鍵となります。
ここでは、委託先と良好なパートナーシップを築き、成果を最大化するための3つのコツを紹介します。
これらを意識することで、単なる業務代行に留まらない、戦略的な採用活動が実現できます。
サービス会社に任せきりにせず協働体制を築く
採用業務支援サービスは、あくまで採用活動をサポートする存在であり、採用の主体は自社にあるという意識を持つことが重要です。
サービス会社を単なる外注先と捉えるのではなく、共に採用成功という共通の目標に向かうパートナーとして接しましょう。
自社の最新情報や現場の声を積極的に共有し、委託先からの提案にも真摯に耳を傾けるなど、対等な立場で意見交換を行う協働体制を築くことが、精度の高い採用活動につながります。
二人三脚で進めていく姿勢が、成果を大きく左右します。
委託する業務範囲と責任の所在を明確にする
サービスを導入する際には、どの業務を委託し、どの業務は自社が担当するのか、その境界線を明確に定めておくことが不可欠です。
例えば、「書類選考は委託先が行うが、その基準の決定と最終確認は自社が行う」「面接日程の調整は委託するが、面接官のアサインは自社が担う」など、各プロセスにおける役割分担と責任の所在を具体的に文書などで合意しておきます。
これにより、業務の重複や漏れを防ぎ、トラブルを未然に回避してスムーズな連携を実現できます。
定期的なミーティングで進捗と課題を共有する
採用活動は、市場の動向や応募者の反応を見ながら、常に状況をアップデートしていく必要があります。
そのため、委託先とは週に一度、あるいは月に一度といった頻度で定例ミーティングの場を設けましょう。
応募数や選考通過率、内定承諾率といったデータを基に進捗状況を確認し、うまくいっている点や課題となっている点を共有します。
課題が見つかった場合は、その原因を分析し、次のアクションプランを共に協議することで、PDCAサイクルを効果的に回し、採用活動の精度を高めていきます。
よくあるご質問
Q1. 料金の相場はどのくらいですか?
A1. 料金はサービス内容や依頼する業務範囲によって大きく異なります。月額固定型で月数万円から数十万円、成果報酬型では採用した人材の年収の20%~35%程度が一般的です。まずは複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
Q2. どのくらいの期間から利用できますか?
A2. 3ヶ月や半年といった期間で契約するケースが多いですが、サービスによっては1ヶ月単位での利用や、特定のプロジェクト期間のみの契約も可能です。企業の採用計画に合わせて柔軟に対応してくれる会社を選ぶと良いでしょう。
Q3. 地方の企業の採用でも対応可能ですか?
A3. 多くのサービスがオンラインでの対応を基本としているため、全国どこの企業でも利用可能です。中には、特定の地域に強みを持つサービスもありますので、自社の所在地や採用エリアに応じて確認してみてください。
Q4. 採用の機密情報は守られますか?
A4. 信頼できるサービス会社は、契約時に必ず秘密保持契約(NDA)を締結します。候補者の個人情報や企業の採用情報など、機密情報の取り扱いについては事前にしっかりと確認しましょう。
Q5. 導入までのおおまかな流れを教えてください。
A5. 一般的には、問い合わせ後にヒアリングが行われ、採用課題に合わせた提案と見積もりが提示されます。内容に合意すれば契約となり、業務範囲や目標のすり合わせを行った上でサービス開始、という流れになります。
まとめ
採用業務支援サービスは、採用戦略の立案から実務の代行、入社後の定着支援まで、企業の採用活動を多角的にサポートする有効な手段です。
サービスを導入することで、専門的な知見を活用して採用力を強化できるほか、人事担当者がコア業務に集中できる環境を整え、採用コストの最適化も期待できます。
サービス選定の際は、自社の採用課題を明確にした上で、サービスの得意分野や支援範囲、料金体系、実績などを総合的に比較検討することが求められます。
導入後はサービス会社に任せきりにせず、主体的に連携して協働体制を築くことで、その効果を最大限に引き出せます。
採用業務支援とあわせて、採用ブランディングで成果を最大化。
Piicでは、採用戦略の実行を支えるだけでなく、企業の魅力を“伝わるかたち”にする採用ブランディングを行っています。
採用ピッチ資料・採用サイト・パンフレット・動画などを通じて、応募率や定着率の向上を実現。
業務効率化と同時に「選ばれる企業づくり」を進めませんか?








