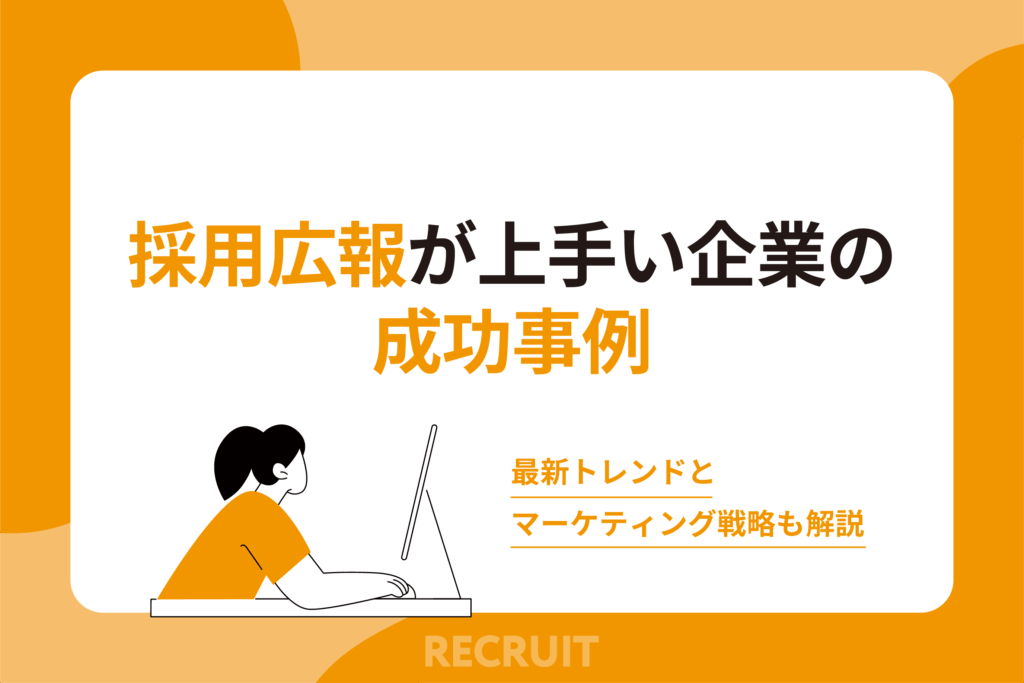
労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、企業が優秀な人材を獲得するためには、採用広報の強化が不可欠です。
本記事では、採用広報が上手い企業の成功事例を戦略別に解説します。
さらに、採用活動を成功に導くための最新トレンドや、マーケティングの視点を取り入れた具体的な戦略についても紹介しますので、自社の採用活動を見直すきっかけとしてご活用ください。

Index
-
なぜ今、採用広報が企業の成長に不可欠なのか?
-
企業の認知度が向上し優秀な人材の母集団が形成される
-
入社後のミスマッチを防ぎ定着率の向上が期待できる
-
採用活動におけるコストパフォーマンスを改善できる
-
採用広報が上手い企業の成功事例【戦略別に解説】
-
SNSを活用して企業文化や働く人の魅力を伝える事例
-
オウンドメディアで社員のリアルな声を届けファンを増やす事例
-
動画コンテンツで仕事内容や職場の雰囲気を伝える事例
-
採用ピッチ資料で事業の将来性やビジョンを明確に示す事例
-
採用広報を成功に導くための5つのステップ
-
Step1. どのような人材に情報を届けたいかターゲットを明確にする
-
Step2. 競合他社にはない自社ならではの魅力を言語化する
-
Step3. ターゲットに最も響く情報発信の媒体を選定する
-
Step4. 候補者の心を動かす魅力的なコンテンツを企画・制作する
-
Step5. 効果測定と改善を繰り返しコンテンツの質を高める
-
【2025年最新】採用広報で活用すべき主要な手法とトレンド
-
オウンドメディア(採用サイト・ブログ)で深い企業理解を促す
-
SNS(X, Instagram)で候補者と気軽にコミュニケーションを図る
-
動画(YouTubeなど)で社風や働く環境をリアルに伝える
-
採用ピッチ資料でデータに基づいた客観的な魅力をアピールする
-
音声メディア(Podcastなど)で移動中などの「ながら聞き」層にリーチする
-
採用広報の効果を最大化させる3つのコツ
-
経営層から現場社員まで全社を巻き込んで取り組む
-
企業のポジティブな面だけでなく課題やリアルな情報も発信する
-
短期的な成果を追わず中長期的な視点で継続的に運用する
-
よくあるご質問
-
Q1.採用広報を始めたいのですが、何から手をつければよいですか?
-
Q2.人手や予算が限られている場合、どの施策から始めるべきですか?
-
Q3.コンテンツのネタがすぐ尽きてしまいそうです。どうすればよいですか?
-
Q4.採用広報の効果はどのように測定すればよいですか?
-
Q5.炎上リスクが怖いのですが、SNS運用で気をつけることはありますか?
-
まとめ
なぜ今、採用広報が企業の成長に不可欠なのか?

現代の採用市場において、採用広報は単に求人情報を発信する以上の役割を担っています。
求職者が企業の情報を主体的に収集するようになった今、企業の理念や文化、働く環境といった情報を積極的に伝えることが、企業の持続的な成長に直結します。
採用広報の目的は、自社にマッチした人材を引きつけ、入社後の定着と活躍を促すことにあり、その重要性はますます高まっています。
企業の認知度が向上し優秀な人材の母集団が形成される
採用広報を通じて自社のビジョンや事業の魅力を継続的に発信することは、企業の認知度向上に直接的に貢献します。
特に、まだ知名度が高くない企業にとって、潜在的な候補者に自社を知ってもらう重要な機会となります。
これにより、転職市場に出てきたときや新卒のリクルート活動が本格化する前から、候補者の中に「気になる企業」として刷り込むことが可能です。
こうした採用ブランディング活動は、求人を出した際に、自社の価値観に共感する優秀な人材が集まりやすい質の高い母集団を形成する基盤となります。
入社後のミスマッチを防ぎ定着率の向上が期待できる
採用広報の大きなメリットの一つに、入社後のミスマッチを軽減できる点が挙げられます。
企業のウェブサイトやSNSを通じて、仕事のやりがいだけでなく、厳しさや組織が抱える課題といったリアルな情報を包み隠さず発信することで、候補者は企業文化や働き方を深く理解した上で応募を判断できます。
特に、キャリアチェンジを考える転職希望者は、次の職場選びで失敗したくないという思いが強いため、こうした透明性の高い情報は安心材料となります。
結果として、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップが減り、社員の定着率向上につながります。
採用活動におけるコストパフォーマンスを改善できる
採用広報に力を入れることは、長期的に見て採用コストの最適化に寄与します。
自社のメディアやSNSアカウントが育てば、有料の求人広告に頼らずとも候補者に直接アプローチできるチャネルを確保できます。
マーケティングフレームワークの4Pを採用に置き換えて考えると、自社の魅力(Product)を定義し、適切なチャネル(Place)で候補者に届ける(Promotion)ことで、効率的な採用活動が実現します。
外部サービスへの依存度を減らし、自社の資産として情報発信の基盤を築くことは、コストパフォーマンスの高い採用戦略の要となります。
採用広報が上手い企業の成功事例【戦略別に解説】

多くの企業が採用広報に取り組む中で、特に成果を上げている企業には共通した戦略が見られます。
ここでは、採用広報が上手い企業の成功例を「SNS活用」「オウンドメディア」「動画」「採用ピッチ資料」という4つの戦略別に分類し、それぞれの手法で人気を集める企業の具体的な取り組みを紹介します。
自社の課題やターゲットに合わせて、参考にできるポイントを見つけてみてください。
SNSを活用して企業文化や働く人の魅力を伝える事例
SNSは、企業の日常や働く人の素顔をリアルタイムに伝え、候補者との距離を縮めるのに最適なツールです。
例えば、株式会社カヤックは「面白法人」というコンセプトを体現するような、ユニークな社内制度やイベントの様子をSNSで積極的に発信しています。
社員が楽しんで働いている姿を伝えることで、企業文化に共感するファンを増やし、採用につなげています。
このように、テキストだけでは伝わりにくい社内の雰囲気や人間関係を、写真や短い動画を交えてカジュアルに発信することが、候補者の興味を引く鍵となります。
オウンドメディアで社員のリアルな声を届けファンを増やす事例
自社で運営するオウンドメディアは、より深く企業の魅力を伝えるためのプラットフォームとして機能します。
株式会社メルカリが運営する「mercan(メルカン)」では、社員一人ひとりの入社経緯や仕事への想い、挑戦や失敗談などが赤裸々に語られています。
このようなストーリー性のあるコンテンツは、候補者の共感を呼び、単なる応募者ではなく企業の「ファン」を育てる効果があります。
自社のメディアを持つことで、外部の媒体に左右されず、伝えたいメッセージを自由な形式で継続的に発信できる点が大きな強みです。
動画コンテンツで仕事内容や職場の雰囲気を伝える事例
動画は、オフィスの雰囲気や実際の業務内容といった情報を、テキストや静止画よりも直感的かつ効果的に伝えることができます。
株式会社クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」では、YouTubeチャンネルで社員の1日に密着したVlogや、仕事内容を紹介するインタビュー動画を公開しています。
これにより、候補者は自分がその会社で働く姿を具体的にイメージしやすくなります。
映像と音声を活用することで、社内の和やかな空気感や社員の人柄まで伝わり、応募前の不安を解消するのに役立っています。
採用ピッチ資料で事業の将来性やビジョンを明確に示す事例
採用ピッチ資料は、候補者に対して自社の事業内容、市場での立ち位置、将来のビジョンなどを論理的に説明するためのツールです。
株式会社SmartHRは、詳細な事業戦略や組織課題までオープンにした採用ピッチ資料を公開しており、多くの企業の参考となっています。
データや図を多用して客観的な情報を提供することで、候補者は企業の成長性と自身のキャリアパスを重ね合わせて検討できます。
特に、自社のビジョンに強く共感し、事業の成長に貢献したいと考える志向性の強い人材に響くアプローチです。
採用広報を成功に導くための5つのステップ

採用広報をこれから立ち上げる、あるいは既存の活動を見直したいと考えている担当者も多いかもしれません。
効果的な採用広報は、戦略に基づいた計画的な実行が不可欠です。
ここでは、採用広報を成功させるためのプロセスを以下5つのステップに分けて具体的に解説します。
Step1. どのような人材に情報を届けたいかターゲットを明確にする
Step2. 競合他社にはない自社ならではの魅力を言語化する
Step3. ターゲットに最も響く情報発信の媒体を選定する
Step4. 候補者の心を動かす魅力的なコンテンツを企画・制作する
Step5. 効果測定と改善を繰り返しコンテンツの質を高める
このステップに沿って進めることで、一貫性のあるメッセージを届け、採用成果の最大化を目指せます。
Step1. どのような人材に情報を届けたいかターゲットを明確にする
採用広報を始める最初のステップは、どのような人材に情報を届けたいのか、ターゲットを具体的に定めることです。
職種やスキルといった条件だけでなく、その人物が持つ価値観、仕事に求めるもの、情報収集に利用するメディアなどを詳細に設定した「ペルソナ」を描き出します。
ターゲットが明確になることで、発信するメッセージの内容やトーン、使用する媒体の選定が的確になり、情報が届きやすくなります。
採用活動全体の目標を達成するためにも、この初期設定が非常に重要です。
Step2. 競合他社にはない自社ならではの魅力を言語化する
次に、設定したターゲットに対して、自社の何をアピールするのかを明確にします。
これは「EVP(EmployeeValueProposition=従業員への価値提案)」と呼ばれ、給与や福利厚生といった待遇面に限らず、事業の社会貢献性、独自の組織文化、成長できる環境、魅力的な仲間といった要素が含まれます。
競合他社と比較した上で、自社ならではの魅力を洗い出し、分かりやすい言葉で言語化することが重要です。
この言語化された魅力が、今後の情報発信の核となり、一貫した採用ブランディングの基盤を築きます。
Step3. ターゲットに最も響く情報発信の媒体を選定する
自社の魅力が言語化できたら、それをどのような媒体で発信するかを選定します。
設定したターゲットが日常的にどのようなメディアに接触しているかを考慮することが重要です。
例えば、若手のビジネスパーソンであればX(旧Twitter)やnote、クリエイティブ職であればInstagramやBehanceといったように、ターゲット層に合わせて最適なプラットフォームを選択します。
一つの媒体に絞るのではなく、オウンドメディアを軸にSNSや動画などを組み合わせ、それぞれの特性を活かした情報発信を行うことで、より広い層にアプローチできます。
Step4. 候補者の心を動かす魅力的なコンテンツを企画・制作する
媒体が決まったら、いよいよコンテンツの企画・制作に入ります。
ここで重要なのは、企業側が伝えたいことだけを一方的に発信するのではなく、「候補者が何を知りたいか」という視点を持つことです。
社員がどのような想いで働いているか、プロジェクトの裏側でどんな苦労があったかなど、リアルで人間味のあるストーリーは候補者の共感を呼びます。
テキストだけでなく、写真やインフォグラフィック、動画など、媒体の特性に合わせて表現方法を工夫し、候補者の心を動かす魅力的なコンテンツを目指します。
Step5. 効果測定と改善を繰り返しコンテンツの質を高める
コンテンツを発信したら、その効果を測定し、改善につなげるプロセスが不可欠です。
各コンテンツの閲覧数や「いいね」の数、ウェブサイトへの流入数、そして最終的な応募数などを分析します。
どのテーマがターゲットに響いたのか、どのような表現が効果的だったのかをデータに基づいて振り返り、次の企画に活かしていくPDCAサイクルを回します。
特にリソースが限られているスタートアップ企業などでは、効果の高い施策に集中するためにも、この改善プロセスが採用広報の成果を大きく左右します。
【2025年最新】採用広報で活用すべき主要な手法とトレンド

採用市場は常に変化しており、候補者にアプローチする手法も進化し続けています。
自社の魅力を効果的に伝え、求める人材と出会うためには、最新のトレンドを理解し、多様な手法を戦略的に活用することが求められます。
ここでは、現代の採用広報において主流となっている以下5つの手法を紹介します。
・オウンドメディア(採用サイト・ブログ)
・SNS(X, Instagram)
・動画(YouTubeなど)
・採用ピッチ資料
・音声メディア(Podcastなど)
それぞれの特徴を理解し、自社に最適な組み合わせを見つけるための参考にしてください。
オウンドメディア(採用サイト・ブログ)で深い企業理解を促す
オウンドメディアは、企業が伝えたい情報を自由な形式で、かつ詳細に発信できる点が最大の強みです。
採用サイトやブログを通じて、事業内容やビジョン、社員インタビュー、独自のカルチャーなどを多角的に紹介することで、候補者は企業について深く理解できます。
コンテンツを継続的に蓄積していくことで、企業のブランディング資産となり、検索エンジンからの流入も期待できます。
時間をかけて自社の魅力を伝え、候補者の入社意欲を醸成する上で中心的な役割を担う手法です。
SNS(X, Instagram)で候補者と気軽にコミュニケーションを図る
X(旧Twitter)やInstagramといったSNSは、リアルタイム性と拡散力に優れており、候補者との心理的な距離を縮めるのに効果的です。
社員の日常や社内イベントの様子などをカジュアルに投稿することで、企業の「素の姿」を見せ、親近感を持ってもらえます。
また、「いいね」やコメント機能を通じて候補者と直接コミュニケーションをとることも可能です。
こうした双方向のやり取りを重ねることで、潜在的な候補者を企業のファンに変え、将来的な応募につなげていくことができます。
動画(YouTubeなど)で社風や働く環境をリアルに伝える
動画コンテンツは、文字や写真だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や人間関係を、視覚と聴覚に訴えかけることでリアルに伝達できます。
オフィスを紹介するルームツアー動画や、社員の一日に密着するVlog、複数の社員による座談会など、企画次第で様々な魅力を発信可能です。
候補者は動画を見ることで、自分がその会社で働く姿をより具体的に想像できるようになり、応募へのハードルが下がります。
YouTubeなどのプラットフォームを活用すれば、幅広い層にリーチすることもできます。
採用ピッチ資料でデータに基づいた客観的な魅力をアピールする
採用ピッチ資料は、候補者に向けて自社の事業戦略や市場での優位性、組織文化などを体系的にまとめた説明資料です。
特に、企業の成長性や将来性を重視する候補者に対し、データやロジックを用いて客観的な魅力を伝えるのに非常に有効です。
この資料をウェブサイトなどで公開することは、情報の透明性が高い企業であるという印象を与え、候補者からの信頼を得ることにもつながります。
ミッションやビジョンへの共感を促し、志望度の高い人材を引きつけます。
音声メディア(Podcastなど)で移動中などの「ながら聞き」層にリーチする
近年、新たな採用広報の手法として注目されているのがPodcastなどの音声メディアです。
通勤中や運動中といった「ながら時間」に情報をインプットする層にアプローチできるのが大きな特徴です。
社員同士の対談形式で仕事の裏話を語ったり、専門知識を持つ社員が業界のトレンドを解説したりすることで、企業のカルチャーや専門性を伝えることができます。
声を通じて発信される情報は、親近感が湧きやすく、テキストや動画とは違った形で企業のファンを増やす可能性があります。
採用広報の効果を最大化させる3つのコツ

採用広報の施策を実行するだけでは、期待した効果が得られないこともあります。
情報発信の効果を最大化し、採用成功につなげるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、採用広報の質を高め、他社との差別化を図るための3つのコツを紹介します。
これらの点を意識することで、より戦略的で一貫性のある広報活動を展開できます。
経営層から現場社員まで全社を巻き込んで取り組む
採用広報は人事部門だけの仕事ではありません。
経営者が自らの言葉でビジョンや事業への想いを語り、現場の社員が日々の仕事のやりがいやリアルな働き方を発信することで、コンテンツに深みと信頼性が増します。
全社が一丸となって採用に取り組む姿勢は、候補者にとって大きな魅力となります。
社員が自社の広報活動に協力しやすい雰囲気を作ったり、コンテンツ作成のプロセスに巻き込んだりするなど、組織全体で採用を盛り上げていく仕組みづくりが求められます。
企業のポジティブな面だけでなく課題やリアルな情報も発信する
企業の魅力的な側面ばかりを強調するのではなく、現在抱えている課題や仕事の厳しさといったネガティブになりうる情報も正直に開示することが、かえって候補者からの信頼を高めます。
完璧な企業は存在しないことを候補者も理解しており、課題に対して会社がどのように向き合い、改善しようとしているのかという姿勢を示すことが重要です。
このようなオープンな情報発信は、入社後のミスマッチを防ぎ、自社の価値観に本当にフィットする人材を引き寄せることにつながります。
短期的な成果を追わず中長期的な視点で継続的に運用する
採用広報の効果は、すぐに目に見える形で現れるとは限りません。
企業の認知度向上やブランドイメージの構築には時間がかかります。
そのため、応募者数の増減といった短期的な指標に一喜一憂するのではなく、中長期的な視点で腰を据えて情報発信を続けることが不可欠です。
地道な活動の積み重ねが、やがて企業のファンを増やし、広告などに頼らなくても自然と人が集まる状態を作り出します。
継続こそが、採用広報を成功させる最大の鍵となります。
よくあるご質問
Q1.採用広報を始めたいのですが、何から手をつければよいですか?
A1.まずは「どのような人材を採用したいか」というターゲット(ペルソナ)を明確にすることから始めましょう。ターゲットが決まれば、その人に何を伝え、どの媒体でアプローチすべきかという戦略の軸が定まります。
Q2.人手や予算が限られている場合、どの施策から始めるべきですか?
A2.まずは費用をかけずに始められるSNSアカウントの開設がおすすめです。X(旧Twitter)などで、社内の日常や働く人の様子を発信するだけでも、企業の雰囲気を伝える第一歩になります。
Q3.コンテンツのネタがすぐ尽きてしまいそうです。どうすればよいですか?
A3.社員に目を向けるのが一番です。新入社員のインタビューや、特定のプロジェクトを担当したチームの座談会、社員のランチ紹介など、働く「人」に焦点を当てるとコンテンツのアイデアは無限に広がります。
Q4.採用広報の効果はどのように測定すればよいですか?
A4.各コンテンツの閲覧数やエンゲージメント率(いいね、シェア数)といった定量的な指標に加え、面接で「何を見て応募しましたか?」と質問し、どの媒体が応募につながっているかを把握する質的な分析も重要です。
Q5.炎上リスクが怖いのですが、SNS運用で気をつけることはありますか?
A5.複数人でのダブルチェック体制を敷き、不適切な表現がないかを確認することが基本です。また、政治や宗教など、意見が分かれる話題には触れないようにし、誠実で一貫性のある姿勢で情報発信を心がけてください。
まとめ
採用広報は、企業の持続的な成長を支える重要な経営課題です。
成功している企業は、自社が求める人材を明確に定義し、そのターゲットに響く魅力を、SNSやオウンドメディアといった多様なチャネルを通じて継続的に発信しています。
重要なのは、単に情報を発信するだけでなく、企業のリアルな姿を伝え、候補者との信頼関係を築くことです。
本記事で紹介した事例やステップを参考に、自社ならではの採用広報戦略を構築し、実践してみてください。
また、本文でも触れた「採用ピッチ資料」は、採用広報の効果を高める実践的なツールとして特に有効です。
Piicでは、採用広報戦略と連動したピッチ資料の企画・デザインを一貫してご提供し、情報発信をより戦略的に、そして候補者に響く形に進化させるお手伝いをしています。








