
企業の成長を左右する採用活動において、客観的で明確な「採用基準」の設定は不可欠です。
適切な採用基準の決め方と作り方を理解することで、自社にマッチした優秀な人材を効率的に見つけ出せます。
本記事では、採用基準を設けるメリットから、具体的な作り方のステップ、さらには新卒採用や中途採用の例を交えながら、実践的なポイントを解説します。

Index
-
そもそも採用基準とは何か?
-
採用基準を設けることで得られる3つのメリット
-
メリット1:面接官による評価のブレをなくせる
-
メリット2:候補者と企業のミスマッチを防止できる
-
メリット3:採用活動の効率化とスピードアップにつながる
-
採用基準の作り方を6つのステップで解説
-
ステップ1:経営層や役員と採用方針を合意する
-
ステップ2:現場で活躍している社員の特徴を分析する
-
ステップ3:求める人物像(ペルソナ)を具体的に設定する
-
ステップ4:評価項目を洗い出して優先順位を決める
-
ステップ5:各評価項目に対する具体的な判断基準を作成する
-
ステップ6:完成した採用基準を面接官など関係者全員で共有する
-
【項目例】採用基準に盛り込みたい評価項目
-
主体性やチャレンジ精神
-
コミュニケーション能力
-
論理的思考力や課題解決能力
-
誠実さや協調性
-
企業理念やビジョンへの共感度
-
【新卒・中途別】採用基準を設定するときのポイント
-
新卒採用では将来性(ポテンシャル)を重視する
-
中途採用では即戦力となるスキルや経験を確認する
-
採用基準を決めるときに注意すべき3つのこと
-
注意点1:誰が評価しても同じ結果になる客観的な基準にする
-
注意点2:就職差別につながる項目は含めない
-
注意点3:高すぎる理想を求めず現実的な基準を設定する
-
よくあるご質問
-
Q1.採用基準は一度決めたら変更しない方が良いですか?
-
Q2.採用基準の評価シートは作成すべきでしょうか?
-
Q3.現場の部署と人事部で求める人物像が違う場合、どうすれば良いですか?
-
Q4.採用基準の項目が多すぎて、面接時間内に確認しきれません。
-
Q5.採用基準を満たす応募者がなかなか現れません。
-
まとめ
-
採用基準を「言語化」したら、次は「共感を生む発信」へ
そもそも採用基準とは何か?

採用基準とは、企業が人材を採用する際に用いる、候補者の能力やスキル、人物像などを評価するための共通の「ものさし」です。
この基準があることで、面接官の主観に頼らず、一貫性のある客観的な評価が可能となります。
自社の経営戦略や事業計画に基づいて必要な人材要件を明確化し、採用活動に関わる全員が共通認識を持つために、採用基準の策定には高い必要性があります。
採用基準を設けることで得られる3つのメリット

明確な採用基準を設けることは、採用活動の質を向上させ、多くの利点をもたらします。
面接官ごとの評価のばらつきをなくし、公平な選考を実現できるだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、採用活動全体の効率化にも寄与します。
ここでは、採用基準がもたらす具体的な3つのメリットについて、それぞれ詳しく見ていきます。
メリット1:面接官による評価のブレをなくせる
採用活動では、人事担当者だけでなく現場の管理職など、複数の面接官が選考に関わることが一般的です。
その際、明確な採用基準がないと、各面接官の個人的な経験や主観に基づいて評価してしまい、候補者によって評価が大きくブレる可能性があります。
共通の採用基準を設けることで、どの面接官が面接を担当しても一貫した視点で評価を下せるようになり、選考の公平性と納得感を高められます。
これにより、組織全体として統一感のある採用が実現します。
メリット2:候補者と企業のミスマッチを防止できる
採用基準が曖昧なまま選考を進めると、スキルや能力は高いものの、企業の文化や価値観に合わない人材を採用してしまうリスクが高まります。
このような採用のミスマッチは、早期離職や組織のパフォーマンス低下につながる大きな要因です。
求める人物像や価値観を具体的に採用基準に落とし込むことで、自社のカルチャーにフィットする候補者を見極めやすくなります。
結果として、入社後の定着率が向上し、長期的に企業へ貢献してくれる人材の獲得が期待できます。
メリット3:採用活動の効率化とスピードアップにつながる
明確な採用基準は、選考プロセスにおける判断の迅速化をもたらします。
書類選考や面接の場で、基準に照らし合わせることで合否の判断に迷う時間が減り、採用活動全体のスピードアップが図れます。
近年の採用市場は変化が激しく、優秀な人材ほど複数の企業からアプローチを受けるため、迅速な意思決定は競争優位性を保つ上で非常に重要です。
判断基準が明確になることで、採用に関わる全てのメンバーの業務負担が軽減され、活動全体の効率化が進みます。
採用基準の作り方を6つのステップで解説

効果的な採用基準は、思いつきではなく、体系的なプロセスを経て作られます。
まず経営層と採用の方向性をすり合わせ、次に現場で活躍する社員の特徴を分析することから始めます。
その情報をもとに具体的な人物像を設定し、評価項目と優先順位を決定します。
最後に、誰が評価してもブレない判断基準を作成し、関係者全員で共有するという流れが重要です。
ステップ1:経営層や役員と採用方針を合意する
ステップ2:現場で活躍している社員の特徴を分析する
ステップ3:求める人物像(ペルソナ)を具体的に設定する
ステップ4:評価項目を洗い出して優先順位を決める
ステップ5:各評価項目に対する具体的な判断基準を作成する
ステップ6:完成した採用基準を面接官など関係者全員で共有する
上記の6つのステップを詳しく解説します。
ステップ1:経営層や役員と採用方針を合意する
採用活動は、企業の将来を担う人材を確保するための重要な経営戦略の一部です。
そのため、まずは経営層や役員と今後の事業計画や組織のビジョンについて深く議論し、どのような人材が企業の成長に必要かをすり合わせます。
中期経営計画や新規事業の展望などを踏まえ、全社的な視点から採用の方針について合意形成を図ることが最初のステップです。
この段階で方向性を固めておくことで、採用活動全体に一貫性が生まれ、その後のプロセスが円滑に進みます。
ステップ2:現場で活躍している社員の特徴を分析する
次に、自社で既に高いパフォーマンスを発揮している社員、いわゆる「ハイパフォーマー」が持つ共通の特徴を分析します。
営業成績が優秀な社員や、チームに良い影響を与えている社員などを対象に、ヒアリングやアンケート調査を実施し、彼らの行動特性、思考パターン、スキル、価値観などを具体的に洗い出します。
この客観的なデータは、理想論ではない、現実に即した「求める人物像」を定義するための重要な基盤となります。
この調査を通じて、自社で活躍できる人材の解像度を高めます。
ステップ3:求める人物像(ペルソナ)を具体的に設定する
経営方針とハイパフォーマー分析から得られた情報をもとに、採用したい人物像、すなわち「ペルソナ」を具体的に設定します。
年齢や性別といった表面的な情報だけでなく、価値観、性格、保有スキル、行動特性など、人物の内面にまで踏み込んで詳細に描き出します。
「コミュニケーション能力が高い」といった抽象的な表現ではなく、「複数の部署と連携し、プロジェクトを円滑に進める調整力を持つ」のように、具体的な行動レベルで定義することが重要です。
このペルソナが、後の評価項目を作成する際の明確な指針となります。
ステップ4:評価項目を洗い出して優先順位を決める
設定したペルソナ像を基に、候補者を評価するための具体的な項目を洗い出します。
スキル、経験、知識、資格といった能力面だけでなく、協調性、主体性、誠実さといった人柄や価値観に関する項目もリストアップします。
洗い出した全ての項目を完璧に満たす人材を見つけるのは困難なため、それぞれの項目について、「絶対に必要(Must)」な条件と、「あると望ましい(Want)」条件に分類し、優先順位を明確に付けます。
これにより、選考過程で判断に迷った際の客観的な評価基準となります。
ステップ5:各評価項目に対する具体的な判断基準を作成する
洗い出して優先順位を付けた評価項目それぞれについて、誰が評価しても同じ判断ができるような具体的な基準を作成します。
例えば、「主体性」という項目であれば、「A:自ら課題を発見し、解決策を提案・実行した経験がある」「B:指示された課題に対し、自ら工夫して取り組んだ経験がある」「C:指示待ちで行動することが多い」のように、評価を3~5段階に分け、それぞれのレベルの定義を言語化します。
これにより、面接官の主観による評価のばらつきを最小限に抑えることが可能になります。
ステップ6:完成した採用基準を面接官など関係者全員で共有する
作成した採用基準は、採用活動に関わる全ての人員で共有し、目線を合わせることが不可欠です。
人事担当者だけでなく、面接官を務める現場社員や役員も対象に、採用基準の内容や各項目の評価方法について説明会や研修を実施します。
なぜこの基準が設けられたのかという背景から丁寧に説明し、評価基準に対する認識のズレをなくします。
関係者全員が同じ「ものさし」を持って選考に臨むことで、初めて採用基準が機能し、組織として一貫した採用活動が実現できます。
【項目例】採用基準に盛り込みたい評価項目
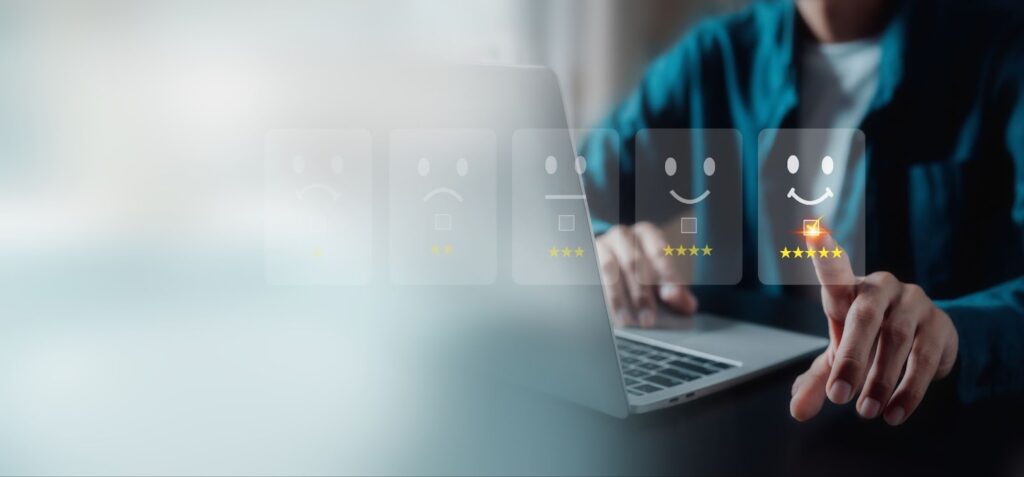
採用基準を具体化する際には、どのような評価項目を設けるかが重要になります。
企業の理念や求める人物像によって項目は異なりますが、多くの企業で共通して重視される要素が存在します。
ここでは、採用基準に盛り込むと良い評価項目の一般的な例を次のいくつか紹介します。
- 主体性やチャレンジ精神
- コミュニケーション能力
- 論理的思考力や課題解決能力
- 誠実さや協調性
- 企業理念やビジョンへの共感度
これらを参考に、自社の状況に合わせて項目をカスタマイズしてみてください。
主体性やチャレンジ精神
指示された業務をこなすだけでなく、自ら課題を見つけ、その解決に向けて行動できる主体性は、多くの企業で高く評価されます。
過去の経験において、現状に満足せず、より良くするために自ら目標を立てて挑戦したエピソードがあるかを確認します。
新しい知識やスキルを学ぶことへの意欲や、困難な状況でも前向きに取り組む姿勢も重要な評価ポイントです。
こうした資質は、入社後に組織の成長を牽引する原動力となり得るため、変化の激しい時代において特に重視される傾向にあります。
コミュニケーション能力
組織で成果を出すためには、他者と円滑に意思疎通を図るコミュニケーション能力が欠かせません。
この能力は、単に話が上手いことだけを指すのではありません。
相手の意図を正確に汲み取る「傾聴力」、自分の考えを論理的かつ分かりやすく伝える「説明力」、そして意見が対立した際に着地点を見出す「調整力」など、多角的な視点で評価する必要があります。
面接での対話を通じて、質問の意図を正しく理解し、的確に返答できるかどうかも、この能力を測る上での重要な指標となります。
論理的思考力や課題解決能力
物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える論理的思考力は、あらゆる業務の土台となる基本的な能力です。
この能力が高い人材は、複雑な問題に直面した際にも、原因を冷静に分析し、本質的な課題を特定できます。
そして、その課題に対して効果的な解決策を立案し、実行に移すことができます。
面接では、過去の成功体験や失敗体験について「なぜそうなったのか」「どのように対処したのか」を深掘りする質問をすることで、候補者の思考プロセスや問題解決能力のレベルを測ります。
誠実さや協調性
チームの一員として周囲と協力し、組織全体の目標達成に貢献できる協調性は、円滑な組織運営において不可欠な要素です。
自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見にも耳を傾け、尊重する姿勢が求められます。
また、仕事に対して真摯に向き合い、責任感を持って取り組む誠実さは、同僚や取引先からの信頼を獲得する上で基盤となります。
グループディスカッションや過去のチームでの経験に関する質問を通じて、自己中心的な姿勢がなく、組織全体の利益を考えて行動できる人物かを見極めます。
企業理念やビジョンへの共感度
候補者が企業の理念やビジョン、事業内容にどれだけ共感しているかは、入社後のモチベーション維持や定着に大きく関わります。
スキルや経験がどんなに優れていても、企業の目指す方向性や価値観と合わなければ、長期的に活躍することは難しいでしょう。
志望動機を尋ねる際には、単に企業の知名度や待遇面だけでなく、事業のどのような点に魅力を感じ、自身の能力をどう活かしていきたいと考えているのかを具体的に語れるかを確認します。
企業への深い理解と共感が、入社後の活躍の土台となります。
【新卒・中途別】採用基準を設定するときのポイント
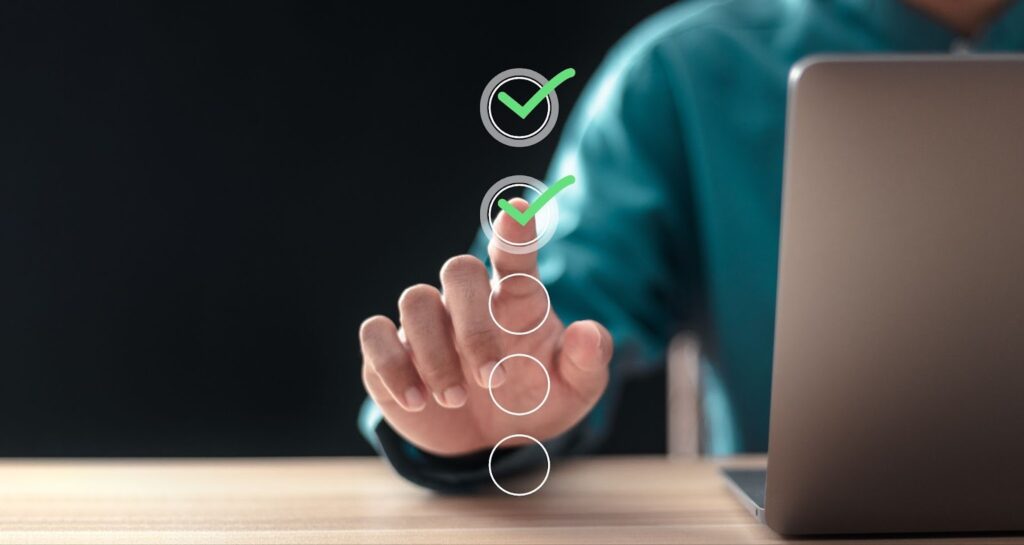
採用基準は、全ての候補者に一律に適用するのではなく、対象に応じて柔軟に設定する必要があります。
社会人経験のない新卒学生と、豊富な実務経験を持つ中途採用者とでは、評価すべきポイントが大きく異なります。
ここでは、新卒採用と中途採用、それぞれの特性を踏まえた上で、採用基準を設定する際の重要なポイントについて解説します。
新卒採用では将来性(ポテンシャル)を重視する
新卒採用においては、候補者に実務経験がないことが前提となるため、現時点でのスキルや能力よりも、将来的にどれだけ成長し、活躍してくれるかという「ポテンシャル」を重視します。
新しいことを素直に吸収する学習意欲、困難な課題にも粘り強く取り組む姿勢、周囲を巻き込みながら目標を達成しようとする力などを評価の軸に据えます。
学生時代の学業や部活動、アルバイトといった経験を通じて、どのような考えで行動し、何を学んだのかを深掘りすることで、その人物が持つ潜在的な能力や伸びしろを見極めることが重要です。
中途採用では即戦力となるスキルや経験を確認する
中途採用の主な目的は、特定のポジションにおける欠員補充や事業拡大に伴う専門人材の確保です。
そのため、中途の候補者には入社後すぐに活躍できる「即戦力性」が求められます。
採用基準では、募集職種で必要とされる専門的なスキルや知識、過去の実務経験を最優先の評価項目とします。
職務経歴書の内容を基に、これまでどのような役割を担い、どのような実績を上げてきたのかを具体的に確認し、その経験が自社でどのように活かせるのかを慎重に見極める必要があります。
採用基準を決めるときに注意すべき3つのこと

採用基準を策定する際には、いくつかの注意点が存在します。
これらを軽視すると、基準が形骸化してしまったり、法的な問題に発展したりする可能性があります。
誰が評価しても同じ結果になる客観性、就職差別につながらない公平性、そして高すぎる理想を追わない現実性の3つの観点から、採用基準を決める上で留意すべきことを説明します。
注意点1:誰が評価しても同じ結果になる客観的な基準にする
採用基準は、面接官の主観や印象に左右されることなく、誰が評価しても一貫した結果が得られる客観的なものである必要があります。
「リーダーシップがある」といった抽象的な項目ではなく、「過去に3人以上のチームを率いて目標を達成した経験がある」のように、具体的な行動や事実に基づいて判断できるレベルまで落とし込みます。
各評価項目に段階的な評価尺度(例:S,A,B,C)を設け、それぞれの定義を明確にしておくことで、評価の属人化を防ぎ、より公平性の高い選考が実現できます。
注意点2:就職差別につながる項目は含めない
採用選考では、応募者の適性や能力とは無関係な事柄を理由に採否を判断してはなりません。
特に、本籍・出生地、家族構成、宗教、支持政党などに関する項目は、就職差別につながる可能性があるため、採用基準に含めることは法律で禁止されています。
同様に、これらを不採用基準とすることも認められません。
採用基準を作成する際には、厚生労働省が示すガイドラインなどを参照し、応募者の基本的人権を尊重した公正な選考となるよう、細心の注意を払う必要があります。
注意点3:高すぎる理想を求めず現実的な基準を設定する
求める人物像を追求するあまり、全ての項目で最高レベルを求めるなど、採用基準が非現実的なほど高くなってしまうケースがあります。
理想が高すぎると、該当する候補者が市場にほとんど存在せず、結果的に採用活動が難航してしまいます。
自社の採用力やターゲットとなる人材市場の状況を客観的に分析し、達成可能な範囲で基準を設定することが肝要です。
絶対に譲れない必須条件(Must)と、あれば尚良い歓迎条件(Want)を明確に区別し、優先順位を付けることで、理想と現実のバランスが取れた採用基準となります。
よくあるご質問

Q1.採用基準は一度決めたら変更しない方が良いですか?
A1.いいえ、採用基準は定期的な見直しが必要です。事業内容の変化、市場の動向、採用活動の結果などを踏まえ、常に最適な基準となるようアップデートしていくことが望ましいです。
Q2.採用基準の評価シートは作成すべきでしょうか?
A2.作成することを強く推奨します。評価シートを用いることで、面接官は基準に沿って抜け漏れなく評価でき、評価の客観性や公平性を担保しやすくなります。また、面接官同士での情報共有もスムーズになります。
Q3.現場の部署と人事部で求める人物像が違う場合、どうすれば良いですか?
A3.まずは双方の意見をしっかりとヒアリングし、なぜその人物像を求めるのか、背景にある課題や期待を共有することが重要です。その上で、経営方針や全社的な視点に立ち返り、議論を通じてすり合わせを行い、着地点を見つけます。
Q4.採用基準の項目が多すぎて、面接時間内に確認しきれません。
A4.全ての項目を一度の面接で確認する必要はありません。書類選考、一次面接、二次面接、最終面接など、選考のフェーズごとに確認すべき項目を分担させましょう。段階的に候補者の適性を見極めることで、効率的かつ多角的な評価が可能になります。
Q5.採用基準を満たす応募者がなかなか現れません。
A5.まずは設定した採用基準が現実的かを見直しましょう。特に必須条件が高すぎないかを確認します。基準に問題がない場合は、募集媒体やスカウトのターゲット層がずれている可能性も考えられるため、採用手法そのものの見直しも検討します。
まとめ
採用基準の決め方に関する解説のまとめとして、その重要性を改めて確認します。
客観的で明確な採用基準は、面接官による評価のブレをなくし、候補者と企業のミスマッチを防ぎ、採用活動全体の効率化を実現するための根幹です。
作成にあたっては、経営層との方針合意から始め、現場で活躍する社員の分析、具体的なペルソナ設定、評価項目の優先順位付けといったステップを着実に踏むことが求められます。
また、新卒と中途で重視する点を変えたり、差別的な項目を含めないように注意したりするなど、状況に応じた適切な運用が不可欠です。
採用基準を「言語化」したら、次は「共感を生む発信」へ
せっかく定義した採用基準も、社外に伝わらなければ意味がありません。
Piicでは、企業が持つ“採用の軸”を言語化し、デザインとストーリーで表現する採用ブランディングを支援しています。
採用ピッチ資料、採用サイト、動画、パンフレットなど、
「どんな人と働きたいか」を一貫して伝えるクリエイティブをトータルで制作。
理念やカルチャーに共感する人材を惹きつけ、定着までつなげます。








