
企業の成長には優秀な人材の確保が不可欠ですが、採用活動には多大なコストがかかります。採用単価とは、一人を採用するためにかかる費用を指します。
この採用単価の計算方法を理解し、現在の平均相場を把握することは、採用コストを見直し、費用対効果の高い採用活動を実現するための第一歩となるでしょう。
本記事では、採用単価を下げるための具体的な方法についても詳しく解説していきます。
コストを抑えて採用効率を向上させたい方は以下の記事もチェックしてみてください。
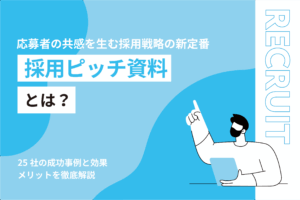
Index
-
そもそも採用単価とは?人材一人を採用するためにかかる費用のこと
-
採用単価を算出するための計算方法
-
採用単価の内訳①:外部コスト
-
採用単価の内訳②:内部コスト
-
【新卒・中途別】一人あたりの採用単価の平均相場
-
新卒採用における一人あたりの平均採用単価
-
中途採用における一人あたりの平均採用単価
-
【企業規模別】通年でかかる採用コストの平均額
-
採用単価を効果的に下げるための8つのアプローチ
-
社員の紹介で採用するリファラル採用を導入する
-
企業から候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティング
-
SNSを活用したソーシャルリクルーティングで接点を作る
-
自社の採用サイトを強化して情報発信する
-
採用広報に力を入れて企業の魅力を伝える
-
採用ターゲットの条件を明確にしてミスマッチを減らす
-
選考フローを見直して社内コストを削減する
-
カジュアル面談で入社後のギャップをなくす
-
採用単価の削減で失敗しないための注意点
-
コスト削減だけでなく費用対効果も重視する
-
自社が本当に求める人材像を明確に定義する
-
入社後の育成や定着支援にも力を入れる
-
まとめ
そもそも採用単価とは?人材一人を採用するためにかかる費用のこと
採用単価とは、企業が一人あたりの人材を採用するために投じる全ての費用を指します。
これは外部に支払うコストだけでなく、採用活動に携わる社員の人件費や、会社説明会の会場費なども含まれます。
この採用単価を正確に把握することは、採用戦略を立てる上で非常に重要な指標となります。
採用単価を算出するための計算方法
採用単価を計算する際には、「採用コストの総額」を「採用人数」で割るという計算方法を用います。
計算式にすると、採用単価=採用コストの総額÷採用人数となります。
この計算を行うことで、一人あたりの採用にどのくらいの費用がかかっているのかを明確にできます。
採用コストの総額には、求人掲載費用、人材紹介手数料、会社説明会の費用、採用担当者の人件費など、採用活動にかかるすべての費用を含めるようにしましょう。
採用単価の内訳①:外部コスト
採用単価を構成する外部コストとは、採用活動において外部のサービスや媒体を利用する際に発生する費用を指します。
具体的には、求人サイトへの掲載料や、人材紹介会社へ支払う成功報酬などがこれに該当します。
広く知られている求人媒体としては、マイナビやリクルートなどの総合型求人サイト、Indeedのようなアグリゲート型求人サイト、Wantedlyのようなブランディング採用に特化したサイトなどがあり、それぞれ掲載費用や利用料が異なります。
これらの費用は、採用単価に大きく影響を与える要素の一つです。
採用単価の内訳②:内部コスト
採用単価を構成する内部コストとは、企業内で採用活動を進めるために発生する費用を指します。これには、採用担当の社員の人件費や、求人票の作成にかかる費用、面接会場の準備費用、内定者への連絡費などが含まれます。
例えば、会社説明会のために社員が準備に時間を費やしたり、遠方から来る候補者の交通費を企業が負担したりする場合も内部コストに分類されます。
内部コストは外部に直接支払う費用ではないため見落とされがちですが、採用単価を正確に把握するためには、これらの隠れたコストも適切に計算に含めることが重要です。
【新卒・中途別】一人あたりの採用単価の平均相場
一人あたりの採用単価は、採用する人材が新卒か中途かによって大きく変動します。
また、職種や企業規模によっても平均相場は異なるため、自社の状況と照らし合わせて参考にすることが重要です。
ここでは、新卒採用と中途採用それぞれの平均採用単価について詳しく見ていきましょう。
新卒採用における一人あたりの平均採用単価
新卒採用における一人あたりの平均採用単価は、一般的に中途採用よりも高くなる傾向があります。新卒採用の一人あたりにかかる採用費用の平均額は93.6万円という調査結果があります。企業規模別にみると、従業員数が多い企業ほど採用コストが高い傾向にありますが、一人あたりの採用単価も高くなるとは限りません。また、上場企業と未上場企業でも採用コストの平均は異なり、上場企業の方が高くなる傾向にあります。
これは、合同企業説明会の出展費用、大学への広報活動、長期インターンシップの受け入れ費用など、選考が本格化する前から様々なコストが発生するためです。特に、多くの学生にアプローチするための広報活動やイベント開催にかかる費用が、採用単価を押し上げる要因となることがあります。
中途採用における一人あたりの平均採用単価
中途採用における一人あたりの平均採用単価は、新卒採用と比較して一般的に高い傾向にありますが、職種や採用手法によって大きく変動します。例えば、2019年のデータでは、新卒採用の平均採用単価が93.6万円であったのに対し、中途採用は103.3万円でした。
求人広告を利用する場合と人材紹介会社を利用する場合では、単価に大きな差が生じます。特に専門性の高い職種や、市場に希少なスキルを持つ人材の採用では、人材紹介の手数料が高額になる傾向があり、結果として採用単価も上昇する可能性があります。
中途採用では、即戦力となる人材を獲得できるメリットがある一方で、採用コストを抑えるためには、複数の採用手法を検討し、自社に最適なアプローチを選択することが重要です。
【企業規模別】通年でかかる採用コストの平均額
企業が通年でかける採用コストは、企業の規模によって大きく異なります。
中小企業では、採用専門の部署を設けていない場合も多く、採用活動にかけられる予算も大企業に比べて限られていることが一般的です。
一方で、大企業は新卒採用から中途採用まで多岐にわたる採用活動を展開し、大規模なプロモーションや採用イベントを実施するため、採用コストの総額は高額になります。
最新のデータを見ると、企業規模が大きくなるほど採用コストも増加する傾向が表れています。
この表は、あくまで平均額であるため、自社の採用目標や採用計画に合わせて費用を見積もることが重要です。
採用単価を効果的に下げるための8つのアプローチ
採用単価を下げるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
職種別、例えば営業職や建築、製造、エンジニアなど、特定のスキルが求められる職種においても、以下に挙げる8つの方法を実践することで、無駄なコストを削減し、採用効率を高めることができます。
正社員だけでなく、アルバイトやパートの採用においても有効な手段となるでしょう。
社員の紹介で採用するリファラル採用を導入する
リファラル採用とは、社員から友人や知人を紹介してもらい、採用につなげる手法です。
この採用方法の最大のメリットは、採用コストを大幅に抑えられる点にあります。
求人広告や人材紹介会社に支払う費用が発生しないため、一人あたりの採用単価を効果的に下げることが可能です。
また、紹介された候補者は、すでに社内の文化や働き方をある程度理解しているため、入社後のミスマッチが少なく、定着率が高い傾向にあることも利点です。
企業から候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者を探し、直接アプローチする採用手法です。一般的な求人媒体への掲載や人材紹介サービスを利用するよりも、採用コストを削減できる可能性があります。
特に、特定のスキルや経験を持つ人材を求める場合、ピンポイントでアプローチできるため、効率的な採用につながります。
企業側が主体的に採用活動を進めることで、自社の魅力をより深く伝える機会も増え、候補者とのミスマッチを防ぐことにもつながるでしょう。
SNSを活用したソーシャルリクルーティングで接点を作る
ソーシャルリクルーティングとは、FacebookやX、LinkedInなどのSNSを活用して採用活動を行う手法です。
求人情報を発信するだけでなく、企業の日常や社員の働く様子を投稿することで、企業の魅力を多角的にアピールできます。
SNSは多くのユーザーが利用しているため、潜在的な候補者との接点を広げ、低コストで広範囲に情報を届けることが可能です。
また、候補者からの直接的な問い合わせや応募を受け付けることで、採用プロセスを簡素化し、結果的に採用単価の削減にも貢献します。
自社の採用サイトを強化して情報発信する
自社の採用サイトを強化することは、採用単価の削減に大きく貢献します。
採用サイトは、企業が伝えたい情報を自由に発信できるため、求人媒体では伝えきれない企業の文化や働きがい、社員の声を詳細に伝えることができます。
魅力的な採用サイトを構築し、SEO対策を行うことで、検索エンジンからの流入を増やし、潜在的な候補者へのリーチを拡大することが可能です。
これにより、高額な求人広告費を削減し、直接応募を促すことで、一人あたりの採用コストを抑えることができます。
採用広報に力を入れて企業の魅力を伝える
採用広報に力を入れることは、単に求人情報を発信するだけでなく、企業の魅力や働く環境を積極的に社会に伝える活動です。これにより、企業の認知度とブランドイメージを高め、応募者数を増やす効果が期待できます。
採用イベントの開催、ブログやSNSでの情報発信、社員インタビュー記事の公開などを通じて、企業の文化やビジョンを具体的に伝えることで、求職者の興味を引きつけ、自社への入社意欲を高めることができます。
結果として、人材紹介サービスへの依存度を減らし、採用単価の削減につながるでしょう。
採用ターゲットの条件を明確にしてミスマッチを減らす
採用ターゲットの条件を明確にすることは、採用単価を削減する上で非常に重要です。
求める人材像が曖昧だと、多くの応募者の中から適切な候補者を見つけるのに時間がかかり、選考コストが増大します。
ミスマッチによる早期離職は、再び採用活動を行う必要が生じるため、結果的に採用単価を高めてしまいます。
スキル、経験、性格、志向性など、具体的な条件を設定することで、応募者の質を高め、選考プロセスを効率化し、長期的に定着する人材の採用に繋げられます。
選考フローを見直して社内コストを削減する
選考フローを見直すことは、採用活動にかかる社内コストを削減するために有効な手段です。
例えば、書類選考の基準を明確化して一次面接に進む人数を絞り込んだり、面接回数を最適化したりすることで、採用担当者の工数を削減できます。
オンライン面接の導入は、候補者の交通費や会場準備の手間を省き、効率的な選考を可能にします。
選考フロー全体を見直し、無駄なプロセスを排除することで、結果として人件費や管理費用といった内部コストの削減に繋がります。
カジュアル面談で入社後のギャップをなくす
カジュアル面談は、選考ではないフランクな場で、候補者と企業が相互理解を深める機会を提供します。
これにより、入社後のギャップを事前に解消し、早期離職のリスクを低減することができます。
早期離職が発生すると、再び採用活動を行う必要が生じ、結果的に採用単価が高騰してしまいます。
カジュアル面談を通じて、候補者が企業の文化や働き方について具体的に理解を深めることで、入社後の定着率向上に繋がり、長期的な採用コストの削減に貢献します。
採用単価の削減で失敗しないための注意点
採用単価の削減は企業の経営において重要な課題ですが、単にコストを切り詰めるだけでは、かえって優秀な人材の獲得機会を逃したり、早期離職につながったりする可能性があります。
ここでは、採用単価を削減する際に失敗しないための注意点について解説します。
適切な目安を立て、慎重に見積もりを行うことが重要です。
コスト削減だけでなく費用対効果も重視する
採用単価の削減を目指す際、単に費用を減らすことに注力してしまうと、結果として採用の質が低下したり、求める人材を獲得できなかったりする可能性があります。
重要なのは、かけた費用に対してどれだけの効果が得られたかという費用対効果を重視することです。
例えば、安価な求人媒体を利用しても応募者が集まらない、あるいはミスマッチが多いといった場合、結果的に再採用コストが発生し、トータルの費用は高くなる可能性もあります。
採用単価を下げつつ、質の高い人材を確保できるバランスの取れた戦略を立てることが求められます。
自社が本当に求める人材像を明確に定義する
採用単価の削減を考える上で、自社が本当に求める人材像を明確に定義することは不可欠です。
求めるスキルや経験、人物像が曖昧なままだと、ターゲットが広範になりすぎ、多額の広告費を投じても適切な人材が集まらない可能性があります。
また、ミスマッチによる早期離職は、再採用のための新たなコストを発生させ、結果的に採用単価を高騰させます。
具体的な人物像を設定し、採用基準を明確にすることで、効率的な採用活動が可能となり、無駄なコストを削減しつつ、定着率の高い採用を実現できます。
入社後の育成や定着支援にも力を入れる
採用単価の削減は、採用活動時のコストを抑えるだけでなく、入社後の定着率を高めることによっても達成されます。
せっかく採用した人材が早期に離職してしまうと、再び採用活動を行う必要が生じ、結果的に採用コストが増大します。
そのため、入社後の育成プログラムを充実させたり、メンター制度を導入して社員が安心して働ける環境を整えたりするなど、定着支援にも力を入れることが重要です。
社員が長く活躍できる環境を提供することで、離職率を下げ、結果として長期的な採用単価の削減に繋がります。
まとめ
採用単価は企業の成長に不可欠な人材確保において重要な指標です。
外部コストと内部コストの両面から算出される採用単価を正確に把握し、平均相場と比較することで、自社の採用活動の現状を客観的に評価できます。
採用単価を下げるためには、リファラル採用やダイレクトリクルーティング、SNS活用など、様々なアプローチを検討し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
また、コスト削減だけでなく、費用対効果や入社後の定着も視野に入れることで、長期的に質の高い採用活動を実現できるでしょう。
これらの情報を参考に、より効果的な採用戦略を構築し、企業の持続的な成長に繋げていきましょう。
採用クリエイティブはPiicにご相談ください
採用戦略の見直しや採用単価の最適化を進めるうえで、企業の“らしさ”を正しく伝える採用クリエイティブは欠かせません。
Piicでは、採用サイトやピッチ資料、動画制作などを通じて、求職者に選ばれるための表現づくりをご支援しています。
自社の魅力を最大限に引き出し、成果につながる採用活動を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。








