
「採用にかかる手間を減らしつつ、欲しい人材をしっかり確保できたら…」 そう考えたことはありませんか?
採用代行(RPO)は、企業の採用活動の一部または全部を、経験豊富な外部の専門チームに任せられるサービスです。 RPOは「Recruitment Process Outsourcing」の略で、採用アウトソーシングとも呼ばれます。求人計画の立案から候補者対応、内定後のフォローまで幅広く代行してもらうことで、社内は本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになります。
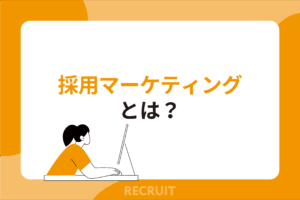

Index
-
採用代行(RPO)の基本情報
-
採用代行(RPO)の定義
-
採用代行サービスが注目される背景
-
採用代行(RPO)で依頼できる業務
-
採用計画と戦略の策定
-
候補者集めと応募管理
-
選考プロセスの実行
-
内定者への対応
-
定着支援
-
その他の関連業務
-
採用代行(RPO)の利点
-
採用担当者の負担を減らせる
-
採用活動の成果を高める
-
コストを最適化できる
-
客観的な視点を取り入れられる
-
採用代行(RPO)の注意点
-
費用が割高になる可能性
-
社内にノウハウが蓄積しにくい
-
ミスマッチのリスク
-
情報漏洩のリスク
-
採用代行(RPO)の費用について
-
料金体系の種類
-
費用相場の目安
-
採用代行(RPO)の導入を検討すべき企業
-
人手が足りない企業
-
採用に関する専門知識や経験がない企業
-
多くの人材を採用したい企業
-
特定の職種や分野で採用を進めたい企業
-
採用代行(RPO)を利用する際の比較ポイント
-
対応可能な業務範囲
-
費用体系と価格帯
-
実績や得意分野
-
情報セキュリティ体制
-
採用代行と他の人材サービスとの違い
-
人材派遣との違い
-
人材紹介との違い
-
サービス比較表
-
採用代行に関するよくある質問(FAQ)
-
Q. 採用代行は業務委託で依頼しても違法にならないの?
-
Q. 「委託募集」って何ですか?
-
Q. 許可が不要なケースは?
-
Q. 違法にならないために注意すべきことは?
-
まとめ
-
Piicのご案内
採用代行(RPO)の基本情報
採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、企業の採用活動の一部または全部を、外部の専門業者に委託するサービスです。日本では「採用アウトソーシング」と呼ばれることもあります。人材確保の競争が激化する中、採用に関わる煩雑な業務を外部に任せることで、企業は自社のコア業務や戦略的な人材施策に集中できるようになります。
このサービスは特に、採用に割ける人員やノウハウが限られている企業にとって効果的です。近年では中小企業やスタートアップにとどまらず、大手企業でも採用プロセスの効率化や質の向上を目的に導入が進んでいます。ここではまず、採用代行の定義と、その需要が高まっている背景を解説します。
採用代行(RPO)の定義
採用代行とは、企業が行う採用業務を外部の専門会社が代行するサービスです。RPO企業は、求人計画の立案から候補者募集、選考、内定者フォローまで、必要に応じて幅広い業務をサポートします。委託範囲は柔軟に設定でき、採用活動全体の効率化と成果向上を目的として活用されます。
この仕組みにより、企業は採用担当者の工数削減やスピードアップを実現しながら、専門家の知見を取り入れた戦略的な採用活動を行うことが可能となります。
採用代行サービスが注目される背景
p>採用代行のニーズが高まっている背景には、以下のような社会的・経営的要因があります。
- 労働人口の減少:少子高齢化により人材確保が年々難しくなっている。
- 採用競争の激化:特にIT、医療、専門職などで優秀人材の獲得競争が熾烈化。
- 採用手法の多様化:オンライン採用、SNS採用、ダイレクトリクルーティングなど新手法への対応が必要。
- 求職者の価値観変化:働き方や企業選びの基準が多様化し、従来の採用手法だけでは効果が薄い。
こうした背景から、多くの企業が自社だけで採用活動を完結させることの限界を感じ、外部の専門力を活用する動きが加速しています。
採用代行(RPO)で依頼できる業務
採用代行(RPO)サービスでは、採用計画の策定から候補者集め、選考、内定者フォロー、入社後の定着支援まで、幅広い業務を外部に委託できます。委託できる範囲はサービス提供会社によって異なり、必要な部分だけを切り出して依頼することも、採用プロセス全体を一括で任せることも可能です。
ここでは、代表的な業務範囲と具体的な内容を詳しく解説します。
採用計画と戦略の策定
採用活動の成功は、計画段階での戦略設計に大きく左右されます。RPOでは、企業の経営戦略や人員計画を踏まえた採用目標の設定、必要な人材のペルソナ設計、採用基準の明確化、採用スケジュールや予算策定などをサポートします。
また、市場トレンドや競合状況の分析、KPI(重要業績評価指標)の設定、採用ブランディング戦略の提案など、データと専門知見を活用したアプローチが可能です。これにより、自社の採用力を底上げし、効果的かつ持続的な採用活動を実現できます。
候補者集めと応募管理
p>母集団形成は採用活動の要です。RPOでは、求人広告の作成・運用、求人媒体の選定、人材紹介会社との連携、スカウトメール配信、企業説明会や採用イベントの企画・運営まで、多様な手法で候補者を集めます。
応募後の管理も包括的に対応可能で、書類受理から一次連絡、問い合わせ対応、書類選考や適性検査の手配・管理までを一括で任せられます。これにより、応募者への初動対応が迅速化し、機会損失の防止にもつながります。
選考プロセスの実行
書類選考通過者への対応から、筆記試験や適性検査の実施、面接日程調整、会場手配、面接官アサインまで、選考のオペレーション全般を委託できます。サービスによっては一次・二次面接の代行も可能で、事前にすり合わせた評価基準に沿って外部面接官が対応します。
これにより、面接基準の均一化や選考スピードの向上が期待できます。
内定者への対応
内定者フォローは、入社意欲の維持と辞退防止に直結します。RPOでは、内定通知の送付、入社承諾確認、懇親会の企画、SNSグループ運営、個別面談の実施などを代行できます。
また、入社前研修の案内や必要書類の管理も含め、きめ細やかなフォローを実現することで、内定者のエンゲージメントを高めます。
定着支援
採用はゴールではなくスタートです。RPOの中には、入社後のオンボーディング支援やメンター制度構築、定期面談の実施など、定着率向上を目的としたサービスを提供する会社もあります。
こうした施策は早期離職の防止や社員の活躍促進につながり、中長期的な人材戦略の安定化に貢献します。
その他の関連業務
採用資料(パンフレットや採用サイト)の制作支援、採用管理システム(ATS)の導入・運用、採用データの分析・レポーティング、課題改善コンサルティングなど、採用周辺業務も委託可能です。
特定職種の採用戦略立案や市場調査、面接官研修、新入社員研修など、人材育成領域までカバーするRPOもあり、採用活動全体の質を高めることができます。
採用代行(RPO)の利点
採用代行(RPO)を導入することで、企業は採用活動の質と効率を大きく向上させることができます。特に採用担当者の負担軽減、採用成果の向上、コストの最適化、客観的な視点の導入という4つのメリットは、多くの企業がRPOを利用する大きな理由となっています。
ここでは、それぞれの利点について具体的に解説します。
採用担当者の負担を減らせる
求人原稿作成、求人媒体の運用、応募者対応、面接日程調整、合否連絡など、採用担当者の日常業務は多岐にわたります。特に複数職種や大量採用を同時に行う場合、その業務量は膨大です。RPOを利用すれば、こうした定型的かつ煩雑な業務を外部に委託できるため、社内の担当者は戦略立案や候補者との深いコミュニケーションなど、より付加価値の高い業務に集中できます。
結果として業務効率の改善だけでなく、残業時間削減や採用活動全体の質向上にもつながります。
採用活動の成果を高める
RPOを提供する企業は、採用市場の最新トレンドや効果的な採用手法に精通しています。そのため、自社では得られないノウハウを活用し、求人媒体の最適化、スカウトメールの改善、ターゲット人材への訴求強化など、母集団形成から選考までの全工程をブラッシュアップできます。
例えば、競合分析による求人票の改善や、応募者の質を高めるための選考基準設計、面接スキル向上のアドバイスなど、専門的な視点からの提案を受けられるため、内定承諾率や定着率の向上にも直結します。
コストを最適化できる
採用活動には、求人広告費、人材紹介手数料、イベント運営費、選考に関わる人件費など、多くのコストが発生します。RPOを活用することで、業務効率化と戦略的な予算配分が可能になり、結果的に採用単価を下げられるケースもあります。
たとえば、無駄な媒体掲載を避け、成果の高いチャネルに集中投資する、成果報酬型の契約形態を選ぶなど、企業の状況に合わせた柔軟なコスト管理が可能です。ただし、業務範囲や契約形態によっては割高になることもあるため、複数社の見積もり比較が不可欠です。
客観的な視点を取り入れられる
自社だけで採用活動を行っていると、従来のやり方や固定観念に縛られ、改善の機会を逃すことがあります。RPOでは、第三者である専門家の客観的な視点を取り入れられるため、自社の採用課題を冷静に分析し、改善策を打ち出すことができます。
新しい採用手法の提案や、面接プロセスの改善、採用ブランディング戦略の見直しなど、外部ならではの柔軟な発想とデータに基づく提案が得られる点も、大きなメリットです。
採用代行(RPO)の注意点
採用代行(RPO)は多くのメリットをもたらしますが、導入にあたっては注意すべきポイントも存在します。特に費用面、社内ノウハウの蓄積不足、ミスマッチのリスク、情報漏洩のリスクは事前に把握しておくことが重要です。これらを理解した上で導入することで、RPOの効果を最大限に引き出せます。
費用が割高になる可能性
RPOは便利な一方で、自社で行う場合よりも費用が高くなるケースがあります。特に、採用戦略立案から定着支援まで広範囲な業務を委託すると、その分コストも増大します。また、採用人数が少ない場合や定型業務だけを依頼する場合は、費用対効果が見合わないこともあります。
導入前には、自社の採用課題と目的を明確にし、どの業務をどこまで外部委託するかを具体的に設定することが必要です。さらに、複数社から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討することで、コストの無駄を防げます。
社内にノウハウが蓄積しにくい
採用業務を外部に委託すると、その過程や判断基準が社内に残らず、ノウハウが蓄積されにくいというデメリットがあります。特に戦略設計や選考基準の策定など、採用の上流工程から丸ごと委託すると、将来自社のみで採用活動を行う際にゼロから構築し直す必要が出てくる可能性があります。
これを防ぐには、業務を丸投げせず、担当者間で情報共有や共同作業を行うことが大切です。採用代行会社と定期的にミーティングを行い、プロセスや評価基準を記録・共有する仕組みをつくることで、社内資産としてノウハウを残せます。
ミスマッチのリスク
外部の担当者が選考を行うため、自社の文化や部署ごとの細かなニーズが候補者に十分に伝わらず、求める人物像とのミスマッチが起こる可能性があります。たとえ評価基準を事前に共有していても、細かなニュアンスの違いから判断がずれることもあります。
リスクを軽減するためには、採用代行会社との密なコミュニケーションが不可欠です。求める人物像や企業の魅力を具体的に共有し、定期的な進捗確認や評価フィードバックを行うことで、ズレを最小限に抑えられます。また、最終面接は自社で行い、最終判断を直接下すことも有効です。
情報漏洩のリスク
RPOでは、候補者の個人情報や自社の機密情報を外部と共有するため、情報漏洩のリスクが伴います。委託先の情報管理体制が不十分な場合、情報が外部に漏れる可能性があります。
対策として、情報セキュリティ認証(例:プライバシーマーク、ISO27001)の有無や過去のトラブル事例を事前に確認しましょう。また、契約時には秘密保持契約(NDA)の締結や、情報の取り扱いに関する明確なルール設定も欠かせません。
採用代行(RPO)の費用について
採用代行(RPO)の費用は、依頼する業務範囲・採用人数・契約期間・サービス提供会社によって大きく変動します。料金体系にも複数の種類があり、目的や予算に応じて最適なプランを選ぶことが重要です。
新卒採用と中途採用では費用感が異なり、さらに職種の難易度や採用市場の状況によっても金額は変わります。ここでは、RPOの主な料金体系の種類と費用相場の目安を解説します。
料金体系の種類
採用代行の料金体系は大きく分けて月額固定型・成果報酬型・従量課金制の3つがあります。
- 月額固定型:契約期間中、毎月一定額を支払う形式。採用人数にかかわらず費用が一定なため、大量採用や長期的なプロジェクトに向いています。
- 成果報酬型:採用が成立した場合のみ費用が発生する形式。採用リスクを抑えられる一方、一人あたりの単価は高くなる傾向があります。
- 従量課金制:面接実施数やスカウトメール送信数など、実際の業務量に応じて課金される形式。特定業務のみ依頼する場合や、業務量が変動する場合に適しています。
自社の採用計画や予算、採用スピードに合わせて、これらを組み合わせたり、段階的に切り替える企業も増えています。
費用相場の目安
費用相場はあくまで目安ですが、参考として以下のようなレンジが挙げられます。
- 新卒採用:月額5万円〜70万円程度(業務範囲やサポート内容により変動)
- 中途採用:月額10万円〜70万円程度
- 成果報酬型:内定者の理論年収の20〜35%が一般的
たとえば、ITエンジニアや医療系などの専門職や採用難易度の高い職種では、この相場より高くなることがあります。また、戦略立案や採用ブランディング支援などコンサルティング要素が強い業務を含む場合、月額数百万円に達することも珍しくありません。
具体的な費用を把握するには、複数のRPO企業から見積もりを取り、業務内容と価格を比較することが必須です。特に同じ金額でも、サポート範囲や品質には大きな差があるため、単純な価格比較ではなく総合的な費用対効果で判断しましょう。
採用代行(RPO)の導入を検討すべき企業
採用代行(RPO)は、あらゆる企業が利用可能ですが、特に採用リソースやノウハウが不足している企業、短期間で多くの人材を採用する必要がある企業、特定職種や分野で採用を強化したい企業にとっては大きな効果を発揮します。
ここでは、RPO導入のメリットが特に大きい企業の特徴を解説します。
人手が足りない企業
求人票の作成、媒体運用、応募者対応、面接調整など、採用活動は日々多くの工数を必要とします。中小企業やスタートアップのように、限られた人員で複数業務を兼任している場合、採用に十分な時間を割くことが難しくなります。
RPOを活用すれば、煩雑なノンコア業務を外部委託でき、担当者は面接や戦略立案といった重要業務に集中可能です。結果として、採用スピードと質の両面が向上します。
採用に関する専門知識や経験がない企業
採用活動を成功させるには、市場トレンドの把握、適切な媒体選定、効果的なスカウト手法、応募者の見極め方など、多岐にわたるスキルが必要です。これまで大規模採用の経験がない企業や設立間もない企業では、これらのノウハウが不足している場合が多くあります。
RPOを導入すれば、採用のプロフェッショナルが戦略設計から実務まで一貫してサポートするため、経験不足による失敗を防ぎ、より理想に近い人材の採用が可能になります。
多くの人材を採用したい企業
事業拡大や新規プロジェクトの立ち上げなど、短期間で大量採用が必要な場合、社内リソースだけでは対応しきれないことがあります。応募者対応や面接日程調整などの業務量は人数に比例して増加するため、現場が疲弊しやすいのも事実です。
RPOを活用すれば、大量採用時のオペレーションを効率化でき、説明会運営や応募者管理などもスムーズに進行できます。これにより、採用計画を遅延なく達成する可能性が高まります。
特定の職種や分野で採用を進めたい企業
ITエンジニア、医療専門職、グローバル人材など、採用難易度が高い職種は、通常の求人広告だけでは応募が集まりにくい傾向があります。この場合、専門知識や人脈を持つRPO企業が有効です。
特定分野に特化したRPOであれば、その業界の採用市場や候補者層に精通しており、スカウト戦略や面接評価のノウハウも蓄積されています。その結果、より適性の高い人材の確保が期待できます。
採用代行(RPO)を利用する際の比較ポイント
採用代行(RPO)を導入する際は、複数のサービス提供会社を比較検討することが不可欠です。同じ「RPO」といっても、対応可能な業務範囲や得意分野、料金体系、セキュリティレベルには大きな差があります。
ここでは、比較時に特に注目すべき4つのポイントを解説します。
対応可能な業務範囲
RPO企業によっては、採用計画から定着支援まで一貫対応できる会社もあれば、書類選考や面接日程調整など特定の業務に特化した会社もあります。自社の採用課題や目的を整理し、「どの業務を外部に委託するのか」を明確にすることが重要です。
必要な業務をすべてカバーできるサービスを選べば、採用活動全体の効率化や成果向上が期待できます。
費用体系と価格帯
料金体系は月額固定型、成果報酬型、従量課金制などさまざまです。同じ業務内容でも企業によって価格差が大きいため、見積もりは必ず複数社から取りましょう。
予算や採用計画に合わせて、最もコストパフォーマンスの高い形態を選びます。特に、採用人数や契約期間に応じて料金が変動するケースも多いため、長期的な採用計画を踏まえて比較することが大切です。
実績や得意分野
RPO企業ごとに、得意とする業界や職種、採用形態があります。たとえば新卒採用に強い会社、ITエンジニア採用に特化している会社など、自社の採用ニーズにマッチしているかを確認しましょう。
過去の成功事例やクライアント企業の業種構成を確認し、自社と同じ課題や条件で成果を出しているかを見極めることがポイントです。
情報セキュリティ体制
採用活動では、候補者の個人情報や企業の機密情報を取り扱います。情報管理体制の甘い企業への委託は大きなリスクとなるため、セキュリティレベルは必ず確認しましょう。
具体的には、プライバシーマークやISO27001などの認証取得状況、アクセス権限管理の運用体制、過去の情報漏洩トラブルの有無などをチェックします。契約時には秘密保持契約(NDA)の内容も必ず確認し、リスクを最小限に抑えることが重要です。
採用代行と他の人材サービスとの違い
p>採用活動を外部に委託するサービスには、採用代行(RPO)のほかに人材派遣や人材紹介があります。これらは混同されがちですが、目的やサービス内容は大きく異なります。自社の採用課題に合わせて最適なサービスを選ぶためには、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。
人材派遣との違い
人材派遣は、派遣会社に登録しているスタッフを企業の業務遂行のために派遣するサービスです。雇用契約は派遣会社と結ばれ、派遣スタッフは派遣会社の指揮命令のもとで働きます。必要なスキルを持つ人材を短期間で確保できるのがメリットですが、自社の社員として長期的に雇用・育成することは前提としていません。
これに対して採用代行は、正社員や契約社員など自社で直接雇用する人材を採用するためのプロセスを外部が代行します。派遣が「労働力の提供」であるのに対し、採用代行は「採用活動そのものの支援」であり、業務範囲や目的が根本的に異なります。
人材紹介との違い
人材紹介は、人材紹介会社(エージェント)が自社に登録している求職者を紹介し、企業が選考・採用を行うサービスです。費用は成功報酬型が多く、特定スキルや経験を持つ即戦力人材を効率的に確保できるのが特徴です。
一方で採用代行は、候補者の紹介そのものではなく、求人媒体の運用、スカウト、応募者対応、面接調整など採用プロセス全体や一部の実務を代行します。人材紹介が「候補者を連れてくる」サービスであるのに対し、採用代行は「候補者を集め、採用に至るまでの過程を動かす」サービスです。
そのため、母集団形成から内定承諾まで一貫してサポートしたい場合や、採用フロー全体を効率化したい場合は採用代行が適しています。
サービス比較表
| サービス種別 | 主な目的 | 契約形態 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 採用代行(RPO) | 自社で直接雇用する人材の採用プロセスを代行 | 業務委託契約 | 求人媒体運用、スカウト、応募管理、面接調整、内定者フォローなど幅広く対応 |
| 人材派遣 | 即戦力としての労働力の提供 | 派遣会社と雇用契約 | 短期・中期の業務遂行向け。自社の社員としては雇用しない |
| 人材紹介 | 登録求職者の紹介とマッチング | 成功報酬型契約 | 特定スキル・経験を持つ人材を効率的に採用可能。採用成立時のみ費用発生 |
採用代行に関するよくある質問(FAQ)
Q. 採用代行は業務委託で依頼しても違法にならないの?
A. 原則として業務委託契約での採用代行依頼は適法です。ただし、委託内容が「職業安定法」における委託募集に該当する場合は、委託元と委託先の双方が許可を取得する必要があります。
Q. 「委託募集」って何ですか?
A. 委託募集とは、企業が自社の社員以外の第三者に募集業務を委託し、求職者を集めてもらう行為です。この場合、厚生労働大臣または都道府県労働局長の許可が必要です。
Q. 許可が不要なケースは?
A. 面接日程の調整や応募書類管理、既定の評価基準に基づく選考補助など、実質的に募集行為を行わない業務は許可不要な場合が多いです。
Q. 違法にならないために注意すべきことは?
A. 契約前に業務範囲が委託募集にあたるかどうかを確認しましょう。必要に応じて許可申請を行い、契約書には役割分担や業務範囲を明記することでトラブルを防げます。
まとめ
採用代行(RPO)は、採用活動を効率化し、社内リソースを戦略的業務に集中させられる有効な手段です。計画策定から候補者対応、内定フォローまで柔軟に委託でき、専門家の知見を活かして成果を最大化できます。
一方で、費用や情報管理リスク、社内ノウハウの蓄積不足などの懸念もあるため、委託範囲の明確化と定期的なすり合わせが不可欠です。派遣や人材紹介との違いを理解し、自社の課題に最適なサービス形態を選びましょう。
最終的には、複数社比較による費用対効果の検証と、合否判断などの重要局面を自社が責任を持つ体制を整えることが成功の鍵です。
採用は企業の未来を左右する投資です。信頼できるパートナーとともに、持続的に成果を出せる採用体制を構築し、次の一歩を踏み出しましょう。
その上で重要なのは、採用活動の要となる「自社の魅力を正しく伝える力」です。
いくら仕組みやフローを整えても、求職者の心を動かすメッセージやデザインが伴わなければ、応募率やマッチング精度は向上しません。
Piicのご案内
株式会社Piicでは、採用サイト制作・採用ピッチ資料作成など、採用活動の成果を高めるクリエイティブ制作を専門に行っています。
企業の「らしさ」を言語化し、デザインに落とし込み、求職者に響く形で発信することで、応募率向上と定着率アップを同時に実現します。
まずはお気軽に、無料相談で貴社の採用課題をお聞かせください。








