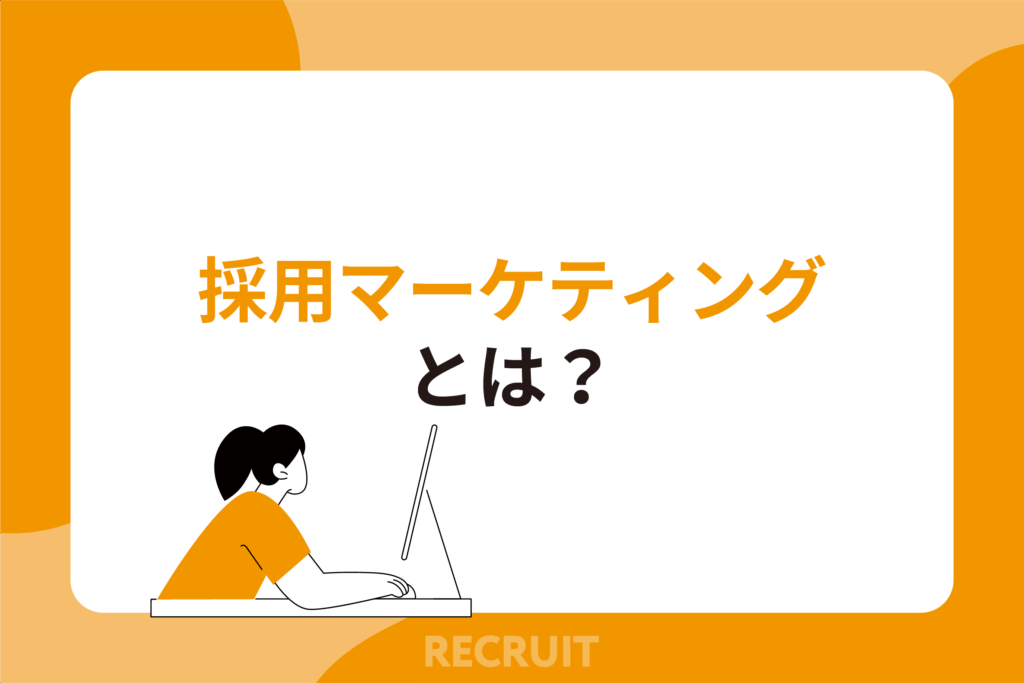
本記事では企業の採用活動にマーケティングの視点を取り入れる意味や、その具体的な手法について詳しく解説します。
「求人広告を出しても応募が集まらない」「自社の魅力がうまく伝わらない」といったお悩みをお持ちの採用担当者の方にとって、課題解決のヒントが満載の内容です。
採用活動をより戦略的に、そして効果的に進めたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
です。

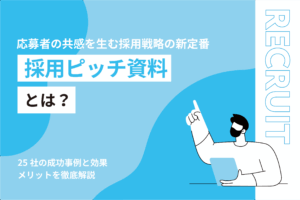
Index
-
採用マーケティングの定義と重要性
-
採用マーケティングの考え方
-
採用ブランディングとの相違点
-
従来の採用活動との違い
-
なぜ採用マーケティングが注目されるのか
-
採用マーケティングの利点
-
求める人材への理解促進
-
入社後のミスマッチ軽減
-
採用関連コストの最適化
-
潜在的な応募層への働きかけ
-
採用マーケティングの進め方
-
現状分析
-
採用ターゲットの設定
-
候補者のニーズ把握
-
効果的な手段の検討
-
採用施策の実行
-
採用マーケティングにおける主要な概念
-
採用ファネルとその活用
-
キャンディデイトジャーニー
-
ペルソナ設定
-
採用マーケティングに役立つフレームワーク
-
3C分析の応用
-
4P分析の活用
-
SWOT分析の活用
-
採用マーケティングで活用されるツール
-
目的別に見るツールの種類
-
代表的な活用ツール
-
採用マーケティングの成功事例
-
IT企業の事例|エンジニア採用に特化した情報発信
-
サービス業の事例|SNSで職場のリアルを伝える
-
製造業の事例|イベントとオウンドメディアの組み合わせ
-
成功に導く共通ポイント
-
新卒・中途採用における有効性
-
新卒採用における有効性
-
中途採用における有効性
-
採用マーケティング支援サービスの活用
-
コンサルティング会社の役割
-
運用代行サービスの活用
-
まとめ:採用マーケティングで自社に合う人材と出会う
採用マーケティングの定義と重要性
採用マーケティングとは、企業の採用活動にマーケティングの視点と手法を取り入れ、戦略的に人材を獲得していく考え方です。求職者を「顧客」と見なし、ニーズや行動を深く理解したうえで、自社の魅力を最適なタイミングと手段で発信することで、理想とする人材との出会いを創出します。
従来のように「求人広告を出して応募を待つ」受動的な採用では、優秀な人材にリーチするのが難しくなっています。そこで重要となるのが、企業自らが発信し、求職者との接点を設計するアプローチです。採用活動全体を「認知→興味→応募→入社→定着」まで一貫して設計することが、成果に直結します。
近年は、少子高齢化や価値観の多様化により、求職者の仕事選びの基準も大きく変化しています。給与や条件よりも「企業文化」や「働きがい」が重視される時代だからこそ、企業は何をどう伝えるかを見直す必要があります。
つまり、採用マーケティングとは、求職者との理解と信頼を深め、選ばれる企業になるための戦略です。単なる広報や告知ではなく、「誰に・何を・どう伝えるか」を軸に、採用の在り方そのものを再構築していくアプローチだと言えるでしょう。
採用マーケティングの考え方
採用マーケティングは、企業が求める人材を獲得するために、市場や競合、求職者の動向を分析しながら戦略を立てていく手法です。その根底には、「求職者を深く理解し、自社の価値を最適な形で届ける」というマーケティングの基本姿勢があります。
この考え方では、求職者を単なる応募者ではなく、企業の顧客と見立ててアプローチします。具体的には、「どのような人に働いてほしいのか」という理想像を描き、その人の価値観・行動パターン・情報収集手段などを丁寧に分析。そのうえで、認知から応募、選考、入社、活躍に至るまでのプロセスを戦略的に設計します。
従来のように「求人票を出して待つ」のではなく、企業自らがターゲット人材に向けて情報を届け、関係性を築き、選ばれる存在になることが求められます。これは単なる広報活動ではなく、継続的な接点づくりを通じて、候補者との信頼関係を構築する取り組みです。
このように採用マーケティングは、「出会いから入社後の活躍まで」を見据えた一貫した採用戦略であり、求職者との中長期的な関係構築を目指す姿勢が核となっています。
採用ブランディングとの相違点
採用マーケティングは、企業が求める人材を獲得するために、市場や競合、求職者の動向を分析しながら戦略を立てていく手法です。その根底には、「求職者を深く理解し、自社の価値を最適な形で届ける」というマーケティングの基本姿勢があります。
この考え方では、求職者を単なる応募者ではなく、企業の顧客と見立ててアプローチします。具体的には、「どのような人に働いてほしいのか」という理想像を描き、その人の価値観・行動パターン・情報収集手段などを丁寧に分析。そのうえで、認知から応募、選考、入社、活躍に至るまでのプロセスを戦略的に設計します。
従来のように「求人票を出して待つ」のではなく、企業自らがターゲット人材に向けて情報を届け、関係性を築き、選ばれる存在になることが求められます。これは単なる広報活動ではなく、継続的な接点づくりを通じて、候補者との信頼関係を構築する取り組みです。
このように採用マーケティングは、「出会いから入社後の活躍まで」を見据えた一貫した採用戦略であり、求職者との中長期的な関係構築を目指す姿勢が核となっています。
従来の採用活動との違い
従来の採用活動は、欠員が出たタイミングで求人情報を掲載し、応募者からの反応を待つという受動的かつ短期的な対応が中心でした。ターゲットは主に転職意欲の高い「顕在層」に限定されることが多く、アプローチの幅も限られていました。
一方、採用マーケティングでは、企業自らが積極的に情報発信を行い、求める人材へと働きかけていくスタンスを取ります。求職者のニーズや行動様式を踏まえ、適切なタイミング・媒体・内容で企業の魅力を届け、応募へと導く戦略が重視されます。
| 項目 | 従来の採用活動 | 採用マーケティング |
|---|---|---|
| アプローチ方法 | 求人広告を掲載して応募を待つ | ターゲットに向けて能動的に発信 |
| 対象層 | 転職顕在層(今すぐ転職したい人) | 転職潜在層や過去応募者も含む広範囲 |
| 期間 | 短期的(欠員補充が目的) | 中長期的(関係構築と母集団形成) |
| 目的 | 応募数の確保 | 企業理解の促進とマッチ度の向上 |
| 主な活動 | 求人媒体への出稿 | SNS発信、コンテンツ制作、イベント開催など |
また、その対象も顕在層にとどまりません。将来的な転職を視野に入れている潜在層や、過去の応募者・退職者なども含めた「長期的な候補者層との関係構築」を行う点が、従来手法との大きな違いです。
採用マーケティングでは、企業を「商品」、求職者を「顧客」として捉え、データを活用した分析と戦略的な施策により、入社後の定着・活躍までを見据えたアプローチを実践します。
なぜ採用マーケティングが注目されるのか
近年、多くの企業が採用マーケティングに注目するようになった背景には、人材獲得を取り巻く環境の変化があります。中でも特に大きいのが、労働人口の減少と求職者の価値観の多様化です。
採用マーケティングが必要とされるようになった主な要因は、以下の通りです。
- 少子高齢化による労働人口の減少:人材不足が深刻化し、従来の採用手法だけでは確保が困難に
- 情報収集手段の多様化:求職者はSNSや口コミ、検索など複数のチャネルを活用して企業情報を取得
- 価値観の変化:給与や待遇だけでなく、企業の文化・理念・働きがいが重視される傾向が強まっている
- 採用競争の激化:求人広告だけでは他社との差別化が難しくなり、企業側の発信力が問われる時代に
このような変化の中で、企業が求職者に選ばれる存在となるには、自社の魅力を明確にし、それを戦略的に届けることが欠かせません。そこで注目されているのが、マーケティングの視点を取り入れた採用アプローチです。
採用マーケティングの利点
採用マーケティングを導入することで、企業は従来の採用活動では得られなかった多くの成果を期待できます。特に、人材の質の向上、採用効率の改善、定着率の向上といった面で大きな効果を発揮します。
具体的には、以下のような利点が挙げられます。
- 求める人材への理解が深まり、的確なアプローチが可能になる
- 応募前から企業との接点を築くことで、入社後のミスマッチを防げる
- 広告費や選考にかかる時間・手間など、採用コストを最適化できる
- 将来的な転職を考える「潜在層」にも長期的にアプローチできる
このように、採用マーケティングは単に応募者数を増やすための手段ではなく、「企業と人材の本質的なマッチング精度を高める」ための取り組みです。次項からは、それぞれの利点について詳しく解説していきます。
求める人材への理解促進
採用マーケティングにおいて最も重要なステップの一つが、自社が採用したい人材を深く理解することです。年齢や経験といった表面的な条件だけでなく、価値観やキャリア志向、情報収集の行動パターンまで把握することが、的確なアプローチの土台となります。
その際に活用されるのが「ペルソナ設定」です。これは、ターゲットとなる人物像を仮想の具体的な一人の人物として描き出す手法で、氏名・年齢・仕事観・生活スタイル・利用メディアなどを詳細に定義します。「どんな人が、どんな情報に反応するのか」を明確にすることで、メッセージやチャネルの選定がブレなくなります。
さらに、候補者が企業を知ってから応募・入社に至るまでの過程を可視化する「カスタマージャーニー(候補者ジャーニー)」の活用も効果的です。どのタイミングでどのような情報が必要かを理解することで、接点ごとに最適なコンテンツを設計できるようになります。
このように、ターゲット人材の行動・思考・ニーズを可視化し、採用戦略と一貫性を持たせることで、企業側は的確にアプローチができ、候補者側も企業への理解を深めやすくなります。結果として、相互理解が進み、マッチ度の高い採用につながっていきます。
入社後のミスマッチ軽減
採用活動における大きな課題のひとつが、入社後のミスマッチによる早期離職です。スキルや経験が合っていても、企業の価値観や職場文化と合わないことで、短期間での退職につながってしまうケースは少なくありません。
採用マーケティングでは、このようなミスマッチを防ぐために、ターゲットが本当に知りたい情報を事前に伝えることを重視します。仕事内容だけでなく、職場の雰囲気や人間関係、カルチャー、成長環境など、リアルな姿を発信することが重要です。
また、企業側も選考時において、単に能力だけでなく、価値観や志向性のマッチングを重視した評価を行うことで、双方の納得度を高めることができます。こうした情報の共有と対話の積み重ねが、入社後のギャップを減らすことにつながります。
結果として、入社後の定着率が向上し、組織への信頼やエンゲージメントの醸成にもつながります。採用マーケティングは、単なる採用成功にとどまらず、社員の活躍と持続的な人材育成を支える仕組みとして機能するのです。
採用関連コストの最適化
採用活動には、広告費や仲介手数料といった目に見えるコストだけでなく、選考にかかる時間や担当者の工数といった「見えにくいコスト」も多く存在します。これらを放置したままの採用活動は、費用対効果が不透明になりがちです。
採用マーケティングでは、あらかじめ採用ターゲットを明確に定義し、その層に届くメッセージを最適なチャネルで発信します。無駄な応募を減らし、選考フローを効率化することで、コスト全体の圧縮が可能になります。
| コスト項目 | 従来の採用 | 採用マーケティング導入後 |
|---|---|---|
| 求人広告費 | 複数媒体に一斉出稿 → 費用が高騰しがち | ターゲットに合った媒体に絞り込み、出稿数を最適化 |
| エージェント手数料 | 成約ごとの成果報酬が高額 | 自社集客による直接応募でコスト削減 |
| 面接・選考工数 | ミスマッチ応募が多く、無駄な対応が発生 | 事前に情報を伝えることで母集団の質が向上 |
| 再採用コスト | 早期離職による追加採用が発生 | 定着率向上により再採用の頻度が減少 |
このように、採用マーケティングは採用活動の精度を高めることで「無駄なコストの発生そのものを防ぐ」仕組みとも言えます。短期的なコスト削減だけでなく、長期的な採用の質と安定性の向上につながるのが大きな利点です。
潜在的な応募層への働きかけ
従来の採用活動は、求人サイトやエージェントを活用し、今すぐ転職を考えている「顕在層」に向けた短期的なアプローチが主流でした。しかし、実際には転職を積極的に考えていない「潜在層」にこそ、有望な人材が多く存在することも少なくありません。
採用マーケティングでは、この潜在層に対して中長期的な関係性構築を重視します。たとえば以下のような手段が効果的です。
- SNSでの情報発信を通じて、企業の雰囲気や価値観を日常的に伝える
- オウンドメディアで社員インタビューや仕事のやりがいを発信し、企業理解を深める
- カジュアル面談やイベントで直接交流し、「いざという時に思い出してもらえる存在」になる
こうした継続的な取り組みにより、「いつか転職するならここがいいかも」という好印象を潜在層に植え付けることができます。そして、実際に転職を考え始めたタイミングで、すでに信頼関係や親近感を持っている企業が選ばれやすくなるのです。
このように、潜在層へのアプローチは将来の母集団形成と、応募前からのロイヤルティ醸成という観点から、採用競争力の向上に直結します。採用マーケティングは、こうした「今すぐではない候補者」との接点づくりにも強みを発揮します。
採用マーケティングの進め方
採用マーケティングは、感覚的に取り組むものではなく、戦略的にステップを踏んで進めることで、成果につながりやすくなります。以下は、実践における基本的な進行手順です。
- 現状分析:自社の採用課題や強み・弱みを客観的に把握する
- 採用ターゲットの設定:どんな人材を採用したいのかを明確にする
- 候補者のニーズ把握:求職者が企業に求めている情報や条件を理解する
- 効果的な手段の検討:チャネル・コンテンツ・アプローチ方法を設計する
- 採用施策の実行と改善:施策を実行し、データをもとに改善を繰り返す
これらのプロセスを踏むことで、「誰に、何を、どう届けるか」という採用活動の根幹が明確になり、ぶれのない戦略設計と継続的な改善が可能になります。
現状分析
採用マーケティングを始めるうえで、まず最初に行うべきなのが現状分析です。これは、自社の採用活動における課題や成功要因、外部環境を客観的に把握し、次の戦略を立てるための土台となります。
特に見落とされがちなのが、「採用活動にどんなボトルネックがあるのか」をデータで可視化することです。感覚ではなく、数字と事実に基づいた分析が、その後の施策の精度を左右します。
以下のような観点から多角的に分析を行いましょう:
- 採用データの確認(応募数・面接通過率・内定率・入社後の定着率など)
- チャネル別効果の比較(求人媒体・紹介・SNSなどの成果)
- 選考プロセスの課題(辞退が多い工程、連絡スピードなど)
- 自社の採用ブランド(候補者からの印象・ネット上の口コミ)
- 競合の採用活動(募集内容・ブランディング・訴求ポイント)
あわせて、社内の現場社員や過去の候補者からのフィードバックをヒアリングすることも有効です。社外の見え方と社内の認識にギャップがないかを確認することで、よりリアルな改善点が見えてきます。
このように現状分析は、採用活動全体の「棚卸し」であり、施策の優先順位を判断するための出発点です。ここが曖昧なままでは、どれだけ施策を打っても狙いが外れてしまいます。
採用ターゲットの設定
現状分析を踏まえて次に行うべきは、どのような人材を採用したいのかを明確にする「採用ターゲットの設定」です。ここが曖昧なままでは、発信するメッセージや使用するチャネルがブレてしまい、効果的な採用につながりません。
この段階では、単に「営業経験3年以上」「20代後半」などの条件を列挙するだけでは不十分です。重要なのは、その人がどんな価値観を持ち、どのような働き方を求めているのかまでを含めて把握することです。
そこで活用されるのが「採用ペルソナ」の設計です。ターゲットを“ひとりの人物”として詳細に描き出すことで、よりリアルなアプローチが可能になります。
採用ペルソナに含める主な要素:
- 基本情報(年齢、性別、居住地、家族構成など)
- 職歴・スキル(経験年数、業界、得意分野など)
- 価値観・志向性(仕事に求めるもの、キャリアビジョンなど)
- 情報行動(どのSNSを使っているか、どんな情報に惹かれるか)
- 転職に対する温度感(転職意欲の強さ、懸念点など)
こうして明確化したターゲット像をもとに、「どこに、どんな言葉で、どんなコンテンツを届けるべきか」を設計していくことで、採用活動全体に一貫性が生まれます。
ペルソナが明確であるほど、採用メッセージの質と届き方は劇的に変わると言っても過言ではありません。採用ターゲットの設定は、採用マーケティングの成否を分ける要となるステップです。
候補者のニーズ把握
採用ターゲットを明確にしたら、次に行うべきはそのターゲットが「企業選びにおいて何を重視しているか」を把握することです。いくら魅力的な情報を発信しても、候補者の関心や価値観とズレていれば、響くことはありません。
候補者のニーズを把握するためには、以下のような手法が有効です。
- アンケートやヒアリング(内定辞退者・入社者・過去の応募者へのフィードバック収集)
- アクセス解析(採用サイトでの滞在時間・閲覧ページなどを分析)
- SNSや口コミのリサーチ(X、Instagram、OpenWorkなどでの投稿内容を調査)
求職者が企業に求める要素は、スキルや給与面だけではありません。たとえば以下のような視点も重要視されています:
- ワークライフバランス
- 企業のカルチャーやビジョンへの共感
- スキルアップやキャリア形成が可能か
- 働きがい・社会的意義のある仕事かどうか
こうした“候補者の本音”を掘り下げることで、採用メッセージやコンテンツの精度が格段に向上します。ニーズを理解することは、ただ発信するためではなく、「選ばれる企業」になるための必須ステップなのです。
効果的な手段の検討
採用ターゲットとそのニーズを把握したら、次はその人物像に最適な手段・チャネル・コンテンツを設計していきます。重要なのは、なんとなく手段を選ぶのではなく、「誰に、どんな情報を、どう届けるか」を戦略的に決めることです。
ここでは大きく2つの観点から検討を行います。
1. どこで届けるか(チャネルの選定)
- 採用サイト・オウンドメディア:企業の世界観を深く伝える中核メディア
- SNS(X, Instagram, TikTokなど):日常的な接点を作りやすく、拡散力も高い
- 求人媒体:顕在層への効率的なリーチに有効
- 社員紹介・リファラル:信頼性とマッチング精度が高いチャネル
- 採用イベント・カジュアル面談:直接コミュニケーションによる関係構築が可能
2. 何を届けるか(コンテンツの企画)
- 社員インタビュー・座談会記事:リアルな雰囲気やキャリア観を伝える
- 働き方・制度紹介:求職者が不安に思う要素を具体的に説明
- 仕事内容の深掘り:入社後のイメージを明確化し、ミスマッチを防ぐ
- 企業のビジョン・文化:共感を生むストーリーや存在意義を訴求
- 動画・SNS投稿・ショートコンテンツ:ライトな接点で認知を広げる
選定の際は、採用ターゲットがどこにいて、どんな情報に価値を感じるかを基準に考えることが重要です。手段が多様化している今だからこそ、「選んで集中する」戦略が成果を左右します。
採用施策の実行
設計した戦略と手段に基づき、いよいよ具体的な採用施策を実行していきます。採用マーケティングは「実行して終わり」ではなく、効果を検証しながら改善を繰り返すことが成果につながる重要なポイントです。
実行フェーズで主に行うアクションには、以下のようなものがあります。
- 採用サイトやSNSの更新・運用(ターゲットに合わせた内容で定期的に発信)
- コンテンツ制作(社員インタビュー、動画、企業文化紹介など)
- 採用イベントの企画・実施(カジュアル面談やウェビナーなど)
- Web広告やスカウトメールの配信(母集団形成や潜在層へのアプローチ)
施策を実施した後は、あらかじめ設定したKPI(例:応募数、CVR、SNSエンゲージメントなど)に基づき、成果を定量的に評価します。そして、数値をもとに仮説を立て、内容やチャネル、頻度などを改善していきます。
また、マーケティング部門や現場社員と連携しながら、社内での情報共有やフィードバックの循環体制を整えることも、施策の成功には欠かせません。採用を「全社的なプロジェクト」として取り組む姿勢が成果に直結します。
このように、採用施策の実行は「打って終わり」ではなく、検証と改善を前提としたPDCAの継続が前提です。柔軟に対応しながら、小さく回し、着実に精度を高めていくプロセスが、成果につながります。
採用マーケティングにおける主要な概念
採用マーケティングを戦略的に進めるためには、いくつかの基本概念やフレームワークを理解しておくことが重要です。ここでは、実務で特に役立つ3つの考え方をご紹介します。
採用ファネルとその活用
採用ファネルとは、求職者が企業と接点を持ってから入社に至るまでのプロセスを段階的に可視化したものです。通常、以下のようなステップに分かれます:
- ① 認知(企業の存在を知る)
- ② 興味・関心(もっと知りたいと思う)
- ③ 応募(選考を受ける意思を持つ)
- ④ 選考(面接・試験を受ける)
- ⑤ 内定・入社(採用が決まり、実際に入社)
このファネルの各フェーズで「どこに離脱ポイントがあるか」「どうすれば次の段階へ進ませられるか」を分析・改善することで、採用プロセス全体の効率と質が向上します。
キャンディデイトジャーニー
キャンディデイトジャーニーとは、求職者が企業との接点を通じてどのように感じ、動くのかを可視化するフレームです。いわば「求職者目線の道のり」を描くものであり、主に以下のような視点で整理します:
- どのタイミングで企業を知るか(接触点)
- どの情報に触れ、どう感じるか(印象)
- どう行動し、どんな不安を抱くか(行動と感情)
この視点を持つことで、求職者が抱える不安や疑問を先回りして解消し、ポジティブな体験を提供する施策設計が可能になります。候補者体験(Candidate Experience)を重視した採用の第一歩として有効です。
ペルソナ設定
ペルソナ設定とは、採用したい人物像を、あたかも実在する1人の人物のように具体化する手法です。前述の「採用ターゲット設定」と密接に関わる考え方で、より実践的に活用する際に有効です。
設定する主な情報には以下が含まれます:
- 氏名・年齢・性別・居住地・職歴
- キャリア志向・仕事観・転職の目的
- 使用するメディア・情報収集手段
- 応募・転職に対する不安や障壁
このように、ターゲット像を深く描き出すことで、その人が心を動かされる言葉・チャネル・タイミングを的確に選ぶことができます。チーム内の認識共有にも非常に有効です。
採用マーケティングに役立つフレームワーク
採用マーケティングをより体系的・戦略的に進めていくうえで、マーケティング領域で活用されてきた定番フレームワークを応用することは非常に有効です。ここでは、特に採用施策に活かしやすい代表的な3つをご紹介します。
3C分析の応用
3C分析とは、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から現状を把握するフレームワークです。採用に応用する際は、次のように置き換えられます。
- Customer(候補者):どんな人材が欲しいか、その人は何を重視しているか?
- Competitor(採用競合):他社はどんな訴求をしていて、何が強みか?
- Company(自社):自社にはどんな魅力や課題があるか?
この3Cをもとに、「どのポジションで戦うべきか」「どのように差別化するか」を明確にすることで、効果的な採用戦略を立てることができます。
4P分析の活用
4Pは本来、商品やサービスの販売戦略を考える際に使われるフレームですが、採用でも応用可能です。採用文脈では、以下のように言い換えると活用しやすくなります。
- Product(採用対象):どんな職種・ポジションを提供するのか?
- Price(待遇):給与や福利厚生などの条件は適切か?
- Place(チャネル):どの媒体や接点で候補者と出会うか?
- Promotion(訴求内容):どんな魅力をどう伝えるか?
この4つの視点から採用活動を設計することで、条件だけでなく伝え方や届け方までを一貫して考えることが可能になります。
SWOT分析の活用
SWOT分析は、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理し、戦略の方向性を検討するためのフレームワークです。採用活動においても、以下のように活用できます。
- Strength(強み):自社にしかない魅力・制度・人材・実績
- Weakness(弱み):知名度の低さ、組織体制の課題 など
- Opportunity(機会):求職者のニーズ変化、採用トレンドの変化
- Threat(脅威):強力な競合他社、業界全体の人材不足 など
SWOT分析をもとに、「強みをどう活かし、弱みをどう補い、競合にどう勝つか」といった具体的な戦略思考を深めることができます。
採用マーケティングで活用されるツール
採用マーケティングを実行・改善していくうえで、デジタルツールの活用は欠かせません。ここでは、主なツールのカテゴリとその活用ポイントを整理してご紹介します。
目的別に見るツールの種類
- 情報発信・ブランディング系
採用サイト、オウンドメディア(ブログ・Noteなど)、SNS(X、Instagram、TikTokなど)を通じて、企業の魅力を継続的に発信します。 - 応募管理・選考支援系
ATS(採用管理システム)や応募フォーム、日程調整ツールなどを使い、選考業務の効率化と一元管理を実現します。 - データ分析・改善系
Google AnalyticsやSNSインサイト、クリック率計測ツールなどにより、施策の効果測定と改善判断が可能になります。 - コミュニケーション系
LINE公式アカウント、ZoomやGoogle Meet、カジュアル面談予約ツールなどで候補者との接点を増やします。
代表的な活用ツール
具体的な採用マーケティング支援ツールとして、以下のようなサービスが挙げられます。
- Wantedly:ストーリーやカルチャーを重視した企業紹介が可能。共感型のマッチングに強い
- Note:社員インタビューや制度紹介、イベントレポートなど、企業の日常をブログ形式で発信
- Google Analytics:採用サイトの訪問者数や離脱ポイントなどを可視化し、改善施策に活かせる
- ATS(採用管理システム):応募者の進捗管理、面接スケジュール調整、レポート作成などを一元化
これらのツールは目的やターゲット、社内リソースに応じて組み合わせて活用することで、採用活動の生産性と精度を大きく向上させることができます。
採用マーケティングの成功事例
採用マーケティングは、実際に多くの企業で導入され、成果を上げています。ここでは、業種の異なる企業の成功事例をいくつかご紹介します。自社に近い業種や規模の取り組みを参考にしながら、活用のヒントを見つけてみてください。
IT企業の事例|エンジニア採用に特化した情報発信
ある中堅IT企業では、WantedlyやQiita、技術ブログを活用し、自社エンジニアによる技術発信を継続。現場の雰囲気や開発環境の魅力を伝えたことで、同業からの自然応募が増加。採用単価も下がり、ミスマッチも減少しました。
サービス業の事例|SNSで職場のリアルを伝える
店舗運営や接客が中心のある企業では、InstagramやTikTokでスタッフの働く姿や現場の雰囲気を動画で発信。若年層の求職者に刺さりやすいライトな内容で、エントリー数が前年比150%に。社員のモチベーション向上にもつながりました。
製造業の事例|イベントとオウンドメディアの組み合わせ
採用に苦戦していた地方の製造業では、定期的な会社見学会や社員座談会を開催し、それらの様子をオウンドメディアで発信。応募前から職場の空気感が伝わるようにし、応募者の志望度が向上。入社後の定着率も改善されました。
成功に導く共通ポイント
- 現場のリアルな声や雰囲気を発信している
- 候補者との接点を複数用意し、認知→応募までの流れを意識している
- 長期的な視点で情報発信を継続している
業種や規模にかかわらず、採用マーケティングの基本は同じです。「誰に、何を、どう届けるか」を明確に設計し、継続的に実行していくことが、成果への近道になります。
新卒・中途採用における有効性
採用マーケティングは、新卒・中途のいずれの採用活動にも活用できますが、ターゲット層の特性や行動パターンの違いに応じたアプローチが必要です。ここではそれぞれの有効性と活かし方を整理します。
新卒採用における有効性
新卒採用では、学生の多くがまだ企業や業界についての知識が少なく、選社軸も曖昧です。そのため、
企業の考え方や文化に「共感してもらう」ことが非常に重要になります。
採用マーケティングの活用例:
- 企業理念やカルチャーを発信するオウンドメディアの構築
- インターンや説明会前に興味を引くSNSコンテンツ
- 先輩社員インタビューや1日の仕事紹介動画
情報発信を通じて「選ばれる企業」になることで、エントリー数の増加や志望度の向上につながります。
中途採用における有効性
中途採用では、求職者が「転職の目的」や「希望条件」を明確に持っているケースが多いため、
訴求内容を具体的・現実的に伝えることがポイントになります。
採用マーケティングの活用例:
- ポジション別の仕事内容やキャリアパスの明示
- 待遇や働き方に関する詳細情報の提示
- 専門性やスキルを活かせる環境であることの訴求
また、転職顕在層だけでなく、まだ転職を検討していない潜在層にもアプローチできる点もマーケティングの強みです。
このように、新卒と中途では訴求ポイントや届け方は異なりますが、「候補者の立場に立ち、適切な情報を届ける」という基本姿勢は共通しています。
採用マーケティング支援サービスの活用
採用マーケティングを実践したい企業の中には、「社内にノウハウがない」「担当者の時間が足りない」といった理由で、なかなか一歩を踏み出せないケースも少なくありません。そうした企業にとって、外部の支援サービスを活用することは、有効な選択肢の一つです。
コンサルティング会社の役割
採用マーケティングのコンサルティング会社は、企業の採用活動における戦略的な土台づくりを担う存在です。単なる施策提案ではなく、以下のような根本的な課題の整理と解決に取り組みます。
- 現状分析・課題の可視化(自社の採用力を定量・定性で評価)
- 採用ペルソナとカスタマージャーニーの設計
- メッセージ設計や採用ブランディング方針の策定
- 最適なチャネルと施策の選定
また、採用サイトやSNSの運用などは外部の制作会社・運用会社と連携する形で、全体のハブとしてプロジェクトを推進する役割も担います。社内に採用広報の専門家がいない場合でも、安心して任せられる伴走型のパートナーとなる存在です。
運用代行サービスの活用
採用マーケティングは「設計して終わり」ではありません。SNSでの情報発信、採用サイトの更新、広告のチューニングなど、日々の細かな運用こそが成果を左右します。しかし、これらを社内で一貫して行うには大きな負担がかかります。
そこで有効なのが運用代行サービスの活用です。たとえば以下のような実務を、外部パートナーに委託することで、成果と効率の両立が可能になります。
- SNS(Instagram、Xなど)の投稿企画・代行
- YouTubeや採用動画の撮影・編集・アップロード
- GoogleやMetaなどの採用広告の出稿・運用最適化
- レポーティングと改善提案の継続的な実施
「社内で判断するべきこと(ビジョン・方針)」と、「外注すべきこと(制作・運用)」を明確に切り分けることで、現場の負担を最小限に抑えながらも、継続的に成果を出しやすい体制を整えることができます。
まとめ:採用マーケティングで自社に合う人材と出会う
採用マーケティングは、単なる採用手法のひとつではなく、企業の魅力を本質的に伝えるための戦略です。自社の理念や文化に共感する人材と出会うためには、ターゲット設計から情報発信、接点づくりまでを一貫して設計する必要があります。
従来の「募集 → 応募 → 面接」という一方向の流れから、候補者との双方向の関係構築へと視点を転換することで、採用活動はより深みのあるものへと変わります。
ただし、実践にはノウハウやリソースが求められるため、必要に応じて外部の専門家や運用代行サービスを活用することも効果的です。重要なのは、自社の採用課題に真正面から向き合い、継続的に改善を重ねていく姿勢です。
時代に合ったアプローチで、企業と求職者の最適な出会いを実現する──。それこそが、採用マーケティングの本質的な価値だと言えるでしょう。
「採用マーケティングを始めたいけれど、自社の魅力をどう伝えればいいか分からない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、私たち株式会社Piicがお手伝いします。
Piicは、採用サイト・動画・SNS投稿・採用ピッチ資料などの制作を通じて、企業の魅力や想いを“伝わるカタチ”にすることを得意としています。「選ばれる企業」に変わるためのクリエイティブ支援を、ぜひご活用ください。








