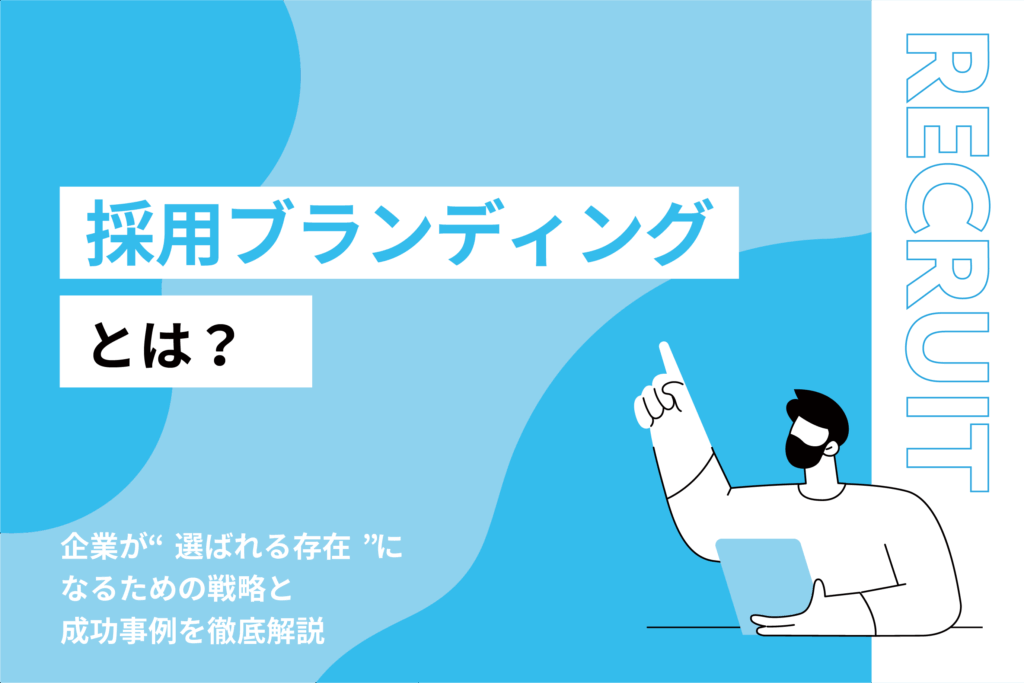
採用活動において、こんなお悩みはありませんか?
- 求職者から選ばれるために、何を発信すればよいのかわからない
- 自社の魅力がうまく言語化できていない
- 応募はあるが、ミスマッチや早期離職が多い
そんな悩みを解決するカギが「採用ブランディング」です。
単なる広報ではなく、「共感を呼び、カルチャーにフィットする人材を惹きつけるための戦略」として、今あらためて注目されています。
この記事では、採用ブランディングの定義やメリット、具体的な進め方、支援会社の選び方までを網羅的に解説します。
採用力を高めたい中小企業や、スタートアップの採用担当者、経営者の方にとって必見の内容です。
自社らしい採用活動を通じて、理想の仲間と出会いたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
Index
-
採用ブランディングとは
-
採用ブランディングの定義と目的
-
採用ブランディングの進め方
-
STEP1:現状分析
-
STEP2:ターゲット設計
-
STEP3:コンセプト開発
-
STEP4:コンテンツ制作
-
STEP5:運用と改善
-
採用ブランディングのメリット
-
採用ブランディングの課題・懸念点
-
採用ブランディングの支援会社との連携
-
採用ブランディング支援会社の選び方
-
費用と期間の目安
-
成功事例に学ぶ採用ブランディングの効果
-
事例①:中堅IT企業の技術者採用
-
事例②:介護・福祉業界の若手採用
-
事例③:老舗メーカーの採用ブランディング刷新
-
採用ブランディングの未来:今後求められる視点とは
-
社員を巻き込んだ採用ブランディングの効果
-
ブランディングが強い会社の共通点
-
採用クリエイティブのご相談はPiicへ
採用ブランディングとは
採用ブランディングとは、企業が採用活動において自社の魅力や価値観を戦略的に発信し、求職者から「この会社で働きたい」と思われるブランドイメージを構築する取り組みです。単に人手不足を補うための活動ではなく、企業のミッション・ビジョン・カルチャーに共感する人材との出会いを創出し、中長期的な組織成長を促す採用戦略の一つです。
採用市場では、売り手市場が続く中で求職者が企業を選ぶ目が厳しくなっています。給料や福利厚生といった条件面だけではなく、働く意義や企業の姿勢、風土といった“見えない価値”が重視されるようになった今、採用ブランディングはもはや必須の取り組みと言えるでしょう。
採用ブランディングの定義と目的
採用ブランディングの目的は、「自社にマッチする人材と、長期的な関係を築くこと」です。具体的には以下の3つに集約されます:
- 魅力の可視化:企業のビジョン・文化・働く環境など、言語化しづらい魅力を伝える
- 共感の醸成:求職者が企業の価値観に触れ、「自分らしく働けるか」を判断できるようにする
- 採用効果の最大化:応募率や定着率、社員の活躍度を高める
このように、採用ブランディングは企業が選ばれる存在になるための“土台づくり”であり、広告や紹介といった短期的手法と異なり、中長期的な視点で取り組む必要があります。
採用ブランディングの進め方
STEP1:現状分析
まずは自社の採用活動における課題と強みを明確にするところから始めます。過去の採用データ(応募数、通過率、辞退率、定着率など)を洗い出し、どの段階に課題があるのかを特定します。また、社員アンケートや退職者インタビューを通じて、自社の魅力や内的課題を“当事者の声”として拾うことが有効です。
STEP2:ターゲット設計
どんな人材を採用したいのかを明文化します。求めるスキルや経験だけでなく、価値観や志向性、働き方への意識、将来ビジョンまで含めて“人物像”として描きます。ここで定義したペルソナが、その後のコンセプト設計やコンテンツ制作における軸になります。
STEP3:コンセプト開発
企業のらしさを言語化するフェーズです。自社の文化やビジョン、働く意義を踏まえ、「この会社だからこそ得られる体験とは何か?」を言葉で定義します。抽象的な表現ではなく、採用現場で使える具体的なメッセージ(例:「地方から世界へ挑む若手を採用」「3年後にリーダーになる成長環境」など)に落とし込むことが重要です。
STEP4:コンテンツ制作
採用サイト、動画、パンフレット、SNSなど、求職者との接点で伝える手段を設計・制作します。媒体ごとに最適なフォーマットやトーンを設計しつつ、一貫したブランドイメージを保つことがポイントです。特に社員インタビューや現場紹介コンテンツは、リアリティと信頼性を高める鍵になります。
STEP5:運用と改善
ブランディングは「作って終わり」ではなく、継続的な運用と改善が必要です。採用KPI(応募数、面接通過率、内定承諾率、定着率など)を定点観測し、効果を測定。必要に応じてコンテンツをアップデートしたり、新しい接点(SNSやオウンドメディアなど)を増やす取り組みを行います。
特に重要なのは「属人化しないこと」。人事担当者だけに任せるのではなく、経営層・現場社員・広報などと連携して全社的な取り組みにすることが成功のカギとなります。
採用ブランディングのメリット
採用ブランディングを進めることで、以下のような成果が期待できます:
- 応募数の増加:採用サイトやSNSを通じて、自社を認知・理解してもらうきっかけが増える
- ミスマッチの削減:企業のカルチャーや実態を正確に伝えることで、入社後のギャップを防止
- 定着率・活躍率の向上:共感を持って入社した人材は、主体的に働き、成果を出しやすい
- 採用コストの抑制:広告費や紹介料に依存せず、自走型の採用活動が可能に
- 社員のモチベーション向上:企業の魅力を再認識することで、誇りやロイヤリティが高まる
特に「カルチャーフィット」を重視する現代の採用においては、表面的な条件ではなく、企業と個人の価値観の一致が重視されます。その意味で、採用ブランディングは組織の未来をつくる基盤戦略といえるでしょう。
採用ブランディングの課題・懸念点
一方で、採用ブランディングには以下のような課題も存在します:
- 成果が出るまでに時間がかかる:短期間で効果が見えづらく、継続的な取り組みが必要
- 制作・運用にコストがかかる:質の高い採用サイトや動画の制作には、一定の予算が必要
- 社内の協力が得られにくい:経営層や現場社員の巻き込みに苦労するケースも
- 美化しすぎた情報は逆効果:過剰演出によるリアリティの欠如は、入社後のミスマッチを招く
これらの課題を乗り越えるためには、外部パートナーの活用や段階的なステップ実行、社内広報との連携などが有効です。無理に全てを内製しようとせず、必要な部分は外部の知見を借りることで、持続可能なブランディングが実現できます。
採用ブランディングの支援会社との連携
採用ブランディングを内製化することは理想的ですが、現実にはリソースやノウハウ不足により限界がある企業も少なくありません。そこで有効なのが、ブランディングに特化した支援会社との連携です。外部パートナーの活用により、戦略の設計・ビジュアル表現・コンテンツ制作・運用支援までを一貫して推進でき、専門的な知見を活かすことが可能になります。
たとえば、採用サイトの構築や動画制作、SNSアカウントの運用支援など、自社単独では対応が難しい領域において、支援会社の力を借りることでスピード感のある展開が可能です。また、第三者視点による強み・課題の抽出もブランディングの精度向上に寄与します。
採用ブランディング支援会社の選び方
数多くある支援会社の中から、自社に合ったパートナーを選ぶには以下の観点が重要です。
- 実績の有無:自社と同じ業界や規模の企業への支援実績があるか
- 戦略力と表現力のバランス:デザイン重視に偏らず、採用戦略を設計できるか
- 担当者との相性:提案力や理解力、プロジェクト推進力の高さ
- 納品後の支援体制:納品して終わりではなく、改善や運用支援があるか
特に重要なのは、単なる制作代行ではなく「採用目標から逆算したブランディング設計」を行えるパートナーであるかどうかです。そのためには、打ち合わせの初期段階でヒアリングの質や提案の筋の良さを確認するとよいでしょう。
費用と期間の目安
採用ブランディングにかかる費用と期間は、取り組みの範囲によって大きく異なります。以下は一例です:
| 支援内容 | 費用目安(税込) | 納期目安 |
| 採用ピッチ資料制作 | 15〜30万円 | 2〜4週間 |
| 採用サイト(3〜5ページ) | 50〜100万円 | 1〜2ヶ月 |
| 採用動画(社員インタビューなど) | 30〜80万円 | 3〜5週間 |
| SNS運用支援(Instagram/TikTok) | 月額10〜30万円 | 初月準備+月次運用 |
| 総合ブランディング支援(戦略設計〜制作一式) | 100〜200万円 | 2〜3ヶ月 |
予算に応じて、段階的に取り組むケースも多く、まずは採用パンフレットや動画制作から着手し、効果を見ながら他施策へ展開することも可能です。
成功事例に学ぶ採用ブランディングの効果
事例①:中堅IT企業の技術者採用
IT業界でエンジニア採用に苦戦していたA社は、社員インタビューを軸にした採用サイトを制作。技術へのこだわりや育成体制を明文化し、職場のリアルな雰囲気を動画で発信したところ、採用ページの閲覧数が3倍に増加。ターゲット人材からの応募が急増し、内定承諾率も大幅に改善されました。
事例②:介護・福祉業界の若手採用
「きつい・汚い・休めない」という業界イメージが強かったB社は、20代職員の声を反映した採用パンフレットと、働き方改革の取り組みを発信。専門学校への訪問時に活用した結果、採用説明会への参加率が前年比170%に増加。新卒採用枠が全て充足されました。
事例③:老舗メーカーの採用ブランディング刷新
創業100年を超えるC社は「堅そう」というイメージが先行し、若手人材の確保に課題がありました。そこでブランドロゴやコーポレートスローガンの刷新を行い、新たなビジュアルイメージで採用サイトを制作。若手社員によるInstagram発信も並行して進めた結果、「変化に挑戦している会社」という印象が広がり、エントリー数は前年比240%に伸長しました。
採用ブランディングの未来:今後求められる視点とは
採用ブランディングは、企業の“らしさ”を内外に伝える活動としてすでに多くの企業で取り組まれ始めていますが、今後はさらに「体験価値」や「候補者視点」が重視されるようになっていくと考えられます。求職者が自分ごととして会社を感じられるようなインターン設計、動画コンテンツ、ダイレクトリクルーティングのコミュニケーション設計など、よりパーソナライズされたブランディングが重要になります。
また、Z世代の台頭により、企業の透明性や社会的意義、働きがいといったテーマがますます重視されています。「この会社で働くことは、自分の人生にどうつながるか」までを伝える必要があります。そのため、単なる見た目の良いデザインではなく、“語れる中身”が求められるようになります。
採用ブランディングは、採用の枠にとどまらず、企業ブランディングそのものと接続する時代に突入しています。人が集まり、人が辞めず、人が育つ企業を目指すなら、いまこそ採用ブランディングを再定義すべきタイミングなのです。
社員を巻き込んだ採用ブランディングの効果
採用ブランディングを企業全体の文化形成にまで昇華させるためには、「社員の巻き込み」が不可欠です。実際に働いている社員の声や表情をコンテンツ化することで、求職者にとっての信頼性やリアリティが高まり、入社後のギャップを防ぐことにもつながります。
たとえば、社員が登場するインタビュー動画やSNS投稿、座談会記事、社内ブログなどは、応募者にとって「この会社の人と働いてみたい」と感じる強いきっかけとなります。また、社内でも「採用は自分ごとである」という認識が育ち、社員の定着やエンゲージメント向上にも寄与します。
採用ブランディングは、経営・人事・広報だけの専売特許ではありません。全社員でつくる、未来の仲間を迎え入れるカルチャーそのものなのです。
ブランディングが強い会社の共通点
成功している企業の採用ブランディングには、いくつかの共通点があります:
- 一貫したメッセージ:どの接点においても、企業の価値観や姿勢がブレていない
- 社員のリアルが見える:職場の雰囲気や人間関係、仕事への想いがコンテンツ化されている
- 求職者視点に立っている:“伝えたいこと”ではなく“知りたいこと”を優先して設計されている
- 社内からの共感:社員自身が「自分たちらしい」と感じる表現である
つまり、デザインやツールの話ではなく「理念と行動の整合性」が採用ブランディングの本質だと言えます。
採用クリエイティブのご相談はPiicへ
Piicでは、採用ピッチ資料・採用サイト・パンフレットなど、採用活動に必要なクリエイティブを一貫して企画・制作しています。
企業の“らしさ”を言語化し、求職者に正しく・魅力的に伝えることで、共感採用やミスマッチの防止を実現します。
「採用にブレない軸を持ちたい」「自社の魅力をうまく伝えられていない」──
そんなときは、ぜひ私たちにご相談ください。








