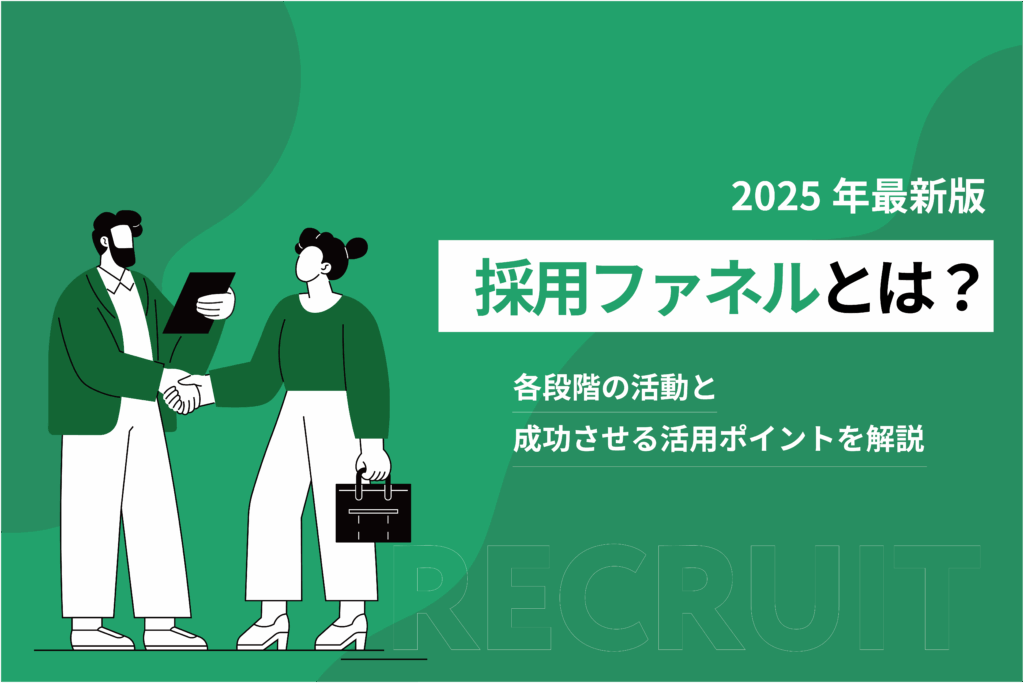
採用ファネルとは、候補者が自社を認知してから入社に至るまでのプロセスを段階的に可視化するフレームワークです。
現代の採用市場では、多様化する採用手法や候補者の行動変化に対応するため、戦略的な採用活動が不可欠になっています。
この記事では、採用ファネルの基本的な考え方から、注目される理由、各段階で実行すべき具体的な活動、そして活用効果を最大化させるためのポイントまでを解説します。

Index
-
採用ファネルとは?採用活動の全体像を可視化するフレームワーク
-
今、採用ファネルが注目される3つの理由
-
理由1:採用手法の多様化で戦略的な活動が必要になったため
-
理由2:候補者の価値観や行動が大きく変化したため
-
理由3:データに基づいた採用活動の改善が求められるため
-
採用活動にファネル分析を取り入れる3つのメリット
-
メリット1:採用プロセスにおける課題点を具体的に特定できる
-
メリット2:各段階での離脱率を改善し、母集団形成を強化できる
-
メリット3:採用ミスマッチの防止と早期離職のリスクを軽減できる
-
【5つの段階別】採用ファネルで実行すべき施策例
-
第1段階「認知」:まずは自社を知ってもらうための施策
-
第2段階「興味・関心」:候補者の関心を惹きつけ、理解を深める施策
-
第3段階「応募」:スムーズな応募体験を提供するための施策
-
第4段階「選考・内定」:候補者の入社意欲を高めるための施策
-
第5段階「入社・定着」:入社後のミスマッチを防ぎ、活躍を支援する施策
-
採用ファネルの活用効果を最大化させる3つのポイント
-
ポイント1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確に定義する
-
ポイント2:各段階の移行率を計測し、改善を繰り返す
-
ポイント3:現場の意見を取り入れ、全社で採用活動に取り組む
-
よくあるご質問
-
Q1:採用ファネルの各段階における理想的な移行率(歩留まり率)の目安はありますか?
-
Q2:採用ファネル分析に役立つツールにはどのようなものがありますか?
-
Q3:中小企業でも採用ファネルは有効ですか?
-
Q4:採用ファネルを導入する際、最初に何から始めるべきですか?
-
Q5:採用ファネル分析で改善策を実施した後、効果測定はどのように行えば良いですか?
-
まとめ
採用ファネルとは?採用活動の全体像を可視化するフレームワーク
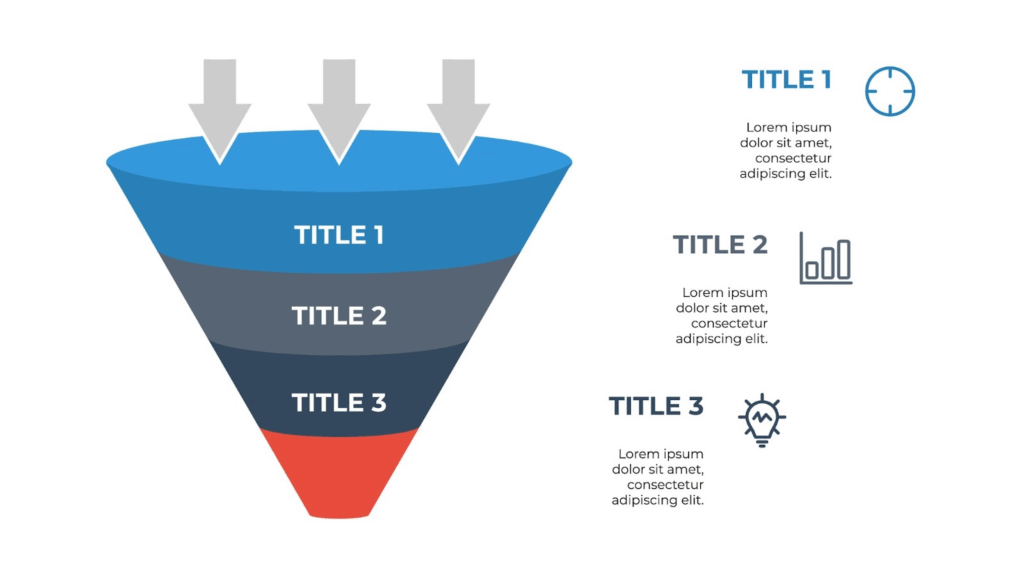
採用ファネルとは、マーケティングで用いられるパーチェスファネルの考え方を採用活動に応用したものです。
候補者が企業を認知し、興味を持ち、応募、選考を経て入社するまでの一連のプロセスを、漏斗のような逆三角形の図で表します。
各段階に進むにつれて候補者の数が絞られていく様子を可視化することで、採用活動の全体像を把握し、どの段階に課題があるのかを特定しやすくなるのが特徴です。
今、採用ファネルが注目される3つの理由
近年の採用市場の変化に伴い、多くの企業が採用ファネルの考え方に注目しています。
かつてのような画一的な採用手法だけでは、優秀な人材の獲得が難しくなっているのが現状です。
採用活動にマーケティングの視点を取り入れ、データに基づいた戦略的なアプローチを行う必要性が高まっています。
ここでは、採用ファネルが現代の採用活動において重要視されるようになった3つの理由を解説します。
理由1:採用手法の多様化で戦略的な活動が必要になったため
従来の求人広告に加え、ダイレクトリクルーティングやSNS、リファラル採用など、企業が候補者と接点を持つ手段は多岐にわたります。
これらの多様な採用手法を場当たり的に運用するのではなく、どの手法がファネルのどの段階に有効かを整理し、戦略的に組み合わせる必要があります。
例えば、SNSでの発信は「認知」拡大に、カジュアル面談は「興味・関心」の醸成に効果的です。
採用活動が企業の魅力を伝える広報活動としての側面も強まる中で、一貫した戦略を描くために採用ファネルが役立ちます。
理由2:候補者の価値観や行動が大きく変化したため
インターネットやSNSの普及により、候補者は企業の公式情報だけでなく、口コミサイトや社員のSNSなどを通じて、能動的に情報を収集するようになりました。
特に新卒採用、中途採用を問わず、給与や待遇といった条件面だけでなく、企業文化や働きがい、社会貢献性といった価値観のマッチングを重視する傾向が強まっています。
このような候補者の変化に対応するためには、採用ファネルの各段階で、候補者が求める情報を適切なタイミングで提供し、深い企業理解を促していくアプローチが求められます。
理由3:データに基づいた採用活動の改善が求められるため
これまでの経験や勘に頼った採用活動から脱却し、客観的なデータに基づいて意思決定を行う「データドリブン採用」への移行が進んでいます。
採用ファネルは、各段階の候補者数や移行率、離脱率といった数値を可視化するためのフレームワークとして非常に有効です。
例えば、「応募から面接への移行率が低い」というデータが得られれば、書類選考の基準や応募後の連絡スピードに課題がある可能性を特定できます。
これにより、企業の採用力を刷新し、継続的な改善活動を促進させることが可能です。
採用活動にファネル分析を取り入れる3つのメリット

採用ファネルを導入し、各段階のデータを分析する「ファネル分析」は、企業の採用活動に多くのメリットをもたらします。
単に候補者を集めるだけでなく、採用プロセス全体を最適化し、質の高い採用を実現するために不可欠なアプローチです。
ここでは、ファネル分析を取り入れることで得られる具体的な3つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
メリット1:採用プロセスにおける課題点を具体的に特定できる
採用ファネルを用いる最大のメリットは、採用プロセス上のボトルネックを客観的な数値で特定できる点です。
例えば、「認知」から「応募」までの歩留まりは高いものの、「一次面接」から「二次面接」への移行率が著しく低い場合、一次面接の内容や面接官の対応に課題があるのではないか、という仮説を立てられます。
このように、漠然とした課題感ではなく、「どこで」「どれくらい」候補者が離脱しているのかを具体的に把握できるため、的を射た改善策を効率的に検討、実行することが可能になります。
メリット2:各段階での離脱率を改善し、母集団形成を強化できる
ファネル分析によって課題が特定できれば、各段階での離脱率を改善するための具体的な施策を講じられます。
例えば、応募フォームの入力項目が多くて離脱しているなら簡素化する、選考結果の連絡が遅くて辞退されているなら迅速化するなどです。
一つひとつの段階で離脱を減らすことで、次の段階へ進む候補者の数が増加します。
これにより、最終的な内定承諾者の数を確保しやすくなるだけでなく、より多くの候補者の中から自社にマッチした人材を選べるようになり、採用の質そのものの向上、つまり母集団形成の強化が実現します。
メリット3:採用ミスマッチの防止と早期離職のリスクを軽減できる
採用ファネルの各段階において、企業理念や事業内容、働き方といった情報を一貫して丁寧に伝えることは、候補者の企業理解を深める上で非常に重要です。
候補者は選考が進むにつれて、よりリアルな情報を求めるようになります。
この過程で、良い面だけでなく課題なども含めてオープンに共有することで、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージでき、納得感を持って意思決定ができます。
結果として、入社後に「こんなはずではなかった」という採用ミスマッチが起こるのを防ぎ、早期離職のリスクを大幅に軽減することに繋がります。
【5つの段階別】採用ファネルで実行すべき施策例

採用ファネルは、一般的に「認知」「興味・関心」「応募」「選考・内定」「入社・定着」という5つの段階で構成されます。
候補者はこれらの段階を順に進んでいくため、それぞれのフェーズにおける候補者の心理や行動を理解し、適切な施策を実行することが重要です。
ここでは、各段階の目的と、その目的を達成するために有効な施策の具体例を紹介します。
第1段階「認知」:まずは自社を知ってもらうための施策
この段階の目的は、自社の採用ターゲットとなる潜在層に、企業の存在や採用活動を行っている事実を知ってもらうことです。
まだ自社を知らない、あるいは転職や就職を具体的に考えていない層へのアプローチが中心となります。
具体的な施策としては、幅広い層にリーチできる求人広告サイトへの掲載、企業の魅力を発信するオウンドメディアやSNSの運用、業界イベントや合同説明会への出展などが挙げられます。
ターゲットがどのような媒体や情報源に触れているかを分析し、効果的なチャネルを選ぶことが重要です。
第2段階「興味・関心」:候補者の関心を惹きつけ、理解を深める施策
自社を認知した候補者に対して、さらに一歩踏み込んだ情報を提供し、「この会社で働くことに興味がある」と感じてもらう段階です。
ここでは、企業のビジョンや事業内容、社風、働く人の魅力などを伝え、企業理解を深めてもらうことが目的となります。
施策例としては、社員インタビューや一日の仕事の流れを紹介するコンテンツをWebサイトに掲載したり、現場社員と気軽に話せるカジュアル面談を実施したりすることが有効です。
また、会社の雰囲気が伝わるような採用ピッチ資料の公開や、インターンシップの開催も候補者の関心を高めます。
第3段階「応募」:スムーズな応募体験を提供するための施策
企業への興味関心が高まり、いよいよ応募へとアクションを起こす段階です。
この段階では、候補者が応募をためらったり、途中で諦めたりすることなく、スムーズに応募を完了できる環境を整えることが最も重要になります。
例えば、応募フォームの入力項目を必要最小限に絞る、履歴書や職務経歴書のフォーマットを限定しない、スマートフォンからでも簡単に入力送信できるデザインにする、といった改善が考えられます。
応募のハードルを下げることで、意欲の高い候補者を取りこぼすリスクを減らせます。
第4段階「選考・内定」:候補者の入社意欲を高めるための施策
応募者の中から自社にマッチする人材を見極めると同時に、候補者からの企業に対する評価も決まる重要な段階です。
選考プロセス全体を通じて、候補者の入社意欲を高めていく意識が求められます。
面接官の質問スキルや態度の質を高めるためのトレーニング、選考結果の迅速な通知、候補者の疑問や不安を解消するための現場社員との座談会の設定などが有効な施策です。
内定を出した後も、定期的なコミュニケーションや内定者懇親会などを通じて、入社までの不安を解消し、繋がりを維持することが大切です。
第5段階「入社・定着」:入社後のミスマッチを防ぎ、活躍を支援する施策
採用活動の成功は、内定承諾ではなく、入社した社員が組織に定着し、本来の能力を発揮して活躍することです。
入社後のギャップを最小限に抑え、スムーズな立ち上がりを支援するための取り組みが不可欠となります。
具体的な施策としては、入社前から配属部署のメンバーと交流する機会を設けたり、入社後には体系的なオンボーディングプログラムを実施したりすることが挙げられます。
また、新入社員一人ひとりに先輩社員が指導役としてつくメンター制度や、定期的な1on1ミーティングも、早期の戦力化と定着率向上に効果的です。
採用ファネルの活用効果を最大化させる3つのポイント

採用ファネルのフレームワークを導入するだけでは、採用成果が向上するわけではありません。
その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、採用ファネルをより効果的に活用し、採用成功へと繋げるための3つのポイントについて解説します。
これらのポイントを意識して取り組むことで、採用活動全体の質が向上します。
ポイント1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確に定義する
どのような人材を採用したいのかが曖昧なままでは、採用ファネルの各段階で打つべき施策も的が外れたものになってしまいます。
まずは、現場の部署や経営層と連携し、採用したい人物像、いわゆる「ペルソナ」を具体的に定義することが不可欠です。
保有スキルや業務経験といった顕在的な要素だけでなく、価値観や志向性、行動特性といった潜在的な要素まで詳細に設定します。
ペルソナが明確であれば、その人物に響くメッセージを発信でき、ファネル全体の移行率を高めることが可能になります。
ポイント2:各段階の移行率を計測し、改善を繰り返す
採用ファネルは、一度作成して終わりではありません。
重要なのは、各段階の候補者数や移行率(歩留まり率)を継続的に計測し、そのデータに基づいて改善を繰り返していくことです。
例えば、「書類選考通過率」や「一次面接通過率」、「内定承諾率」などをKPIとして設定し、定期的に数値を追跡します。
数値が想定よりも低い段階があれば、そこがボトルネックであると特定し、原因の仮説を立てて改善策を実施します。
このPDCAサイクルを回し続けることで、採用プロセスは着実に最適化されていきます。
ポイント3:現場の意見を取り入れ、全社で採用活動に取り組む
採用は人事部門だけのミッションではなく、企業全体の成長に関わる重要な活動です。
特に、実際に候補者と働くことになる現場部門との連携は不可欠です。
ペルソナの設計や面接の評価基準作りにおいては、現場のリアルな意見を積極的に取り入れるべきです。
また、現場社員に面接官として協力してもらったり、社員紹介(リファラル採用)を推進してもらったりと、全社を巻き込んだ採用体制を構築することが重要です。
経営層から現場までが一体となり、採用に対する当事者意識を持つことで、採用活動の精度と成功確率は格段に高まります。
よくあるご質問
ここでは、採用ファネルに関するよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。採用ファネルの導入や運用を進める中で生じる疑問を解消し、より効果的な採用活動の一助としてご活用ください。
Q1:採用ファネルの各段階における理想的な移行率(歩留まり率)の目安はありますか?
A1:一般的に、業界や職種、企業の知名度によって移行率は大きく変動するため、一概に「理想的な数値」を提示することは難しいです。まずは過去の採用データを基に自社の平均的な移行率を算出し、それをベンチマークとして設定することをおすすめします。他社の事例はあくまで参考とし、自社の状況に合わせた目標設定が重要です。
Q2:採用ファネル分析に役立つツールにはどのようなものがありますか?
A2:採用ファネル分析には、採用管理システム(ATS)やタレントマネジメントシステムが有効です。これらのツールは、候補者情報の管理から選考状況のトラッキング、各段階でのデータ計測、レポート作成までを自動化し、採用ファネル全体の可視化と分析をサポートします。Excelなどのスプレッドシートでも管理は可能ですが、データ量が増えると手間がかかるため、専用ツールの導入を検討すると良いでしょう。
Q3:中小企業でも採用ファネルは有効ですか?
A3:はい、中小企業でも採用ファネルは非常に有効です。企業規模に関わらず、採用活動における課題を特定し、効率的な改善を図るためのフレームワークとして活用できます。特にリソースが限られている中小企業においては、採用ファネルによって「どこに注力すべきか」が明確になり、費用対効果の高い採用活動を実現することに繋がります。
Q4:採用ファネルを導入する際、最初に何から始めるべきですか?
A4:採用ファネルを導入する際の最初のステップは、採用したい人物像(ペルソナ)を明確に定義することです。ペルソナが曖昧なままでは、効果的な施策を打つことができません。現場の社員とも連携し、どのようなスキルや経験、価値観を持つ人材が必要なのかを具体的に言語化しましょう。それができたら、次に現状の採用プロセスをファネルの各段階に落とし込み、課題を洗い出す作業に進みます。
Q5:採用ファネル分析で改善策を実施した後、効果測定はどのように行えば良いですか?
A5:改善策を実施した後は、再度各段階の移行率(歩留まり率)を計測し、施策実施前と比較して数値がどのように変化したかを評価します。例えば、応募フォームを簡素化したのであれば、その後の「認知」から「応募」への移行率が向上しているかを確認します。効果が認められればその施策は継続し、改善が見られない場合は、別の原因を探り、新たな改善策を検討するといったPDCAサイクルを回していくことが重要です。
まとめ
採用ファネルは、候補者の認知から入社・定着までの一連のプロセスを可視化し、採用活動における課題を特定・改善するための強力なフレームワークです。
採用手法が多様化し、候補者の価値観が変化する現代において、データに基づいた戦略的な採用活動を行う上でその重要性は増しています。
採用したい人物像を明確に定義した上で、ファネルの各段階で適切な施策を実行し、数値を計測しながら継続的に改善を繰り返すことが求められます。
また、人事部だけでなく現場部門も巻き込み、全社一丸となって取り組む姿勢が、採用ファネルの活用効果を最大化させます。
ただ、採用ファネルの改善だけでは、優秀な人材の心は動きません。
Piic(ピーク)は、採用サイト・ピッチ資料・パンフレットを通じて、企業の“らしさ”を形にし、候補者の共感と応募意欲を高める採用ブランディングを実現します。
「選ばれる理由」をデザインでつくる——それがPiicの採用支援です。








