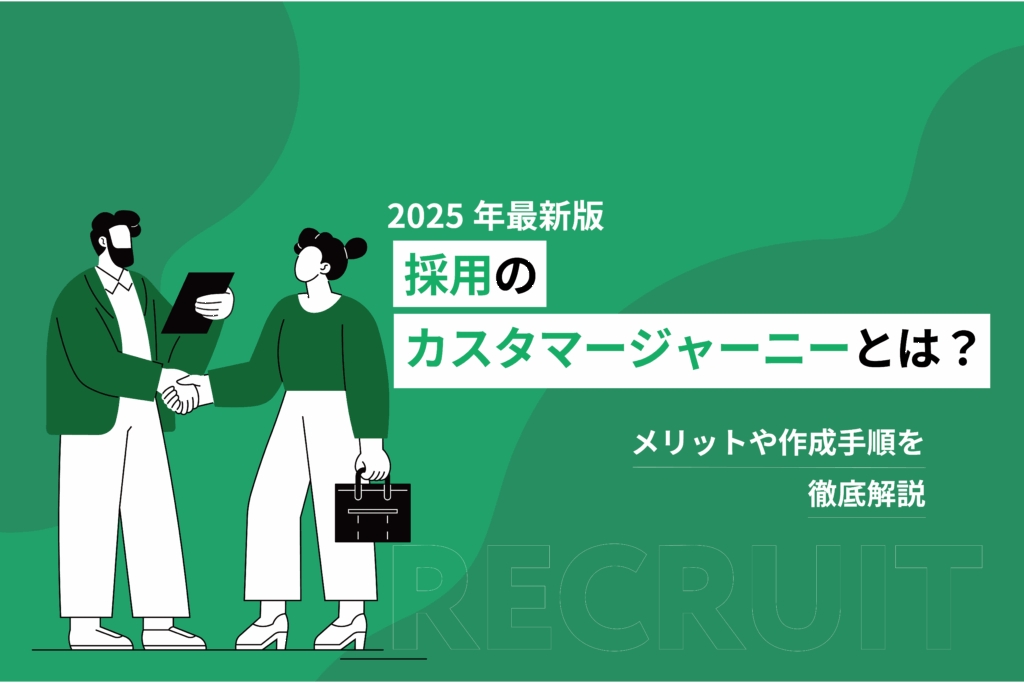
採用のカスタマージャーニーとは、求職者が企業を認知してから応募、選考、そして入社に至るまでの一連の体験を「旅」になぞらえて可視化するマーケティングの手法です。
この手法を用いることで、求職者の視点に立った採用戦略を設計し、各段階で最適なアプローチを実行できます。
本記事では、採用活動におけるカスタマージャーニーの基礎知識から、具体的なメリット、マップの作成手順、そして効果的な活用法までを分かりやすく解説します。
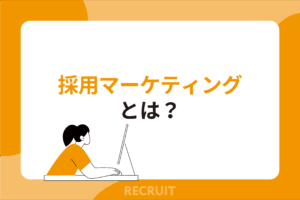
Index
-
採用活動で注目されるカスタマージャーニーの基本
-
採用にカスタマージャーニーを導入する5つのメリット
-
求める人材に的確なアプローチができる
-
入社後のミスマッチを未然に防ぐ
-
根拠に基づいた採用戦略を立てられる
-
採用チーム内で共通認識を持てる
-
採用活動の費用対効果が向上する
-
採用カスタマージャーニーマップの作り方【4ステップで解説】
-
ステップ1:採用活動のゴールを明確に設定する
-
ステップ2:採用したい人物像(ペルソナ)を具体化する
-
ステップ3:ペルソナの行動と感情を時系列で洗い出す
-
ステップ4:フレームワークに沿ってマップを完成させる
-
作成したマップを効果的に活用するための3つのポイント
-
常に求職者の立場に立って考える
-
一度作って終わりにせず、定期的に見直す
-
チーム全体でマップを共有し、日々の活動に活かす
-
よくあるご質問
-
Q1.カスタマージャーニーマップの作成にはどれくらいの時間がかかりますか?
-
Q2.ペルソナは複数設定しても良いですか?
-
Q3.専門のツールを使わなくても作成できますか?
-
Q4.小規模な企業でも導入するメリットはありますか?
-
Q5.マップ作成後、何から手をつければ良いですか?
-
まとめ
採用活動で注目されるカスタマージャーニーの基本

もともとマーケティング分野で活用されていたカスタマージャーニーは、顧客が商品やサービスを知り、購入に至るまでのプロセスを図式化したものです。
この考え方を採用活動に応用したものが「採用のカスタマージャーニー」と呼ばれます。
求職者を「顧客」と捉え、彼らがどのような思考や感情で就職・転職活動を進めるのかを時系列で追い、企業との接点ごとに最適なコミュニケーションを設計することで、採用力の強化を図ります。
採用にカスタマージャーニーを導入する5つのメリット

採用活動にカスタマージャーニーを導入すると、求職者一人ひとりの視点に立ったきめ細やかなアプローチが可能になります。
これにより、求める人材との出会いを創出し、入社後の定着率向上にも良い影響を与えます。
また、採用チーム内での認識統一や、データに基づいた戦略的な採用計画の立案にも役立つでしょう。
ここでは、導入によって得られる具体的な下記5つのメリットを掘り下げていきます。
- 求める人材に的確なアプローチができる
- 入社後のミスマッチを未然に防ぐ
- 根拠に基づいた採用戦略を立てられる
- 採用チーム内で共通認識を持てる
- 採用活動の費用対効果が向上する
求める人材に的確なアプローチができる
求職者がどのタイミングでどのような情報を求めているのかを深く理解できるようになります。
例えば、転職を考え始めたばかりの「認知」段階の候補者には、いきなり求人情報を送るのではなく、まずは企業のビジョンや業界の動向に関する情報を提供した方が興味を引きやすいかもしれません。
このように、各フェーズにおける候補者の心理状態や行動を予測し、それに合わせた情報発信や接触方法を選択することで、アプローチの精度を高め、自社への関心を効果的に醸成できます。
入社後のミスマッチを未然に防ぐ
入社後のミスマッチは、企業と求職者の間で期待値にズレがある場合に発生しがちです。
カスタマージャーニーを作成する過程で、求職者が抱くであろう疑問や不安を事前に洗い出すことができます。
例えば、「選考中に職場のリアルな雰囲気が分からない」という不安が想定されるなら、面接の場に現場の社員を同席させたり、オフィスツアーを実施したりといった対策を講じられます。
求職者の期待や懸念に先回りして応えることで、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを最小限に抑えられます。
根拠に基づいた採用戦略を立てられる
これまでの採用活動が担当者の経験や勘に頼りがちだった場合、カスタマージャーニーを導入することで、より客観的なデータに基づいた戦略立案が可能になります。
各選考フェーズでの離脱率が高い、特定媒体からの応募が少ないといった課題を特定し、その原因が「求職者のどの段階の、どのような体験」にあるのかを仮説立てて検証できるようになります。
これにより、施策の優先順位付けが明確になり、根拠のある採用計画を策定し、実行できます。
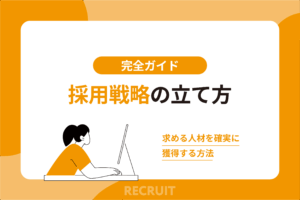
採用チーム内で共通認識を持てる
採用活動には、人事担当者だけでなく、現場の面接官や役員など多くの人が関わります。
カスタマージャーニーマップは、採用したい人物像(ペルソナ)や、各選考段階でのアプローチ方針を可視化するツールとして機能します。
このマップをチーム全体で共有することで、「誰に」「いつ」「何を伝えるべきか」という認識が統一され、一貫性のあるメッセージを求職者に届けられます。
担当者によって言うことが違うといった事態を防ぎ、組織全体で質の高い採用活動を展開できます。
採用活動の費用対効果が向上する
求職者の行動プロセスと各接点での課題が明らかになるため、効果の薄い施策をやめ、より効果的な施策に予算や人員を集中させられます。
例えば、内定辞退が多いという課題がある場合、その原因が内定後のフォロー不足にあると特定できれば、広告費を増やすのではなく、内定者向けのイベントやコミュニケーション施策にリソースを振り分けるといった判断ができます。
このように、課題に対して的確な打ち手を講じることで、無駄なコストを削減し、採用活動全体の費用対効果を改善できます。

採用カスタマージャーニーマップの作り方【4ステップで解説】

採用カスタマージャーニーマップは、求職者の視点に立った採用活動を実現するための設計図です。
このマップを作成することで、求職者が企業を認知してから入社するまでのプロセスで、どのような感情を抱き、どのような情報を求めているのかを可視化できます。
これから紹介する下記4つのステップに沿って進めることで、自社の採用課題を解決に導く、効果的なカスタマージャーニーマップを作成できるでしょう。
- 採用活動のゴールを明確に設定する
- 採用したい人物像(ペルソナ)を具体化する
- ペルソナの行動と感情を時系列で洗い出す
- フレームワークに沿ってマップを完成させる
ステップ1:採用活動のゴールを明確に設定する
最初に、今回の採用活動で何を達成したいのか、具体的な目標を定めます。
例えば、「2026年度の新卒採用で、エンジニア職を10名採用する」「3ヶ月以内に、即戦力となるマーケティング担当の中途採用を1名決定する」といったように、職種、人数、期間などを具体的に設定します。
ゴールが曖昧なままだと、その後の人物像の設定や施策の検討がぶれてしまう可能性があります。
チーム全体で目指すべきゴールを共有し、採用活動の方向性を一致させることが、最初の重要なステップです。
ステップ2:採用したい人物像(ペルソナ)を具体化する
次に、設定したゴールに基づいて、どのような人材を採用したいのか、具体的な人物像(ペルソナ)を詳細に設定します。
新卒採用であれば、学部、サークル活動、価値観、就職活動で重視することなどを考えます。
中途採用の場合は、年齢、経歴、スキル、転職理由、情報収集の方法といった項目を具体的に描きます。
このペルソナが実在の人物であるかのように、ライフスタイルや性格まで深掘りすることで、その後の行動や感情の洗い出しがよりリアルになり、効果的なアプローチのヒントが見つかります。
ステップ3:ペルソナの行動と感情を時系列で洗い出す
設定したペルソナが、どのようなプロセスを経て自社に応募し、入社に至るのかを時系列で具体的に想像し、洗い出していきます。
新卒採用であれば「合同説明会で偶然ブースを訪れる」、中途採用なら「転職サイトでスカウトメールを受け取る」など、企業との最初の接点から始めます。
その時々でペルソナが「何を考え、何を感じるか」「どのような情報を探すか」といった内面的な変化も記述します。
社内の若手社員や、実際に応募してきた求職者へのヒアリングも、リアルな情報を得るために有効な手段です。
ステップ4:フレームワークに沿ってマップを完成させる
洗い出した情報を、フレームワークを使って一枚のシートにまとめていきます。これがカスタマージャーニーマップです。
一般的には、横軸に時間経過(フェーズ)を、縦軸にペルソナの行動や思考、感情などを設定します。
このマップを完成させることで、求職者の体験全体が俯瞰できるようになり、どのフェーズに課題があり、どのような改善策が考えられるのかをチームで議論するための土台ができます。
特別なツールは不要で、スプレッドシートやホワイトボードでも作成可能です。
横軸:認知から応募・入社までのフェーズ
カスタマージャーニーマップの横軸には、求職者が企業と関わる段階を時系列で設定します。
一般的には、「認知」「興味・関心」「比較・検討」「応募」「選考」「内定」「入社」といったフェーズに分けられます。
例えば、「認知」フェーズでは求職者が初めて企業の名前を知る段階、「比較・検討」フェーズでは競合他社と自社を比べる段階です。
自社の採用プロセスに合わせて、より細かくフェーズを設定することもあります。
この横軸が、求職者の「旅」の道のりを示す骨格部分になります。
縦軸:行動・思考・感情・タッチポイントなど
カスタマージャーニーマップの縦軸には、各フェーズにおけるペルソナの状態を多角的に捉えるための項目を設定します。
具体的には、「行動(何をするか)」「思考(何を考えるか)」「感情(どう感じるか)」といった内面的な要素に加え、「タッチポイント(企業との接点)」「課題(不満や不安)」「施策(企業側のアプローチ)」などを記載します。
これらの項目を埋めていくことで、各フェーズで求職者がどのような体験をしているのかが詳細に分かり、具体的な改善策を立てるヒントが見つかります。
作成したマップを効果的に活用するための3つのポイント

採用カスタマージャーニーマップは、作成すること自体が目的ではありません。
完成したマップを採用活動の羅針盤として日々活用し、継続的に改善していくことが重要です。
マップをチームの共通認識とし、常に求職者視点を忘れない姿勢を持つことで、採用活動の質は大きく向上するでしょう。
ここでは、マップを形骸化させず、成果につなげるために意識すべき3つのポイントを紹介します。
常に求職者の立場に立って考える
マップを作成する過程では求職者の視点で考えますが、日々の業務に追われると、企業側の都合や論理を優先してしまいがちです。
例えば、選考プロセスを検討する際に「このフローが社内的に一番効率的だ」と判断するのではなく、「このフローは求職者にとって分かりやすく、ストレスがないか」と自問自答する癖をつけることが求められます。
マップを常に参照し、施策を考える際には必ずペルソナの視点に立ち返ることで、求職者に寄り添った採用活動を実現できます。
一度作って終わりにせず、定期的に見直す
求職者の価値観や情報収集の方法、また労働市場の状況は常に変化しています。
一度作成したマップが永遠に有効であり続けるわけではありません。
そのため、定期的にマップの内容を見直し、更新していく必要があります。
採用活動の結果(応募数、内定承諾率、早期離職率など)を分析し、マップで立てた仮説と実際の結果にズレがないかを確認します。
そして、新たな課題や発見があればマップに反映させるというサイクルを回すことで、常に現状に即した最適な採用戦略を維持できます。
チーム全体でマップを共有し、日々の活動に活かす
作成したマップは、採用担当者だけのものにしてはいけません。
面接を担当する現場の社員や経営層など、採用に関わるすべてのメンバーで共有し、共通言語として活用することが重要です。
例えば、面接官には「この候補者は今『比較・検討』フェーズにいるので、競合他社との違いを丁寧に説明しよう」といったように、マップに基づいた具体的な役割を伝えることができます。
チーム全員が同じ地図を持って採用活動に臨むことで、一貫性のある効果的なアプローチが可能になります。
よくあるご質問
Q1.カスタマージャーニーマップの作成にはどれくらいの時間がかかりますか?
A1.企業の規模や採用目標によりますが、一般的には数回のワークショップを経て、数週間から1ヶ月程度で初版を作成することが多いです。ペルソナ設定や情報収集に時間をかけるほど、より精度の高いマップが完成します。
Q2.ペルソナは複数設定しても良いですか?
A2.はい、問題ありません。募集する職種が複数ある場合や、新卒と中途でターゲットが大きく異なる場合は、それぞれにペルソナを設定し、個別のマップを作成することが効果的です。
Q3.専門のツールを使わなくても作成できますか?
A3.はい、作成できます。スプレッドシートやプレゼンテーションソフト、あるいはホワイトボードと付箋を使っても十分に作成可能です。まずは手軽な方法で始めてみることが重要です。
Q4.小規模な企業でも導入するメリットはありますか?
A4.むしろ、リソースが限られている小規模な企業こそ、導入するメリットは大きいです。効果的な施策に資源を集中させることで、大手企業との差別化を図り、採用活動の費用対効果を高めることができます。
Q5.マップ作成後、何から手をつければ良いですか?
A5.まずは、マップ上で特定された「課題」のうち、最も影響が大きく、かつ改善しやすいものから着手することをおすすめします。小さな成功体験を積み重ねることが、継続的な改善活動につながります。
まとめ
採用カスタマージャーニーは、求職者の視点に立って採用活動全体を設計し直すための強力なフレームワークです。
求職者の行動や感情を深く理解することで、各フェーズに最適なアプローチを実行し、求める人材とのエンゲージメントを高められます。
マップの作成は、採用チーム内の共通認識を醸成し、データに基づいた戦略的な意思決定を可能にします。
一度作成して終わりではなく、市場の変化や採用活動の結果を踏まえて定期的に見直し、改善を続けることで、継続的な採用力の強化が期待できるでしょう。
採用戦略を「設計」で終わらせず、「伝わり方」まで磨く。
Piicでは、採用ピッチ資料・採用サイト・パンフレットを通じて、
貴社の採用カスタマージャーニーを最適化します。








