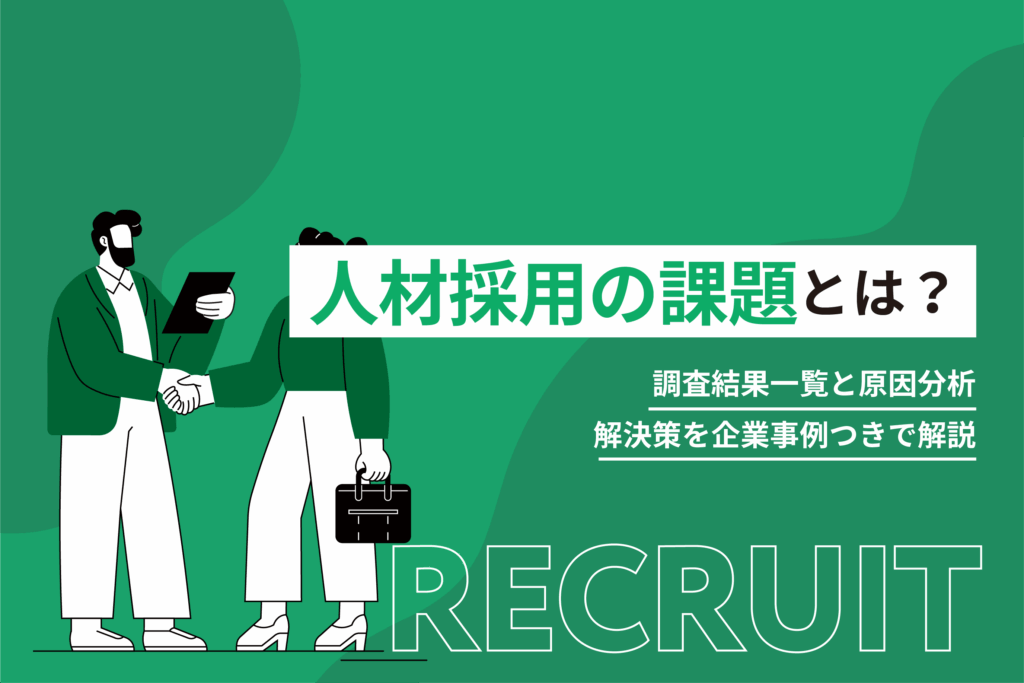
企業の成長に不可欠な人材採用ですが、多くの企業が課題を抱えています。
本記事では、採用活動で直面しがちな課題を調査結果の一覧を交えながら、募集・選考・入社後のフェーズごとに整理します。
それぞれの課題に対する原因を分析し、具体的な解決策や成功事例を通じて、採用活動を成功に導くためのヒントを提供します。

Index
-
まずは採用活動のフェーズごとに課題を整理しよう
-
【募集段階】で起こりがちな採用課題と解決策
-
十分な応募者が集まらないときの対処法
-
ターゲットとは異なる人材からの応募が多い原因と対策
-
応募が殺到してしまい対応リソースが不足する場合の解決策
-
【選考段階】で起こりがちな採用課題と解決策
-
面接や選考の途中で候補者が辞退してしまう
-
内定を出しても承諾してもらえない理由と改善策
-
最終面接でミスマッチが発覚し合格者が出ない
-
【入社後】に起こりがちな採用課題と解決策
-
新入社員が短期間で離職してしまう問題へのアプローチ
-
入社後に期待したパフォーマンスを発揮できないミスマッチを防ぐ方法
-
採用活動を成功に導くための5つの重要ポイント
-
求める人物像(採用ペルソナ)を具体的に設定する
-
候補者目線で自社の本当の魅力を言語化する
-
募集から内定までの選考フロー全体を見直す
-
内定者への手厚いフォローで入社意欲を高める
-
採用代行や支援ツールの活用も視野に入れる
-
採用課題の解決に成功した企業の事例を紹介
-
事例1:採用広報の見直しで母集団形成に成功したケース
-
事例2:選考プロセスの改善で内定辞退率を大幅に下げたケース
-
事例3:入社後のオンボーディング強化で定着率が向上したケース
-
よくあるご質問
-
Q1.採用コストを抑えつつ、良い人材を確保するにはどうすればよいですか?
-
Q2.中小企業が大企業に採用競争で勝つためのポイントは何ですか?
-
Q3.面接官によって評価にばらつきが出てしまいます。
-
Q4.採用活動に活用できる補助金や助成金はありますか?
-
Q5.採用のオンライン化は、どこまで進めるべきでしょうか?
-
まとめ
まずは採用活動のフェーズごとに課題を整理しよう

採用課題とは、企業の採用活動において目標達成を妨げる問題全般を指します。
効果的な対策を講じるためには、まず自社の課題がどの段階で発生しているのかを特定することが重要です。
採用活動は、大きく分けて「募集」「選考」「入社後」の3つのフェーズに分類できます。
各フェーズで起こりうる問題を整理し、採用計画のどこにボトルネックがあるのかを把握することが、人事担当者にとっての第一歩です。
【募集段階】で起こりがちな採用課題と解決策

募集段階では、応募者が集まらない、あるいはターゲットと異なる人材からの応募が多いといった課題が発生しがちです。
これらは母集団形成に関わる問題であり、採用市場の動向や求人サイトの活用方法が大きく影響します。
自社の魅力を正しく伝え、求める人材に的確にアプローチできているかどうかが、この段階での成否を分ける鍵となります。
十分な応募者が集まらないときの対処法
応募者が集まらない背景には、求人情報の魅力不足や、ターゲット層に情報が届いていない可能性が考えられます。
特に専門性の高い経験者や、競争の激しい若手層の採用では、一般的な求人媒体だけでは不十分なケースも少なくありません。
対策として、まずは求人票の内容を見直し、具体的な業務内容や得られるスキル、キャリアパスを明確に示しましょう。
また、企業側から直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、社員の紹介を通じて候補者を探すリファラル採用といった、攻めの手法を取り入れることも有効な手段です。
ターゲットとは異なる人材からの応募が多い原因と対策
求める人材とは違う層からの応募が多い場合、求人情報で発信しているメッセージが曖昧であることが主な原因です。
例えば、「コミュニケーション能力が高い人」といった抽象的な表現では、人によって解釈が異なり、ミスマッチを引き起こしやすくなります。
これを防ぐためには、現場の社員へヒアリングを行い、実際にどのようなスキルや志向性を持った人材が活躍しているのかを具体的に言語化する必要があります。
その上で、具体的な業務内容やキャリアの展望を求人票に落とし込み、候補者が自身に合う仕事かどうかを判断しやすい情報を提供することが重要です。
応募が殺到してしまい対応リソースが不足する場合の解決策
想定以上に応募が殺到すると、書類選考や応募者へのメール連絡などに時間がかかり、担当者の業務負荷が増大します。
対応が遅れると、有力な候補者が他社に流れてしまう機会損失にもつながりかねません。
この問題を解決するためには、採用管理システム(ATS)を導入して応募者情報を一元管理し、選考プロセスを効率化するのが有効です。
また、必須条件を明確にしてスクリーニングの基準を設けたり、説明会への参加を応募条件に加えたりすることで、自社への志望度が高い候補者に絞り込む工夫も考えられます。
【選考段階】で起こりがちな採用課題と解決策

選考段階に進むと、候補者の辞退や内定承諾率の低さといった新たな課題が浮上します。
面接などのプロセスを通じて、候補者の入社意欲を維持・向上させることができなければ、採用成功には至りません。
候補者とのコミュニケーションの質を高め、お互いの理解を深めるプロセスを設計することが、この段階での課題解決の鍵となります。
面接や選考の途中で候補者が辞退してしまう
選考途中の辞退は、企業にとって大きな痛手です。
特に優秀な候補者ほど複数の企業からアプローチを受けているため、選考プロセスが長引いたり、連絡が遅れたりすると、他社に流れてしまう可能性が高まります。
中途の候補者はスピーディーな選考を望む傾向があり、新卒の候補者は面接官の印象や対応を重視することが多いです。
この問題の解決には、選考フローを見直して期間を短縮することや、面接官のトレーニングを実施し、候補者の魅力や能力を引き出すような質の高い面接を提供することが効果的です。
内定を出しても承諾してもらえない理由と改善策
内定を出しても承諾に至らない主な理由は、他社と比較検討した結果、条件面や働き方に魅力を感じられなかったり、入社後のキャリアに対する不安が払拭できなかったりすることにあります。
複数の内定を持つ候補者にとって、最後の決め手となるのは、企業がどれだけ自分を必要としているかという熱意や、入社後の活躍イメージです。
内定者フォロー面談を設け、配属予定部署の社員と話す機会を作ったり、企業の将来性に関する情報を提供したりすることで、不安を解消し入社への動機付けを強化する取り組みが求められます。
ある調査では、内定辞退の理由に関するデータも公開されており、参考になります。
最終面接でミスマッチが発覚し合格者が出ない
最終面接まで進んだにもかかわらず、経営層と候補者の間でミスマッチが発覚し、結果的に合格者が出ないというケースがあります。
これは、一次・二次面接の段階でスキルや経験ばかりを重視し、企業のカルチャーや価値観との適合性を見極められていないことが原因です。
対策としては、選考の初期段階から、自社のビジョンや社会における役割を伝え、候補者の価値観と合致するかを確認する質問を取り入れることが重要です。
また、事前に経営陣と現場で求める人物像のすり合わせを徹底し、選考基準に一貫性を持たせることも不可欠です。
【入社後】に起こりがちな採用課題と解決策

採用活動のゴールは内定承諾ではなく、入社した社員が定着し、活躍することです。
しかし、入社後に早期離職やパフォーマンス不足といった問題が発生することも少なくありません。
特に新卒や中途で入社した社員が組織にスムーズに馴染めるよう、受け入れ体制や入社後のフォローが重要になります。
新入社員が短期間で離職してしまう問題へのアプローチ
新入社員の早期離職は、入社前に抱いていたイメージと入社後の現実に大きなギャップがある場合に起こりがちです。
これを防ぐためには、選考段階において、仕事の魅力だけでなく、厳しさや大変な側面も正直に伝えることが重要です。
また、入社後におけるサポート体制の構築も欠かせません。
例えば、定期的な1on1ミーティングで上司が悩みを聞いたり、メンター制度を導入して先輩社員が相談に乗ったりすることで、新入社員の孤立を防ぎ、組織へのスムーズな適応を支援します。
入社後に期待したパフォーマンスを発揮できないミスマッチを防ぐ方法
採用した人材が期待通りのパフォーマンスを発揮できない場合、スキルやカルチャーフィットの見極めが不十分だった可能性があります。
特にエンジニアのような専門職を採用する際は、面接での受け答えだけでなく、実際のスキルレベルを正確に把握することが不可欠です。
対策として、コーディングテストや実際の業務に近い課題に取り組んでもらうワークサンプルテストを導入する方法があります。
また、選考過程でチームメンバーと話す機会を設け、現場の雰囲気や働き方が本人に合うかをお互いに確認することも、入社後のミスマッチを防ぐ上で有効です。
採用活動を成功に導くための5つの重要ポイント

これまで見てきた課題を踏まえ、採用活動全体を成功させるためには、以下5つの重要なポイントがあります。
- ペルソナを具体的に設定する
- 候補者目線で自社の魅力を言語化
- 選考フロー全体の見直し
- 内定者への手厚いフォローを実施
- 採用支援ツールの活用
これらを意識することで、採用の精度と効率を大きく向上させることが可能です。
求める人物像(採用ペルソナ)を具体的に設定する
採用活動の起点となるのが、どのような人材を求めているのかを明確にすることです。
スキルや経験といった条件だけでなく、価値観、志向性、働き方のスタイルまで含めた具体的な人物像(採用ペルソナ)を設定しましょう。
ペルソナが明確であれば、求人広告の文面や面接での質問内容に一貫性が生まれ、採用に関わるメンバー全員が共通の認識を持って選考に臨めます。
これは正社員だけでなく、外国人材やアルバイトの採用においても同様に重要で、ミスマッチを防ぎ、採用の精度を高めることにつながります。
候補者目線で自社の本当の魅力を言語化する
多くの企業が求人情報を発信する中で、自社を選んでもらうためには、候補者にとっての魅力を的確に伝える必要があります。
給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンや事業の社会性、社員の成長を支える文化、独自の制度など、他社にはない魅力を言語化することが重要です。
働く社員のインタビュー記事や一日のスケジュールを紹介するなど、候補者が入社後の自分を具体的にイメージできるような情報発信を心がけましょう。
企業の本当の魅力を伝えることで、共感した候補者からの応募を増やすことができます。
募集から内定までの選考フロー全体を見直す
候補者にとって、選考プロセスは企業との最初の接点であり、その体験が企業イメージを大きく左右します。
応募書類が多すぎる、選考結果の連絡が遅い、面接の日程調整が煩雑といった点は、候補者のストレスとなり、辞退の原因にもなりかねません。
定期的に選考フロー全体を見直し、オンライン面接の活用や応募者管理ツールによる迅速な連絡など、候補者体験を向上させるための改善を続けましょう。
スムーズで丁寧な選考プロセスは、候補者の入社意欲を高めるだけでなく、企業の評判向上にも貢献します。
内定者への手厚いフォローで入社意欲を高める
内定を出してから入社するまでの期間は、候補者が本当に入社すべきか悩む時間でもあります。
この期間にコミュニケーションが途絶えると、内定者の不安が増大し、辞退につながるリスクが高まります。
これを防ぐためには、内定者への手厚いフォローが不可欠です。
定期的な連絡はもちろん、内定者懇親会や社員との座談会を企画し、会社の雰囲気を知ってもらったり、同期とのつながりを作ってもらったりする機会を提供しましょう。
入社前の不安を解消し、迎え入れる姿勢を示すことで、入社への期待感を醸成します。
採用代行や支援ツールの活用も視野に入れる
採用担当者の業務は多岐にわたり、すべての業務を限られたリソースで完璧にこなすのは困難です。
ノンコア業務に追われ、候補者とのコミュニケーションといった本質的な業務に時間を割けないという課題も少なくありません。
このような場合、採用代行(RPO)サービスを利用してスカウト配信や日程調整を外部に委託したり、採用管理システム(ATS)を導入して応募者管理を効率化したりするのも有効な手段です。
外部の専門知識やツールをうまく活用することで、採用担当者はより戦略的な業務に集中でき、採用活動全体の質を高めることが可能です。
採用課題の解決に成功した企業の事例を紹介
ここでは、実際に企業がどのように採用課題を乗り越えてきたのか、具体的な成功事例を紹介します。
大企業の取り組みから中小企業の工夫まで、自社の状況と照らし合わせながら、課題解決のヒントを見つけてください。
他社の成功事例を学ぶことは、自社の採用戦略を見直す上で非常に有益な示唆を与えてくれます。
事例1:採用広報の見直しで母集団形成に成功したケース
あるITベンチャー企業は、知名度の低さからエンジニアの応募が集まらないという課題を抱えていました。
そこで、従来の求人広告だけでなく、自社の技術ブログやSNSでの情報発信を強化。
開発チームが取り組んでいるプロジェクトの裏側や、使用している技術、エンジニアの働きがいなどを具体的に伝えるコンテンツを定期的に発信しました。
その結果、企業の技術力やカルチャーに共感した質の高いエンジニアからの応募が増加し、採用目標を達成。
ターゲットに響く情報発信へと切り替えることで、母集団形成に成功した好例です。
事例2:選考プロセスの改善で内定辞退率を大幅に下げたケース
あるメーカーでは、選考期間が長く、その間に候補者が他社の内定を承諾してしまうケースが多発していました。
この課題を解決するため、まず書類選考から最終面接までの期間を従来の半分に短縮する目標を設定。
Web面接を積極的に導入し、面接官のスケジュールを事前に確保することで、迅速な日程調整を実現しました。
また、面接のフィードバックを即日候補者に伝えるルールを徹底。
スピーディーで誠実な対応が候補者からの信頼を得て、結果的に内定辞退率を大幅に改善することに成功しました。
事例3:入社後のオンボーディング強化で定着率が向上したケース
新入社員の定着率の低さに悩んでいたある小売企業は、入社後の受け入れ体制に問題があると分析しました。
そこで、入社後3ヶ月間を「オンボーディング期間」と位置づけ、体系的なプログラムを導入。
具体的には、配属先の先輩社員がメンターとして公私にわたる相談に乗る制度や、週に一度の上長との1on1面談を義務化しました。
また、人事部主催のフォローアップ研修を定期的に開催し、同期との交流を促進。
このような手厚いサポート体制を構築した結果、新入社員の孤立感が解消され、定着率が劇的に向上した良い例です。
よくあるご質問
Q1.採用コストを抑えつつ、良い人材を確保するにはどうすればよいですか?
A1.社員の紹介を通じて採用するリファラル採用や、企業から直接候補者にアプローチするダイレクトリクルーティングは、求人広告費を抑えられる有効な手法です。また、自社の採用サイトやSNSを充実させ、情報発信力を高めることも、低コストで母集団を形成する方法の一つです。
Q2.中小企業が大企業に採用競争で勝つためのポイントは何ですか?
A2.大企業にはない魅力をアピールすることが重要です。例えば、若いうちから裁量権の大きい仕事ができる、経営層との距離が近い、意思決定のスピードが速いといった点は中小企業ならではの強みです。働き方の柔軟性やアットホームな社風も魅力的に映る場合があります。
Q3.面接官によって評価にばらつきが出てしまいます。
A3.評価基準を明確にした共通の「面接評価シート」を作成し、事前に面接官全員で目線合わせを行うことが効果的です。質問項目や評価ポイントを標準化する「構造化面接」の手法を取り入れることで、面接官個人の主観による評価のブレを減らすことができます。
Q4.採用活動に活用できる補助金や助成金はありますか?
A4.はい、国や地方自治体が提供する様々な制度があります。例えば、特定の求職者(高齢者、障害者など)を雇用した場合の「特定求職者雇用開発助成金」や、試行的に雇用するための「トライアル雇用助成金」などです。詳しくは厚生労働省やハローワークのウェブサイトで確認できます。
Q5.採用のオンライン化は、どこまで進めるべきでしょうか?
A5.企業説明会や一次面接など、多くの候補者に対応する必要がある初期段階はオンライン化することで効率を高められます。一方で、会社の雰囲気を感じてもらったり、最終的な意思決定を促したりする最終面接や職場見学は、対面で実施するハイブリッド型が効果的です。自社の状況に合わせて最適なバランスを見つけることが重要です。
まとめ
採用に関する課題は、募集、選考、入社後と様々なフェーズで発生します。
重要なのは、まず自社の課題がどの段階にあるのかを正確に把握し、その原因を分析することです。
その上で、求める人物像の具体化、自社の魅力の言語化、選考プロセスの見直し、入社後のフォロー体制の構築といった具体的な対策を講じていく必要があります。
採用活動は一朝一夕に成果が出るものではありませんが、本記事で紹介したポイントや事例を参考に、採用担当者が中心となって粘り強く改善を続けることで、自社にマッチした優秀な人材の獲得につながります。
用活動を成功させるためには、課題を把握するだけでなく、
自社の魅力をわかりやすく伝え、定着につながる採用体験を設計することが欠かせません。
株式会社Piicでは、採用ピッチ資料や採用サイト制作を中心に、
応募率・定着率を高める「採用ブランディング」を支援しています。
「自社にマッチした優秀な人材を獲得し、長く活躍してもらう」ための仕組みづくりを、御社に合わせてご提案いたします。








