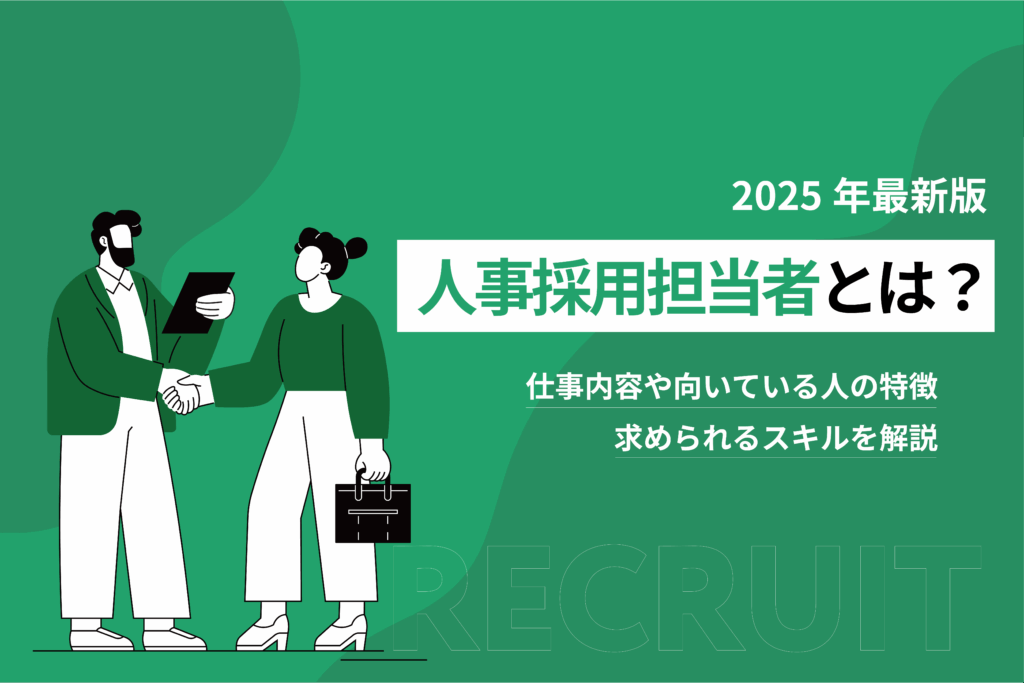
人事部門における採用担当者とは、企業の成長に不可欠な人材を確保する専門職です。
その仕事内容は、採用計画の策定から選考活動、内定者のフォローまで多岐にわたります。
この記事では、採用担当の具体的な仕事内容とは何か、どのような特徴を持つ人が向いているのか、そして業務を遂行する上で必要なスキルについて解説します。
企業の未来を担う人事としての役割を理解し、自身のキャリアを考える上で参考にしてください。

Index
-
採用担当とは企業の未来を創る重要なポジション
-
採用担当の仕事内容を7つのステップで解説
-
ステップ1:採用戦略の策定と計画立案
-
ステップ2:求める人物像(ペルソナ)の具体化
-
ステップ3:募集方法の選定と求人媒体の活用
-
ステップ4:母集団形成のための募集活動
-
ステップ5:書類選考や面接の実施
-
ステップ6:内定通知と入社条件の交渉
-
ステップ7:内定者へのフォローアップと入社準備
-
採用担当に求められる5つの必須スキル
-
候補者の本音を引き出すコミュニケーション能力
-
会社の魅力を伝えるプレゼンテーション能力
-
採用市場の動向を捉える情報収集力
-
複数業務を同時に進めるマルチタスク能力
-
客観的な視点で候補者を評価する分析力
-
あなたはどっち?採用担当に向いている人と向いていない人の特徴
-
採用担当の適性がある人の特徴
-
採用担当には不向きかもしれない人の特徴
-
採用活動で直面しがちな3つの課題と解決策
-
課題1:応募者が集まらない(母集団形成の難しさ)
-
課題2:選考途中や内定後の辞退者が多い
-
課題3:採用した人材がすぐに辞めてしまう(早期離職)
-
【最新版】採用成功に導くトレンドの採用手法4選
-
ダイレクトリクルーティング
-
リファラル採用
-
ソーシャルリクルーティング
-
カジュアル面談
-
優秀な人材を惹きつける採用担当になるためのポイント
-
1. 自社の魅力を“自分の言葉”で語れること
-
2. 求職者の価値観を理解し、共感を示す姿勢
-
3. 一貫したコミュニケーションと誠実な対応
-
4. 社員や現場を巻き込む“チーム採用”の意識
-
5. 面接を「評価の場」ではなく「共感の場」に
-
よくあるご質問
-
Q1. 採用担当になるために必要な資格はありますか?
-
Q2. 未経験から採用担当になれますか?
-
Q3. 採用担当の繁忙期はいつ頃ですか?
-
Q4. 採用面接で特に気をつけるべきことは何ですか?
-
Q5. オンライン面接のメリットとデメリットを教えてください。
-
まとめ
採用担当とは企業の未来を創る重要なポジション

採用担当は、会社の将来を担う人材を見つけ出し、組織に迎え入れるという重い責任を持つ職種です。
単に欠員を補充するだけでなく、企業の経営戦略や事業計画に基づいて、どのような人材が必要かを考え、獲得に動きます。
採用担当者の判断一つで、会社の未来が大きく変わる可能性もあるため、非常に重要なポジションと言えるでしょう。
そのため、採用活動の責任者として、常に経営的な視点を持ち、企業全体の成長に貢献する意識が求められます。
採用担当の仕事内容を7つのステップで解説
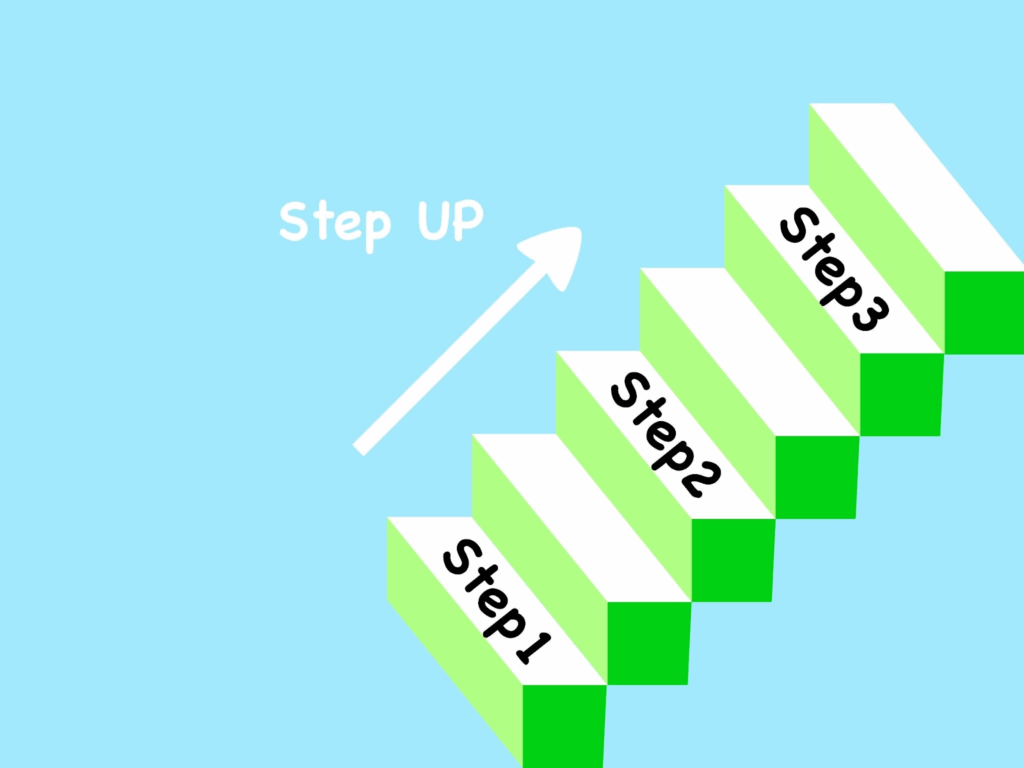
採用担当の仕事内容は多岐にわたり、年間を通じてスケジュール管理が大変な職務です。
特に新卒採用が始まる繁忙期には、多くの業務を同時に進める必要があります。
初めて採用業務に携わる場合、まずは一連の流れを把握することが重要です。
ここでは、採用計画から入社後のフォローまで、具体的な仕事内容を下記7つのステップに分けて解説します。
- 採用戦略の策定と計画立案
- 求める人物像(ペルソナ)の具体化
- 募集方法の選定と求人媒体の活用
- 母集団形成のための募集活動
- 書類選考や面接の実施
- 内定通知と入社条件の交渉
- 内定者へのフォローアップと入社準備
営業的な側面や労務に関する知識も求められるため、マニュアルだけに頼らず、幅広い経験が活かせる仕事です。
ステップ1:採用戦略の策定と計画立案
採用活動の第一歩は、経営計画や事業戦略に基づいて採用戦略を立てることです。
具体的には、各部署のニーズをヒアリングし、事業の成長のためにどのようなスキルや経験を持つ人材が、いつまでに何人必要なのかを明確にします。
この採用計画は、単に人数を算出するだけでなく、採用市場の動向や競合の状況を分析するマーケティングの視点も不可欠です。
また、募集や選考の過程では、労働関連の法律を遵守する必要があるため、採用担当者には関連法規に関する正確な知識も求められます。
これらの情報を総合的に判断し、効果的な採用計画を立案します。
ステップ2:求める人物像(ペルソナ)の具体化
採用計画が固まったら、次に「求める人物像(ペルソナ)」を具体的に設定します。
これは、採用のミスマッチを防ぎ、選考の精度を高めるために非常に重要なプロセスです。
新卒採用、中途採用(キャリア採用)、アルバイトなど、募集するポジションごとに、必要なスキルや経験はもちろん、性格や人柄、価値観といった定性的な要素まで掘り下げて定義します。
年齢や経歴だけでなく、チームの中でどのような役割を果たしてほしいか、どのようなキャリアを歩んでほしいかまでを明確にすることで、採用基準が具体的になり、関係者間での目線合わせもスムーズに進みます。
ステップ3:募集方法の選定と求人媒体の活用
求める人物像が明確になったら、その人物にアプローチするための最適な募集方法を選定します。
代表的な方法には、転職サイトへの求人広告掲載、人材紹介サービスの利用、自社採用サイトの活用などがあります。
媒体の選び方一つで応募者の質や数が大きく変わるため、ターゲット層が多く利用する媒体を見極めることが重要です。
特に中小企業の場合は、限られた予算の中で最大限の効果を出すために、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
各求人媒体の特徴を理解し、自社の採用戦略に合ったものを組み合わせることで、効率的な母集団形成が可能になります。
ステップ4:母集団形成のための募集活動
求人媒体への掲載と並行して、より積極的に候補者との接点を作るための募集活動を行います。
具体的には、自社で開催する会社説明会や、大学などが主催する合同企業説明会への出展が挙げられます。
これらのイベントでは、候補者に対して直接企業の魅力を伝え、質疑応答を通じて相互理解を深めることが可能です。
また、近年では業界や職種に特化した採用イベントや、エンジニア向けの技術交流会などに参加し、潜在的な候補者と関係性を築く手法も増えています。
こうした活動を通じて、自社に興味を持つ候補者の母集団を形成していきます。
ステップ5:書類選考や面接の実施
応募者が集まったら、書類選考と面接を通じて、求める人物像に合致するかを見極める選考プロセスに入ります。
まず、履歴書や職務経歴書から、候補者の経験やスキルが募集要件を満たしているかを確認します。
書類選考を通過した候補者とは、日程調整を行い面接を実施します。
一次面接から最終面接へと進む中で、候補者の能力や人柄を多角的に評価し、自社とのマッチ度を判断します。
面接官の服装や態度は、候補者が企業に抱く印象を大きく左右するため、企業の顔としての自覚を持った対応が不可欠です。
ステップ6:内定通知と入社条件の交渉
最終面接を経て、採用する候補者が決まったら、速やかに内定の連絡をします。
内定通知は電話やメールで行い、その後、労働条件や入社日などを明記した内定通知書を送付するのが一般的です。
この際、文書の宛名で「様」や返信用封筒で「行」を使うなど、ビジネスマナーに則った丁寧な対応を心がけます。
候補者によっては、給与や待遇面での交渉が発生することもあります。
保有している資格やこれまでの経験を正しく評価し、双方にとって納得のいく形で条件を整えることが、入社意欲を高める上で重要になります。
ステップ7:内定者へのフォローアップと入社準備
内定承諾から入社日までの期間は、内定者の不安を解消し、入社意欲を維持するためのフォローアップが欠かせません。
具体的には、内定者懇親会や社員との座談会を開催したり、定期的に連絡を取って気軽に相談できる関係性を築いたりすることが有効です。
こうした取り組みは、内定者のエンゲージメントを高め、内定辞退の防止に繋がります。
また、入社後のスムーズなスタートを支援するため、社会保険の手続きや必要な書類の案内、配属先の情報提供など、具体的な入社準備も進めていきます。
入社後も孤立しないよう、手厚いサポート体制を整えることが重要です。
採用担当に求められる5つの必須スキル

企業の成長を担う採用担当者として成果を出すためには、様々な能力が求められます。
候補者と真摯に向き合い、自社の魅力を伝え、客観的な視点で評価を下す一連の業務には、複合的なスキルが必要です。
ここでは、採用担当者にとって特に重要とされる下記の5つの必須スキルを解説します。
- コミュニケーション能力
- プレゼンテーション能力
- 情報収集力
- マルチタスク能力
- 分析力
これらのスキルを意識し、日々の業務を通じて自身のスキルアップを図ることが、採用活動の成功に直結します。
候補者の本音を引き出すコミュニケーション能力
採用担当者には、候補者がリラックスして話せる雰囲気を作り、その人の本質や本音を引き出す高いコミュニケーション能力が求められます。
面接という緊張感のある場面では、多くの候補者が準備してきた模範解答を話しがちです。
しかし、採用のミスマッチを防ぐためには、候補者の価値観や仕事に対する考え方、弱みといった、より深い部分を理解する必要があります。
一方的に質問するのではなく、相手の話に真摯に耳を傾ける傾聴力や、会話を広げる質問力を通じて、候補者の本音の部分に触れることが重要です。
会社の魅力を伝えるプレゼンテーション能力
採用活動は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者から「選ばれる」場でもあります。
そのため、採用担当者には自社の魅力を的確かつ魅力的に伝えるプレゼンテーション能力が不可欠です。
事業の将来性や仕事のやりがい、独自の社風、福利厚生など、候補者が求める情報や価値観に合わせて、伝えるべき魅力を取捨選択し、分かりやすく説明するスキルが求められます。
会社の「広告塔」として、候補者に「この会社で働きたい」と思わせるような、熱意あるプレゼンテーションを心がけることが大切です。
採用市場の動向を捉える情報収集力
採用市場は景気や社会情勢、法改正などによって常に変動しています。
特に若い世代の仕事に対する価値観の変化や新しい転職サービスの登場などトレンドの移り変わりは速いです。
採用担当者にはこうした市場の動向を常に把握し自社の採用戦略に反映させるための情報収集力が求められます。
業界ニュースや調査レポートに目を通したり人事関連のセミナーに参加したりするなど常にアンテナを高く張り最新の情報をキャッチアップしていく姿勢が必要です。
複数業務を同時に進めるマルチタスク能力
採用担当者の仕事は、採用計画の策定から始まり、候補者との面接日程調整、各部署との連携、メール対応、内定者フォローまで、非常に多岐にわたります。
特に採用シーズンには、これらの業務が同時並行で発生するため、優先順位を的確に判断し、効率的にタスクを処理していくマルチタスク能力が必須です。
スケジュール管理能力はもちろんのこと、情報を正確に整理し、関係者とスムーズに共有するスキルも、業務を円滑に進める上で重要になります。
客観的な視点で候補者を評価する分析力
面接では、候補者の印象やコミュニケーション能力に評価が偏りがちですが、採用担当者には主観を排し、客観的な事実に基づいて候補者を評価する分析力が求められます。
事前に設定した評価基準に照らし合わせ、候補者の経験やスキルが自社の求める要件と合致するかを冷静に見極める必要があります。
面接での対話内容だけでなく、履歴書や職務経歴書、場合によっては適性検査の結果なども含めて多角的に情報を分析し、論理的な根拠に基づいて採用判断を下すことが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。
あなたはどっち?採用担当に向いている人と向いていない人の特徴

採用担当という仕事は、単に人と話すのが好きというだけでは務まりません。
企業の代表として候補者と接する責任感が求められ、候補者を選ぶ立場だという勘違いは禁物です。
企業の未来を左右する重要な役割を担うからこそ、特有の適性が存在します。
ここでは、採用担当に向いている人と、もしかしたら不向きかもしれない人の特徴をそれぞれ解説します。
自身の特性と照らし合わせながら、採用担当としての適性を考えてみましょう。
採用担当の適性がある人の特徴
採用担当の適性がある人は、まず自社への理解と愛情が深く、その魅力を自分の言葉で情熱的に語れる人です。
また、相手の立場に立って物事を考えられる共感力も重要で、候補者の不安や疑問に寄り添う姿勢が信頼関係を築きます。
採用業務には、候補者とのコミュニケーションだけでなく、日程調整やデータ分析といった地道な作業も多いため、粘り強さや計画性も欠かせません。
最終的に自社に最適な人材を採用するという強い責任感を持ち、目標達成に向けて主体的に行動できる人が向いていると言えます。
採用担当には不向きかもしれない人の特徴
一方で、採用担当には向いていない可能性のある特徴も存在します。
例えば、第一印象や学歴といった先入観で人を判断してしまう傾向がある人は、候補者の本質を見抜けず、公正な評価が難しくなります。
また、自分の話ばかりしてしまい、相手の話をじっくり聞くのが苦手な人も、候補者の本音を引き出すことはできないでしょう。
複数の業務を同時に管理するのが苦手な場合、多くのタスクを抱える中でミスが増え、候補者や関係部署に迷惑をかけてしまうかもしれません。
企業の顔であるという自覚がなく、高圧的な態度を取る人は、採用担当にはいない方が良いでしょう。
採用活動で直面しがちな3つの課題と解決策

採用活動は計画通りに進むことばかりではなく、多くの採用担当者が様々な課題や悩みに直面します。
特に「応募者が集まらない」「辞退者が多い」「採用してもすぐに辞めてしまう」という3つの課題は、多くの企業に共通する悩みです。
これらの課題を放置すると、採用コストが無駄になるだけでなく、組織の成長を停滞させる原因にもなります。
ここでは、採用活動で直面しがちな3つの課題を取り上げ、それぞれの具体的な解決策について考えていきます。
課題1:応募者が集まらない(母集団形成の難しさ)
求人広告を出しても期待した数の応募が集まらないという課題は、多くの企業が抱えています。
この原因としては、求人情報の魅力が伝わっていない、ターゲット層にアプローチできていない、そもそも労働市場で競争力が低い、といった点が考えられます。
対策としては、まず自社の強みや仕事のやりがいを明確にし、求職者の心に響くような求人票を作成することが基本です。
加えて、転職サイトに掲載して待つだけでなく、企業側からアプローチするダイレクトリクルーティングでスカウトメールを送るなど、攻めの姿勢で母集団を形成していくことが求められます。
課題2:選考途中や内定後の辞退者が多い
順調に選考が進んでいた候補者や内定を出した候補者から辞退の連絡が来ると採用計画に大きな狂いが生じます。
選考途中や内定辞退の背景には他社の選考が先に進んだ、面接での印象が悪かった、提示された条件が合わなかったなど様々な理由が考えられます。
この課題を解決するには選考プロセス全体をスピーディに進めること、面接官が企業の魅力を十分に伝え候補者の入社意欲を高めること、そして内定後も定期的にコミュニケーションを取り内定者の不安を解消するフォローを手厚くすることが有効です。
課題3:採用した人材がすぐに辞めてしまう(早期離職)
時間とコストをかけて採用した人材が、入社後すぐに辞めてしまう早期離職は、企業にとって深刻な問題です。
早期離職の主な原因は、「入社前に聞いていた話と違う」というリアリティショックにあります。
これを防ぐためには、採用段階で良い面ばかりでなく、仕事の厳しさや組織の課題といったリアルな情報も正直に伝えることが重要です。
入社後は、上司や人事担当者が定期的に面談を行い、悩みや困っていることがないかを確認し、孤立させない体制づくりが求められます。
相談された際には迅速な返信を心がけるなど、丁寧なサポートが定着に繋がります。
【最新版】採用成功に導くトレンドの採用手法4選

労働市場の変化やテクノロジーの進化に伴い、採用のあり方も大きく変わりつつあります。
従来の求人広告を出すだけの「待ち」の採用手法では、優秀な人材の獲得競争に勝つことは難しくなっています。
今、注目されているのは、企業側から積極的に候補者へアプローチする「攻めの採用」や、候補者との相互理解を深める手法です。
ここでは、採用成功の可能性を高めるために押さえておきたい、最新の採用トレンドを4つ紹介します。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が転職サイトのデータベースやSNSなどを活用し、求める要件に合う人材を探し出して直接アプローチする採用手法です。
転職市場には出てきていないものの、良い機会があれば転職を考えている「転職潜在層」にもアプローチできる点が大きな強みです。
企業が候補者一人ひとりに合わせてスカウトメールを送るため、自社の魅力をピンポイントで伝えることができ、ミスマッチの少ない採用が期待できます。
ただし、候補者の選定やアプローチに手間と時間がかかるため、計画的な運用が必要です。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員に友人や知人を紹介してもらい、選考を行う採用手法です。
社員からの紹介であるため、候補者のスキルや人柄に対する信頼性が高く、企業文化にフィットしやすいというメリットがあります。
また、求人広告費や人材紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も魅力です。
一方で、紹介者と候補者の人間関係に配慮が必要な点や、似たような人材ばかりが集まり、組織の多様性が損なわれる可能性もあるため、制度設計や運用には注意が求められます。
ソーシャルリクルーティング
ソーシャルリクルーティングは、X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInといったSNSを活用する採用手法です。
企業の公式アカウントから日々の業務の様子や社風、社員インタビューなどを発信することで、企業のファンを増やし、自然な形で採用に繋げることができます。
特に若い世代へのアプローチに有効で、従来の求人媒体では伝えきれないリアルな魅力を発信できるのが特徴です。
継続的な情報発信が求められるほか、不適切な投稿による炎上リスクも考慮した上で、慎重に運用する必要があります。
カジュアル面談
カジュアル面談は本格的な選考に入る前に企業と候補者がお互いのことを気軽に情報交換する場です。
選考ではないため候補者はリラックスした状態で質問ができ企業側も候補者の潜在的なキャリア観や興味を引き出すことができます。
転職をまだ具体的に考えていない層にも「まずは話だけでも聞いてみませんか」とアプローチしやすく自社に興味を持ってもらうきっかけになります。
企業と候補者の相互理解を深めることでその後の選考プロセスにおけるミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
優秀な人材を惹きつける採用担当になるためのポイント
採用競争が激化する中で、優秀な人材に自社を選んでもらうためには、採用担当者の役割が非常に重要です。
候補者は、面接でのやり取りを通じて、その企業の文化や働く人々を判断しています。
つまり、採用担当者の言動一つひとつが、企業の印象を左右するのです。
優秀な人材から「この会社で、この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるような魅力的な採用担当者になるには、どのような点を意識すれば良いのでしょうか。
ここでは、そのための具体的なポイントを解説します。
1. 自社の魅力を“自分の言葉”で語れること
採用担当者にとって最も重要なのは、会社の理念や事業、働く人の想いを“自分の言葉”で伝えられることです。
パンフレットやスライドに書かれた情報をそのまま話すのではなく、自分自身がその企業で働く意義を感じ、心から共感していることが伝わる話し方が求められます。
候補者は、情報の正確さよりも「この人が本気でこの会社を好きなのか」を敏感に感じ取ります。まずは自社の強みや文化を自分なりの視点で再定義し、リアルなストーリーとして語れるように準備しましょう。
2. 求職者の価値観を理解し、共感を示す姿勢
優秀な人材ほど、自分のキャリアビジョンや働き方の価値観を明確に持っています。
採用担当者は、その価値観を“企業に合わせさせる”のではなく、“自社の環境の中でどう実現できるか”を一緒に考える姿勢が大切です。
質問に対してすぐに答えを出すよりも、「その考え方、すごく良いですね」と共感を挟むことで、対話の温度が変わります。
採用担当者は“選ぶ側”ではなく“選ばれる側”でもあることを意識しましょう。
3. 一貫したコミュニケーションと誠実な対応
面接の日程調整や合否連絡といった一つひとつの対応にも、企業の誠実さは表れます。
レスポンスの速さや文章の丁寧さ、トーンの統一感など、細部の積み重ねが候補者体験を左右します。
特にSNSや口コミサイトで情報が拡散されやすい時代では、採用担当者の対応がそのまま企業の評判につながることも少なくありません。
“企業の顔”としての自覚を持ち、常に誠実で透明性の高い対応を心がけましょう。
4. 社員や現場を巻き込む“チーム採用”の意識
優秀な人材は、採用担当者だけでなく、実際に働くメンバーや上司の姿からも会社を判断します。
採用担当者が一人で完結するのではなく、現場社員の声やリアルな働き方を採用活動に取り入れることで、企業の信頼性が格段に高まります。
例えば、社員インタビュー記事や採用動画を通じて“生の声”を届けることも効果的です。
採用を「人事部の仕事」ではなく、「会社全体のミッション」と捉えることで、自然と魅力的な採用活動が生まれます。
5. 面接を「評価の場」ではなく「共感の場」に
面接は、スキルを見極めるだけの場ではありません。
候補者が自社の文化や価値観に共感できるか、またその人の個性がどう活かせるかを一緒に探る“対話の場”です。
評価のための質問だけでなく、「どんなときに仕事が楽しいですか?」など、候補者の本音を引き出す質問を意識することで、信頼関係が深まります。
“共感の積み重ね”が、最終的な入社意欲の醸成につながります。
よくあるご質問
Q1. 採用担当になるために必要な資格はありますか?
A1. 採用担当に必須の資格はありません。
しかし、「キャリアコンサルタント」や「社会保険労務士」といった資格を取得しておくと、候補者へのキャリアアドバイスや労務管理の知識が深まり、業務に役立ちます。
Q2. 未経験から採用担当になれますか?
A2. はい、未経験からでも採用担当になることは可能です。
特に営業職や販売職などで培った高いコミュニケーション能力や目標達成意欲は、採用業務でも大いに活かせます。
ただし、労働法規などの専門知識は、自主的に学習する必要があります。
Q3. 採用担当の繁忙期はいつ頃ですか?
A3. 企業によって異なりますが、一般的に新卒採用活動が本格化する3月〜6月頃や、中途採用の募集が増える年度の変わり目や下半期が繁忙期になることが多いです。
しかし、通年採用を行う企業も増えており、年間を通して忙しい場合もあります。
Q4. 採用面接で特に気をつけるべきことは何ですか?
A4. 候補者がリラックスして話せるような雰囲気作りを心がけることが第一です。
また、評価基準を明確にし、面接官の主観だけで判断しないこと、そして企業の代表として誠実かつ丁寧な態度で接することが重要です。
圧迫面接や差別につながる質問は厳禁です。
Q5. オンライン面接のメリットとデメリットを教えてください。
A5. メリットは、遠方に住む候補者とも面接ができ、日程調整がしやすい点です。
一方、デメリットとしては、通信環境に左右されることや、対面の面接に比べて候補者の雰囲気や人柄が掴みにくい場合がある点が挙げられます。
まとめ
採用担当者は、企業の成長戦略に基づき、採用計画の立案から募集、選考、内定者フォロー、入社後の定着支援まで、一貫して人材獲得に関わる重要な職務です。
その仕事は単なる人員補充にとどまらず、企業の未来を創るという大きな役割を担っています。
採用を成功させるためには、コミュニケーション能力や分析力といった個人のスキルに加え、採用市場のトレンドを常に把握し、ダイレクトリクルーティングのような新しい手法を柔軟に取り入れる姿勢が不可欠です。
採用活動で直面する様々な課題に対しては、その原因を冷静に分析し、一つひとつ着実に対策を講じることが解決に繋がります。
企業の顔として候補者と接する採用担当者の振る舞いは、企業の魅力そのものを体現するものであり、常に誠実さと客観性を持って業務にあたることが求められます。
採用担当者として日々奮闘されている皆さまへ。
株式会社Piic(ピーク)は、「採用をデザインで強くする」をテーマに、採用ブランディング支援を行っています。
採用サイトやピッチ資料、パンフレットなどの制作を通じて、企業の想いや魅力を“言語化×デザイン化”し、応募者の共感を生む採用活動をサポートしています。
滋賀を拠点に、関西全域をはじめ全国の企業へフルリモート対応。
企業が“伝える力”で選ばれる時代に、Piicはそのパートナーとして伴走します。








