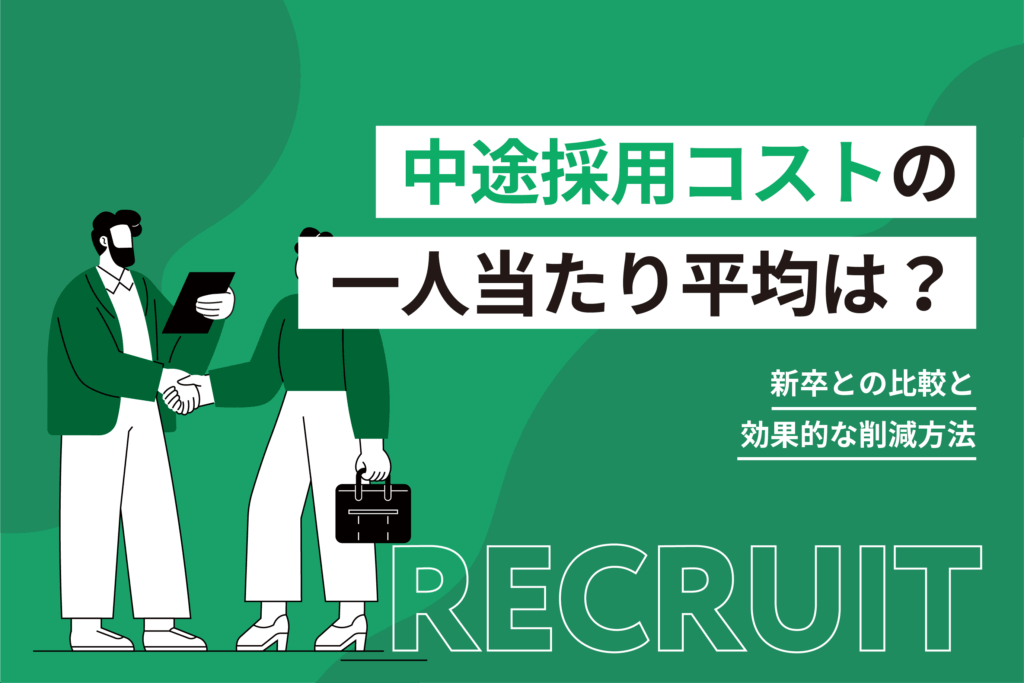
企業の成長に欠かせない中途採用ですが、その活動には様々なコストが発生します。
中途採用のコストが想定以上にかさんでいると感じる担当者も少なくありません。
採用活動を成功させるためには、一人当たりの採用コストがどのくらいかかるのかを正しく把握し、適切に管理することが求められます。
この記事では、中途採用にかかるコストの内訳や平均相場、新卒採用との違いを解説するとともに、コストを効果的に削減するための具体的な方法を紹介します。

Index
-
そもそも中途採用コストとは?内訳となる2つの費用を解説
-
求人広告費や紹介手数料などの「外部コスト」
-
面接官の人件費や社内調整費などの「内部コスト」
-
一人当たりの採用コストはいくら?具体的な計算方法を紹介
-
【データで見る】中途採用の一人当たり平均コスト
-
新卒採用にかかるコストとの比較
-
【企業規模別】中途採用コストの平均相場
-
【業種別】中途採用コストの平均相場
-
中途採用のコストが高騰してしまう主な原因
-
採用活動の長期化による選考費用の増加
-
入社後のミスマッチが引き起こす早期離職
-
【実践】中途採用コストを効果的に削減する7つの方法
-
1. 求める人物像を明確にし採用のミスマッチを防ぐ
-
2. 自社の採用サイトやSNSを活用して直接募集する
-
3. 社員紹介制度(リファラル採用)を活性化させる
-
4. 企業から候補者に直接アプローチする
-
5. 費用対効果を分析して求人媒体を見直す
-
6. 採用業務を外部に委託し人件費を最適化する
-
7. 内定者への手厚いフォローで入社辞退を防止する
-
コスト削減で失敗しないために押さえておきたい注意点
-
よくあるご質問
-
Q1.中途採用コストの勘定科目は何ですか?
-
Q2.採用コストはいつまでに支払う必要がありますか?
-
Q3.無料でできる中途採用の方法はありますか?
-
Q4.採用した人がすぐに辞めてしまった場合、紹介手数料は返金されますか?
-
Q5.採用コストを削減しすぎて失敗するケースは?
-
まとめ
そもそも中途採用コストとは?内訳となる2つの費用を解説

中途採用コストとは、企業が中途採用活動を行う際に発生する費用の総称です。
採用コストは、社外のサービス利用料など直接的に支払いが発生する「外部コスト」と、社内の人件費など目に見えにくい「内部コスト」の2種類に大きく分けられます。
採用活動全体の費用を正確に把握し、費用対効果を分析するためには、これらのコストの内訳を正しく理解しておくことが第一歩となります。
それぞれのコストにどのような項目が含まれるのかを具体的に見ていきましょう。
求人広告費や紹介手数料などの「外部コスト」
外部コストとは、採用活動のために社外の企業やサービスへ支払う費用のことです。
具体的には、求人サイトへの広告掲載料、人材紹介会社へ支払う成功報酬、合同企業説明会や転職フェアへの出展料、採用パンフレットや動画の制作を外注した場合の費用などが挙げられます。
特に、人材紹介サービスを利用した場合の成功報酬は、採用した人材の年収の30~35%が相場となっており、採用コストの中でも大きな割合を占める傾向にあります。
これらの費用は支出として明確に把握しやすいため、コスト管理の際にはまず注目すべき項目です。
面接官の人件費や社内調整費などの「内部コスト」
内部コストとは、採用活動に際して社内で発生する費用のことです。
これには、書類選考や面接を行う採用担当者および面接官の人件費、応募者との連絡や日程調整にかかる時間的コスト、社員紹介制度(リファラル採用)で社員に支払うインセンティブ報酬などが含まれます。
これらのコストは、通常の業務費として計上されることが多く、見過ごされがちです。
しかし、新卒採用と比べて個別対応が多くなる中途採用では、この内部コストが予想以上に膨らむことも少なくありません。
採用活動全体の費用を正確に把握するためには、こうした目に見えにくいコストもしっかりと算出することが重要です。
一人当たりの採用コストはいくら?具体的な計算方法を紹介

一人当たりの採用コストを算出する計算式は非常にシンプルです。
まず、採用活動にかかった全ての「外部コスト」と「内部コスト」を合計して、採用コストの総額を算出します。
次に、その総額を採用が決定した人数で割ることで、一人当たりの採用コストが求められます。
計算式で表すと「(外部コストの合計+内部コストの合計)÷採用人数」となります。
この計算を行うことで、採用活動全体の費用対効果を客観的な数値で把握できます。
定期的にこの数値を算出し、過去の実績や目標値と比較分析することが、採用戦略の見直しやコスト削減策を検討する上で不可欠です。
【データで見る】中途採用の一人当たり平均コスト

自社の採用コストが高いのか低いのかを判断するためには、市場の平均値を知ることが有効です。
ここでは、公表されているデータを基に、中途採用における一人当たりの平均コストを具体的に見ていきます。
新卒採用のコストと比較することで、中途採用のコスト構造の特徴がより明確になります。
また、企業規模や業種によっても採用コストには違いが見られるため、自社がどのセグメントに属するかを意識しながら参考にすることで、より実践的な分析が可能になります。
新卒採用にかかるコストとの比較
ある調査によると、2019年度の中途採用における一人当たりの平均採用コストは103.3万円であったのに対し、新卒採用では93.6万円という結果が出ています。
かつては、大規模な説明会の開催やパンフレットの大量印刷などが必要な新卒採用の方がコストは高いとされていました。
しかし、近年は人材獲得競争の激化から中途採用のコストも上昇傾向にあり、両者の差は縮まっています。
特に、専門性の高いハイクラス人材を人材紹介サービス経由で採用する場合、成功報酬が高額になり、新卒採用のコストを大幅に上回るケースも珍しくありません。
【企業規模別】中途採用コストの平均相場
中途採用のコストは、企業の規模によって変動する傾向があります。マイナビの「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」によると、従業員規模が大きくなるほど、中途採用にかかる費用も高くなる傾向が見られます。具体的には、従業員数が50名以下の企業では年間86.7万円、51~300名の企業では299.0万円、301~1000名の企業では550.4万円、1,001名以上の企業では1,290.5万円と、規模が大きくなるにつれて採用コストが増加しています。これは、大企業ほど採用人数が多いことや、人材紹介サービスを利用するケースが多いことが主な要因と考えられます。
一方で、中小企業やベンチャー企業は、知名度を補うために求人媒体への出稿を増やしたり、人材紹介サービスを積極的に活用したりする必要があるため、採用コストが高くなる傾向が見られる場合があります。ただし、大企業であっても、特定の専門職や経営幹部クラスを採用する際には、コストが高騰することもあります。
【業種別】中途採用コストの平均相場
採用コストは業種による影響も大きく受けます。
特にIT・通信・インターネット業界やコンサルティング、金融といった専門知識が求められる業種では、人材の需要が高い一方で供給が限られているため、人材獲得競争が激しくなります。
その結果、採用手法が多様化し、一人当たりの採用コストは高騰しやすい傾向にあります。
これに対し、流通・小売業やサービス業などでは、比較的採用コストが低い水準にとどまることもあります。
自社の属する業界の平均コストを把握し、競争環境を理解した上で採用戦略を立てることが求められます。
中途採用のコストが高騰してしまう主な原因

中途採用において、計画予算を上回るコストが発生する背景には、下記に記載したような複数の要因が考えられます。これらの問題は、単独で発生するだけでなく、互いに関連し合いながら採用コストを増加させる可能性があります。これらの事象がコスト増につながる仕組みを理解することは、効果的な対策を検討する上で重要です。
採用活動の長期化による選考費用の増加
採用活動が予定よりも長引いてしまうと、様々な追加コストが発生します。
例えば、求人広告の掲載期間を延長すれば追加の広告費がかかりますし、選考プロセスが長引けば、その分だけ面接官や採用担当者の人件費も増加します。
採用活動が長期化する主な原因としては、応募者の母集団形成がうまくいかないケースや、応募はあっても求めるスキルや経験を持つ人材が見つからないケースが挙げられます。
また、社内の選考基準が曖昧であったり、最終的な意思決定に時間がかかったりすることも、候補者の離脱を招き、結果として活動の長期化につながります。
入社後のミスマッチが引き起こす早期離職
入社後のミスマッチによる早期離職は、採用コストを著しく高騰させる最大の要因の一つです。
一人の社員が早期に離職してしまうと、その採用にかけた求人広告費や人材紹介手数料、面接に関わった社員の人件費など、全てのコストが無駄になってしまいます。
さらに、欠員を補充するために、再びゼロから採用活動を始めなければならず、追加で同等以上のコストが発生します。
ミスマッチは、スキルや業務内容の不一致だけでなく、社風や人間関係、価値観といったカルチャー面での不一致によっても起こるため、選考段階でいかに相互理解を深められるかが重要です。
【実践】中途採用コストを効果的に削減する7つの方法

中途採用のコスト高騰を招く原因を理解した上で、具体的な削減策を検討していくことが重要です。
ただし、やみくもに費用を削るだけでは、採用の質が低下し、かえってミスマッチを招くことにもなりかねません。
ここでは、採用の質を維持、あるいは向上させながら、コストを最適化するための実践的な以下7つの方法を詳しく紹介します。
1. 求める人物像を明確にする
2. 自社の採用サイトやSNSを活用する
3. 社員紹介制度(リファラル採用)を活性化させる
4. 企業から候補者に直接アプローチする
5. 費用対効果を分析して求人媒体を見直す
6. 採用業務を外部に委託する
7. 内定者への手厚いフォローで入社辞退を防止する
自社の採用課題や状況に合わせて、これらの手法を組み合わせながら取り組むことで、より高い効果が期待できます。
1. 求める人物像を明確にし採用のミスマッチを防ぐ
採用コスト削減の最も基本的で重要なステップは、採用する人物像を具体的に定義することです。
現場の部署が求めるスキルや経験を詳細にヒアリングするだけでなく、社風に合い、長期的に活躍してくれる人材の性格や価値観までを言語化し、関係者間で共有します。
この「採用ペルソナ」が明確になることで、求人票の訴求内容が具体的になり、応募者のスクリーニング精度も向上します。
結果として、選考プロセスの効率が上がり、入社後のミスマッチも大幅に減少するため、早期離職による再募集コストの発生を防ぐことにつながります。
2. 自社の採用サイトやSNSを活用して直接募集する
自社が運営する採用サイトやSNSアカウントは、外部の求人媒体に頼らずに応募者を集めるための強力なツールです。
これらのオウンドメディアを通じて、企業のビジョンや働く環境、社員の声を積極的に発信することで、企業文化に魅力を感じる候補者からの直接応募を促せます。
初期のサイト構築やコンテンツ制作にコストはかかりますが、一度軌道に乗れば、求人広告費や紹介手数料を大幅に削減することが可能です。
また、企業のリアルな情報を伝えやすいため、候補者との相互理解が深まり、ミスマッチの防止にも効果的です。
3. 社員紹介制度(リファラル採用)を活性化させる
リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。
社員からの紹介であるため、候補者のスキルや人柄に対する信頼度が高く、企業文化への適合性も期待できます。
紹介した社員へインセンティブを支払う場合でも、人材紹介会社への成功報酬と比較すれば、コストを大幅に抑えることが可能です。
選考プロセスも短縮できるため、内部コストの削減にもつながります。
この制度を成功させるには、社員へ制度を十分に周知し、紹介しやすい仕組みを整えるとともに、紹介してくれた社員が正当に評価される文化を醸成することが不可欠です。
4. 企業から候補者に直接アプローチする
ダイレクトリクルーティングは、企業が人材データベースなどを活用して候補者を自ら探し出し、直接スカウトメッセージを送る「攻め」の採用手法です。転職潜在層を含む幅広い人材プールの中から、求めるスキルや経験を持つ候補者にピンポイントでアプローチできるため、効率的な母集団形成が可能です。
ダイレクトリクルーティングの料金体系には、主に「成功報酬型」「定額型」「ハイブリッド型」があります。成功報酬型は採用が決定した際に費用が発生し、定額型は採用人数にかかわらず月額または年額の費用が発生します。ハイブリッド型は、これらを組み合わせた料金体系です。サービスによっては、データベースの利用料などの基本料が別途発生する場合や、初期費用がかからない完全成功報酬型もあります。採用コストは、利用するサービスやプランによって異なりますが、人材紹介サービスと比較して総コストを抑えられる可能性があります。
企業の魅力を直接伝えられるため、候補者の入社意欲を高めやすい点もメリットです。
5. 費用対効果を分析して求人媒体を見直す
現在利用している求人広告媒体について、定期的に費用対効果を検証することが重要です。
単に応募数や採用数だけでなく、「どの媒体経由の応募者が採用に至り、入社後も定着・活躍しているか」という質的な側面まで分析します。
各媒体の応募単価や採用単価を算出し、効果の低い媒体への出稿を停止または減額し、その分の予算を効果の高い媒体に集中させることで、広告費を最適化します。
媒体ごとに登録しているユーザー層は異なるため、自社の求める人物像とマッチする媒体を戦略的に選定する視点を持つことが必要です。
6. 採用業務を外部に委託し人件費を最適化する
採用業務の一部または全部を外部の専門業者に委託するRPO(採用代行)サービスを活用することも、コスト削減の有効な手段です。
例えば、応募者対応やスカウトメールの送信、面接の日程調整といったノンコア業務を外部に任せることで、社内の採用担当者は候補者の見極めや採用戦略の策定といった、より重要度の高いコア業務に集中できます。
これにより、採用担当者の業務負荷が軽減され、残業代などの内部コスト削減につながるほか、採用活動全体の生産性向上も期待できます。
7. 内定者への手厚いフォローで入社辞退を防止する
内定を出した後も、候補者は複数の企業を比較検討していることが少なくありません。
内定辞退が発生すると、それまでにかけてきた採用コストが全て水の泡となり、再び採用活動を行う必要が出てきます。
これを防ぐためには、内定承諾後から入社までの期間、候補者への手厚いフォローが不可欠です。
定期的な連絡はもちろん、現場社員との懇親会や社内イベントへの招待、個別の面談などを通じて、入社前の不安を解消し、企業への帰属意識を高めます。
こうした丁寧なコミュニケーションが入社への意思を固めさせ、最終的なコスト増を防ぎます。
コスト削減で失敗しないために押さえておきたい注意点
採用コストの削減に取り組む際、最も注意すべきは、単なる費用の切り詰めが採用の質の低下を招いてしまうことです。
例えば、広告費を削りすぎた結果、応募者の母集団が形成できず、採用活動が長期化してしまうケースは少なくありません。
また、内部コストである面接官の人件費を惜しんで面接時間を短縮したり、トレーニングを怠ったりすると、候補者の見極めが不十分になり、ミスマッチによる早期離職につながる恐れがあります。
採用コストは未来への投資であるという視点を持ち、どこに費用をかけるべきか、どこを効率化すべきかを戦略的に判断することが重要です。
短期的なコスト削減に囚われず、長期的に企業の成長に貢献する人材を獲得するという本質的な目的を見失わないようにしましょう。
よくあるご質問
Q1.中途採用コストの勘定科目は何ですか?
A1.会計処理上の勘定科目は費用によって異なります。
一般的に、求人広告費は「広告宣伝費」、人材紹介会社への成功報酬は「支払手数料」、面接官の交通費は「旅費交通費」、社内担当者の人件費は「給与手当」として計上されます。
ただし、企業の会計方針により異なるため、詳細は経理部門に確認してください。
Q2.採用コストはいつまでに支払う必要がありますか?
A2.支払いタイミングは利用するサービスによって様々です。
求人広告は掲載前の前払いや掲載後の後払いが一般的です。
人材紹介サービスの成功報酬は、紹介された候補者が入社した月の末日など、契約で定められた期日に支払うのが通例です。
Q3.無料でできる中途採用の方法はありますか?
A3.はい、あります。
ハローワークへの求人掲載、自社のウェブサイトやSNSでの告知、社員紹介制度(リファラル採用)をインセンティブなしで運用する方法などが考えられます。
ただし、これらの方法は応募者を集めるための情報発信や運用に社内リソース(内部コスト)を要する点を考慮する必要があります。
Q4.採用した人がすぐに辞めてしまった場合、紹介手数料は返金されますか?
A4.多くの人材紹介会社では、採用した人材が入社後一定期間内に自己都合で退職した場合、支払った手数料の一部が返金される「返還金規定」を設けています。
返金率や対象となる期間は契約内容によって異なるため、契約前に必ず確認することが重要ですす。
Q5.採用コストを削減しすぎて失敗するケースは?
A5.費用対効果を考えずに広告費を一律でカットした結果、応募者が全く集まらなくなるケースが典型的です。
また、安価な媒体に絞ったために求めるスキルを持つ人材に出会えず、採用活動が長期化することもあります。
内部コストを削減しようと面接を簡略化し、結果的にミスマッチを招くのもよくある失敗例です。
まとめ
中途採用コストは、求人広告費などの「外部コスト」と、社内の人件費などの「内部コスト」から構成されます。
一人当たりの平均コストを把握することは、採用活動の費用対効果を測定し、改善策を講じるための第一歩です。
コストが高騰する主な原因として、採用活動の長期化と入社後のミスマッチが挙げられます。
これらの課題に対応するためには、求める人物像の明確化、リファラル採用やダイレクトリクルーティングといった多様な手法の活用、内定者フォローの強化などが有効です。
単に費用を削るのではなく、採用の質を維持・向上させるという視点を持ち、戦略的にコストを最適化していく必要があります。
Piicでは、企業の魅力をしっかりと伝える採用ブランディングを通じて、採用活動の効率化をサポートしています。
「応募数を増やしたい」「ミスマッチを減らしたい」といった課題に対し、採用ピッチ資料や採用LPなどのクリエイティブで解決策をご提案。
コストを抑えつつ、求める人材に届く採用を一緒に実現しませんか?








