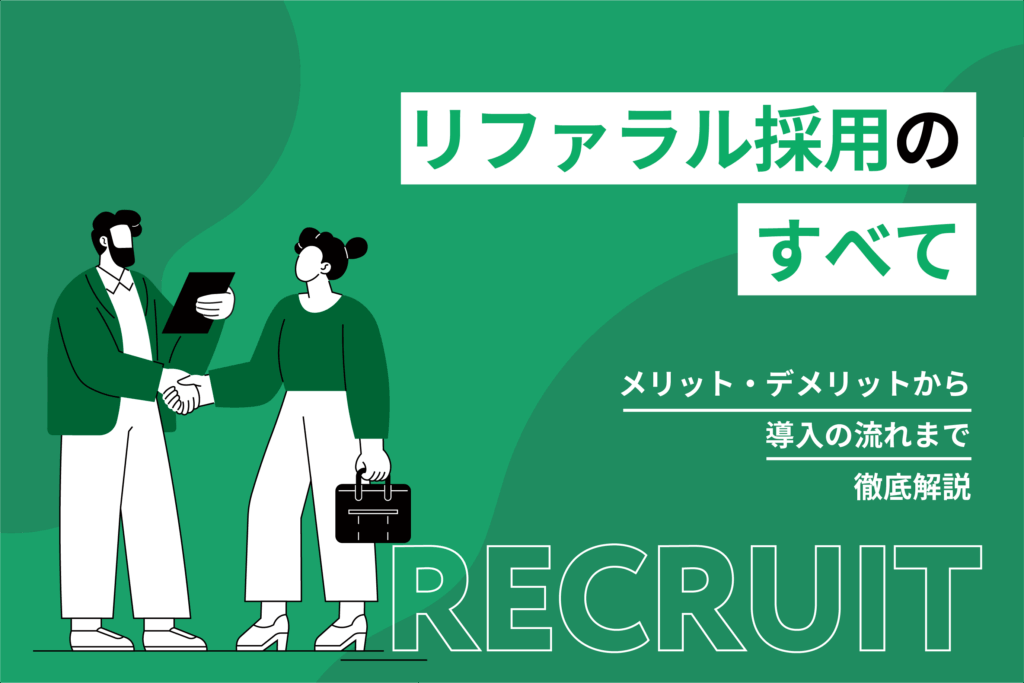
近年、リファラル採用は優秀な人材を確保するうえで欠かせない手法として注目を集めています。本記事では、リファラル採用の定義やメリット・デメリット、導入ステップや成功事例に至るまで詳しく解説します。
すでに取り入れている企業も多いリファラル採用ですが、その効果を最大化するためには制度設計や社内での周知が欠かせません。導入を検討している企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。
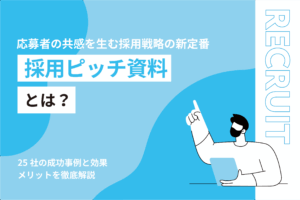

Index
-
リファラル採用の定義と目的
-
リファラル採用と縁故採用の違いとは?
-
リファラル採用と縁故採用の比較表
-
リファラル採用が注目される背景
-
リファラル採用のメリット
-
1. ミスマッチを防ぎやすく、離職リスクを軽減できる
-
2. 採用コスト・工数を抑えやすい
-
3. 自社のカルチャーにマッチした人材を採用しやすい
-
4. 転職潜在層にもアプローチできる
-
5. 社員のエンゲージメントが高まりやすい
-
リファラル採用のデメリット・注意点
-
1. 不採用時のフォローが必要になる
-
2. 人材の多様性が偏る可能性がある
-
3. 採用完了までに時間がかかることがある
-
4. 法的リスクや制度設計の不備に注意
-
リファラル採用の報酬制度を設計するポイント
-
1. 報酬の形式は「金銭」以外にも選択肢を
-
2. 報酬支給のタイミングは慎重に決める
-
3. 社員が理解・納得できるルール設計を
-
4. 過度な報酬設定や法的リスクにも注意
-
リファラル採用の導入ステップ
-
ステップ1:目的と目標の明確化
-
ステップ2:社内への制度周知と協力体制の構築
-
ステップ3:報酬制度・評価基準の設計
-
ステップ4:採用管理ツールや専用サービスの活用
-
リファラル採用を成功させるためのポイント
-
1. 社員へのリクルーター教育を行う
-
2. 他の採用チャネルと併用する
-
3. 紹介したくなる職場環境を整える
-
リファラル採用の成功事例
-
事例1:IT企業|エンジニア採用でコスト削減と定着率向上に成功
-
事例2:飲食チェーン|店舗スタッフの安定採用と職場の活性化
-
成功事例から見える4つの共通点
-
まとめ|リファラル採用で最適な人材と組織をつなげよう
-
リファラル採用に最適化された「採用ピッチ資料」を、Piicがつくります
リファラル採用の定義と目的
リファラル採用とは、社員や取引先など、企業と信頼関係のある人物から候補者を紹介してもらう採用手法です。
従来の求人媒体やエージェントと異なり、既存のネットワークから優秀な人材を探せるのが大きな特徴です。
この方法が注目されている理由は、ミスマッチを防ぎやすいこと。紹介者は候補者の人柄やスキルをよく知っているため、自社との相性が合いやすい傾向にあります。
紹介された側も、事前に会社の雰囲気や仕事内容を把握できるため、入社後のギャップを感じにくく、早期離職のリスクが低減されます。
さらに、転職サイトに登録していない「転職潜在層」にもアプローチできるため、競合より一歩先んじた人材確保が可能です。
リファラル採用は、精度の高い人材確保だけでなく、紹介した社員のエンゲージメント向上にもつながります。
制度として導入する際は、採用数の目標や期待する人材像を明確にし、紹介ルートや報酬制度の整備を進めることが成功のポイントです。
リファラル採用と縁故採用の違いとは?
リファラル採用と縁故採用は、どちらも「関係者からの紹介」を出発点とする点で似ていますが、制度の設計意図や選考プロセスには大きな違いがあります。両者を混同してしまうと、制度導入時に誤解や懸念が生じる可能性があるため、正しく理解しておくことが重要です。
リファラル採用と縁故採用の比較表
| 項目 | リファラル採用 | 縁故採用 |
|---|---|---|
| 紹介者 | 社員や業務関係者(信頼できる社内ネットワーク) | 親族や血縁者など、私的関係者が中心 |
| 選考プロセス | 通常の面接や評価を通じて公正に判断 | 選考が形式的になりがちで、評価基準が曖昧 |
| 採用基準 | スキルや価値観、社風との相性を重視 | 関係性の強さが優先されやすい |
| 企業リスク | 透明性のある採用が可能で不満が出にくい | 不公平感・社内不満が生じやすい |
| 制度の印象 | オープンで協力を得やすく企業文化に合う | コネ採用・古い体質という印象を与えやすい |
このように、リファラル採用は「業務に基づく紹介+公正な選考」が基本であり、あくまで採用の精度を高めるための制度的アプローチです。対して縁故採用は、私的な関係性に依存するため、導入には注意が必要です。
制度導入時に社員や経営層の理解を得るためにも、両者の違いを明確に整理し、透明性の高い設計を行うことが、成功の第一歩となります。
リファラル採用が注目される背景
リファラル採用が多くの企業で導入されるようになった背景には、採用難の時代における母集団形成の困難さと、採用ミスマッチへの対策ニーズが大きく関係しています。
日本では少子高齢化や労働人口の減少により、あらゆる業界で人材確保が困難になっています。特に若手や即戦力の人材を獲得するには、従来の求人媒体や人材紹介サービスだけでは限界があると感じている企業が増えています。
その一方で、採用後のミスマッチによる早期離職も増加傾向にあります。求人広告では見えづらい社風や職場の雰囲気が、入社後のギャップとして現れることで、せっかく採用した人材が短期間で離職してしまう――このような課題に対する有効な手段として、社員の信頼関係を活用するリファラル採用が注目されています。
また、SNSやビジネスチャット、オンラインコミュニティなどのツールが普及したことで、社員が気軽に知人・友人を紹介できる環境が整ってきたことも大きな後押しとなっています。
こうした背景から、リファラル採用は「人材の質」と「採用活動の効率」の両面においてバランスよく対応できる手法として、中小企業から大手企業まで広く導入が進んでいるのです。
リファラル採用のメリット
安定的で質の高い人材確保を実現する手段として、リファラル採用の導入を進める企業が増えています。ここでは、リファラル採用がもたらす主なメリットを、実務的な観点から詳しく解説します。
1. ミスマッチを防ぎやすく、離職リスクを軽減できる
リファラル採用では、紹介者が候補者の人柄や価値観、スキルを理解したうえで推薦するため、企業との相性が合いやすくなります。さらに、候補者も紹介者を通じて入社前からリアルな職場環境や業務内容を把握できるため、入社後のギャップが少なく、早期離職の防止につながりやすいのが特徴です。
2. 採用コスト・工数を抑えやすい
求人媒体への出稿やエージェントの活用に比べて、リファラル採用では媒体費や手数料がかかりにくく、採用単価を抑えることが可能です。さらに、紹介によって応募者の母集団がある程度選別された状態になるため、書類選考や面接の工数削減にもつながります。
特に、専門性の高い人材やエンジニアなどを採用する際には、コストと時間の両面で効率的な手法といえるでしょう。
3. 自社のカルチャーにマッチした人材を採用しやすい
紹介者は、自社の価値観や働き方を理解したうえで候補者を選定します。そのため、紹介された人材は企業文化になじみやすく、入社後の定着率や活躍度も高まる傾向があります。
「この人なら社内にうまくフィットしそうだ」という前提で紹介されるため、スキルマッチだけでは測れない“人間関係の相性”も見極めやすくなります。
4. 転職潜在層にもアプローチできる
リファラル採用では、まだ転職を積極的に考えていない「転職潜在層」にアプローチできるのも大きな強みです。求人広告や転職サイトには現れない優秀人材を、社員の人脈を通じて発掘できる機会が広がります。
企業にとっては、競合他社より早く優秀な人材と接点を持つことができ、採用競争において優位性を確保しやすくなります。
5. 社員のエンゲージメントが高まりやすい
自社を人に紹介するという行為は、社員が自分の職場に誇りや信頼を持っていることの表れでもあります。リファラル採用のプロセスを通じて、社員が会社とのつながりを再認識し、エンゲージメントが高まる効果が期待できます。
また、報酬制度や評価制度と連動させることで、紹介活動をポジティブな行動として社内文化に組み込むことも可能です。
リファラル採用のデメリット・注意点
リファラル採用は多くのメリットがある一方で、制度の運用や組織環境によっては、いくつかの注意点やデメリットも存在します。導入にあたっては、こうした側面を正しく理解し、事前に対策を講じることが重要です。
1. 不採用時のフォローが必要になる
紹介された候補者が不採用となった場合、紹介者との関係性によっては、気まずさやモチベーションの低下を招く恐れがあります。特に社員同士や友人関係の場合は、丁寧なコミュニケーションと結果のフィードバックが不可欠です。
小規模な組織ほど、紹介者と候補者の関係が密な傾向があるため、選考理由をしっかり伝え、紹介者が引き続き前向きに関われるような配慮が求められます。
2. 人材の多様性が偏る可能性がある
リファラル採用では、社員のネットワーク内での紹介が中心になるため、似たようなスキル・価値観・バックグラウンドの人材が集まりやすくなります。その結果、多様性やイノベーションの機会が損なわれる可能性もあります。
特に新規事業やクリエイティブ職種では、幅広い視点を持つ人材の確保が求められるため、他の採用手法との併用によってバランスを取ることが重要です。
3. 採用完了までに時間がかかることがある
リファラル採用は、社員が候補者を探し、声をかけ、承諾を得て応募してもらうという流れになるため、即効性のある手法ではありません。募集してすぐに応募が来るわけではなく、じっくりと関係性を築く必要があります。
採用にスピード感が求められる場合には、求人媒体や人材紹介サービスなど、他のチャネルとの併用が望まれます。
4. 法的リスクや制度設計の不備に注意
紹介者にインセンティブ(報酬)を支払う場合は、職業安定法や税務・社会保険のルールを守る必要があります。制度設計を誤ると、法的リスクや社内不公平を招く恐れがあります。
特に、アルバイトやパートタイム従業員の紹介、候補者本人への報酬制度などを導入する際は、雇用形態ごとの取り扱いルールを確認し、公平性を担保した設計が求められます。
リファラル採用の報酬制度を設計するポイント
リファラル採用を活性化させるには、社員が「紹介したい」と自然に思える環境づくりが欠かせません。その中でも、適切な報酬制度の設計は、社員の協力を得るための重要な要素です。
報酬の形や支給タイミングによっては、制度全体の印象や参加率が大きく左右されるため、導入前に設計のポイントをしっかり押さえておく必要があります。
1. 報酬の形式は「金銭」以外にも選択肢を
リファラル報酬は、現金やギフト券などの金銭的インセンティブが一般的ですが、必ずしもそれだけが効果的とは限りません。社内表彰や評価ポイントへの加点、福利厚生の拡充など、企業文化になじむ形で設計することが重要です。
たとえば、紹介者の貢献が見えるように表彰制度を取り入れることで、「金銭報酬よりもやりがいを感じる」という社員のモチベーションにつながるケースもあります。
2. 報酬支給のタイミングは慎重に決める
報酬は、紹介しただけで支払うのではなく、候補者が入社し、一定期間の勤務継続が確認された段階で支給するのが一般的です。たとえば「入社後3カ月継続で確定」といった基準を設けることで、安易な紹介を防ぎ、制度の信頼性を保つことができます。
また、一次面談通過時点、内定時点、入社後といった各フェーズごとに小額の段階的インセンティブを設定する企業もあります。社員の紹介活動を継続的に促したい場合には有効な手法です。
3. 社員が理解・納得できるルール設計を
制度をうまく運用するためには、対象者・対象職種・報酬額・支給条件などを明文化し、社員全員に明確に共有することが大切です。「誰が対象で、どの条件を満たせば、どんな報酬が得られるのか」がわかりやすく説明されていないと、制度の形骸化や不満の原因になります。
社内ポータルや説明会などでQ&Aを含めたガイドを整備し、いつでも確認できる状態にしておくと、制度の透明性と公平性を保ちやすくなります。
4. 過度な報酬設定や法的リスクにも注意
インセンティブ金額を高く設定しすぎると、「紹介のために無理に声をかける」「公平性に欠ける」といった副作用が起きる恐れがあります。報酬の目的はあくまで自発的な協力を促すための動機づけであり、過度な競争や営業的行為を助長しないよう配慮が必要です。
また、職業安定法などの法令に抵触しないよう、報酬の支払い対象や方法が合法であるかを事前に確認しておくことも不可欠です。雇用形態(正社員・アルバイト等)ごとの対応ルールもチェックしましょう。
リファラル採用の導入ステップ
リファラル採用は、導入すればすぐに成果が出るものではありません。目的を明確にし、社内の理解と協力を得ながら段階的に制度を整備することが成功の鍵です。
ここでは、スムーズにリファラル採用を立ち上げ、効果的に運用していくための4つのステップを紹介します。
ステップ1:目的と目標の明確化
最初に行うべきは、リファラル採用を導入する目的の整理です。たとえば、「カルチャーフィットする人材を増やしたい」「採用コストを抑えたい」「離職率を下げたい」といった目的に応じて、採用人数・職種・人材像などの目標設定を行いましょう。
短期・中長期それぞれの目標を持つことで、KPIの設計や制度の改善もしやすくなります。経営陣・人事・現場の認識をそろえることも重要です。
ステップ2:社内への制度周知と協力体制の構築
リファラル採用は、社員の理解と協力がなければ成立しません。制度の目的やメリット、参加方法、報酬内容などを具体的かつ丁寧に社内へ周知することが不可欠です。
社内説明会やマニュアル配布、Q&Aの共有などを通じて、不明点が残らないようサポート体制も整えておきましょう。管理職やリーダー層の巻き込みも、社内への浸透を加速させるポイントです。
ステップ3:報酬制度・評価基準の設計
制度を定着させるには、紹介者にとって納得感のある報酬設計が必要です。金銭的なインセンティブだけでなく、表彰制度や評価項目への反映など、複数の軸で制度を構築することで、さまざまなタイプの社員にアプローチできます。
また、「どの時点で支給されるのか」「対象となる職種は何か」といった条件を明文化し、社内で透明性を確保することも重要です。
ステップ4:採用管理ツールや専用サービスの活用
リファラル採用の紹介・選考状況を適切に把握・管理するためには、採用管理ツールの導入が効果的です。誰が誰を紹介したのか、どのフェーズにいるのかといった情報を共有できることで、人事と現場の連携がスムーズになります。
社内チャットツールやSNSと連携させるなど、紹介のハードルを下げる工夫も大切です。必要に応じて、リファラル採用専用の外部サービスを活用するのも選択肢の一つです。
リファラル採用を成功させるためのポイント
リファラル採用は制度を整えるだけでは十分とはいえません。社員の理解と協力を引き出し、継続的に機能させるためには、制度設計以外の“土台づくり”も不可欠です。
ここでは、リファラル採用を長期的に成功させるために企業が押さえておくべき3つの実践ポイントをご紹介します。
1. 社員へのリクルーター教育を行う
社員が自社の魅力や採用ニーズを正しく伝えられなければ、せっかくのネットワークも活用しきれません。紹介活動をスムーズに進めるために、社員に“社内リクルーター”としての役割を伝え、情報提供や教育の機会を設けることが重要です。
例えば、社内勉強会や説明資料、簡単なトークスクリプトを配布することで、紹介時の不安を軽減できます。面接経験のある人事担当やマネージャーがサポートに入る仕組みをつくるのも効果的です。
2. 他の採用チャネルと併用する
リファラル採用は効果的な手法ですが、それだけに依存すると人材の偏りやスピード不足につながる可能性があります。求人媒体や転職イベント、人材紹介サービスなどと併用しながら、最適なバランスを模索しましょう。
特に「短期間で複数名を採用したい」「新規領域の人材を確保したい」場合には、他チャネルとの組み合わせが不可欠です。全体戦略の一部としてリファラルを位置づけると、より安定した採用基盤を築けます。
3. 紹介したくなる職場環境を整える
どれだけ報酬制度を整えても、社員が「この会社を紹介したい」と思える環境でなければ、リファラル採用は機能しません。社員満足度が高く、誇りを持てる職場づくりこそが制度の根幹です。
柔軟な働き方、キャリア支援、社内コミュニケーションの活性化など、エンゲージメントを高める取り組みを並行して進めることで、自然と紹介の機会も生まれます。制度と職場環境をセットで考えることが、リファラル採用の持続的な成功につながります。
リファラル採用の成功事例
ここでは、実際にリファラル採用を導入して成果を上げた企業の事例を2つ紹介します。それぞれの業界特性に合わせた工夫や運用ポイントを深掘りし、自社導入時の参考にしてください。
事例1:IT企業|エンジニア採用でコスト削減と定着率向上に成功
中堅規模のIT企業では、エンジニアやプロジェクトマネージャーの採用に苦戦しており、人材紹介会社の利用による高コストや、入社後の早期離職が大きな課題でした。
そこで導入したのが、現場主導のリファラル採用制度。以下のような具体策が功を奏しました。
- 社内リクルーター研修を導入し、紹介時の会話や説明スキルを強化
- 報酬は段階的に支給(内定時3万円+入社後3カ月で追加5万円)
- 技術部門が一次面談を担当し、スキルマッチ精度を向上
その結果、採用コストを年間40%削減。加えて、リファラル経由の入社者の定着率は90%超を記録し、採用の質と効率の両面で大きな成果が生まれました。
事例2:飲食チェーン|店舗スタッフの安定採用と職場の活性化
従業員300名超の飲食チェーンでは、店舗スタッフの離職率が高く、求人広告への依存とコスト負担が課題でした。そこで、リファラル採用を活用し、現場主導で人材確保に取り組みました。
具体的には、現場が「気軽に紹介できる仕組み」を意識して以下を実施。
- LINEで完結する紹介フォームを導入し、紹介のハードルを大幅に低下
- 研修サポート・シフト調整など、紹介後の貢献も評価対象に
- 紹介時にドリンクチケットなどの軽インセンティブを即時付与
結果として、リファラル経由の入社者が全体の45%にまで増加。紹介者との関係性から職場定着も進み、店舗間の連携や雰囲気の改善にもつながりました。
成功事例から見える4つの共通点
2社の成功事例から、次のような共通ポイントが見えてきます。
- 社員教育やマニュアル整備で、紹介のハードルを下げている
- インセンティブ制度を段階的かつフェアに設計している
- 人事と現場が協力して制度を運用している
- 紹介後のフォロー体制(定着支援・研修など)も制度化している
リファラル採用は単なる制度ではなく、社内文化や風土として根づかせることが成功のカギです。導入する際は、こうした実践的な工夫を参考に、自社の組織特性に合った運用を検討してみてください。
まとめ|リファラル採用で最適な人材と組織をつなげよう
リファラル採用は、単なる「人材確保の手段」ではなく、社員のつながりを活かして、企業文化にフィットした人材を採用できる仕組みです。ミスマッチの軽減や採用コストの削減、定着率の向上など、さまざまな効果が期待できる一方で、制度設計や社内周知、法令遵守といった準備も欠かせません。
成功のためには、以下の3点が特に重要です。
- 目的と目標を明確にし、制度の設計を丁寧に行うこと
- 社員の理解と協力を得るための情報共有とフォロー体制の構築
- 働きたくなる職場環境そのものをつくること
これらを整えることで、リファラル採用は単発的な施策ではなく、企業の成長に直結する「持続可能な採用戦略」として機能します。
社員が「この会社なら紹介したい」と感じ、候補者が「この会社で働きたい」と思える。そんな好循環を生むリファラル採用は、まさに最適な人材と組織をつなぐ架け橋となるのです。
自社に合った制度を丁寧に設計し、リファラル採用の可能性を最大限に引き出していきましょう。
リファラル採用に最適化された「採用ピッチ資料」を、Piicがつくります
社員が「紹介したくなる企業」とは、想いが“自然に伝わる”ツールを持っている企業です。
Piicでは、企業の魅力をわかりやすく伝える「採用ピッチ資料」の設計・制作を通じて、リファラル採用を推進する採用クリエイティブをご支援しています。
「社員が友人に会社を紹介するとき、どんな資料を見せるか?」
この問いに真っ向から向き合い、
理念・カルチャー・働く人の姿を、“紹介されるための形”に落とし込むのが私たちの役割です。
「会社を紹介したい」という気持ちが自然に芽生える──
そんなリファラル採用の土台となるピッチ資料を、ぜひ一緒につくりましょう。








