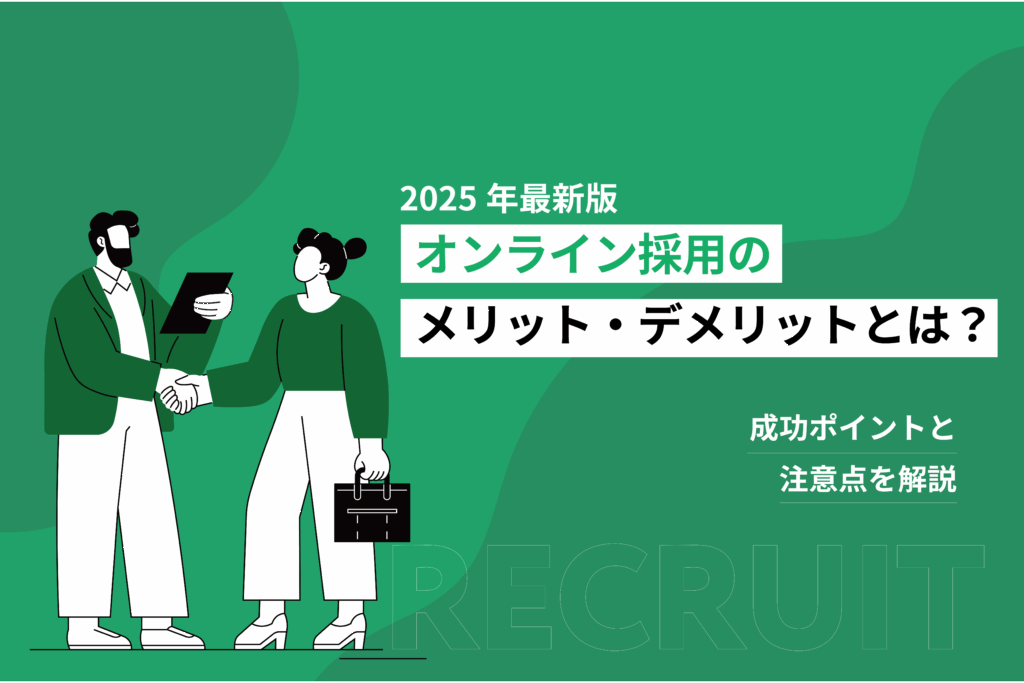
近年、多くの企業で導入が進むオンライン採用活動は、場所や時間の制約を受けずに優秀な人材と接点を持てるメリットがあります。
その一方で、応募者の人柄が掴みにくいといった課題もあり、対面とは異なる工夫が求められます。
採用活動のオンライン化を成功させるには、メリットを最大限に活かしつつ、課題を克服するためのポイントを理解することが不可欠です。
この記事では、オンライン採用のメリットとデメリット、導入ステップ、成功のポイントから注意点までを網羅的に解説します。
Index
-
オンライン採用とは?対面形式との違いをわかりやすく解説
-
オンライン採用が急速に普及した3つの背景
-
オンライン採用を導入する5つのメリット
-
遠方に住む優秀な人材にもアプローチできる
-
採用にかかる会場費や交通費などのコストを削減可能
-
選考プロセスを効率化し内定までの時間を短縮できる
-
応募者の移動時間や費用といった負担を軽減できる
-
先進的な採用活動で企業イメージの向上につながる
-
オンライン採用で起こりうる5つのデメリット
-
応募者の細かな表情や人柄が把握しにくい
-
自社の雰囲気や社風が候補者に伝わりづらい
-
通信環境のトラブルで選考が中断するリスクがある
-
グループディスカッションのような複数人での選考が実施しにくい
-
入社後のミスマッチや内定辞退につながる可能性がある
-
オンライン採用を導入するための4ステップ
-
ステップ1:目的を明確にしオンライン化する範囲を決める
-
ステップ2:採用フローと評価基準を再設計する
-
ステップ3:Web会議システムやマイクなどのツールを準備する
-
ステップ4:面接官向けのトレーニングやリハーサルを実施する
-
オンライン採用を成功に導く5つのポイント
-
候補者の緊張を和らげるアイスブレイクを用意する
-
対面よりもリアクションを大きく取り、はっきりと話す
-
事前に接続テストを行い安定した通信環境を確保する
-
通信トラブルに備えて緊急連絡先や代替案を準備しておく
-
画面共有を活用し企業の魅力を伝える資料を見せる
-
オンライン採用で失敗しないための注意点
-
情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策を徹底する
-
なりすまし防止のために候補者の本人確認を確実に行う
-
オンラインでのやりとりに不慣れな候補者へ配慮する
-
オンライン採用に役立つシステム・ツールの種類
-
Web会議システム
-
採用管理システム(ATS)
-
動画面接・録画面接ツール
-
よくあるご質問
-
Q1.オンライン面接と対面面接は、どちらを優先すべきですか?
-
Q2.通信トラブルで面接が中断した場合、候補者の評価はどうなりますか?
-
Q3.オンライン面接で候補者がカンペを見ているのを防ぐ方法はありますか?
-
Q4.オンライン採用で内定辞退を減らすにはどうすればよいですか?
-
Q5.どのツールを選べばいいか分かりません。
-
まとめ
オンライン採用とは?対面形式との違いをわかりやすく解説

オンライン採用とは、会社説明会から面接、内定者フォローまで、採用活動の全てまたは一部を、Web会議システムなどのオンラインツールを活用して実施する採用手法です。
対面形式の採用活動との最も大きな違いは、企業と候補者が物理的に同じ場所にいる必要がない点にあります。
これにより、場所や移動時間の制約がなくなり、採用の可能性が大きく広がります。
一方で、画面越しのコミュニケーションとなるため、非言語的な情報が伝わりにくく、オンラインでの効果的なアプローチが求められます。
オンライン採用が急速に普及した3つの背景

オンライン採用が急速に普及した背景には、主に3つの要因が挙げられます。
一つ目に考えられるのは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面での採用活動が困難になったことが直接的なきっかけです。
二つ目は、5Gなどの通信技術の進化と各種オンラインツールの普及により、場所を問わず安定したコミュニケーションが可能になった技術的基盤が整ったこと。
最後に、リモートワークの浸透など働き方の多様化が進み、企業も候補者も時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を求めるようになったこともオンライン採用の需要が増加した原因の一つとして挙げられます。
ある調査でも、多くの企業がオンライン採用を継続する意向を示しています。
オンライン採用を導入する5つのメリット

オンライン採用の導入は企業にとって下記のような多くのメリットをもたらします。
- 遠方に住む優秀な人材にもアプローチできる
- 採用にかかる会場費や交通費などのコストを削減可能
- 応募者の移動時間や費用といった負担を軽減できる
- 選考プロセスを効率化し内定までの時間を短縮できる
- 先進的な採用活動で企業イメージの向上につながる
最大の利点は地理的な制約がなくなることでこれまでアプローチが難しかった遠方の優秀な人材にも選考機会を提供できることです。
また説明会や面接の会場費担当者や候補者の交通費宿泊費といったコストを大幅に削減できます。
さらに移動時間が不要になるため日程調整がしやすくなり選考プロセス全体の効率化とスピードアップが図れます。
候補者側の負担も軽減されるため応募のハードルが下がり企業の先進的なイメージ向上にも貢献します。
遠方に住む優秀な人材にもアプローチできる
オンライン採用を導入する大きなメリットの一つは、採用ターゲットの幅を地理的に大きく広げられる点です。
従来の対面形式では、面接会場まで足を運べる距離に住む候補者が応募者の中心になりがちでした。
しかし、オンラインであれば、国内の遠隔地はもちろん、海外に住む優秀な人材にもアプローチが可能です。
これにより、これまで接点のなかった多様なバックグラウンドを持つ人材と出会う機会が生まれ、企業の競争力強化に不可欠な人材の確保につながります。
母集団形成の観点からも、居住地を問わずに採用活動を展開できる影響は非常に大きいと言えます。
採用にかかる会場費や交通費などのコストを削減可能
採用活動におけるコスト削減は、多くの企業にとって重要な課題です。
オンライン採用は、この課題に対する有効な解決策となります。
例えば、大規模な会社説明会を開催するための会場レンタル費用や設営費が不要になります。
また、面接官が各拠点へ出張する際の交通費や宿泊費、さらには遠方から来る候補者に支給していた交通費も削減できます。
その他、会社案内や配布資料などのペーパーレス化も進めやすく、印刷コストの削減も可能です。
これらのコストを抑えることで、採用予算を他の施策に充当するなど、より戦略的な採用活動を展開できるようになります。
選考プロセスを効率化し内定までの時間を短縮できる
オンライン採用は、選考プロセス全体のスピードアップに大きく貢献します。
対面での面接では、面接官と候補者双方の移動時間を考慮して日程を調整する必要がありましたが、オンラインではその必要がありません。
これにより、候補者との面接日程の調整が格段に容易になり、短期間で多くの面接を実施できます。
結果として、応募から内定出しまでのリードタイムを大幅に短縮することが可能です。
採用競争が激化する中で、競合他社よりも早く優秀な人材にアプローチし、内定承諾を得るための大きなアドバンテージとなり得ます。
応募者の移動時間や費用といった負担を軽減できる
オンライン採用は、企業側だけでなく応募者側にも大きなメリットがあります。
特に、遠方に住んでいる学生や、現職で働きながら転職活動をしている社会人にとって、面接のたびに企業へ足を運ぶのは時間的にも金銭的にも大きな負担です。
オンラインであれば、自宅などから気軽に参加できるため、移動時間や交通費を気にする必要がありません。
この負担軽減は、これまで地理的・時間的な制約で応募をためらっていた層からの応募を促進する効果が期待できます。
結果として、より多くの多様な候補者からの応募が集まり、母集団の質の向上にも貢献します。
先進的な採用活動で企業イメージの向上につながる
オンライン採用を積極的に導入し、スムーズに運用している企業は、候補者に対して先進的で柔軟な姿勢を持っているという印象を与えます。
特に、ITリテラシーの高い人材や、新しい働き方を求める若年層にとって、オンラインツールを使いこなす企業の姿は魅力的に映ります。
採用活動のオンライン化は、単なる選考手法の変更にとどまらず、企業のDX推進度や変化への対応力を示す機会でもあります。
このようなポジティブな企業イメージは、候補者の志望度を高めるだけでなく、企業のブランディングにも良い影響を及ぼす可能性があります。
オンライン採用で起こりうる5つのデメリット
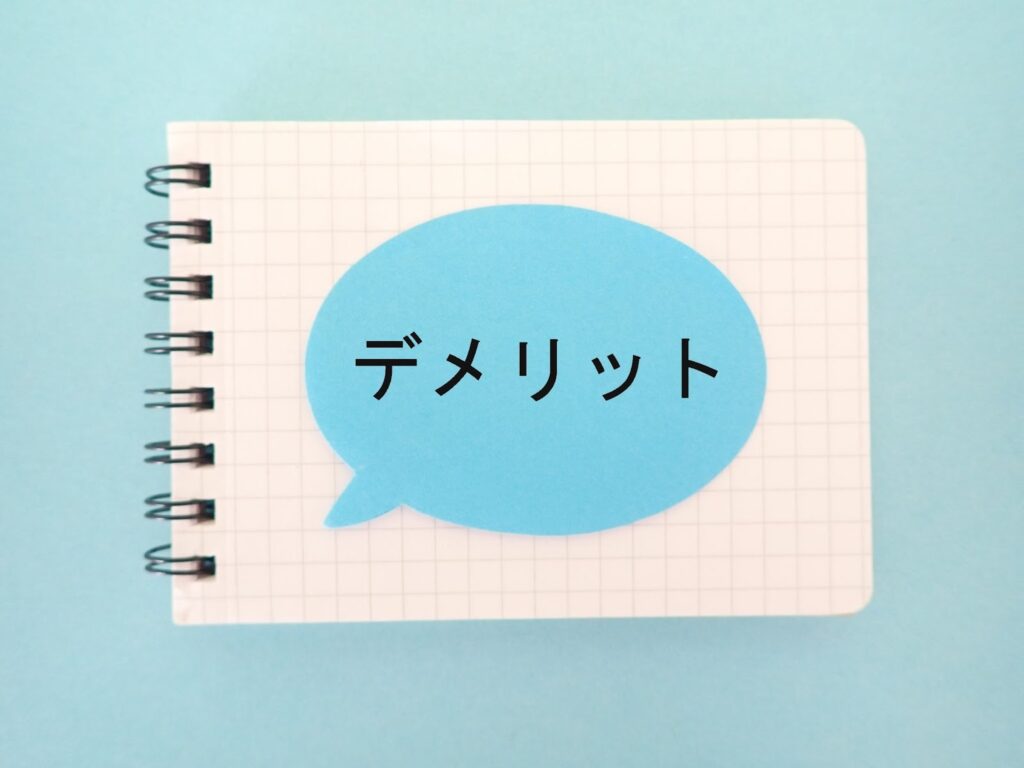
多くのメリットがある一方で、オンライン採用には下記のような注意すべきデメリットも存在します。
- 応募者の細かな表情や人柄が把握しにくい
- 自社の雰囲気や社風が候補者に伝わりづらい
- 通信環境のトラブルで選考が中断するリスクがある
- グループディスカッションのような複数人での選考が実施しにくい
- 入社後のミスマッチや内定辞退につながる可能性がある
最も大きな課題は、画面越しのコミュニケーションでは応募者の細かな表情や仕草から伝わる人柄といった非言語的な情報が把握しにくい点です。
同様に、自社のオフィス環境や社員の雰囲気といった「社風」も候補者に伝わりづらくなります。
また、通信環境のトラブルによって選考が中断するリスクや、複数人での議論を評価するグループディスカッションが実施しにくいという制約も考慮しなければなりません。
これらの要因が、入社後のミスマッチや内定辞退を引き起こす可能性も潜んでいます。
応募者の細かな表情や人柄が把握しにくい
オンライン面接における最大の課題の一つは、応募者の人柄や個性を深く理解することが難しい点です。
対面のコミュニケーションでは、言葉の内容だけでなく、表情の微妙な変化、声のトーン、視線、身振り手振りといった非言語的な情報から相手の感情や人となりを総合的に判断しています。
しかし、Web会議システムを通すと、映像や音声の質によってはこれらの情報が欠落したり、タイムラグによって不自然に見えたりすることがあります。
その結果、候補者の本来の魅力や熱意が伝わりにくく、評価が表層的なものにとどまってしまうリスクがあります。
自社の雰囲気や社風が候補者に伝わりづらい
候補者が企業を選ぶ上で、社風や職場の雰囲気は非常に重要な要素です。
対面での選考であれば、候補者はオフィスを訪れることで、エントランスの様子、働いている社員たちの表情や会話、オフィスの活気などを肌で感じ取ることができます。
しかし、オンライン採用ではこうした「空気感」を伝えることが困難です。
言葉や資料だけで社風を説明しようとしても、その魅力が十分に伝わらず、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージしにくくなります。
この企業理解の不足が、候補者の不安を招き、内定辞退や入社後のミスマッチの一因となる可能性があります。
通信環境のトラブルで選考が中断するリスクがある
オンライン採用は、企業と候補者双方の通信環境に大きく依存します。
そのため、インターネット回線の速度や安定性によっては、面接の途中で映像が固まったり、音声が途切れたり、最悪の場合は接続が切断されたりするリスクが常に伴います。
こうしたトラブルが発生すると、面接がスムーズに進行しないだけでなく、限られた時間内で候補者の能力を正しく評価することが難しくなります。
また、トラブルが候補者側に起きた場合、それが本人の責任でなくても、動揺してしまい本来のパフォーマンスを発揮できなくなる可能性も考慮しなければなりません。
グループディスカッションのような複数人での選考が実施しにくい
候補者の協調性やリーダーシップなどを評価するために有効なグループディスカッションも、オンラインでの実施には難しさがあります。
Web会議システムでは、複数人が同時に発言すると音声が重なって聞き取りにくくなるため、議論が停滞しがちです。
また、対面であれば自然に行われるアイコンタクトや頷きといった非言語的なコミュニケーションが取りにくく、誰が次に発言すべきかタイミングを計るのが困難になります。
ファシリテーターがうまく進行を管理しないと、一部の候補者しか発言できないなど、公平な評価が難しくなる場面も想定されます。
入社後のミスマッチや内定辞退につながる可能性がある
オンライン採用における相互理解の不足は、最終的に入社後のミスマッチや内定辞退を招く可能性があります。
企業側は候補者の人柄を把握できず、候補者側も企業の雰囲気を理解できないまま選考が進むと、互いの期待値にズレが生じやすくなります。
その結果、内定を出しても「思っていた会社と違った」と感じた候補者が辞退してしまったり、入社後に「こんなはずではなかった」と早期離職につながったりするリスクが高まります。
企業と候補者、双方にとって不幸な結果を避けるためにも、オンラインでの相互理解を深める工夫が不可欠です。
オンライン採用を導入するための4ステップ
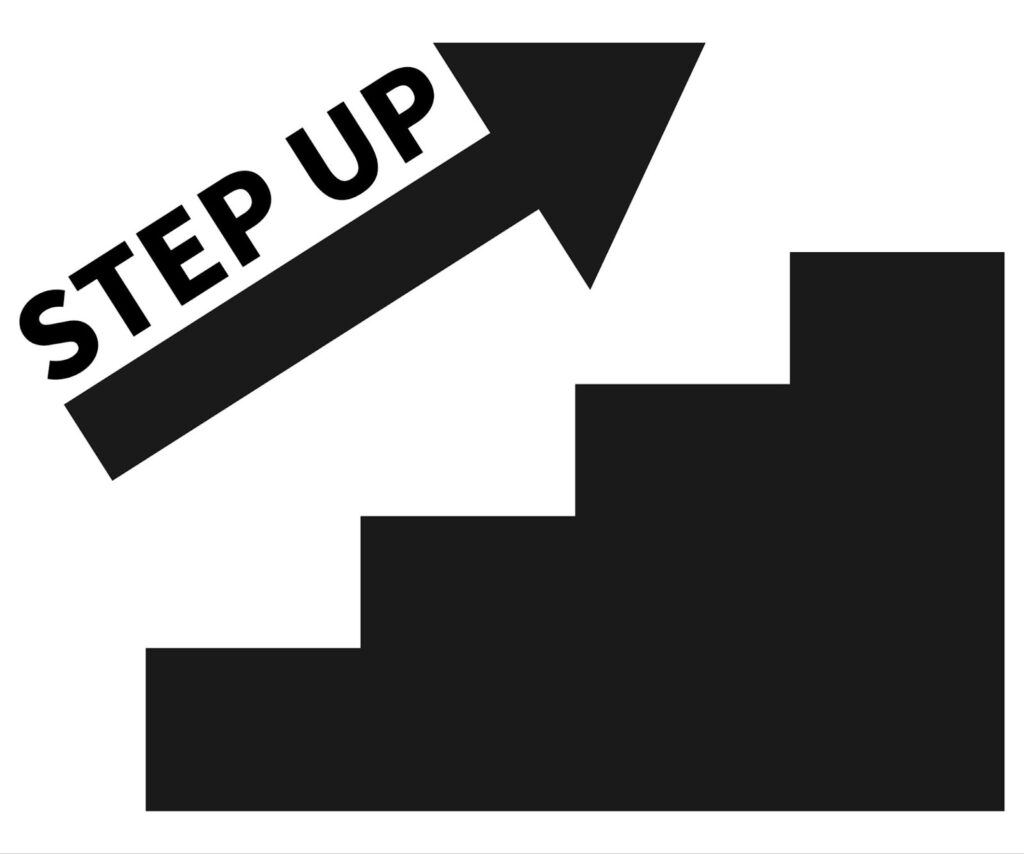
オンライン採用を効果的に導入するためには、計画的な準備が不可欠です。
まず、なぜオンライン化するのかという目的を明確にし、説明会や面接など、どの選考フローに導入するのか範囲を決定します。
次に、その目的に合わせて、オンラインに適した選考プロセスや評価基準を再設計する必要があります。
続いて、Web会議システムやマイク、カメラといった必要なツールを準備し、安定した通信環境を整えます。
最後に、面接官がオンライン面接の特性を理解し、スムーズに進行できるようトレーニングやリハーサルを実施することが重要です。
この4つのステップを着実に進めることが成功の鍵となります。
ステップ1:目的を明確にしオンライン化する範囲を決める
オンライン採用の導入を検討する最初のステップは、「何のためにオンライン化するのか」という目的を明確にすることです。
例えば、「採用コストを削減したい」「地方在住の優秀な学生にもっと応募してもらいたい」「選考のスピードを上げて内定辞退を防ぎたい」など、企業によって目的は様々です。
この目的が明確になることで、その後の施策に一貫性が生まれます。
目的を定めたら、次にオンライン化する範囲を具体的に決めます。
会社説明会だけをオンラインにするのか、一次面接までか、あるいは最終面接まで全てをオンラインで完結させるのか、自社の目的や採用ポジションの特性に合わせて最適な範囲を検討します。
ステップ2:採用フローと評価基準を再設計する
オンライン採用の導入にあたっては、従来の対面形式の採用フローをそのまま移行するだけでは不十分です。
オンラインの特性を踏まえ、採用フロー全体を再設計する必要があります。
例えば、一次選考に録画式の動画面接を取り入れてスクリーニングの効率を上げたり、オンライン適性検査を組み合わせて客観的な評価指標を増やしたりするなどの工夫が考えられます。
同時に、評価基準も見直しが不可欠です。
オンラインでは「熱意」や「雰囲気」といった曖昧な要素が伝わりにくいため、「論理的思考力」や「具体的なエピソードに基づいた行動特性」など、より明確で客観的に判断できる評価項目を設定することが重要になります。
ステップ3:Web会議システムやマイクなどのツールを準備する
オンライン採用を円滑に実施するためには、適切なツールの準備が欠かせません。
中心となるのは、ZoomやMicrosoftTeams、GoogleMeetといったWeb会議システムです。
利用人数やセキュリティ要件、使いやすさを考慮して、自社に合ったシステムを選定します。
ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの準備も重要です。
PC内蔵のカメラやマイクでは画質や音質が不十分な場合があるため、よりクリアな映像と音声を届けるための外付けWebカメラやマイク、ヘッドセットを用意することが推奨されます。
また、面接官の表情が明るく見えるように、照明(リングライトなど)を準備することも有効です。
ステップ4:面接官向けのトレーニングやリハーサルを実施する
オンライン面接は、対面とは異なるスキルや配慮が求められるため、面接官への事前トレーニングが成功の鍵を握ります。
トレーニングでは、使用するWeb会議システムの基本的な操作方法から、オンラインでの効果的な質問の仕方、対面以上に大きなリアクションを心がけるといったコミュニケーションのコツまでを共有します。
また、通信トラブルが発生した際の具体的な対応手順についても確認しておく必要があります。
知識をインプットするだけでなく、実際に面接官役と候補者役に分かれて模擬面接を行うリハーサルを実施し、本番さながらの環境で流れを確認しておくことが、当日のスムーズな運営につながります。
オンライン採用を成功に導く5つのポイント
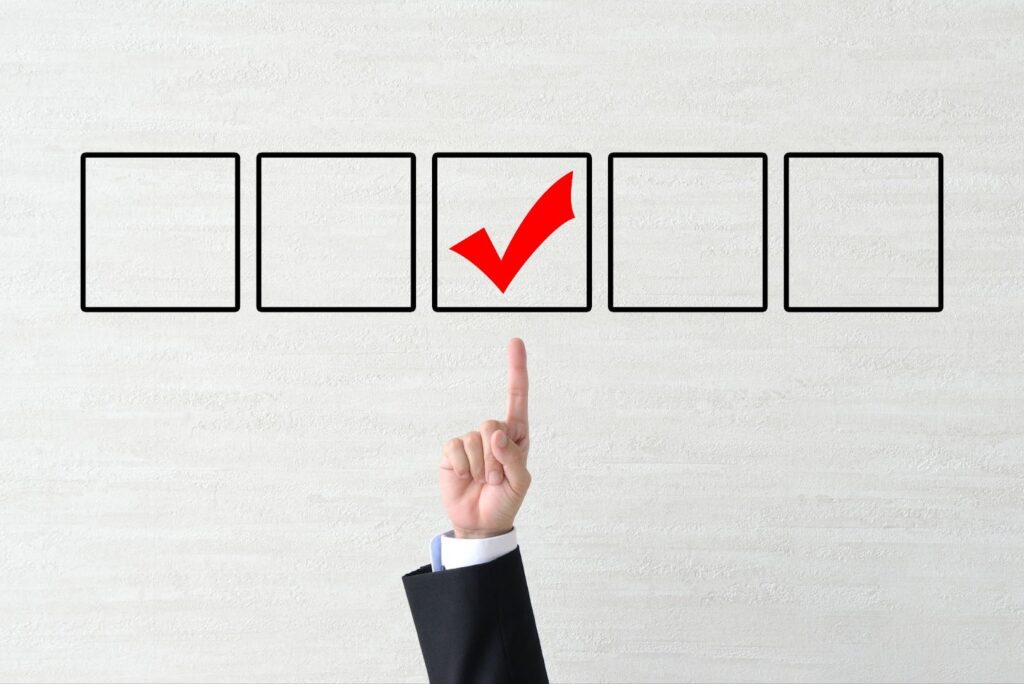
オンライン採用を成功させるためには、対面とは異なる環境であることを意識した工夫が必要です。
特に多くの学生と接する新卒採用などでは、きめ細やかな配慮が求められます。
まず、候補者の緊張を和らげるためのアイスブレイクを大切にしましょう。
面接官は、意識的にリアクションを大きくし、はっきりと話すことで円滑なコミュニケーションを促します。
また、技術的なトラブルを避けるため、事前の接続テストで安定した通信環境を確保し、万一のトラブルに備えて緊急連絡先を共有しておくことも不可欠です。
企業の魅力を伝えるためには、画面共有機能を活用し、視覚的な資料を見せながら説明する工夫も効果的です。
候補者の緊張を和らげるアイスブレイクを用意する
慣れないオンライン環境での面接は、候補者にとって対面以上の緊張を強いることがあります。
緊張のあまり、本来の自分をうまく表現できないまま面接が終わってしまうのは、候補者にとっても企業にとっても不幸なことです。
そのため、面接の冒頭で意識的にアイスブレイクの時間を設けることが非常に重要です。
面接官の簡単な自己紹介から始め、候補者の趣味や出身地に関する軽い雑談を交えることで、場の雰囲気を和らげることができます。
リラックスした状態で対話を始めることで、候補者は安心して自分の考えや経験を話せるようになり、企業側も候補者の素顔や本質的な部分を見極めやすくなります。
対面よりもリアクションを大きく取り、はっきりと話す
オンラインでのコミュニケーションは、画面越しであるため感情やニュアンスが伝わりにくいという特性があります。
面接官が真剣に話を聞いていても、無表情に見えてしまうと、候補者は「自分の話に興味がないのかもしれない」と不安に感じてしまいます。
これを避けるため、面接官は対面の時よりも意識的にリアクションを大きくすることが求められます。
具体的には、はっきりと頷く、笑顔を見せる、相槌を声に出して打つといった行動です。
また、マイクの性能や通信環境によっては音声が不明瞭になることもあるため、普段よりも少しゆっくり、そして明瞭な発声を心がけることが、スムーズでポジティブな対話の基盤を築きます。
事前に接続テストを行い安定した通信環境を確保する
オンライン面接における最大の懸念事項の一つが、通信トラブルです。
面接当日に音声が聞こえない、映像が映らないといったトラブルが発生すると、貴重な面接時間が失われるだけでなく、候補者に余計なストレスを与えてしまいます。
こうした事態を防ぐために、面接の数日前に候補者と接続テストを行うことを推奨します。
これにより、企業側と候補者側の双方の通信環境や機材に問題がないかを確認できます。
また、候補者にとっては、事前に使用するWeb会議システムに触れる良い機会となり、当日の操作に対する不安を軽減する効果も期待できます。
安定した環境を整えることが、公平な選考の第一歩です。
通信トラブルに備えて緊急連絡先や代替案を準備しておく
どれだけ入念に準備をしても、予期せぬ通信トラブルが発生する可能性はゼロではありません。
重要なのは、トラブルが起きた際に慌てず、冷静に対処できる体制を整えておくことです。
そのために、面接の案内メールなどで、当日の緊急連絡先(電話番号やメールアドレス)を候補者に必ず伝えておきましょう。
万が一、Web会議システムに接続できなくなった場合に、速やかに連絡を取り合うことができます。
また、「音声が途切れた場合はチャット機能で補足する」「接続が完全に切断された場合は電話面接に切り替える」あるいは「日程を再調整する」など、状況に応じた代替案を事前に複数用意しておくことも大切です。
画面共有を活用し企業の魅力を伝える資料を見せる
オンラインでは、言葉だけでは企業の魅力や働く環境を伝えきるのが難しいという課題があります。
この課題を解決するのに有効なのが、Web会議システムの画面共有機能です。
例えば、オンライン説明会や面接中に、オフィス内の様子を撮影した写真や動画、社員インタビューの映像、あるいは図やグラフを多用した分かりやすい事業説明資料などを画面共有で見せることで、候補者は企業に対する理解を深め、入社後のイメージを具体的に膨らませることができます。
視覚的な情報を効果的に活用することは、候補者の興味関心を引きつけ、志望度を高める上で非常に強力な手段となります。
オンライン採用で失敗しないための注意点

オンライン採用を円滑に進めるためには、注意点を押さえておく必要があります。
特に、個人情報を取り扱う上で、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策は最重要課題です。
社内でのルールを徹底し、安全なツールを選定することが求められます。
また、なりすましといった不正行為を防止するため、面接時には候補者の本人確認を確実に行うプロセスも不可欠です。
さらに、全ての候補者がオンラインでのやりとりに慣れているわけではないため、PC操作が苦手な候補者にも丁寧に寄り添い、ITリテラシーの差が選考結果に影響しないよう配慮する姿勢が、企業の信頼につながります。
情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策を徹底する
オンライン採用では、履歴書やエントリーシートといった個人情報をデータでやり取りする機会が増えるため、情報漏洩のリスクに対して細心の注意を払う必要があります。
万が一、応募者の個人情報が外部に流出してしまえば、企業の社会的信用は大きく損なわれます。
こうした事態を防ぐため、まずはセキュリティレベルの高いツールやシステムを選定することが基本です。
加えて、Web会議のURLにはパスワードを設定し、関係者以外に共有しない、社内で個人情報を取り扱う際のルールを明確化し全担当者に周知徹底する、といった運用面での対策も不可欠です。
セキュリティ対策は、オンライン採用を安全に実施するための大前提となります。
なりすまし防止のために候補者の本人確認を確実に行う
オンライン面接では、カメラに映っている人物が応募者本人であるかを直接確認することが難しいため、「なりすまし」のリスクがゼロではありません。
悪意のある第三者が応募者の代わりに面接を受けたり、複数人で協力して回答したりする不正行為の可能性も考えられます。
こうした不正を防ぎ、選考の公平性を担保するためには、本人確認のプロセスを導入することが有効です。
例えば、面接の冒頭で、候補者にカメラ越しに運転免許証や学生証などの顔写真付き身分証明書を提示してもらう方法があります。
この一手間を加えることで、不正行為を抑止し、信頼性の高い選考を実施することができます。
オンラインでのやりとりに不慣れな候補者へ配慮する
採用活動において、候補者全員が最新のデジタルツールやオンラインでのコミュニケーションに精通しているわけではない、ということを忘れてはなりません。
特に、PCの操作に不慣れな方や、オンライン面接の経験がない方にとっては、ツールの設定や操作自体が大きなストレスになる可能性があります。
企業側は、こうした候補者の不安を払拭するための配慮を心がけるべきです。
具体的には、事前にWeb会議システムの使い方を画像付きで分かりやすく説明したマニュアルを送付したり、希望者には接続テストの機会を個別に設けたりするなどのサポートが考えられます。
丁寧なフォローが、候補者の企業に対する安心感や好感度を高めます。
オンライン採用に役立つシステム・ツールの種類

オンライン採用を効率的かつ効果的に進めるためには、様々なシステムやツールの活用が不可欠です。
最も基本的なツールは、リアルタイムでの面接や説明会を行うためのWeb会議システムです。
さらに、応募者情報の一元管理や選考進捗の可視化を実現する採用管理システム(ATS)を導入することで、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
また、一次選考の効率化を図るために、候補者があらかじめ録画した動画で自己PRを行う、harutakaのような動画面接・録画面接ツールも注目されています。
これらのツールを自社の目的や採用規模に応じて組み合わせることで、オンライン採用の質を高めることが可能です。
Web会議システム
Web会議システムは、オンライン採用における面接や会社説明会を実施するための最も基本的なツールです。
代表的なものにZoom、MicrosoftTeams、GoogleMeetなどがあり、リアルタイムでの映像と音声によるコミュニケーションを可能にします。
多くのシステムには、資料を共有しながら説明できる画面共有機能や、面接内容を後から振り返るための録画機能、複数人を小グループに分けるブレイクアウトルーム機能などが搭載されています。
ツールを選定する際は、自社のセキュリティポリシーに準拠しているか、一度に参加できる人数、操作のしやすさなどを比較検討し、目的に合ったものを選ぶことが重要です。
無料プランから始められるものも多いため、まずは試してみるのも良いでしょう。
採用管理システム(ATS)
採用管理システム(ATS:ApplicantTrackingSystem)は、応募者の情報を一元管理し、採用業務全体の効率化を図るためのツールです。
求人媒体からの応募者情報を自動で取り込んだり、選考の進捗状況を可視化したり、面接官との日程調整を自動化したりする機能があります。
オンライン採用では、メールやチャットでのやり取りが増え、応募者情報が散在しがちですが、ATSを導入することで、全ての情報を一箇所に集約し、抜け漏れや対応の遅れを防ぐことができます。
Web会議システムや動画面接ツールと連携できるものも多く、採用プロセス全体をシームレスに管理することが可能になります。
動画面接・録画面接ツール
動画面接・録画面接ツールは、特に一次選考の効率化に大きく貢献するツールです。
これは、企業が事前に設定した質問に対して、候補者がスマートフォンやPCを使い、自分の都合の良い時間に回答を動画で撮影・提出するものです。
採用担当者は、時間や場所の制約なく、候補者の自己PR動画を視聴して合否を判断できます。
これにより、膨大な数の応募者をスクリーニングする手間と時間を大幅に削減できます。
また、動画であれば、候補者の話し方や表情、雰囲気といった、書類だけでは分からない情報を得られるというメリットもあります。
リアルタイムの面接とは異なり、候補者がじっくり考えて回答できる点も特徴です。
よくあるご質問
Q1.オンライン面接と対面面接は、どちらを優先すべきですか?
A1.企業の採用方針や募集職種、候補者の状況によって最適な方法は異なります。
双方のメリットを活かした「ハイブリッド型」が有効です。
例えば、遠方の候補者や一次選考はオンラインで効率的に行い、最終選考や重要な局面では対面で実施し、相互理解を深めるという使い分けが一般的です。
Q2.通信トラブルで面接が中断した場合、候補者の評価はどうなりますか?
A2.通信トラブルは候補者の責任ではないため、それによって評価が不利になることがないよう配慮が必要です。
事前に「トラブル発生時は日程を再調整します」と伝えておくことで、候補者の不安を和らげることができます。
公平性を保つためにも、トラブル時の対応ルールを社内で決めておきましょう。
Q3.オンライン面接で候補者がカンペを見ているのを防ぐ方法はありますか?
A3.カンペの利用を完全に防ぐことは困難です。
しかし、用意した文章を読むだけでは答えられないような、深掘りする質問や対話形式の質問を増やすことで、候補者自身の思考力や対応力を見極めることができます。
「なぜそう考えたのですか?」「具体的にはどのような行動をしましたか?」といった質問が有効です。
Q4.オンライン採用で内定辞退を減らすにはどうすればよいですか?
A4.候補者の企業理解を深め、入社意欲を高めるための工夫が重要です。
オンラインでの社員座談会を企画して気軽に質問できる場を設けたり、オフィスツアー動画で職場の雰囲気を伝えたりすることが効果的です。
また、内定後も定期的にコミュニケーションを取り、候補者の不安を解消していくことが内定辞退の防止につながります。
Q5.どのツールを選べばいいか分かりません。
A5.まずは、ZoomやGoogleMeetなど無料で利用できるWeb会議システムから試してみるのがおすすめです。
採用規模が大きくなり、応募者管理に課題を感じるようになったら採用管理システム(ATS)の導入を、一次選考の効率化を図りたい場合は動画面接ツールの導入を検討するなど、自社の課題やフェーズに合わせて段階的にツールを導入していくと良いでしょう。
まとめ
オンライン採用は、居住地を問わず優秀な人材にアプローチできる点や、コスト削減、選考の効率化など多くの利点を持つ採用手法です。
その一方で、候補者の人柄が把握しにくい、企業の魅力が伝わりづらいといった課題も存在します。
オンライン採用を成功させるには、こうした特性を十分に理解した上で、自社の目的に合わせてオンライン化の範囲を定め、評価基準の見直しやツールの準備、面接官のトレーニングといった入念な準備を行うことが不可欠です。
対面での選考の良さも取り入れながら、自社にとって最適な採用の形を構築していく必要があります。
オンライン採用で重要なのは、限られた画面の中で、どれだけ自社の魅力を伝えられるか。
Piicでは、オンライン面接や説明会でも使いやすい、採用ピッチ資料を制作しています。
スライド形式で見やすく、候補者との対話の中で
「どんな会社か」「どんな人が働いているか」「どんな成長ができるか」を自然に伝えられます。
ZoomやTeamsなどのオンラインツールにそのまま投影できるため、
資料ひとつで“伝わる採用”を実現できます。








