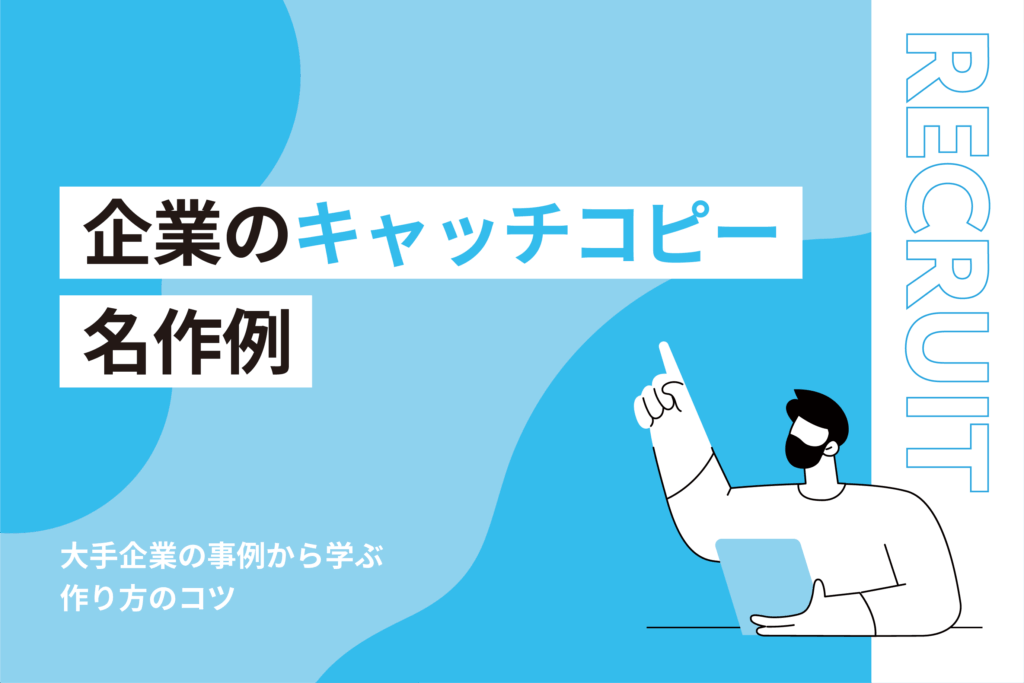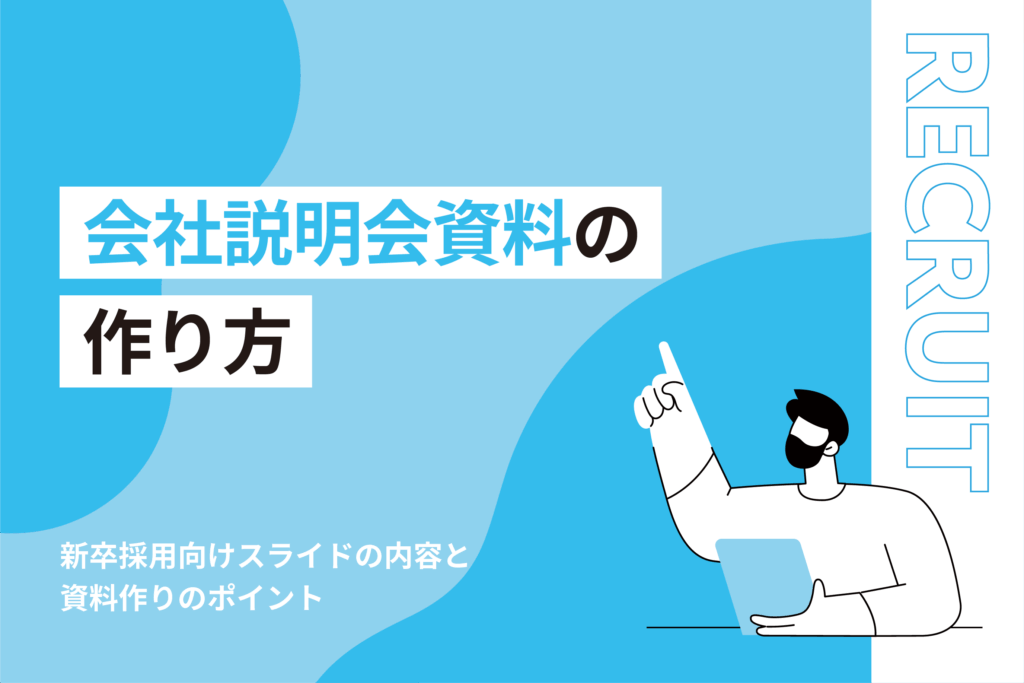
新卒採用における会社説明会は、学生が企業への理解を深め、入社意欲を高める重要な機会です。
その成否を大きく左右するのが、説明会資料(スライド)の質です。分かりやすく魅力的な資料作りは、学生の心を掴むための第一歩と言えるでしょう。
この記事では、学生に響く会社説明会資料の構成例から、スライド作成の具体的なコツ、プレゼンテーションのポイントまで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。
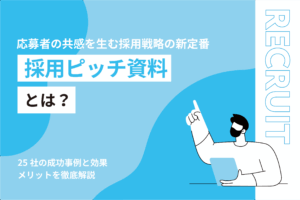
Index
-
会社説明会で参加者の心を掴む資料が重要な理由
-
企業の魅力を視覚情報で効果的にアピールする
-
学生の手元に残り後から見返してもらえる
-
説明する情報の質を均一に保ち誤解を防ぐ
-
会社説明会で学生が本当に知りたいと思っていること
-
【構成例】学生の興味を引く会社説明会スライド9つの項目
-
1. 会社概要|事業内容を分かりやすく紹介する
-
2. 企業理念・ビジョン|会社の目指す未来を語る
-
3. 事業内容|具体的なビジネスモデルを図で示す
-
4. 仕事内容|入社後の働き方がイメージできる具体例を盛り込む
-
5. キャリアパス|社員の成長モデルや研修制度を紹介する
-
6. 社風・文化|職場の雰囲気が伝わる写真や社員インタビューを載せる
-
7. 募集要項|求める人物像を明確に伝える
-
8. 待遇・福利厚生|安心して働ける環境を提示する
-
9. 選考フロー|今後のスケジュールを具体的に案内する
-
学生に刺さる会社説明会資料を作成する6つのコツ
-
1スライド1メッセージを徹底し情報を詰め込みすぎない
-
文字量を減らして図やグラフで視覚的に分かりやすくする
-
スライド全体でデザインやフォントのトンマナを統一する
-
会社のリアルな雰囲気が伝わる写真や動画を活用する
-
ここでしか聞けない限定的な情報を盛り込み特別感を出す
-
学生がメモを取りやすいようにスライドに余白を設ける
-
資料の効果を最大化するプレゼンテーションのポイント
-
若手社員が登壇し学生が親近感を持てるようにする
-
専門用語を避け誰にでも理解できる平易な言葉で話す
-
資料をただ読み上げるのではなく体験談を交えて説明する
-
質疑応答の時間を十分に確保し学生の疑問を解消する
-
会社説明会資料の作成を効率化する方法
-
デザイン性の高いテンプレートを活用して作成時間を短縮する
-
クオリティを重視するなら資料作成の代行サービスを検討する
-
よくあるご質問
-
Q1:会社説明会資料を作成する際に、特に意識すべきポイントは何ですか?
-
Q2:資料の情報量を調整する際のコツはありますか?
-
Q3:資料作成の効率化を図るには、どのような方法がありますか?
-
Q4:学生に会社の雰囲気を伝えるにはどうすれば良いですか?
-
Q5:説明会での質疑応答の時間はどのように活用すべきですか?
-
まとめ
会社説明会で参加者の心を掴む資料が重要な理由

会社説明会で配布・投影する資料は、単なる補足情報ではありません。
企業の第一印象を決定づけ、学生の志望度を大きく左右する重要な役割を担っています。
企業説明会において、視覚的に分かりやすく整理された資料を用意することで、口頭での説明だけでは伝わりきらない企業の魅力を効果的に伝え、学生の深い企業理解を促すことができます。
質の高い資料は、採用活動の成功に直結する重要なツールなのです。
企業の魅力を視覚情報で効果的にアピールする
口頭での説明だけでは、事業内容の面白さや社風といった抽象的な魅力を伝えるのには限界があります。
写真や動画、グラフ、イラストといった視覚情報を活用することで、学生は直感的に企業の姿を理解できるようになります。
例えば、活気あるオフィスの写真一枚で、文章で長々と説明するよりも雄弁に職場の雰囲気を伝えられます。
洗練されたデザインのスライドは、企業の先進性や信頼性を印象付け、ブランドイメージの向上にも寄与します。
視覚的な訴求力を高めることで、言葉だけでは伝えきれない企業の魅力を深く、そして正確に学生の記憶に刻み込むことが可能になります。
学生の手元に残り後から見返してもらえる
会社説明会に参加した学生は、一度に多くの企業情報をインプットするため、時間が経つと内容を忘れてしまうことも少なくありません。
しかし、説明会で用いた資料を配布資料として渡したり、後日オンラインで公開したりすることで、学生は帰宅後や選考が進む過程で何度も内容を見返すことができます。
手元に残る資料は、企業研究を深めるための重要な手がかりとなり、他社と比較検討する際の判断材料にもなります。
分かりやすくまとめられた資料は、学生の企業理解を助け、長期的に志望度を維持・向上させる効果が期待できるのです。
説明する情報の質を均一に保ち誤解を防ぐ
複数の担当者が各地で会社説明会を実施する場合、担当者ごとの話術や知識量によって、学生に伝わる情報にばらつきが生じるリスクがあります。
しっかりと作り込まれた資料を共通の土台として使用することで、どの説明会に参加しても学生に伝えるべき内容の質と量を均一に保つことができます。これにより、重要な情報が伝え漏れたり、担当者の解釈によって内容が異なったりする事態を防ぎます。
正確で一貫性のある情報を提供することは、学生の正しい企業理解を促し、入社後のミスマッチを防ぐ上でも極めて重要です。
会社説明会で学生が本当に知りたいと思っていること

学生が会社説明会で求めているのは、企業のウェブサイトに載っているような表面的な情報だけではありません。
彼らが本当に知りたいのは、入社後に自分がどのように働き、成長できるのかというリアルな情報です。具体的な仕事内容やキャリアパス、給与や福利厚生といった待遇面はもちろん、職場の人間関係や社風といった、実際に働いてみないと分からない部分に関心を持っています。
これらの学生の知りたい内容に寄り添い、資料に盛り込むことが満足度の高い説明会につながります。
【構成例】学生の興味を引く会社説明会スライド9つの項目

学生を惹きつけ、企業の魅力を最大限に伝えるためには、スライドの構成が非常に重要です。
話の流れを意識し、学生が知りたい情報を適切な順序で提供することで、理解度と興味を深めることができます。
ここでは、会社説明会のスライドで盛り込むべき9つの項目を、具体的なサンプル例として紹介します。
1. 会社概要
2. 企業理念・ビジョン
3. 事業内容
4. 仕事内容
5. キャリアパス
6. 社風・文化
7. 募集要項
8. 待遇・福利厚生
9. 選考フロー
この構成を基本とすることで、伝えたいメッセージが整理され、説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。
1. 会社概要|事業内容を分かりやすく紹介する
最初のスライドでは、企業の基本的なプロフィールを紹介します。
社名、設立年、所在地、代表者名、従業員数、資本金といった基本情報に加え、何をしている会社なのかを学生が直感的に理解できるよう、事業内容を簡潔にまとめます。
特に、学生にとって馴染みの薄いBtoB企業の場合は、社会の中で自社の製品やサービスがどのように役立っているのかを、身近な例を挙げて説明すると良いでしょう。
このスライドで、企業の全体像を掴んでもらうことが目的です。
長々と説明するのではなく、要点を絞って分かりやすく示すことが求められます。
2. 企業理念・ビジョン|会社の目指す未来を語る
企業理念やビジョンは、その会社が何のために存在し、社会に対してどのような価値を提供しようとしているのかを示す、いわば会社の「魂」です。
学生は、その企業の価値観や目指す未来に共感できるかどうかを見ています。
このスライドでは、ただ理念の文言を並べるだけでなく、その言葉が生まれた背景にある創業者の想いや、具体的なエピソードを交えて語ることで、より深く学生の心に響きます。
自社が未来に向けてどのような挑戦をしようとしているのかを情熱的に伝えることで、学生の共感を呼び起こし、一緒に働きたいという気持ちを醸成します。
3. 事業内容|具体的なビジネスモデルを図で示す
事業内容のスライドでは、会社がどのようにして利益を生み出しているのか、具体的なビジネスモデルを分かりやすく解説します。
「誰に(顧客)」「何を(製品・サービス)」「どのように(提供方法)」提供しているのかを明確に示しましょう。
特に、複数の事業を展開している場合は、それぞれの事業の関係性や収益の柱となっている事業などを図やイラストを用いて視覚的に表現すると、学生の理解が深まります。
業界内での立ち位置や競合と比較した際の強みなどを客観的なデータと共に示すことで、事業の安定性や将来性をアピールできます。
4. 仕事内容|入社後の働き方がイメージできる具体例を盛り込む
学生が最も知りたい情報の一つが、入社後にどのような仕事をするのかという点です。
このスライドでは、募集する職種ごとに具体的な業務内容を紹介します。
一日のスケジュールの例や、これまで手掛けたプロジェクト事例などを盛り込むと、学生は自分が働く姿をより鮮明にイメージできます。
特に、若手社員がどのような役割を担い、どのような裁量権を持って活躍しているのかを具体的に示すと効果的です。
仕事のやりがいだけでなく、大変な点や乗り越えるべき壁についても触れることで、誠実な印象を与え、入社後のミスマッチを防ぎます。
5. キャリアパス|社員の成長モデルや研修制度を紹介する
学生は入社後の自身の成長に関しても強い関心を持っています。
このスライドでは、新入社員研修から始まる一連の教育・研修制度について具体的に説明し、会社が社員の成長をどのようにサポートしていくのかを示します。
また、入社後、社員がどのようなステップを経てキャリアアップしていくのか、複数のモデルケースを提示すると良いでしょう。
例えば、「入社5年目でリーダーに」「専門職として技術を追求する道」など、多様なキャリアの可能性を示すことで、学生は自身の将来像を描きやすくなります。
長期的な視点で成長できる環境があることをアピールします。
6. 社風・文化|職場の雰囲気が伝わる写真や社員インタビューを載せる
給与や仕事内容と同じくらい、学生が重視するのが社風です。
自分に合った雰囲気の会社で働きたいと考える学生は少なくありません。
このスライドでは、言葉で説明するだけでなく、オフィスで働く社員の自然な様子の写真や、休憩中の談笑風景などを多く使用し、リアルな職場の雰囲気を伝えます。
社員インタビューの動画を挿入したり、座談会形式で複数の社員に登場してもらったりするのも効果的です。
部活動や社内イベントなど、業務外での交流の様子を紹介することで、企業の持つ文化や人柄を多角的に見せることができます。
7. 募集要項|求める人物像を明確に伝える
募集要項のスライドでは、募集職種、採用予定人数、勤務地、応募資格といった事務的な情報を正確に伝えます。
それに加えて、企業がどのような資質や価値観を持った人材を求めているのか、「求める人物像」を具体的に言語化することが重要です。「コミュニケーション能力」といった曖昧な言葉ではなく、「多様な意見を持つメンバーと協力し、一つの目標に向かって粘り強く取り組める人」のように、自社の事業や社風と関連付けて説明することで、学生は何をアピールすればよいのかが明確になり、企業と学生双方のミスマッチを防ぎます。
8. 待遇・福利厚生|安心して働ける環境を提示する
給与、賞与、昇給、休日休暇、勤務時間といった待遇面は、学生が企業を選ぶ上で非常に重要な判断基準となります。
これらの情報を曖昧にせず、スライドで明確に提示することで、学生に安心感と信頼感を与えます。
また、住宅手当や社員食堂、資格取得支援制度、育児・介護休業制度といった、法定以上の福利厚生制度があれば、積極的にアピールしましょう。
社員の働きやすさやプライベートを大切にする企業の姿勢を示すことは、他社との差別化につながり、学生にとって大きな魅力となります。
9. 選考フロー|今後のスケジュールを具体的に案内する
説明会の最後には、今後の選考プロセスについて具体的に案内します。エントリーシートの提出方法と締切日、Webテストの有無、面接の回数と形式(個人・集団・オンラインなど)、内々定までの大まかなスケジュールを時系列で分かりやすく示しましょう。
これにより、学生は今後の就職活動の見通しを立てやすくなります。
また、選考でどのような点を見ているのか、面接でどのようなことを聞きたいのかといったヒントを少し伝えることで、学生は準備をしやすくなり、企業への志望度も高まります。
次のアクションを明確に促す重要なスライドです。
学生に刺さる会社説明会資料を作成する6つのコツ

せっかく良い内容を盛り込んでも、スライドの見せ方が悪ければ学生の心には響きません。
情報を効果的に伝え、記憶に残してもらうためには、資料作成の段階でいくつかのポイントを押さえる必要があります。
ここでは、学生の興味を引きつけ、理解を促進させるための具体的な資料作成のコツを以下6つ紹介します。
・1スライド1メッセージを徹底し情報を詰め込みすぎない
・文字量を減らして図やグラフで視覚的に分かりやすくする
・スライド全体でデザインやフォントのトンマナを統一する
・会社のリアルな雰囲気が伝わる写真や動画を活用する
・ここでしか聞けない限定的な情報を盛り込み特別感を出す
・学生がメモを取りやすいようにスライドに余白を設ける
これらのテクニックを活用することで、説明会の効果を最大化できるでしょう。
次のセクションから詳しくご説明していきますのでご覧ください。
1スライド1メッセージを徹底し情報を詰め込みすぎない
一枚のスライドに多くの情報を詰め込んでしまうと、結局何が一番重要なのかが伝わりにくくなります。
聞き手の集中力を維持させるためにも、「1スライドにつき伝えたいメッセージは1つ」という原則を徹底しましょう。
スライドには、そのメッセージを象徴するキーワードや短いフレーズ、そしてそれを補足する図やグラフだけを配置します。
詳細な説明は口頭で行うか、配布資料に記載するとメリハリが生まれます。
情報を絞ることで、かえって伝えたいことが明確になり、学生の記憶に残りやすくなるのです。
文字量を減らして図やグラフで視覚的に分かりやすくする
文字ばかりのスライドは、見るだけで退屈な印象を与えてしまいがちです。
人間は文字情報よりも視覚情報の方が記憶に残りやすいと言われています。
そのため、文章で説明するのではなく、できるだけ図やグラフ、アイコンなどを用いて情報をビジュアル化する工夫が求められます。
例えば、企業の成長性を示すには売上推移の棒グラフを、複雑なビジネスモデルはイラストを交えた相関図で示すと、直感的に理解を促せます。
洗練されたデザインは、情報の伝達効率を高めるだけでなく、企業のイメージアップにもつながります。
スライド全体でデザインやフォントのトンマナを統一する
スライドごとに色使いやフォント、レイアウトが異なると、全体的にまとまりがなく、見づらい資料になってしまいます。
資料作成を始める前に、デザインのトーン&マナー(トンマナ)を決め、最後までそれを守ることが重要です。
企業のロゴに使われているコーポレートカラーを基本の色とし、アクセントカラーを含めて3〜4色程度に絞ると統一感が出ます。
フォントも、読みやすいゴシック体を基本とし、見出しと本文で種類を統一しましょう。
一貫性のあるデザインは、内容の理解を助けるだけでなく、企業の信頼性や専門性を演出します。
会社のリアルな雰囲気が伝わる写真や動画を活用する
学生が知りたいのは、加工された綺麗なイメージではなく、ありのままの会社の姿です。
そのため、インターネット上で手に入るようなフリー素材の画像ではなく、実際に自社で撮影した写真や動画を積極的に活用しましょう。
社員が活き活きと働いている様子や、チームでディスカッションしている場面、社内イベントで楽しんでいる姿など、リアルな写真を使うことで、会社の雰囲気が伝わり、学生は親近感を覚えます。
このひと手間が、他社との差別化を図る上で重要なポイントとなります。
ここでしか聞けない限定的な情報を盛り込み特別感を出す
ウェブサイトや採用パンフレットを見れば分かる情報ばかりでは、学生は説明会に参加した価値を感じにくいものです。
説明会に参加してくれた学生への特典として、ここでしか聞けない限定的な情報を盛り込むことで、満足度と特別感を高めることができます。
例えば、現場で働く社員だからこそ話せる仕事の失敗談や成功秘話、現在開発中の新製品に関する少しだけ踏み込んだ情報などがそれに当たります。
こうした限定情報は、学生の知的好奇心を刺激し、企業への興味をさらに深める重要なポイントです。
学生がメモを取りやすいようにスライドに余白を設ける
スライドの上下左右に十分な余白を設けることで、圧迫感がなくなり、洗練された見やすいレイアウトになります。情報が整理されている印象を与え、聞き手は内容に集中しやすくなります。
また、学生が説明を聞きながらメモを取ることを想定し、配布資料には書き込みができるスペースを確保しておくと親切です。
スライドのデザイン段階から余白を意識することは、単なる見た目の問題だけでなく、聞き手の理解を助けるという機能的な役割も果たします。細やかな配慮が、学生のエンゲージメントを高めます。
資料の効果を最大化するプレゼンテーションのポイント

優れた会社説明会資料を作成しても、その魅力を伝えきれなければ意味がありません。
プレゼンテーションは、資料に命を吹き込み、学生の感情に訴えかけるための重要なプロセスです。
ここでは、資料の効果を最大限に引き出し、学生の入社意欲を掻き立てるためのプレゼンテーションのポイントを解説します。
話し方や立ち居振る舞いを少し工夫するだけで、学生に与える印象は大きく変わります。
若手社員が登壇し学生が親近感を持てるようにする
人事担当者による説明に加えて、学生と年齢の近い若手社員が登壇する時間を設けると、企業説明会全体の効果が高まります。
学生は、自分の数年後の姿を若手社員に重ね合わせることで、入社後のキャリアをより具体的にイメージできます。
仕事のやりがいや苦労、就職活動時の体験談などを自身の言葉で語ってもらうことで、話にリアリティが生まれ、学生は親近感を抱きやすくなります。
ベテラン社員や役員とは異なる視点からの話は、企業を多角的に理解する上で貴重な情報源となります。
専門用語を避け誰にでも理解できる平易な言葉で話す
企業説明会には、業界や自社の事業について予備知識のない学生も多数参加します。
普段社内で使っている専門用語や業界用語、略語は、学生にとっては理解を妨げる壁になりかねません。
プレゼンターは、「初めて聞く人」を意識し、誰にでも分かる平易な言葉を選んで話すよう心がける必要があります。
どうしても専門用語を使わなければならない場合は、その都度意味を丁寧に解説する配慮が求められます。
分かりやすい言葉で語りかける姿勢は、企業の誠実さとして学生に伝わります。
資料をただ読み上げるのではなく体験談を交えて説明する
スクリーンに映し出されたスライドの文章をそのまま読み上げるだけのプレゼンテーションは、学生を退屈させてしまいます。
資料はあくまで話の骨子や視覚的な補助と捉え、自身の言葉で語りかけることが重要です。
特に、自身の体験談を交えながら説明することで、話に具体性と熱がこもり、学生を惹きつけます。
仕事で直面した困難をどう乗り越えたか、プロジェクトが成功した時の喜びなど、個人的なエピソードを語ることで、単なる情報伝達を超えた、感情的な共感を生み出す企業説明会になります。
質疑応答の時間を十分に確保し学生の疑問を解消する
プレゼンテーションは一方的な情報提供で終わらせるべきではありません。
学生が抱いた疑問や不安をその場で解消できるよう、質疑応答の時間を十分に確保することが不可欠です。
どんな質問にも真摯に、そして正直に答える姿勢を見せることで、企業への信頼感が高まります。
もし学生から質問が出にくい雰囲気であれば、「よく聞かれる質問ですが…」と前置きして、給与や残業といった聞きにくいテーマについて自ら切り出すのも一つの手です。
企業説明会を通じて学生との双方向のコミュニケーションを図ることが、満足度の向上につながります。
会社説明会資料の作成を効率化する方法
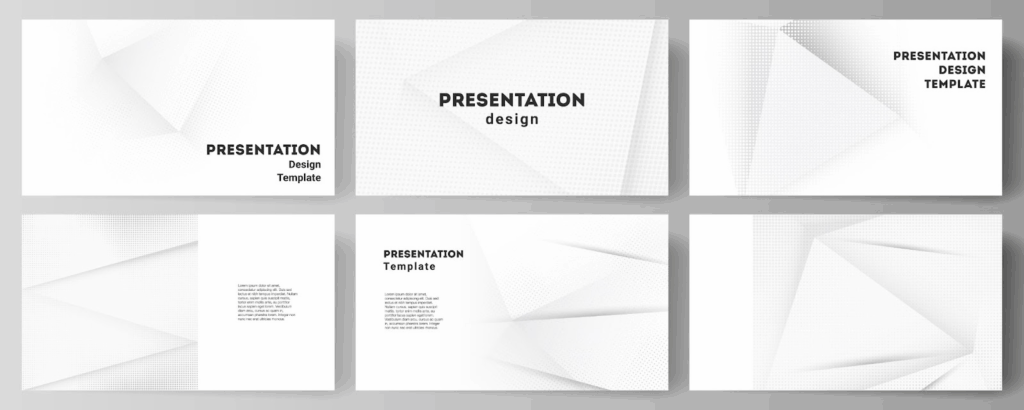
採用担当者は、候補者との面接や内定者フォローなど、多岐にわたる業務を抱えています。
そのため、会社説明会の資料作成に多くの時間を割くのは難しいのが実情でしょう。
しかし、便利なツールやサービスを活用すれば、クオリティを維持しつつ、作成時間を大幅に短縮することが可能です。
ここでは、忙しい担当者でも効率的に質の高い資料を作成するための具体的な方法を2つ紹介します。
デザイン性の高いテンプレートを活用して作成時間を短縮する
ゼロからスライドデザインを考えるのは時間と手間がかかります。そこで有効なのが、デザインテンプレートの活用です。
PowerPointなどのプレゼンテーションソフトに内蔵されているもののほか、ウェブ上には無料で利用できる高品質なテンプレートが数多く公開されています。
これらのテンプレートを土台にすれば、デザインの専門知識がなくても、見た目が整った統一感のある資料を短時間で作成可能です。自社のロゴを配置したり、コーポレートカラーに合わせて色を調整したりするだけで、オリジナリティのある資料に仕上げることができます。
クオリティを重視するなら資料作成の代行サービスを検討する
自社だけでは学生に響く資料が作れない、他のコア業務に集中したいといった場合には、プロの力を借りるのも賢明な選択です。
資料作成の代行サービスに依頼すれば、採用市場を熟知した専門家が、構成の立案からデザインまで一貫して手掛けてくれます。
費用は発生しますが、自社の魅力を最大限に引き出すための客観的な視点や、効果的な見せ方のノウハウを提供してもらえるメリットは大きいでしょう。
結果的に、資料作成にかかる工数を削減し、より訴求力の高い資料を手に入れることができます。
よくあるご質問

Q1:会社説明会資料を作成する際に、特に意識すべきポイントは何ですか?
A1:学生が本当に知りたい情報を盛り込むことが重要です。事業内容、仕事の具体例、キャリアパス、社風など、入社後のイメージが湧くようなリアルな情報提供を心がけましょう。
Q2:資料の情報量を調整する際のコツはありますか?
A2:1スライド1メッセージを徹底し、情報を詰め込みすぎないことが大切です。文字量を減らし、図やグラフを多用して視覚的に分かりやすく表現することで、学生の理解を促進できます。
Q3:資料作成の効率化を図るには、どのような方法がありますか?
A3:デザイン性の高いテンプレートを活用することで、作成時間を短縮できます。また、より高品質な資料を目指すのであれば、資料作成の代行サービスを利用することも有効な手段です。
Q4:学生に会社の雰囲気を伝えるにはどうすれば良いですか?
A4:会社のリアルな雰囲気が伝わる写真や動画を積極的に活用しましょう。社員が活き活きと働く様子や社内イベントの風景などを盛り込むことで、親近感を持ってもらえます。
Q5:説明会での質疑応答の時間はどのように活用すべきですか?
A5:学生の疑問や不安を解消するために、質疑応答の時間を十分に確保することが重要です。どんな質問にも真摯に答える姿勢を見せ、学生との双方向のコミュニケーションを図りましょう。
まとめ
会社説明会の資料は、学生に対して企業の第一印象を形成し、その後の選考に進んでもらうための動機付けとなる、採用活動における極めて重要なツールです。
学生が本当に知りたいと思っているのは何かを追求し、事業内容や仕事の魅力、社風といった情報を分かりやすく伝える必要があります。
今回紹介した構成例や作成のコツ、プレゼンテーションのポイントを実践することで、学生の心を掴み、採用成功へと繋がる説明会を実現することが可能です。
効果的な資料作りを通じて、自社の未来を担う優秀な人材との出会いを創出してください。
学生に選ばれる説明会は、単なる情報提供ではなく「共感」を生む場です。
Piicの採用ピッチ資料は、企業の想いをストーリーとして可視化し、候補者の心を動かすクリエイティブ。説明会をより印象的にし、次のステップへ導きます。