
企業の成長に不可欠な採用活動ですが、その手法は多様化し、複雑になっています。
人事担当者として、どの手法が自社に最適かを見極めるのは簡単ではありません。
この記事では、最新の採用トレンドを交えながら、主要な採用手法のメリット・デメリットを比較し、自社の課題解決につながる最適な手法の選び方を解説します。
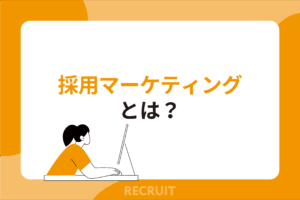
Index
-
【一覧比較】主な採用手法9選の特徴とメリット・デメリット
-
人材紹介サービスでミスマッチを防ぐ
-
求人サイトで多くの求職者にアプローチする
-
ダイレクトリクルーティングで欲しい人材を直接探す
-
リファラル採用で社員の人脈を活用する
-
ソーシャルリクルーティングで企業の魅力を発信する
-
自社採用サイトで応募者の意欲を高める
-
転職フェア・合同説明会で直接コミュニケーションをとる
-
アルムナイ採用で即戦力となる元社員を呼び戻す
-
ヘッドハンティングでハイスキル人材を獲得する
-
【2025年最新】知っておきたい採用市場のトレンド
-
新卒採用で注目されるオンライン化と個別アプローチ
-
中途採用で主流化する「攻め」の採用戦略
-
失敗しない!自社に合った採用手法を選ぶ3つのポイント
-
ポイント1:採用における自社の課題を洗い出す
-
ポイント2:求める人物像(ペルソナ)を明確に描く
-
ポイント3:複数の手法を組み合わせて効果を最大化する
-
まとめ
【一覧比較】主な採用手法9選の特徴とメリット・デメリット

採用手法には数多くの種類が存在し、それぞれに異なる特徴があります。
自社の採用ターゲットや予算、課題に合わせて最適な手法を選択するためには、まず各手法の概要を一覧で把握し、メリット・デメリットを比較検討することが重要です。
ここでは、以下代表的な9つの採用手法を取り上げ、その特性を詳しく見ていきます。
・人材紹介サービス
・求人サイト
・ダイレクトリクルーティング
・リファラル採用
・ソーシャルリクルーティング
・自社採用サイト
・転職フェア・合同説明会
・アルムナイ採用
・ヘッドハンティング
人材紹介サービスでミスマッチを防ぐ
人材紹介サービスとは、企業と求職者の間にエージェントが入り、マッチングを支援するサービスです。
エージェントが企業の求める人物像をヒアリングし、登録者の中から適した人材を推薦してくれるため、採用工数を大幅に削減できます。
また、非公開求人として募集できるため、事業戦略に関わる重要なポジションの採用にも向いています。
成功報酬型が一般的で、採用が決定するまで費用が発生しないケースが多いですが、採用決定時の手数料が年収の30〜35%程度と比較的高額になる点がデメリットです。
求人サイトで多くの求職者にアプローチする
求人サイトは、幅広い層の求職者に対して自社の求人情報を届けられる代表的な採用手法です。
掲載課金型や応募課金型など、サイトによって料金体系はさまざまで、予算に応じてプランを選べます。
近年では、特定の職種や業界に特化したサイトも増え、働き方の多様化に対応した求人情報も多く見られます。
多くの求職者の目に触れる機会がある一方で、応募者の質がばらつきやすく、多数の応募があった場合は書類選考や連絡対応に多くの工数がかかる可能性があります。
ダイレクトリクルーティングで欲しい人材を直接探す
ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースなどから求める人材を探し出し、直接アプローチする「攻め」の採用手法です。
転職市場には出てきていない潜在層にもアプローチできる点が大きな魅力で、企業が主体となって動くため、採用におけるミスマッチを減らしやすいというメリットもあります。
この手法を採用する場合、候補者の選定からスカウトメールの作成、面談調整まで、人事が一貫して対応する必要があります。
そのため、従来の手法とは異なるノウハウや工数が求められます。
リファラル採用で社員の人脈を活用する
リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう手法です。
社員が自社の文化や業務内容を理解した上で紹介するため、候補者のスキルや人柄の信頼性が高く、入社後の定着率が高い傾向にあります。
また、広告費がかからないため、採用コストを大幅に抑えられる点もメリットです。
この手法を採用する際は、紹介制度の整備や社員への周知徹底が不可欠です。
一方で、人間関係が絡むため不採用時の対応に配慮が必要なことや、人脈に偏りがあると採用できる人材のタイプが限定される可能性があります。
ソーシャルリクルーティングで企業の魅力を発信する
ソーシャルリクルーティングは、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを活用した採用手法です。
企業の日常や文化、社員の様子などを発信することで、求職者に親近感を持ってもらい、企業のファンを増やすことができます。
特に、従来の求人媒体ではアプローチしにくかった若年層との接点を作りやすいのが特徴です。
労働市場の変化に伴い注目される手法ですが、アカウントの継続的な運用やコンテンツ作成に手間がかかるほか、不適切な発信による炎上リスクも考慮しなくてはなりません。
自社採用サイトで応募者の意欲を高める
自社採用サイトは、求人情報だけでなく、企業理念や事業内容、社員インタビューといったコンテンツを自由に掲載できるオウンドメディアです。
求人サイトの限られたフォーマットでは伝えきれない自社の魅力を深く訴求し、候補者の入社意欲を高める効果が期待できます。
応募までのステップをサイト内で完結させることで、スムーズな採用フローを設計可能です。
ただし、サイトを立ち上げるだけでは応募者は集まらないため、SEO対策やWeb広告など、別途集客施策を講じる必要があります。
転職フェア・合同説明会で直接コミュニケーションをとる
転職フェアや合同説明会は、多くの求職者と直接対話できる貴重な機会です。
自社のブースを設けたり、セミナー形式でプレゼンテーションを行ったりすることで、Web上では伝わりにくい企業の雰囲気や事業の魅力を直接伝えられます。
求職者の反応をその場で見ながら、疑問点にすぐ答えられるため、相互理解を深めやすいのがメリットです。
一方で、出展には数十万円から数百万円の費用がかかるほか、当日の運営スタッフの確保や配布資料の準備など、事前の負担が大きい点が挙げられます。
アルムナイ採用で即戦力となる元社員を呼び戻す
アルムナイ採用は、過去に自社で働いていた元社員を再雇用する手法です。
元社員はすでに企業文化や事業内容を理解しているため、入社後のミスマッチが極めて少なく、即戦力として活躍することが期待できます。
他社での経験を積んでいるため、新たな視点やスキルを社内に持ち込んでくれる可能性もあります。
中途採用の有効な選択肢ですが、退職者との良好な関係を維持しておく仕組みづくりが不可欠です。
また、採用できる対象者が限定されるため、この手法だけで採用計画を立てるのは難しいでしょう。
ヘッドハンティングでハイスキル人材を獲得する
ヘッドハンティングは、企業の経営層や幹部候補、高度な専門スキルを持つ人材など、特定のハイスキル人材を獲得するために用いられる手法です。
ヘッドハンターが企業の依頼に基づき、他社で活躍している優秀な人材に直接アプローチします。
転職市場には出てこない層に接触できるため、事業の根幹を担う重要なポジションの採用に適しています。
採用が成功した場合の報酬は高額になることが一般的で、着手金が必要な場合もあります。
また、候補者との交渉が長期化することもあるため、時間的な余裕が必要です。
【2025年最新】知っておきたい採用市場のトレンド

労働人口の減少や働き方の多様化といった社会的な変化を受け、採用市場のトレンドも大きく変わりつつあります。
従来の「待ち」の採用スタイルから、企業が主体的に動く「攻め」のスタイルへの転換が求められています。
ここでは、特に新卒採用と中途採用の領域で注目すべき最新の動向について解説します。
新卒採用で注目されるオンライン化と個別アプローチ
新卒採用の領域では、選考プロセスのオンライン化が完全に定着しました。
説明会や面接をオンラインで実施することで、地方学生との接点を増やし、採用活動の効率化を図る企業が増えています。
一方で、オンラインだけでは学生の個性や意欲を見極めるのが難しいという課題も浮上しています。
そのため、長期インターンシップや個別の社員面談、内定者向けのイベントなどを通じて、学生一人ひとりと深くコミュニケーションを取り、相互理解を深める個別アプローチの重要性が高まっています。
中途採用で主流化する「攻め」の採用戦略
中途採用市場では、人材獲得競争が激化しており、求人サイトに広告を掲載して応募を待つだけでは、優秀な人材の確保が難しくなっています。
そこで主流となりつつあるのが、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用といった「攻め」の採用戦略です。
企業側から積極的に候補者を探し出し、直接アプローチすることで、転職潜在層を含む幅広い人材にリーチします。
中途採用においては、自社の魅力を能動的に発信し、候補者との関係を構築していく姿勢がこれまで以上に求められます。
失敗しない!自社に合った採用手法を選ぶ3つのポイント
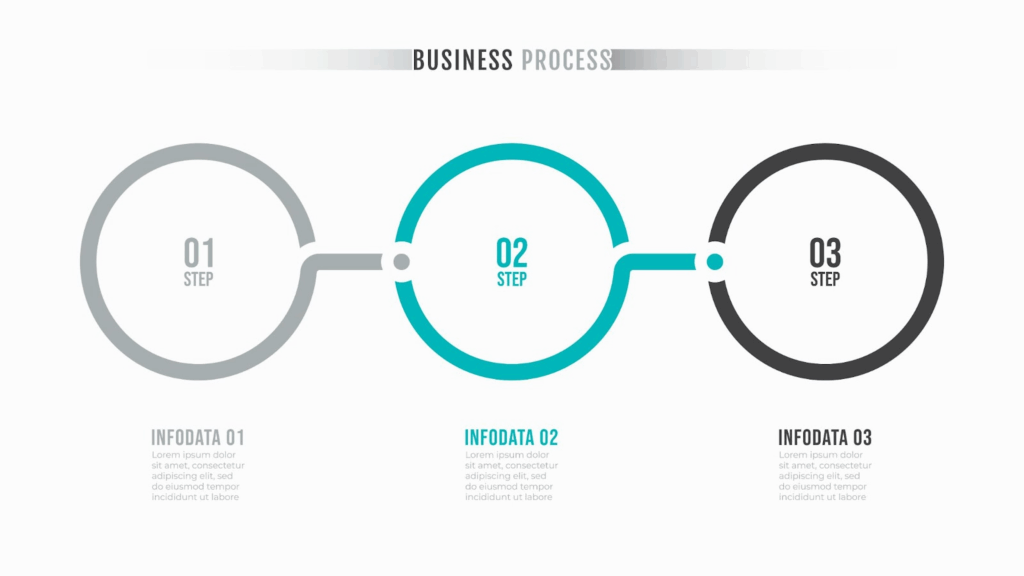
数ある採用手法の中から、自社にとって最適なものを選ぶには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
特に、採用にかけられるリソースが限られている中小企業にとっては、手法の選定が採用活動の成否を大きく左右します。
ここでは、採用手法の選定で失敗しないための3つの重要なポイントを具体的に解説します。
ポイント1:採用における自社の課題を洗い出す
まずは、自社の採用活動が抱える課題を明確にすることがスタート地点です。
「そもそも応募が集まらない」「応募はあるが求める人材と合わない」「内定を出しても辞退されてしまう」など、企業によって課題はさまざまです。
これらの課題を人事部内で正確に把握し、優先順位をつけることで、どの採用手法が課題解決に最も効果的かが見えてきます。
例えば、応募数が少ないのであれば求人サイトへの出稿を強化し、内定辞退が多いのであれば面接プロセスや自社の魅力発信の方法を見直すといった方向性が定まります。
ポイント2:求める人物像(ペルソナ)を明確に描く
次に、どのような人材を採用したいのか、求める人物像(ペルソナ)を具体的に設定します。
単に「コミュニケーション能力が高い人」といった抽象的な表現ではなく、スキルや経験、価値観、行動特性などを細かく定義することが重要です。
例えば、エンジニアを採用する場合、使用言語や開発経験だけでなく、「チーム開発を円滑に進められる協調性」や「新しい技術への探求心」といった具体的な要素まで落とし込みます。
ペルソナが明確であればあるほど、その人物像に響くメッセージを発信でき、アプローチすべき採用手法もおのずと絞られてきます。
ポイント3:複数の手法を組み合わせて効果を最大化する
一つの採用手法に固執するのではなく、複数の手法を組み合わせて「採用ポートフォリオ」を構築することが、採用効果を最大化する鍵です。
例えば、幅広い層にアプローチするために求人サイトを活用しつつ、ピンポイントで欲しい人材にはダイレクトリクルーティングでアプローチするといった組み合わせが考えられます。
各手法のメリット・デメリットを比較し、自社の採用課題やペルソナに合わせて、それぞれの長所を活かせるように組み合わせを検討します。
定期的に各手法の効果を測定し、ポートフォリオを見直していくことも重要です。
まとめ
本記事のまとめとして、採用活動の成功は、自社の現状と課題を正確に把握することから始まります。
多様な採用手法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、最新のトレンドも常に変化しています。
今回紹介した手法の一覧比較や選び方のポイントを参考に、まずは自社の採用課題は何か、本当に求めている人物像はどのような人かを改めて定義してみてください。
その上で、一つの手法に頼るのではなく、複数の手法を戦略的に組み合わせることで、採用目標の達成に近づきます。
自社に最適な採用手法を見つけ、効果的な採用活動を設計することが企業の成長基盤を築きます。
採用の成功は、ただ「人を集める」ことではなく、候補者に自社の魅力を“正しく伝える”ことから始まります。
Piicの採用クリエイティブは、企業の価値観や文化を分かりやすく可視化し、求職者の心に届く形に仕立てます。
採用手法と合わせて「伝え方」まで磨き上げることで、採用成果は大きく変わります。








