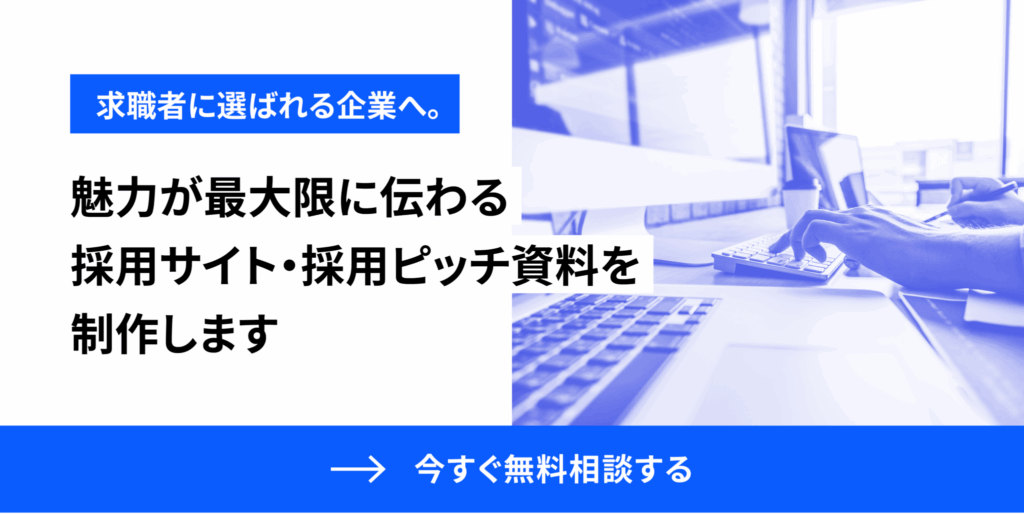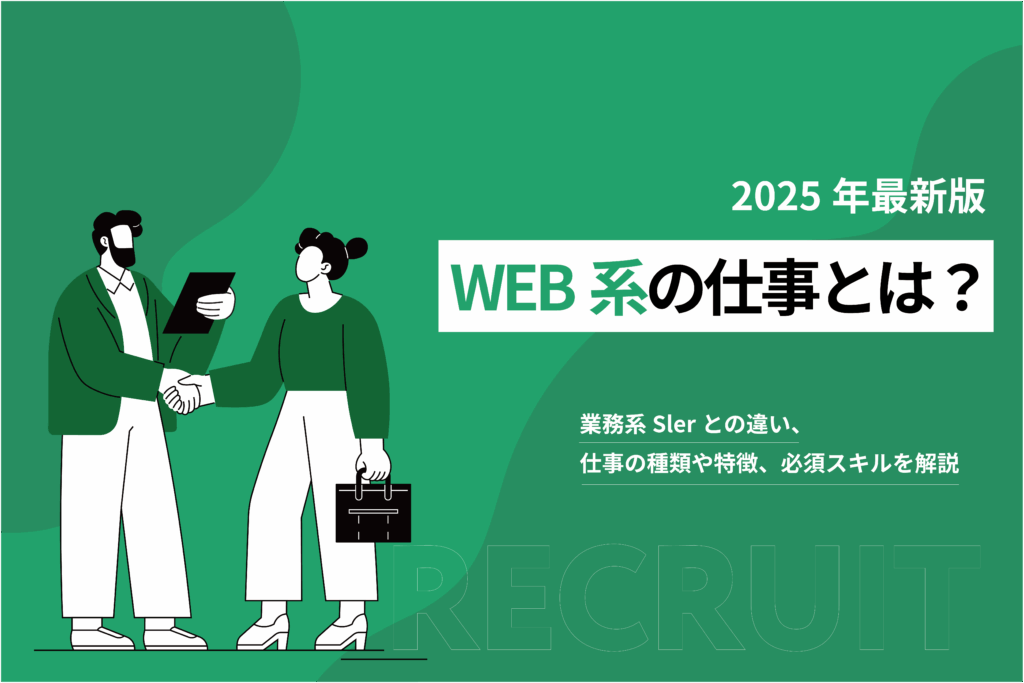
Web系とは、インターネット上で展開されるWebサイトやアプリなどのサービス開発を担うIT分野を指します。
本記事では、IT業界の中でも特に人気の高いWeb系の仕事について、混同されやすい業務系SIerとの違いを比較しながら、その種類や求められるスキルを解説します。
これからWeb系のキャリアを目指す方や、採用を検討しているIT企業の人事担当者にとって、Web系とは何かを理解する一助となる情報を提供します。

Index
-
Web系とは?BtoCの身近なサービス開発を担うIT分野
-
【徹底比較】Web系とSIer(業務系)の主な違い
-
開発対象となるシステムの違い
-
開発手法の違い(アジャイルとウォーターフォール)
-
求められる技術やスキルの違い
-
組織文化や働き方の違い
-
Web系企業の代表的な職種と仕事内容
-
フロントエンドエンジニアの役割
-
バックエンドエンジニアの役割
-
インフラエンジニアの役割
-
Webデザイナーの役割
-
Webディレクターの役割
-
Webマーケターの役割
-
Web系エンジニアに求められる必須スキル
-
プログラミング言語やフレームワークの知識
-
クラウドサービスやサーバーに関する知識
-
新しい技術を自ら学ぶキャッチアップ能力
-
チーム開発を円滑に進めるコミュニケーション能力
-
Web系企業で働くことのメリット
-
ユーザーからの反応を直接感じられる
-
最新の技術に触れる機会が豊富にある
-
比較的自由なスタイルで働きやすい
-
未経験からWeb系エンジニアになるための学習ステップ
-
プログラミングの基礎を学習する
-
ポートフォリオとしてWebサービスを開発する
-
転職エージェントや求人サイトに登録する
-
よくあるご質問
-
Q1: 文系出身の未経験でもWeb系エンジニアになれますか?
-
Q2: SIerからWeb系への転職は可能ですか?
-
Q3: 30代未経験からでも挑戦できますか?
-
Q4: 必要な資格はありますか?
-
Q5: 平均的な年収はどのくらいですか?
-
まとめ
-
Webサイト制作・運用のご相談は Piic へ
Web系とは?BtoCの身近なサービス開発を担うIT分野
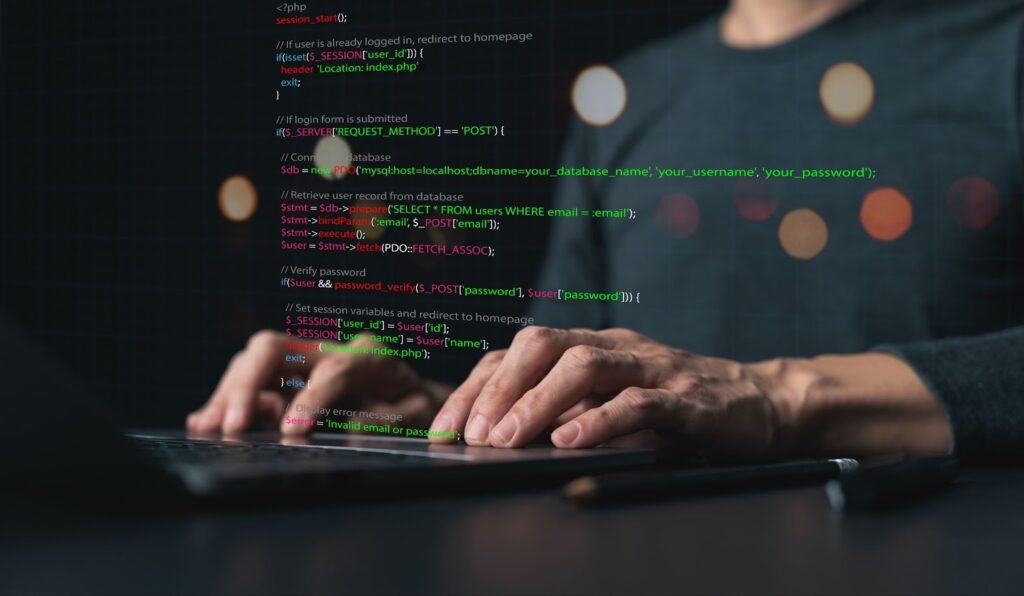
Web系の仕事とは、主に一般消費者向けのWebサービスやスマートフォンアプリなどの開発・運営を担うIT分野のことです。
私たちが日常的に利用するSNS、ECサイト、情報検索サイトといったソフトウェアの多くが該当します。
この分野のIT企業には、新しい技術を積極的に採用するスタートアップやベンチャーが多く、変化のスピードが速いのが特徴です。
そのため、トレンドに敏感で自律的に学習を進められる人が向いていると言えます。
ユーザーの反応を直接感じながら開発を進められる点が人気で、やりがいの大きいIT系の仕事内容です。
【徹底比較】Web系とSIer(業務系)の主な違い

IT業界にはWeb系のほか、顧客企業のシステム開発を請け負うSIer(システムインテグレータ)が存在します。
特に業務系SIerは、企業の基幹システムなどを手掛けるため、Web系とは多くの点で異なります。
SIerが扱う分野には、オープン系のほか、金融機関で使われる汎用系や、家電製品に組み込まれる組み込み系のシステムなどがあります。
ここでは、開発対象や手法、求められる技術、組織文化といった観点から、Web系と業務系SIerの違いを比較し、それぞれのSEの役割の違いを明らかにします。
開発対象となるシステムの違い
Web系と業務系SIerでは、開発対象となるシステムが大きく異なります。
Web系の企業は、自社で企画・運営するWebサービスや、不特定多数のユーザーが利用するスマートフォン向けのアプリ開発が中心となります。
これに対し、業務系SIerは、特定のクライアント企業から案件を受注し、その企業の業務効率化を目的とした会計システムや生産管理システムといった、業務に特化したシステム開発を担います。
Web系が一般消費者向けのサービスを手掛けるのに対し、SIerは法人顧客の課題解決を目的とした開発を行う点が大きな違いです。
開発手法の違い(アジャイルとウォーターフォール)
開発の進め方にも明確な違いが見られます。
Web系の開発現場では、短期間のサイクルで設計、開発、テストを繰り返しながら機能を追加・改善していく「アジャイル開発」が主流です。
市場のニーズやユーザーの反応に素早く対応するため、仕様変更に柔軟なこの手法が好まれます。
一方、業務系SIerでは、要件定義から設計、実装、テストといった各工程を順番に進めていく「ウォーターフォール開発」が一般的です。
大規模なシステムを計画通りに開発することが求められるため、厳格な工程管理を重視するこの手法が採用される傾向にあります。
求められる技術やスキルの違い
Web系企業では、Ruby、PHP、Pythonといったオープンソースのプログラミング言語や、React、Vue.jsなどの新しいフレームワークが頻繁に利用されます。
技術のトレンドが速く、常に最新の技術を追いかける姿勢が求められるのが特徴です。
一方、業務系SIerでは、JavaやC#、COBOLといった開発言語が使われることが多く、大規模システムを安定稼働させるための堅牢な技術や、金融機関などで長年使われてきた実績のある技術が重視される傾向にあります。
求められる技術スタックが異なるため、エンジニアのスキルセットも大きく分かれます。
組織文化や働き方の違い
組織文化や働き方にも違いがあります。
Web系の企業は、服装が自由でフラットなコミュニケーションを重視するなど、比較的カジュアルな文化を持つ中小企業やベンチャーが多いです。
リモートワークの導入も進んでおり、柔軟な働き方がしやすい環境が整っています。
対照的に、業務系SIerは大手企業やその子会社が多く、スーツ着用が基本であるなど、より伝統的な日本の大企業の文化が色濃く残っている場合があります。
京都など地方にも特色あるWeb系のおすすめ企業は存在し、多様な選択肢があります。
Web系企業の代表的な職種と仕事内容
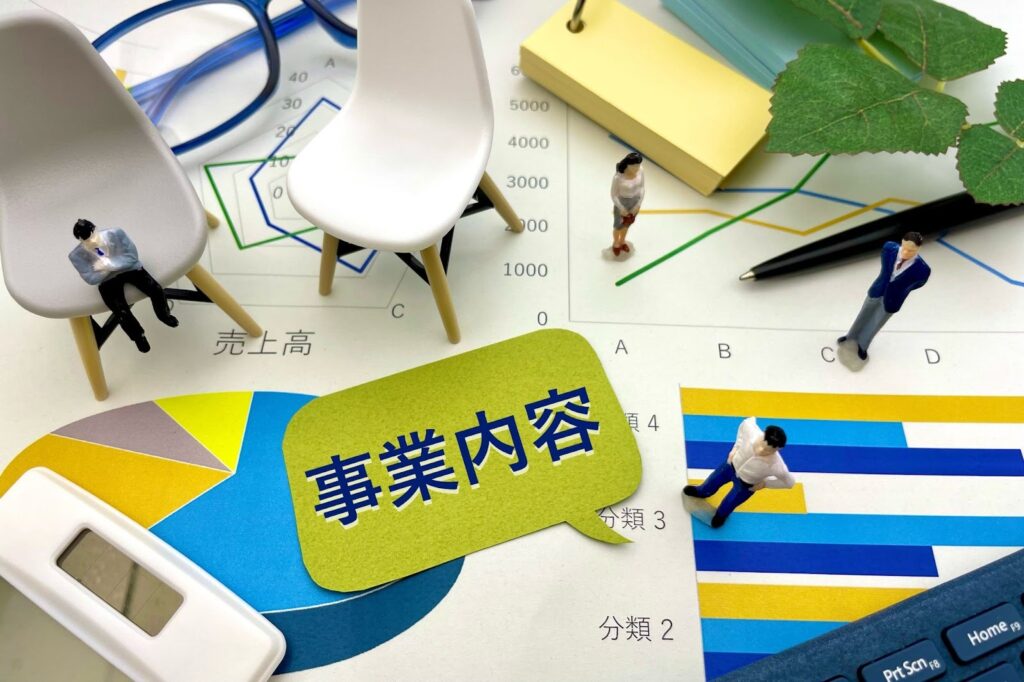
Web系の企業には、多様な職種が存在し、それぞれの専門性を活かしてサービス開発に貢献しています。
一般的に知られるエンジニアやプログラマーといった技術職以外にも、デザイナーやディレクターなど、様々なクリエイターや管理系の職業が活躍しています。
ITエンジニアとして経験を積んだ後のキャリアパスも多彩で、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントに進む道もあれば、技術を極めるスペシャリストとして活躍し続ける道もあります。
ここでは、代表的な職種とその仕事内容を紹介します。
フロントエンドエンジニアの役割
フロントエンドエンジニアは、ユーザーがWebサイトやアプリケーションで直接触れる部分、すなわちフロント(UI:ユーザーインターフェース)の実装を担当します。
Webデザイナーが作成したデザイン案に基づき、HTML、CSS、JavaScriptといった技術を駆使して、Webブラウザ上で視覚的に再現します。
近年では、ReactやVue.jsといったJavaScriptのフレームワークを用いることが多く、ユーザーにとって快適な操作性や、アニメーションなどの動的な表現を実現する重要な役割を担っています。
バックエンドエンジニアの役割
バックエンドエンジニアは、ユーザーの目には見えないサーバーサイドのシステム開発を担当します。
Webサービスの裏側で動作するプログラムや、データベースの設計・構築・運用が主な業務です。
具体的には、ユーザー情報の登録やログイン認証、商品の決済処理、データの保存や更新といった機能の実装を行います。
PHP、Ruby、Python、Goなどのプログラミング言語が用いられ、フロントエンドから送られてきたリクエストに応じて適切な処理を行い、結果を返すというサーバーサイドの仕組みを支えています。
インフラエンジニアの役割
インフラエンジニアは、Webサービスが24時間365日安定して稼働するための土台となるITインフラの設計、構築、運用保守を担います。
サーバーやネットワーク、OS、ミドルウェアなどの構成を考え、サービスのパフォーマンスやセキュリティを担保する重要な職務です。
近年では、物理的なサーバーを自社で保有するのではなく、AWS(AmazonWebServices)などのクラウドサービスを利用してインフラを構築することが主流となっています。
そのため、クラウドに関する深い知識や運用スキルがインフラエンジニアには不可欠です。
Webデザイナーの役割
Webデザイナーは、Webサイトやアプリの見た目に関する部分全般を制作します。
ユーザーにとっての使いやすさ(UI)や、サービスを利用する上での心地よさ(UX)を考慮しながら、全体のレイアウトや配色、ロゴ、アイコン、アニメーションなどをデザインします。
ただ単に美しいビジュアルを作成するだけでなく、サービスの目的やターゲットユーザーを理解し、ビジネス的な成果につながるデザインを設計する能力が求められます。
コーディング知識を持つデザイナーも多く、エンジニアとの連携も重要な業務の一つです。
Webディレクターの役割
Webディレクターは、Webサイトやアプリなどの制作プロジェクトにおける現場の責任者です。
プロジェクト全体の進捗管理、品質管理、予算管理を行い、エンジニア、デザイナー、Webマーケターといった関係者をまとめ上げ、プロジェクトを成功に導く役割を担います。
クライアントや社内の関連部署との調整役も務め、仕様の決定からリリースまでの全工程に関わります。
Web制作に関する幅広い知識と、高いコミュニケーション能力、マネジメントスキルが求められる職種です。
Webマーケターの役割
Webマーケターは、開発したWebサービスやWebサイトへの集客を担当し、その成果を最大化させる役割を担います。
SEO(検索エンジン最適化)による検索順位の向上、Web広告の運用、SNSを活用した情報発信、コンテンツマーケティングなど、様々な手法を駆使します。
アクセス解析ツールを用いてデータを分析し、ユーザーの行動やニーズを把握した上で、改善施策を立案・実行することが主な仕事です。
デジタルマーケティングに関する専門知識と、データに基づいた論理的な思考力が求められます。
Web系エンジニアに求められる必須スキル

Web系エンジニアとして活躍するためには、プログラミングスキル以外にも様々な能力が求められます。
特定の国家資格や検定、例えば応用情報技術者試験などが採用の必須条件となることは稀ですが、Web開発に関する基本的な知識や専門用語の理解は不可欠です。
資格の難易度よりも、むしろ実務で通用する技術力や、チームで成果を出すためのソフトスキルが重視される傾向にあります。
ここでは、Web系エンジニアにとって特に重要となるスキルを具体的に解説します。
プログラミング言語やフレームワークの知識
Web系エンジニアにとって、プログラミング言語の知識は基本中の基本です。
フロントエンドであればJavaScript、バックエンドであればRuby、PHP、Pythonなどが代表的です。
さらに、効率的に開発を進めるためのフレームワーク、例えばReactやRubyonRailsなどの知識も欠かせません。
Web業界は技術のトレンドの移り変わりが非常に速いため、特定の技術に固執するのではなく、常に新しい言語やフレームワークの情報を収集し、学習し続ける姿勢が重要になります。
クラウドサービスやサーバーに関する知識
現在のWebサービス開発において、AWSやGoogle Cloud Platformといったクラウドサービスの利用は当たり前になっています。
そのため、サーバーの構築や運用、データベースの管理などをクラウド上で行うための知識が必須です。
特に、仮想サーバーの構築やネットワーク設定、負荷に応じたリソースの自動調整など、クラウドが提供する様々な機能を理解し、適切に活用するスキルが求められます。
Dockerなどのコンテナ技術をはじめとする最新技術の知識も、サービスの信頼性や開発効率を向上させる上で重要度を増しています。
新しい技術を自ら学ぶキャッチアップ能力
Web業界は技術革新のスピードが非常に速く、昨日まで主流だった技術が今日には古くなっていることも珍しくありません。
このような環境で活躍し続けるためには、現状のスキルに満足せず、常に新しい技術や情報を自主的に学び続けるキャッチアップ能力が不可欠です。
国内外の技術ブログを読んだり、勉強会やセミナーに参加したり、オープンソースの活動に貢献したりと、能動的に知識やスキルをアップデートしていく姿勢がエンジニアとしての市場価値を大きく左右します。
チーム開発を円滑に進めるコミュニケーション能力
Webサービスの開発は、個人の力だけで完結することはほとんどありません。
多くの場合、Webディレクターやデザイナー、他のエンジニアなど、様々な職種のメンバーと協力してプロジェクトを進めます。
そのため、技術的なスキルと同等に、円滑なコミュニケーション能力が重視されます。
自分の考えを論理的に説明する力、他者の意見を正しく理解する傾聴力、課題や懸念点を適切に報告・相談する能力などが求められ、採用の面接においても重要な評価ポイントとなります。
Web系企業で働くことのメリット
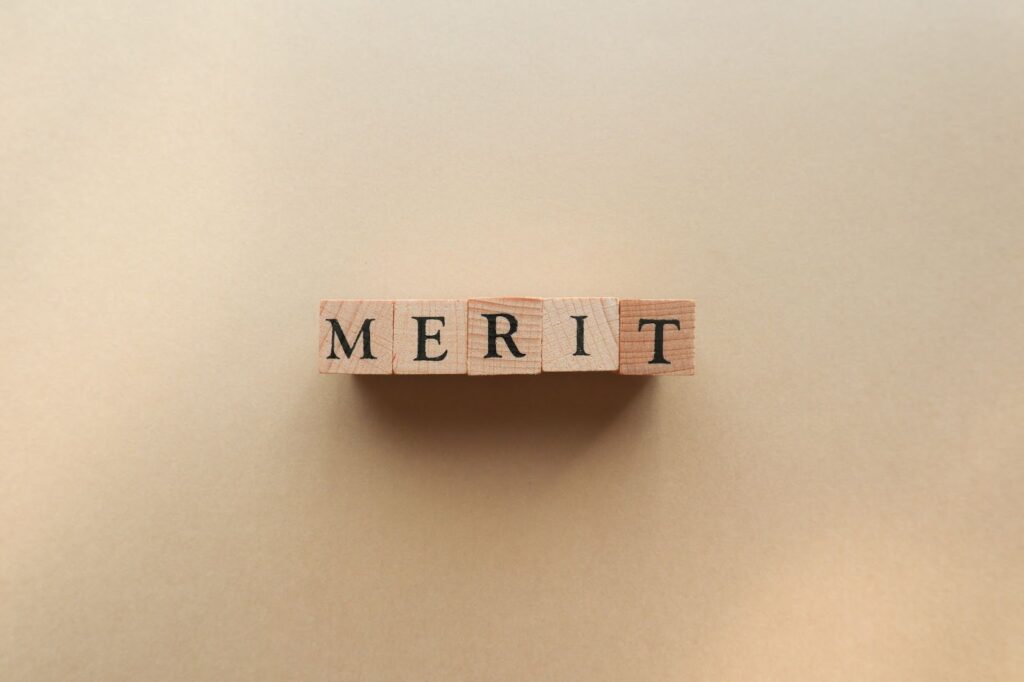
Web系企業で働くことには、技術者にとって多くの魅力があります。
自社サービスを手掛けることが多いため、ユーザーの声を直接開発に活かせたり、最新技術に触れる機会が豊富にあったりします。
また、比較的自由な社風の企業が多く、働き方の柔軟性が高い点もメリットの一つです。
自身のスキルが会社の業績や個人の年収に直結しやすく、成果が正当に評価される環境で働きたいと考える人にとって、やりがいの大きい職場と言えるでしょう。
ユーザーからの反応を直接感じられる
Web系企業が開発するサービスの多くは、一般の消費者が日々利用するものです。
そのため、自分が実装した機能や改善したデザインに対して、SNSやアプリストアのレビューなどを通じてユーザーからのフィードバックを直接得ることができます。
肯定的な意見は大きな達成感につながり、たとえ否定的な意見であっても、次の改善に向けた貴重な情報となります。
時に「やめとけ」と言われるような厳しい意見もありますが、自分の仕事が世の中に与える影響をダイレクトに感じられる点は、Web系で働く大きなやりがいです。
最新の技術に触れる機会が豊富にある
Web業界は技術の進化が速く、企業間の競争も激しいため、多くの企業が新しい技術や開発手法を積極的に取り入れています。
その結果、エンジニアは業務を通じて常に最新の技術トレンドに触れる機会に恵まれます。
新しいプログラミング言語やフレームワーク、クラウドサービスなどを実務で活用しながらスキルを磨くことが可能です。
常に学び続ける姿勢が求められるため、人によってはきついと感じるかもしれませんが、知的好奇心が旺盛なエンジニアにとっては非常に刺激的で成長できる環境です。
比較的自由なスタイルで働きやすい
Web系企業は、伝統的な大企業に比べて、比較的自由で柔軟な働き方ができる文化が根付いています。
服装や髪型が自由な企業が多く、フレックスタイム制や裁量労働制を導入している場合も少なくありません。
特にリモートワークの普及率は高く、場所に縛られずに働くことも可能です。
このような自由度の高い環境は、将来的にフリーランスとしての独立を考えている人にとっても良い経験となるでしょう。
ワークライフバランスを重視する人にとって、後悔の少ない選択肢となり得ます。
未経験からWeb系エンジニアになるための学習ステップ

Web系エンジニアは、専門性が高い職種でありながら、未経験からでも目指すことが可能です。
新卒や第二新卒はもちろん、高卒や文系出身者、30代からキャリアチェンジを目指す既卒の方も少なくありません。
ただし、異業種からの転職を成功させるためには、計画的かつ効率的な学習が不可欠です。
ここでは、未経験からWeb系エンジニアになるための具体的な学習ステップを紹介し、転職を実現するための道筋を示します。
プログラミングの基礎を学習する
最初に、プログラミングの基礎知識を習得することが必要です。
Webページの見た目を作るHTML/CSSと、動きを加えるJavaScriptは必須のスキルと言えます。
これらに加え、PHPやRubyといったサーバーサイドで動くプログラミング言語を一つ選んで深く学習すると、作れるものの幅が広がります。
独学での習得も可能ですが、効率的に学びたい場合は、専門学校やオンラインのプログラミングスクールが提供する講座の受講も有効な手段です。
体系的なカリキュラムで、挫折せずに学習を進めやすくなります。
ポートフォリオとしてWebサービスを開発する
プログラミングの基礎を学んだ後は、その知識を活かしてオリジナルのWebサービスやアプリケーションを開発しましょう。
この開発した成果物は「ポートフォリオ」となり、転職活動において自身のスキルを証明する最も強力な武器となります。
単に知識があるだけでなく、学んだことを応用して実際にプロダクトを完成させられる能力を示すことが重要です。
アイデアの企画から設計、開発、公開までの一連のプロセスを経験することで、実践的な開発スキルが身につきます。
転職エージェントや求人サイトに登録する
ポートフォリオが完成したら、いよいよ本格的な転職活動を開始します。
IT業界やWeb系に特化した転職エージェントや求人サイトに登録し、積極的に情報を収集しましょう。
特に転職エージェントを活用すると、一般には公開されていない求人の紹介を受けられたり、職務経歴書の添削や面接対策といったサポートを受けられたりするメリットがあります。
未経験者の採用に積極的な企業を見つけ、作成したポートフォリオを提示しながら、自身の学習意欲やポテンシャルをアピールすることが採用への近道です。
よくあるご質問
Q1: 文系出身の未経験でもWeb系エンジニアになれますか?
A1: はい、可能です。Web系エンジニアに必要なのは論理的思考力や継続的な学習意欲であり、文系・理系は関係ありません。実際に多くの文系出身者が活躍しています。プログラミングスクールなどを活用して基礎を固め、スキルを証明するポートフォリオを作成することが重要です。
Q2: SIerからWeb系への転職は可能ですか?
A2: 可能です。ただし、開発文化や使用する技術が異なるため、RubyやPHP、JavaScriptといったWeb系の技術を自主的に学習する必要があります。SIerで培ったシステム開発の基礎知識やプロジェクト経験は、Web系への転職においても強みとして活かせます。
Q3: 30代未経験からでも挑戦できますか?
A3: はい、挑戦可能です。20代に比べると求人の幅は狭まる可能性がありますが、学習意欲とポテンシャルを示すことができれば採用のチャンスは十分にあります。これまでの社会人経験で得たコミュニケーション能力や課題解決能力をアピールすることも有効です。
Q4: 必要な資格はありますか?
A4: Web業界では必須とされる特定の資格は基本的にありません。資格の有無よりも、ポートフォリオなどで示せる実践的な開発スキルが重視されます。ただし、「基本情報技術者試験」などの資格は、ITに関する基礎知識を客観的に証明する上で役立つ場合があります。
Q5: 平均的な年収はどのくらいですか?
A5: 年収は本人のスキルや経験、企業の規模によって大きく変動します。未経験からのスタートの場合、300万円台から400万円台が一般的ですが、スキルを磨いて経験を積むことで、年収を大幅に向上させることが可能です。実力主義の傾向が強い業界です。
まとめ
Web系の仕事は、技術の進化とともに今後も社会的な需要が高まり続ける将来性のある分野です。
最新の技術に触れながら、ユーザーの反応をダイレクトに感じられる点は大きな魅力と言えます。
未経験からのキャリアチェンジは決して簡単ではなく、継続的な学習が不可欠ですが、正しいステップを踏めば道は開けます。
柔軟な働き方がしやすいため副業やアルバイトとしても関わりやすく、スキル次第では70代でも現役で活躍できる可能性があります。
難しいと感じる場面もありますが、それ以上にやりがいのある仕事です。
Webサイト制作・運用のご相談は Piic へ
採用・集客・ブランディングまで、“成果につながる”Web体験を設計します。
- 要件整理/情報設計(IA)/ワイヤー作成
- デザイン・コピー開発(トーン&マナー統一)
- WordPress/ヘッドレスCMS実装・表示速度最適化
- GA4/GTM計測設計・CV改善(SEO/UI改善)
- 運用保守・更新代行・記事制作
「まずは小さくLPから」「既存サイトの改善だけ」など、段階的な進め方もOK。
お気軽にご相談ください。