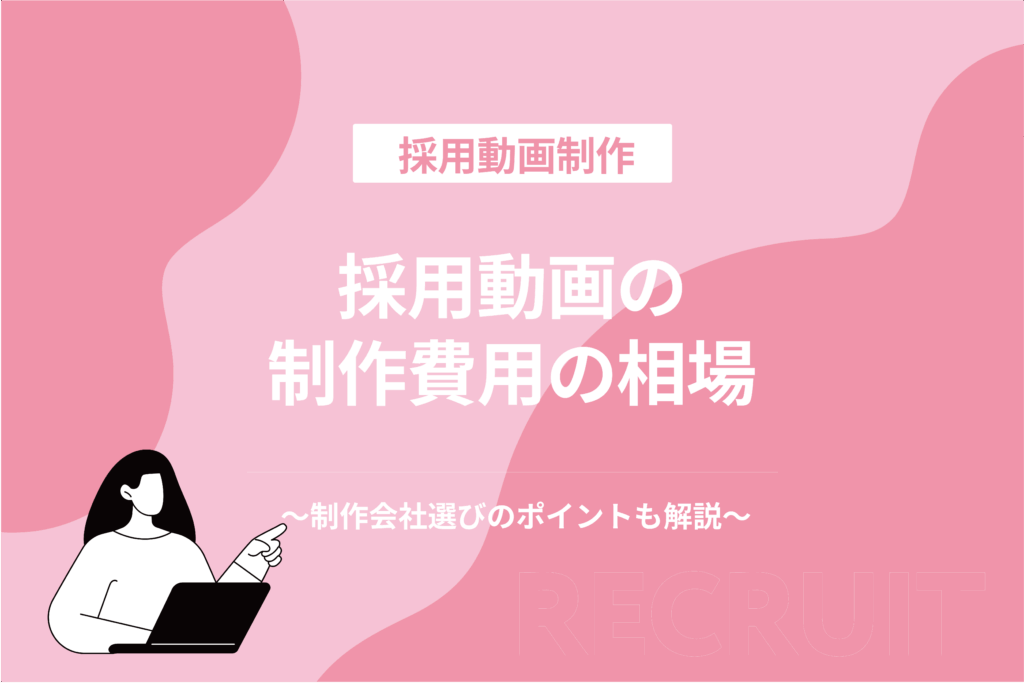
採用動画とは、企業の魅力や働き方を映像で伝え、求職者の応募意欲を高めるための動画です。
テキストや写真だけでは伝わりにくいリアルな雰囲気を届けられるため、動画採用は多くの企業にとって重要なリクルート手法となっています。
この記事では、採用動画の制作にかかる費用相場を価格帯別に解説するとともに、制作会社を選ぶ際のポイントやコストを抑えるコツを紹介します。
自社に合った動画制作を実現するための参考にしてください。
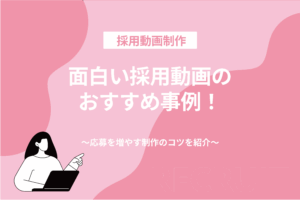
Index
-
採用動画制作の費用相場を価格帯別に解説
-
10万円~50万円で制作できる採用動画の内容
-
50万円~100万円で制作できる採用動画の内容
-
100万円~200万円で制作できる採用動画の内容
-
200万円以上で制作できる採用動画の内容
-
採用動画を制作するメリット
-
企業の魅力や社風をリアルに伝えられる
-
応募者の入社後のミスマッチを減らせる
-
WebサイトやSNSで拡散しやすく多くの求職者に届く
-
採用動画を制作するデメリット
-
制作にコストと時間がかかる
-
情報の修正が簡単にはできない
-
採用動画の制作費用を安く抑える5つのコツ
-
動画の尺(長さ)を短くする
-
撮影場所や日数を最小限にする
-
従業員に出演してもらう
-
アニメーションやCGなど特殊な編集を避ける
-
テンプレートやパッケージプランを活用する
-
失敗しない!採用動画制作会社を選ぶ3つのポイント
-
採用動画の制作実績が豊富か確認する
-
企画や構成からサポートしてくれるか見極める
-
見積もりの内訳が明確で分かりやすいかチェック
-
採用動画制作を外注する際の注意点
-
動画制作の目的とターゲットを明確に伝える
-
伝えたい企業の強みやメッセージを絞り込む
-
予算と希望納期を事前に共有する
-
制作後の動画の著作権や使用範囲を確認しておく
-
よくあるご質問
-
Q1:採用動画の制作期間はどれくらいかかりますか?
-
Q2:動画の修正はどこまで可能ですか?
-
Q3:撮影場所が地方でも対応してもらえますか?
-
Q4:BGMやナレーションもお願いできますか?
-
Q5:自社で撮影した素材を使って編集だけお願いすることはできますか?
-
まとめ
-
採用ブランディング・採用クリエイティブのご相談はPiicへ
採用動画制作の費用相場を価格帯別に解説

採用動画の制作費用は、動画の種類やクオリティによって数十万円から数百万円までと大きな幅があります。
例えば、シンプルなインタビュー動画と、CGやアニメーションを駆使したブランディング動画では、必要な人員や機材、制作時間が全く異なるためです。
まずは価格帯ごとの一般的な動画内容を把握し、自社が求めるクオリティと予算のバランスを見極めることが、費用対効果の高い動画制作につながります。
ここでは、主な価格帯別に制作できる動画の内容を解説します。
10万円~50万円で制作できる採用動画の内容
この価格帯では、比較的シンプルな構成の採用動画を制作できます。
主な内容としては、社員1〜2名へのインタビュー動画や、既存の写真素材をスライドショー形式で見せる動画が中心です。
撮影は1日で、場所も自社オフィス内に限定されることが多く、企画や構成も制作会社と相談しつつ、ある程度自社で主導する必要があります。
動画の長さは30秒から数分程度のものが多く、特定の職種に絞った仕事紹介や、説明会用の短いオープニング映像といった、用途を限定した動画制作に向いています。
基本的な撮影と編集に絞ることで、コストを抑えた制作が可能です。
50万円~100万円で制作できる採用動画の内容
50万円から100万円の価格帯になると、より企画性の高い採用動画の制作が可能になります。
複数の社員インタビューを組み合わせたり、オフィス内の風景や働く様子をインサート映像として加えたりすることで、よりリッチな内容にできます。
また、簡単なアニメーションやCGを取り入れて、企業の事業内容やデータを分かりやすく見せることも選択肢に入ります。
撮影が複数日にわたったり、複数のロケーションで撮影したりすることも可能です。
企業の理念や社風といった、より深いメッセージを伝えたい場合に適した価格帯といえます。
100万円~200万円で制作できる採用動画の内容
100万円を超えると、企業のブランディングを強く意識したクオリティの高い採用動画が制作できます。
プロの脚本家によるシナリオ作成や、ドローンを使ったダイナミックな空撮、オリジナルのBGM制作など、表現の幅が大きく広がります。
社員の働き方に密着するドキュメンタリー調の動画や、ストーリー性のあるドラマ仕立ての動画など、視聴者の感情に訴えかけるような演出も可能です。
プロの役者を起用したり、本格的なスタジオで撮影したりすることもでき、企業の魅力を最大限に引き出すための多様な選択肢が生まれます。
200万円以上で制作できる採用動画の内容
200万円以上の予算をかける場合、テレビCMに匹敵するハイクオリティな採用動画の制作が視野に入ります。
著名なタレントや俳優を起用したキャスティングや、大規模なロケーションでの撮影、映画のような質の高いCGやVFXを駆使した映像表現が可能です。
単なる採用ツールとしてだけでなく、企業のプロモーション全体の一環として活用できるレベルの動画を制作できます。
企画の段階から制作会社が深く関与し、採用戦略に基づいたコンセプト設計からサポートしてくれるため、企業のブランドイメージを大きく向上させる効果が期待されます。
採用動画を制作するメリット
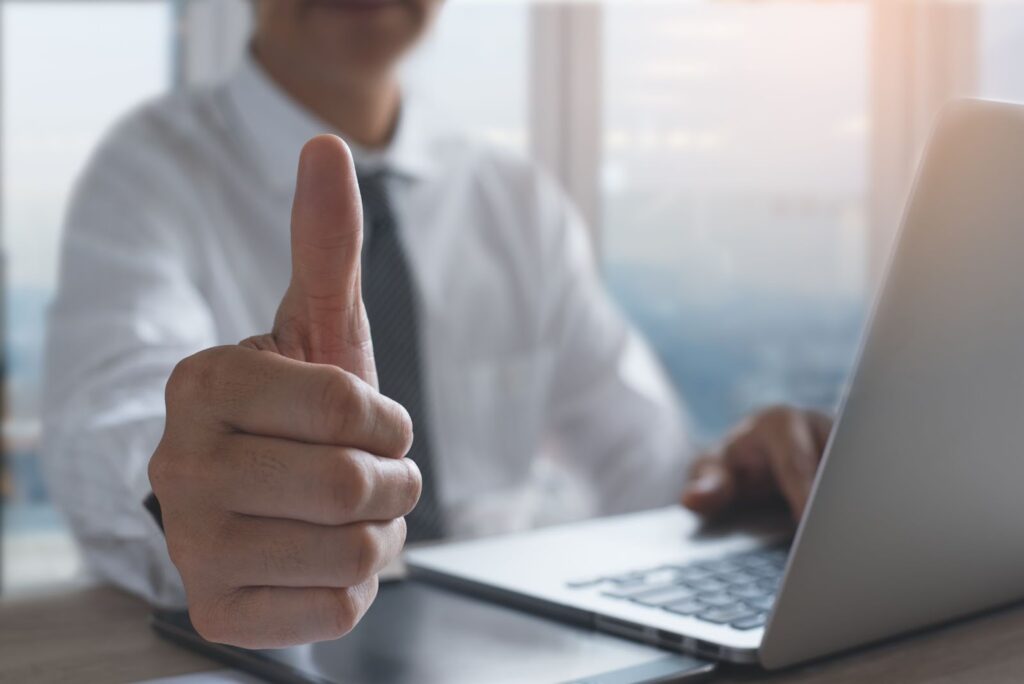
採用動画を制作することには多くのメリットがあります。
文章や静止画だけでは伝えきれない企業の雰囲気や社員の生の声を届けることで、求職者の企業理解を深め、応募意欲を高める効果が期待できます。
また、制作した動画は様々な媒体で活用できるため、幅広い層の求職者にアプローチする機会を創出します。
ここでは、採用動画がもたらす具体的な利点について詳しく見ていきます。
企業の魅力や社風をリアルに伝えられる
採用動画の最大のメリットは、企業の魅力や社風をリアルに伝えられる点です。
映像と音声を通じて、オフィスの雰囲気や実際に働く社員の表情、声のトーンなどを直接的に届けられます。
これにより、求職者はその企業で働く自分の姿を具体的にイメージしやすくなります。
テキストだけでは伝わりにくい「社員同士のコミュニケーションの様子」や「活気ある職場の空気感」といった無形の価値を可視化できるため、求職者の共感を得やすく、企業への興味関心を高める効果が期待できます。
ストーリー性を持たせることで、企業理念やビジョンをより深く印象付けることも可能です。
応募者の入社後のミスマッチを減らせる
リアルな情報を事前に提供することは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に効果的です。
採用動画を通じて、仕事の良い面だけでなく、大変な部分や求められるスキルなどを正直に伝えることで、求職者は企業に対して適切な理解を持つことができます。
特に、社会人経験の少ない新卒や、異なる環境からの転職を考えている中途採用者にとって、働く環境を事前に映像で確認できることは、重要な判断材料となります。
これにより、「思っていた仕事内容と違った」「社風が合わなかった」といった理由による早期離職のリスクを低減させ、定着率の向上に貢献します。
WebサイトやSNSで拡散しやすく多くの求職者に届く
動画コンテンツは、SNSとの親和性が非常に高いという特徴があります。
制作した採用動画をYouTubeチャンネルや企業の公式SNSアカウントに投稿することで、多くの求職者の目に触れる機会が生まれます。
内容が魅力的であれば、視聴者による「いいね」やシェアを通じて情報が自然に拡散され、これまで自社を知らなかった潜在的な候補者層へもアプローチできます。
また、Yahoo!JAPANのようなプラットフォームで動画広告を配信すれば、ターゲットを絞って効率的に情報を届けることも可能です。
Webサイトに埋め込むだけでなく、多様なチャネルで活用できる拡散力の高さは大きなメリットです。

採用動画を制作するデメリット
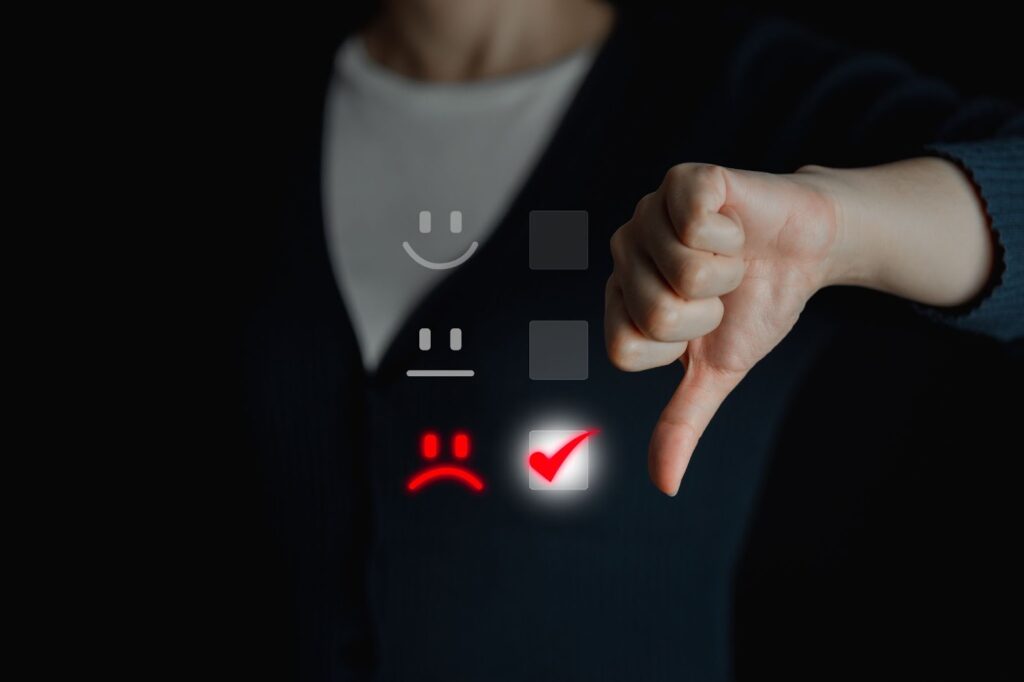
採用動画には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
動画の作成には、時間やコストがかかるほか、一度公開すると情報の修正が難しいといった側面もあります。
これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、採用動画を成功させるためには不可欠です。
ここでは、採用動画を制作する際に考慮すべきデメリットについて解説します。
制作にコストと時間がかかる
採用動画の制作には、費用と時間が必要です。
クオリティの高い動画を目指す場合、企画、撮影、編集などの各工程で専門的なスキルが求められ、外部の制作会社に依頼するのが一般的です。
その際の費用は、動画の内容や長さによって数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
また、制作会社との打ち合わせ、企画の策定、撮影スケジュールの調整、編集、修正の確認といったプロセスを経るため、完成までには数週間から数ヶ月の期間を要します。
予算とスケジュールの確保が、動画制作に着手する上での前提となります。
情報の修正が簡単にはできない
動画コンテンツは、テキストや画像と比べて情報の修正が容易ではありません。
例えば、動画内で紹介した福利厚生制度が変更になったり、オフィスが移転したりした場合、該当部分だけを差し替えるのは技術的に難しく、再編集には追加のコストと時間がかかります。
そのため、採用動画で伝える情報は、変更の可能性が低い普遍的な内容(企業理念やビジョン、社風など)を中心にする工夫が必要です。
特にSNSなどで一度拡散された動画は、古い情報が残り続けるリスクもあるため、公開する内容については慎重な検討が求められます。
採用動画の制作費用を安く抑える5つのコツ

採用動画の制作にはコストがかかりますが、いくつかの工夫によって費用を抑えることが可能です。
予算が限られている場合でも、ポイントを押さえることで効果的な採用向け動画は制作できます。
やみくもにコストを削るのではなく、動画の目的やクオリティとのバランスを考えながら、賢く費用をコントロールすることが重要です。
- 動画の尺(長さ)を短くする
- 撮影場所や日数を最小限にする
- 従業員に出演してもらう
- アニメーションやCGなど特殊な編集を避ける
- テンプレートやパッケージプランを活用する
ここでは、制作費用を安く抑えるための上記の具体的な5つのコツを紹介します。
動画の尺(長さ)を短くする
動画の制作費用は、尺の長さに比例して高くなる傾向があります。
動画が長くなるほど、撮影に必要な時間や編集作業の手間が増えるためです。
伝えたいメッセージを明確にし、要点を絞り込むことで、動画全体の長さをコンパクトにまとめられます。
特にWeb上で視聴される採用動画は、長すぎると視聴者が途中で離脱してしまう可能性も高まります。
1分〜3分程度の短い尺でも、構成を工夫すれば企業の魅力を十分に伝えることは可能です。
動画の目的を再確認し、本当に必要な要素だけを残すことで、コスト削減と視聴維持率の向上を両立できます。
撮影場所や日数を最小限にする
撮影にかかる費用は、制作コストの大きな割合を占めます。
撮影場所が増えれば移動時間や機材の運搬・設置に手間がかかり、撮影日数が増えればカメラマンやスタッフの人件費もその分増加します。
費用を抑えるためには、撮影場所を自社のオフィスや会議室など1〜2箇所に限定し、撮影スケジュールを効率的に組んで1日で完了させることが有効です。
これにより、交通費や施設利用料、人件費といった諸経費を削減し、制作全体のコストダウンを図れます。
事前に撮影の流れを詳細に計画しておくことが、スムーズな進行の鍵です。
従業員に出演してもらう
従業員を動画に起用することで、プロの役者やモデルを起用する際に発生するキャスティング費用を抑えることが可能です。
従業員が自身の言葉で仕事のやりがいや会社の雰囲気を語ることは、求職者にとって何より説得力のあるメッセージになります。
リアルな働き方が伝わることで、視聴者は親近感を抱きやすく、より深く企業文化を理解できます。
出演を依頼する際は、従業員の負担にならないよう事前に十分な説明を行い、協力的な雰囲気を作ることが、スムーズな撮影と動画のクオリティ向上につながります。
アニメーションやCGなど特殊な編集を避ける
アニメーションやCG、ドローンでの空撮といった特殊な編集や撮影技術は、専門のクリエイターや機材が必要になるため、制作費用を引き上げる大きな要因となります。
これらの凝った演出を避け、インタビューや社内風景などの実写映像を主体に構成することで、編集にかかるコストを大幅に削減可能です。
事業内容の説明など、図やグラフが必要な場面では、シンプルなテロップやインフォグラフィックスで代用することもできます。
動画の種類や目的に応じて、本当に特殊な演出が必要かどうかを見極めることが重要です。
テンプレートやパッケージプランを活用する
多くの動画制作会社は、あらかじめ用意されたフォーマットに沿って動画を制作するテンプレートプランや、撮影から編集までをセットにしたパッケージプランを提供しています。
これらを活用すれば、企画や構成を一から作り上げるフルオーダーメイドの会社紹介動画に比べて、費用を大きく抑えることが可能です。
デザインや構成の自由度は低くなりますが、低予算かつ短納期で、一定のクオリティが担保された動画を制作したい場合には非常に有効な選択肢です。
複数の制作会社のプランを比較検討し、自社の要望に合ったものを選びましょう。
失敗しない!採用動画制作会社を選ぶ3つのポイント

採用動画の成果は、どの制作会社に依頼するかによって大きく左右されます。
数多く存在する制作会社の中から、自社の魅力を最大限に引き出し、採用目標の達成に貢献してくれるパートナーを見つけることが成功の鍵です。
ここでは、制作会社選びで失敗しないために、必ずチェックしておきたい3つのポイントを解説します。
これらの視点を参考に、自社に最適な一社を選びましょう。
おすすめの比較方法も紹介します。
採用動画の制作実績が豊富か確認する
まず最初に、制作会社の公式ウェブサイトなどで、過去の制作実績を確認しましょう。
特に重要なのは、単に映像がきれいなだけでなく、採用という目的に特化した動画の制作経験が豊富かどうかです。
自社と同じ業界や、似たような課題を持つ企業の採用動画を手がけた実績があれば、業界特有の事情や求職者のインサイトを理解している可能性が高く、スムーズな意思疎通が期待できます。
作りたい動画のテイストやクオリティが、その会社の実績と合っているかどうかも重要な判断基準です。
実績を通して、その会社の得意な表現方法や企画力を見極めましょう。
企画や構成からサポートしてくれるか見極める
優れた採用動画を制作するためには、撮影や編集の技術力だけでなく、求職者の心に響く企画や構成が不可欠です。
制作会社を選ぶ際には、技術的な側面だけでなく、「何を、誰に、どのように伝えるか」という企画の根幹から相談に乗ってくれるかを見極めましょう。
自社の漠然としたイメージを具体的な動画の形に落とし込み、企業の強みや魅力を引き出す提案をしてくれる会社は、心強いパートナーとなります。
初回のヒアリングや打ち合わせの際に、担当者がどれだけ採用課題に寄り添い、効果的な内容を一緒に考えてくれるかで判断できます。
見積もりの内訳が明確で分かりやすいかチェック
複数の制作会社から見積もりを取得し、比較検討することは基本です。
その際に必ず確認したいのが、見積もりの内訳の明確さです。
単に「制作費一式」と記載されているだけでなく、「企画構成費」「撮影人件費」「機材費」「編集費」といったように、どの作業にどれだけの費用がかかるのかが詳細に記載されているかチェックしましょう。
内訳が明確であれば、予算に応じて「この部分の費用を抑えたい」といった具体的な相談がしやすくなります。
不明瞭な項目がある場合は、契約前に必ず質問し、納得のいく説明を得ることがトラブル防止につながります。
採用動画制作を外注する際の注意点

採用動画の制作を外部の専門会社に依頼する場合、ただ任せきりにするのではなく、発注側として押さえておくべきポイントがいくつかあります。
制作をスムーズに進め、最終的に期待通りの成果物を得るためには、事前の準備と制作会社との円滑なコミュニケーションが不可欠です。
ここでは、制作を外注する際に特に注意すべき点を解説します。
これらを意識することで、制作会社とのミスマッチを防ぎ、より効果的な動画制作を実現できます。
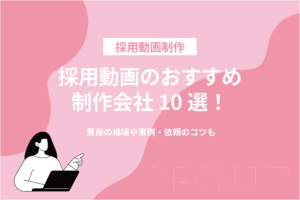
動画制作の目的とターゲットを明確に伝える
制作会社に依頼する前に、まず「何のために動画を作るのか」という目的と、「誰に見てほしいのか」というターゲットを社内で明確にしておく必要があります。
「企業の認知度向上」「エントリー数の増加」「内定辞退率の低下」など、目的によって動画で訴求すべき内容は変わります。
また、ターゲットが新卒学生なのか、特定のスキルを持つ中途採用者なのかによっても、響くメッセージや表現方法は異なります。
この目的とターゲットを具体的に制作会社に伝えることで、より的確で効果的な採用向け動画の企画提案を受けられます。
伝えたい企業の強みやメッセージを絞り込む
動画で伝えられる情報量には限りがあります。
自社の魅力をあれもこれもと詰め込みすぎると、結局何が言いたいのか分からない、印象に残らない動画になってしまいます。
制作を依頼する前に、今回の動画で最も伝えたい企業の強みやメッセージは何かを1つか2つに絞り込みましょう。
「挑戦できる社風」「ワークライフバランスの充実」「社会貢献性の高い事業内容」など、最も訴求したい核となるメッセージを定めることで、動画全体の構成に一貫性が生まれます。
この軸を制作会社と共有することが、メッセージ性の高い動画を作るための第一歩です。
予算と希望納期を事前に共有する
制作会社との最初の打ち合わせの段階で、確保している予算の上限と、いつまでに動画を完成させたいかという希望納期を明確に伝えましょう。
予算を事前に共有することで、制作会社はその範囲内で実現可能な最適な企画やクオリティを提案してくれます。
また、希望納期を伝えることで、そこから逆算した現実的な制作スケジュールを組むことができます。
この2つの情報が曖昧なまま話を進めると、後から「予算が合わない」「納期に間に合わない」といったトラブルに発展しかねません。
事前の情報共有が、円滑なプロジェクト進行の鍵です。
制作後の動画の著作権や使用範囲を確認しておく
動画制作の契約を結ぶ際には、成果物である動画の著作権がどちらに帰属するのかを必ず確認しましょう。
一般的には、制作費を支払うことで著作権も発注側に譲渡されることが多いですが、契約内容によっては制作会社が保持する場合もあります。
また、制作した動画の使用範囲についても、「自社の採用サイトのみ」「SNSや動画広告での利用も可」「イベントでの上映も可」など、どこまで利用して良いのかを事前に明確にしておく必要があります。
後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容を十分に確認し、不明な点は必ず質問してください。
よくあるご質問
Q1:採用動画の制作期間はどれくらいかかりますか?
A1:動画の内容や長さによって異なりますが、企画の打ち合わせから撮影、編集、納品まで、一般的には1.5ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。修正の回数やお客様の確認スピードによっても変動します。
Q2:動画の修正はどこまで可能ですか?
A2:多くの制作会社では、編集の初稿が上がってきた段階で1〜2回程度の修正に対応しています。ただし、撮影をやり直す必要があるような大幅な内容変更や、契約回数以上の修正は、追加費用が発生することが一般的です。契約時に修正の範囲や回数を確認しておくと安心です。
Q3:撮影場所が地方でも対応してもらえますか?
A3:全国対応している制作会社は多いですが、本社から撮影場所までの距離に応じて、別途交通費や宿泊費などの出張費がかかる場合があります。依頼を検討している制作会社に、事前にお問い合わせください。
Q4:BGMやナレーションもお願いできますか?
A4:はい、ほとんどの制作会社で対応可能です。BGMは著作権フリーの音源ライブラリから選んだり、オリジナルで制作したりします。ナレーションもプロのナレーターを手配することができ、動画の雰囲気に合わせて声のトーンなどを選べます。
Q5:自社で撮影した素材を使って編集だけお願いすることはできますか?
A5:編集作業のみを受け付けている制作会社もあります。ただし、スマートフォンなどで撮影した素材は、画質や音質がプロの機材に劣るため、完成する動画のクオリティに影響が出る場合があります。依頼する際は、素材のデータ形式や品質について事前に相談することをおすすめします。
まとめ
採用動画は企業の魅力を直感的に伝え、求職者とのミスマッチを防ぐ強力なリクルートツールです。
動画採用を成功させるためには、まず自社の目的とターゲットを明確にすることが不可欠です。
費用は動画の種類やクオリティによって大きく変動しますが、本記事で紹介したようにコストを抑える工夫も可能です。
制作会社を選ぶ際は、実績やサポート体制、見積もりの透明性を確認し、信頼できるパートナーを見つけましょう。
計画的に準備を進めることで、費用対効果の高い動画制作が実現し、採用活動の成果を大きく向上させます。
採用ブランディング・採用クリエイティブのご相談はPiicへ
Piic(ピーク)は、採用ピッチ資料や採用サイト、パンフレット、SNS運用など、採用に関わるすべてのクリエイティブを一貫してサポートしています。
企業の価値観やカルチャーを“見える化”し、求職者が共感できる採用体験を設計することで、応募率や内定承諾率の向上につなげます。
「採用がうまくいかない」「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」
そんな課題を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。








