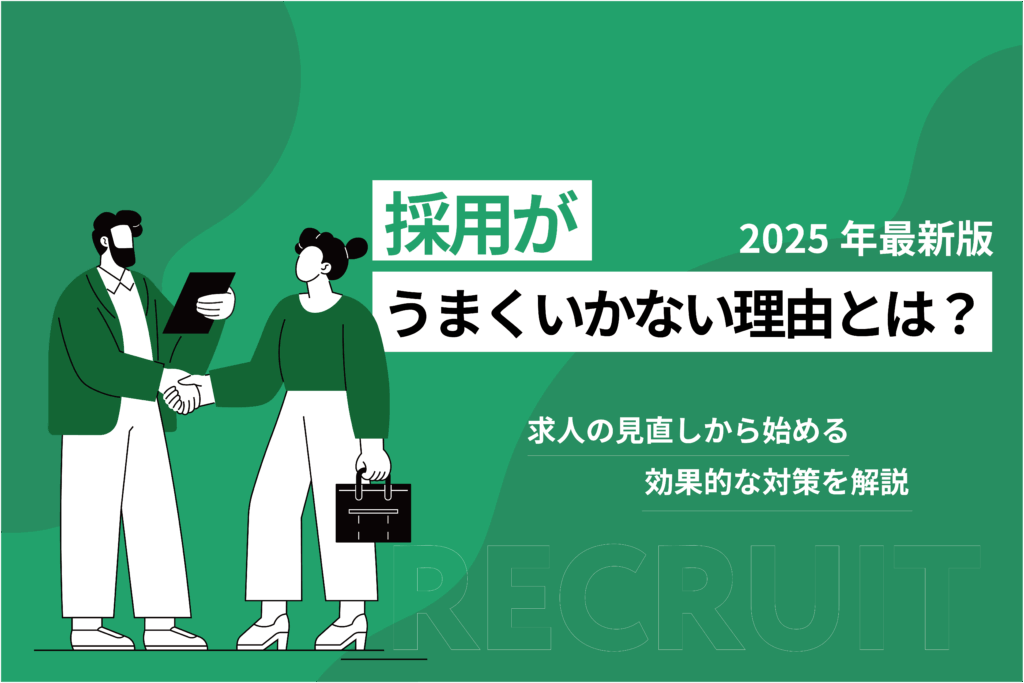
募集をかけても人が集まらない、内定を出しても辞退されるなど、採用活動が思うように進まず、頭を悩ませていませんか。
採用が困難な状況が続くと、事業計画に遅れが生じるリスクも高まります。
人が取れない背景には、求人内容や選考プロセス、市場の変化など様々な理由が考えられます。
本記事では、採用がうまくいかない根本的な原因を解き明かし、求人の見直しから始められる具体的な改善策までを詳しく解説します。

Index
-
あなたの会社はどっち?採用できない2つの典型的なパターン
-
そもそも求人に応募が全く集まらない
-
選考や内定の段階で辞退されてしまう
-
なぜ採用できない?企業側に見られる7つの根本的な原因
-
【原因1】どんな人材が欲しいのかが曖昧になっている
-
【原因2】求人情報で企業の魅力や仕事内容を伝えきれていない
-
【原因3】ターゲット層に届かない採用手法を選んでいる
-
【原因4】他社と比較されたときに選ばれる強みがない
-
【原因5】選考スピードが遅く候補者の熱が冷めてしまう
-
【原因6】面接官の対応が候補者の入社意欲を下げている
-
【原因7】売り手市場や働き方の多様化など外的要因を考慮していない
-
採用できない状況から脱却するための具体的な6つの改善策
-
【対策1】求める人物像を具体的に定義する
-
【対策2】求職者の視点に立って求人票の情報を充実させる
-
【対策3】採用したい層に合わせた採用チャネルへ切り替える
-
【対策4】自社の強みを言語化し、採用ブランディングを推進
-
【対策5】選考プロセスを見直し、候補者体験の向上を
-
【対策6】面接官のスキルを標準化するためのトレーニング
-
【中小企業向け】採用できない状況を乗り越えるためのヒント
-
知名度の低さをカバーする情報発信を強化する
-
限られたリソースを有効活用できる採用代行(RPO)を検討
-
柔軟な働き方や独自の福利厚生で魅力を高める
-
よくあるご質問
-
Q.応募は来るのですが、求める人材からの応募がありません。どうすればいいですか?
-
Q.給与や待遇面で他社に見劣りしてしまいます。
-
Q.内定を出しても、いつも辞退されてしまいます。
-
Q.採用にかけられるコストが限られています。効果的な方法はありますか?
-
Q.急な欠員で、すぐにでも人が欲しいのですが。
-
まとめ
あなたの会社はどっち?採用できない2つの典型的なパターン

採用できない状況に陥っている企業は、大きく二つのパターンに分類できます。
一つは「そもそも応募が集まらない」ケース、もう一つは「応募はあるのに採用に至らない」ケースです。
自社がどちらのパターンに当てはまるのかを把握することが、課題解決の第一歩となります。
両方の課題を抱えている企業も少なくなく、まずは現状を客観的に分析し、どこに問題があるのかを正確に見極める必要があります。
そもそも求人に応募が全く集まらない
求人への応募が全くない、あるいは非常に少ない場合、求人情報が求職者の目に触れていないか、見られても魅力的に映っていない可能性があります。
原因としては、求人媒体の選択がターゲット層とずれている、提示している給与や待遇が市場の相場と比べて低い、求人票に記載された仕事内容が曖昧で働くイメージが湧かない、などが考えられます。
この状態が続くと、採用の母集団を形成できず、比較検討の機会もないまま採用活動を進めることになり、結果的にミスマッチのリスクが高まります。
選考や内定の段階で辞退されてしまう
書類選考や面接には進むものの、選考の途中や内定通知後、最終的に辞退されてしまうケースも少なくありません。
この背景には、選考プロセスそのものに問題が潜んでいることが多いです。
例えば、書類選考の結果通知や面接日程の調整に時間がかかりすぎている、面接官の態度が高圧的で不信感を抱かせた、求人票の内容と面接で聞いた話に食い違いがあった、などが辞退の引き金になります。
最悪の場合、内定後の連絡を無視されることもあり、企業の評判低下にもつながりかねません。
なぜ採用できない?企業側に見られる7つの根本的な原因

採用活動が停滞する背景には、企業側に起因する根本的な原因が存在します。
求める人物像の曖昧さから、外的要因の見落としまで、その問題は多岐にわたります。
これらは単独で存在するのではなく、複数が複雑に絡み合って採用を困難にしている場合がほとんどです。
- どんな人材が欲しいのかが曖昧になっている
- 求人情報で企業の魅力や仕事内容を伝えきれていない
- ターゲット層に届かない採用手法を選んでいる
- 他社と比較されたときに選ばれる強みがない
- 選考スピードが遅く候補者の熱が冷めてしまう
- 面接官の対応が候補者の入社意欲を下げている
- 売り手市場や働き方の多様化など外的要因を考慮していない
自社の採用活動を振り返り、どの部分に課題があるのかを客観的に見つめ直すための、7つの視点を提供します。
【原因1】どんな人材が欲しいのかが曖昧になっている
採用活動の出発点である「どんな人材を採用したいか」という定義が曖昧なままでは、その後の全てがうまくいきません。
例えば、新卒採用と中途採用では求めるポテンシャルやスキルが異なりますし、同じ中途でも営業職とエンジニアでは評価軸が全く違います。
アルバイトの募集であっても、シフトへの貢献度や求めるスキルレベルを明確にしなければ、適切な人材は集まりません。
ターゲットがぼやけていると、求人広告のメッセージが誰にも響かず、応募があったとしてもミスマッチが頻発し、採用コストが無駄になる可能性があります。
【原因2】求人情報で企業の魅力や仕事内容を伝えきれていない
多くの求人情報が、業務内容や応募資格の羅列に終始してしまい、求職者が本当に知りたい情報を提供できていません。
求職者は、給与や待遇といった条件面に加え、「その会社で働くことでどのような経験が得られるのか」「どのような社風で、どんな人たちと働くのか」「会社の将来性やビジョンは何か」といった点に強い関心を持っています。
これらの魅力や働くイメージを具体的に伝えられなければ、数多くの求人の中に埋もれ、候補者の応募意欲を喚起することはできません。
情報不足は不安につながり、応募をためらわせる大きな要因となります。
【原因3】ターゲット層に届かない採用手法を選んでいる
採用したい人物像と、利用している採用チャネルが合っていないことも、応募が集まらない大きな原因です。
例えば、最新の技術を扱うITエンジニアを募集する際に、ハローワークだけに求人を掲載しても、ターゲット層に情報が届く可能性は低いでしょう。
若手の営業職なら就職・転職サイトやSNS、専門職なら特化型のエージェントやダイレクトリクルーティングなど、ターゲットが普段どのような媒体で情報収集しているかを理解し、適切な手法を選ぶことが不可欠です。
手法のミスマッチは、貴重な採用予算を投じても全く反応がないという事態を招きます。
【原因4】他社と比較されたときに選ばれる強みがない
求職者は、複数の企業を同時に比較検討しながら応募先を決めるのが一般的です。
その際に、給与や休日といった労働条件だけで他社に勝てない場合でも、何かしら「この会社で働きたい」と思わせる独自の強みがなければ、選ばれることはありません。
それは、事業の社会貢献性の高さ、独自の技術力、スキルアップを支援する研修制度、風通しの良い社風、ユニークな福利厚生など、企業によって様々です。
自社の魅力を客観的に分析し、言語化して伝えられなければ、より条件の良い他社へと優秀な人材は流れていってしまいます。
【原因5】選考スピードが遅く候補者の熱が冷めてしまう
応募から内定までの選考プロセスが長引くことは、候補者の入社意欲を低下させる大きな要因です。
特に、引く手あまたの優秀な人材は、複数の企業から同時にアプローチを受けているため、対応が遅い企業は早々に見切りをつけられてしまいます。
書類選考の結果連絡が1週間以上かかったり、面接後に送ったメールへの返信がなかったりするだけで、候補者は「自分は重要視されていない」と感じてしまいます。
迅速で丁寧なコミュニケーションは、候補者に対する誠意の表れであり、志望度を維持するために不可欠な要素です。
【原因6】面接官の対応が候補者の入社意欲を下げている
面接は、候補者が企業を直接知る貴重な機会であり、面接官の立ち居振る舞いは企業の印象そのものを決定づけます。
高圧的な質問、候補者の経歴を否定するような言動、プライベートに関する不適切な詮索などは、入社意欲を著しく削ぎます。
面接官が自社の魅力やビジョンを語れない場合も同様です。
不快な面接体験は、SNSなどを通じて瞬く間に拡散されるリスクもあり、企業のブランドイメージを大きく損なう可能性があります。
面接官は「会社の顔」であるという自覚を持ち、候補者に敬意を払った対応を徹底することが求められます。
【原因7】売り手市場や働き方の多様化など外的要因を考慮していない
採用がうまくいかない原因を自社の中だけに求めてしまい、労働市場全体の変化という外的要因を見過ごしているケースも散見されます。
少子高齢化による生産年齢人口の減少は、長期的な売り手市場を形成しており、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。
また、リモートワークの普及に代表されるように、求職者が仕事に求める価値観や働き方は大きく多様化しました。
こうした市場の変化に対応せず、旧来の採用手法や画一的な働き方を提示し続けていては、求職者から選ばれることはますます困難になります。
採用できない状況から脱却するための具体的な6つの改善策

採用がうまくいかない原因を特定したら、次はその課題を解決するための具体的な行動に移す必要があります。
ここで紹介する6つの改善策は、採用活動の根幹を見直すための重要なステップです。
- 求める人物像を具体的に定義する
- 求職者の視点に立って求人票の情報を充実させる
- 採用したい層に合わせた採用チャネルへ切り替える
- 自社の強みを言語化し、採用ブランディングを推進
- 選考プロセスを見直し、候補者体験の向上を
- 面接官のスキルを標準化するためのトレーニング
やみくもに施策を打つのではなく、自社の課題に合わせて優先順位をつけ、一つずつ着実に実行していくことが、採用成功への道を切り拓きます。
採用活動は、企業の未来を左右する重要なプロセスです。
【対策1】求める人物像を具体的に定義する
採用活動の羅針盤となるのが、求める人物像(ペルソナ)の明確な定義です。
必要なスキルや経験といった「能力面」だけでなく、どのような価値観を持ち、仕事を通じて何を成し遂げたいかといった「志向性」、そして自社の文化に馴染めるかという「人柄」まで、多角的に掘り下げて具体化します。
この作業は人事部だけで完結せず、実際に人材を受け入れる現場の部署と深く議論し、共通認識を形成することが不可欠です。
明確なペルソナを設定することで、誰に、何を、どのように伝えるべきかという採用戦略全体がクリアになり、ミスマッチのない人材を採用する確度が高まります。

【対策2】求職者の視点に立って求人票の情報を充実させる
求人票は単なる募集要項ではなく、求職者との最初のコミュニケーションツールです。
求職者が「この会社で働いてみたい」と思えるよう、彼らの視点に立って情報を充実させましょう。
具体的な仕事内容はもちろん、その仕事を通じて得られるやりがいや成長の機会、チームの雰囲気、1日の仕事の流れなどを具体的に記述します。
成功事例や活躍している社員のインタビューを掲載するのも効果的です。
また、企業の良い面だけでなく、仕事の厳しさや乗り越えるべき課題についても正直に伝えることで、誠実な姿勢が伝わり、入社後のギャップを減らすことにも繋がります。
【対策3】採用したい層に合わせた採用チャネルへ切り替える
具体化したペルソナが、普段どのようなメディアに接触し、どのように仕事を探しているのかを徹底的にリサーチし、採用チャネルを最適化します。
総合的な求人サイトだけでなく、特定の職種や業界に特化したサイト、企業側からアプローチできるダイレクトリクルーティング、SNSを活用したソーシャルリクルーティング、社員の紹介によるリファラル採用など、選択肢は多岐にわたります。
一つの手法に固執せず、ターゲットに応じて複数のチャネルを組み合わせることで、アプローチできる母集団が広がります。
各チャネルの効果測定を定期的に行い、費用対効果を見ながら改善を続ける姿勢が重要です。

【対策4】自社の強みを言語化し、採用ブランディングを推進
他社との差別化を図り、求職者から選ばれる企業になるためには、自社の魅力を明確に言語化し、一貫したメッセージとして発信する「採用ブランディング」が不可欠です。
給与や知名度では大手企業に及ばなくても、「社会課題の解決に貢献できる事業内容」「若手でも裁量権を持って挑戦できる環境」「独自の福利厚生制度」など、働く人にとっての価値は必ず存在します。
これらの強みを経営層から現場社員までが共有し、求人票、ウェブサイト、面接など、あらゆる場面で一貫して伝えることで、その魅力に共感する人材を採用できる可能性が高まります。
【対策5】選考プロセスを見直し、候補者体験の向上を
候補者が応募してから内定に至るまでの一連の接点における体験、すなわち「候補者体験」の質を高めることは、辞退率を低下させる上で極めて重要です。
まずは、書類選考から内定までの期間を可能な限り短縮し、選考の進捗をこまめに、かつ丁寧な言葉で連絡することを徹底します。
面接では、候補者の緊張を和らげる雰囲気づくりを心がけ、一方的に質問するだけでなく、候補者からの質問にも真摯に答える時間を十分に確保します。
すべての候補者に対して敬意を払う姿勢は、企業の評判を高め、たとえ今回縁がなくても将来的な応募や顧客につながる可能性があります。
【対策6】面接官のスキルを標準化するためのトレーニング
面接官の個人的な主観や経験だけに頼った面接は、評価にばらつきを生み、候補者に不公平な印象を与えかねません。
これを防ぐため、面接官向けのトレーニングを実施し、スキルを標準化することが有効です。
まず、自社が求める人物像や評価基準を明確に記したガイドラインを作成・共有します。
その上で、候補者の潜在能力や本質を見抜くための質問方法、コンプライアンス上問題のある質問の回避、自社の魅力を効果的に伝える方法などについて、ロールプレイングを交えながら研修を行います。
面接官全員が採用活動における自らの役割の重要性を認識することが、質の高い採用を実現します。
【中小企業向け】採用できない状況を乗り越えるためのヒント

採用にかけられる予算や人員が限られる中小企業にとって、人材獲得競争は特に厳しいものになりがちです。
しかし、大手企業と同じ戦略を取る必要はありません。
中小企業ならではの機動力や独自性を活かすことで、採用市場での存在感を高めることは可能です。
知名度の低さをカバーする情報発信や、柔軟な制度設計など、コストを抑えながら実践できるヒントを紹介します。
知名度の低さをカバーする情報発信を強化する
大手企業に比べて知名度が低いことは、中小企業の採用における共通の課題です。
このハンデを克服するためには、求人媒体の情報だけに頼らず、自社から積極的に情報を発信し続けることが重要になります。
自社のウェブサイトに採用特設ページを設けたり、公式ブログやSNSを活用したりして、事業への想い、働く社員の姿、社内のイベントといった日常的な風景を発信しましょう。
こうした地道な情報発信は、求職者が企業名を検索した際の安心材料となり、働くイメージを具体的に想起させ、興味を喚起するきっかけとなります。
限られたリソースを有効活用できる採用代行(RPO)を検討
採用業務に専任の担当者を置くことが難しい、あるいは他の業務と兼務していて手が回らないという中小企業にとって、採用代行(RPO)は有効な選択肢の一つです。
採用のプロフェッショナルに、母集団形成、応募者対応、面接日程の調整といった業務の一部、または全てを委託できます。
これにより、社内の担当者は面接や内定者フォローといったコア業務に集中できるだけでなく、専門的なノウハウを取り入れて採用活動全体の質を向上させることが可能です。
外部リソースを賢く活用することも、戦略的な採用活動の一環です。
柔軟な働き方や独自の福利厚生で魅力を高める
中小企業は大手企業にはない意思決定の速さや柔軟性を武器に魅力的な労働環境を構築できます。
例えばフルリモートワークやフレックスタイム制、週3日勤務といった多様な働き方をいち早く導入することは優秀な人材を引きつける強力なフックになります。
また高額な費用がかかる福利厚生でなくても書籍購入費の補助、資格取得支援制度、社員の誕生日を祝うユニークな制度など企業の文化や価値観を反映した独自の制度を設けることで他社との差別化を図ることが可能です。
こうした取り組みは従業員を大切にする企業姿勢の表れとして求職者にポジティブに映ります。
よくあるご質問
Q.応募は来るのですが、求める人材からの応募がありません。どうすればいいですか?
A.ターゲット層が利用していない求人媒体を使っているか、求人票の訴求内容がターゲットに響いていない可能性があります。まずは求める人物像を再定義し、その人物が魅力を感じるであろう仕事内容や働き方を具体的に記載しましょう。採用チャネルの見直しも有効です。
Q.給与や待遇面で他社に見劣りしてしまいます。
A.給与以外の魅力をアピールすることが重要です。事業の社会貢献性、個人の裁量が大きいこと、スキルアップできる環境、良好な人間関係など、自社ならではの強みを洗い出し、求人票や面接で伝えましょう。働き方の柔軟性なども有効なアピールポイントになります。
Q.内定を出しても、いつも辞退されてしまいます。
A.選考プロセスに問題がある可能性があります。選考スピードが遅くないか、面接官の対応は適切か、内定後のフォローは十分か、といった点を見直しましょう。内定者と定期的にコミュニケーションを取り、入社への不安を解消することも効果的です。
Q.採用にかけられるコストが限られています。効果的な方法はありますか?
A.コストを抑えるなら、ハローワークや自社サイトでの募集に加え、社員紹介(リファラル採用)の強化がおすすめです。また、SNSを活用した情報発信は、費用をかけずに企業の認知度を高めることができます。採用代行(RPO)も、部分的に利用すればコストを抑えつつ専門家の支援を受けられます。
Q.急な欠員で、すぐにでも人が欲しいのですが。
A.緊急性が高い場合は、人材紹介サービスや、特定の職種に特化した求人サイトの利用がスピーディーです。ただし、焦って採用するとミスマッチのリスクが高まります。最低限の採用基準は明確にし、妥協しないことが長期的な視点では重要です。派遣社員や業務委託の活用も一時的な解決策として検討できます。
まとめ
採用がうまくいかない状況は、単一の原因ではなく、求める人物像の不明確さ、求人情報の訴求力不足、採用手法のミスマッチ、不適切な選考プロセスといった複数の要因が絡み合って生じます。
この課題を解決するためには、まず自社の採用活動を客観的に分析し、どこに根本的な原因があるのかを突き止める必要があります。
その上で、求める人物像の再定義から始め、求人票の改善、採用チャネルの見直し、候補者体験の向上といった具体的な対策を、一つずつ着実に実行していくことが求められます。
採用活動は企業の将来を築くための重要な投資であり、継続的な見直しと改善が成功の鍵となります。
採用がうまくいかない原因の多くは、「伝え方」や「見せ方」にもあります。
Piicでは、企業の採用課題を丁寧にヒアリングし、
採用ピッチ資料・採用サイト・パンフレットなどのクリエイティブを通じて、“選ばれる理由”を可視化する支援を行っています。
採用活動を根本から見直し、
貴社らしい魅力が伝わる採用ブランディングを一緒に築きませんか?








