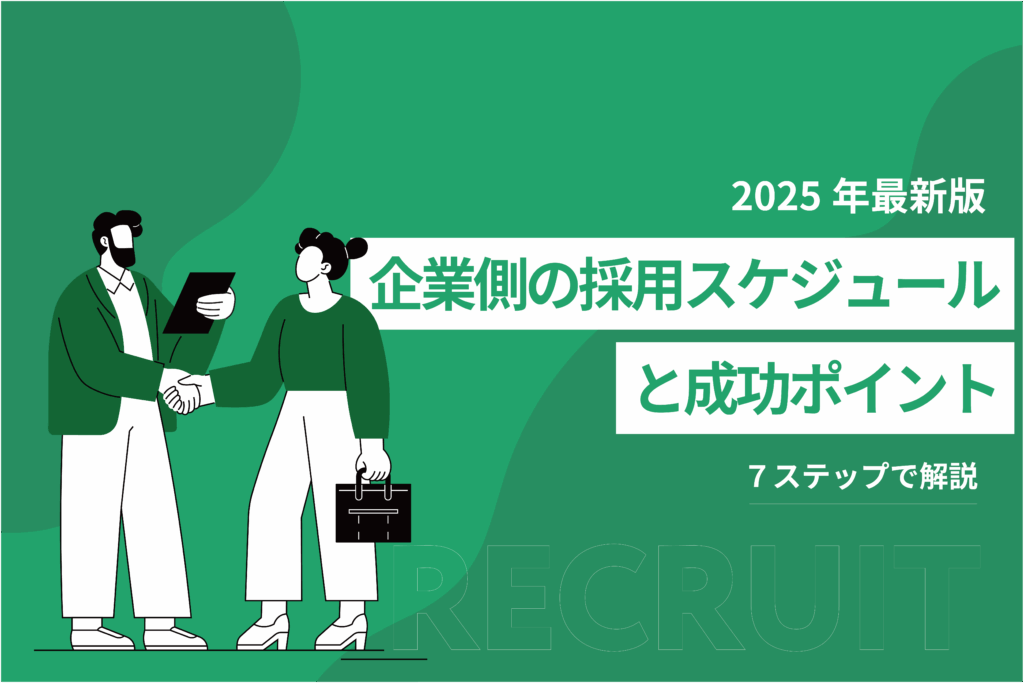
企業の採用活動は、事業の成長を支える重要な取り組みです。
しかし、計画的なスケジュールを立て、適切な進め方をしなければ、求める人材の確保は困難になります。
企業の採用活動を成功させるためには、全体の流れを把握し、各ステップで何をすべきかを明確にすることが不可欠です。
この記事では、採用活動の基本的な流れから具体的な進め方、成功確率を高めるポイントまで、7つのステップに沿って解説します。

Index
-
そもそも採用活動とは?企業が取り組む目的を再確認
-
始める前に知っておきたい新卒・中途採用のスケジュールと特徴
-
新卒採用の一般的なスケジュールと進め方
-
中途採用で一般的なスケジュールと進め方
-
企業が行う採用活動の具体的な7ステップ
-
ステップ1:事業計画と連動した採用計画を立てる
-
ステップ2:求める人物像を具体化するペルソナを設計する
-
ステップ3:ターゲットに響く最適な採用手法を選ぶ
-
ステップ4:企業の魅力を伝える求人募集を開始する
-
ステップ5:ミスマッチを防ぐ選考プロセスを設計し実行する
-
ステップ6:内定辞退を防ぐための丁寧なフォローを実施する
-
ステップ7:入社後の活躍を支援し定着率を高める
-
採用活動の成功確率を上げる3つの重要ポイント
-
自社の強みとアピールポイントを客観的に分析
-
候補者体験を意識したコミュニケーションを
-
採用活動の成果を定期的に分析→改善を繰り返す
-
知っておきたい採用活動の最新トレンド
-
SNSを活用したダイレクトリクルーティング
-
社員紹介で質の高い人材を確保するリファラル採用
-
自社メディアで発信するオウンドメディアリクルーティング
-
相互理解を深めるカジュアル面談の導入
-
よくあるご質問
-
Q1:採用活動は何から始めるべきですか?
-
Q2:採用コストはどれくらいかかりますか?
-
Q3:面接で候補者を見極めるポイントは?
-
Q4:内定辞退を防ぐ効果的な方法はありますか?
-
Q5:採用がうまくいかない場合、どうすればいいですか?
-
まとめ
そもそも採用活動とは?企業が取り組む目的を再確認

採用活動とは、企業が事業計画を達成するために必要な人材を確保する一連の活動を指します。
その目的は、単に欠員を補充するだけではありません。
新規事業の立ち上げや事業拡大に伴う増員、組織の若返り、新たなスキルの導入など、企業の成長戦略と密接に結びついています。
採用活動の目的を明確にすることで、どのような人材が必要かという人物像が具体化し、採用基準も定まります。
成功する採用活動の第一歩は、この目的設定にあります。
始める前に知っておきたい新卒・中途採用のスケジュールと特徴

採用活動を始めるにあたり、新卒採用と中途採用のスケジュールや特徴の違いを理解しておくことが重要です。
特に新卒採用は、近年の就職活動の早期化という変化が見られ、インターンシップなどを通じた学生との接触時期が早まる傾向にあります。
一方で、中途採用は通年で行われることが多く、企業の状況に応じて柔軟な対応が求められます。
それぞれの特性を把握し、自社に合った採用計画を立てることが、効率的な採用活動につながります。
新卒採用の一般的なスケジュールと進め方
新卒採用のスケジュールは、政府からの「採用活動に関する要請」によって大まかなルールが定められています。
一般的に、広報活動が解禁されるのは大学3年生の3月1日であり、この時期から会社説明会などが本格化します。
そして、採用選考活動の解禁は大学4年生の6月1日とされており、この日から面接や筆記試験が始まります。
内定は10月1日以降に出すのが正式なルールですが、実際には早期化の傾向が強く、6月1日に内々定を出す企業も少なくありません。
採用活動がいつまで続くかは企業によって異なりますが、多くの企業は秋頃までに採用活動を終えることを目指します。
この要請はあくまで指針であり、罰則はないため、企業は独自のスケジュールで動くこともあります。
中途採用で一般的なスケジュールと進め方
中途採用は、新卒採用と異なり、特定の時期に限定されず通年で実施されるのが一般的です。
企業の事業計画や欠員状況に応じて、必要なタイミングで募集が開始されます。
スケジュールは募集職種や採用人数によって変動しますが、一般的には応募から内定まで1ヶ月から3ヶ月程度で進むことが多いです。
特に中小企業では、経営層との距離が近く、迅速な意思決定が可能なため、選考プロセスが短期間で完結する傾向にあります。
進め方としては、まず募集要件を固め、求人媒体の選定、書類選考、複数回の面接を経て内定という流れが基本です。
候補者の転職活動の状況に合わせて、柔軟に選考スケジュールを調整することも求められます。
企業が行う採用活動の具体的な7ステップ
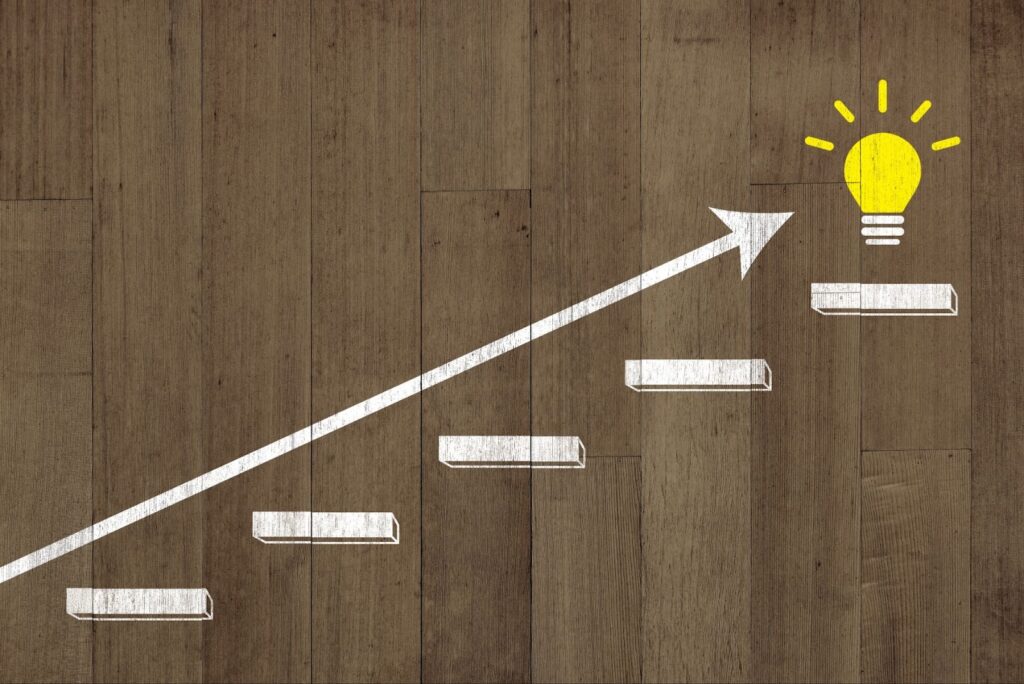
企業の採用活動は、行き当たりばったりで進めると失敗に終わる可能性が高まります。
成功のためには、計画から入社後のフォローまで、一貫した流れを意識することが重要です。
ここでは、採用活動を7つの具体的なステップに分解して解説します。
各段階で発生しがちな採用活動の課題を理解し、一つひとつのプロセスを丁寧に進めることで、自社にマッチした優秀な人材の獲得につながります。
ステップ1:事業計画と連動した採用計画を立てる
採用活動を始めるにあたり、最初に行うべきは事業計画と連動した採用計画の立案です。
会社の将来的なビジョンや目標達成のために、どの部門で、どのようなスキルを持つ人材が、いつまでに何人必要なのかを明確にします。
この段階で、採用手法の選定や全体のスケジュール、一人当たりの採用にかけられる費用なども概算で設定しておきます。
事業の成長戦略と人材戦略を紐づけることで、採用活動の目的が明確になり、その後のプロセスにおける判断基準も定まります。
場当たり的な採用を避け、企業の成長に直接貢献する人材を獲得するための基盤となる重要なステップです。
ステップ2:求める人物像を具体化するペルソナを設計する
採用計画で定めた人材要件を、より具体的に掘り下げて「ペルソナ」として設計します。
ペルソナとは、求める人物像をスキルや経験といった定量的な要素だけでなく、価値観、性格、キャリア志向などの内面的な要素も含めて、一人の架空の人物として詳細に設定する手法です。
これにより、採用に関わるメンバー間での人物像に対する認識のズレを防ぎ、評価基準を統一することができます。
また、ペルソナが明確になることで、求人票のキャッチコピーや仕事内容の説明文、面接での質問内容なども、ターゲットに響くものを作成しやすくなり、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。
ステップ3:ターゲットに響く最適な採用手法を選ぶ
設計したペルソナに効果的にアプローチするため、最適な採用手法を選択します。
求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、多種多様な手法が存在し、それぞれに特徴やコスト、かかる手間が異なります。
例えば、幅広い層にアプローチしたい場合は求人広告、専門性の高い人材を求めるなら人材紹介やダイレクトリクルーティングが有効です。
自社の採用体制や予算、かけられる時間を考慮しながら、ターゲットとなる人材が最も多く利用していると考えられる手法を選ぶことが重要です。
複数の手法を組み合わせることで、より多くの候補者と出会う機会を創出できます。

ステップ4:企業の魅力を伝える求人募集を開始する
採用手法が決まったら、実際に求人募集を開始します。
求人票を作成する際は、業務内容や応募条件といった基本的な情報だけでなく、企業のビジョンや社風、働く環境、仕事のやりがいといった、候補者が魅力を感じるであろう情報を具体的に盛り込むことが重要です。
ステップ2で設計したペルソナが、どのような情報に関心を持つかを意識して、言葉を選ぶ必要があります。
また、企業の採用サイトやブログ、SNSなどを活用し、社員インタビューや一日の仕事の流れを紹介するなど、求人票だけでは伝わらないリアルな情報を発信することも、応募意欲を高める上で効果的です。
ステップ5:ミスマッチを防ぐ選考プロセスを設計し実行する
書類選考や面接といった選考プロセスは、候補者のスキルや経験、人柄を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝え、相互理解を深めるための重要な場です。
ミスマッチを防ぐためには、評価基準を明確にし、面接官によって評価がブレないように事前にトレーニングを行うことが不可欠です。
複数の面接官で多角的に評価したり、候補者の過去の行動に基づいて質問する「構造化面接」を取り入れたりすることで、より客観的な評価が可能になります。
候補者がリラックスして自分らしさを発揮できるよう、圧迫感のない雰囲気作りを心掛けることも、本音を引き出す上で重要です。
ステップ6:内定辞退を防ぐための丁寧なフォローを実施する
内定を出した後も、採用活動は終わりではありません。
内定から入社までの期間、候補者の入社意欲を維持し、内定辞退を防ぐためのフォローが重要になります。
定期的な連絡はもちろんのこと、社員との座談会やランチ会、社内イベントへの招待などを企画し、入社後の働くイメージを具体的に持ってもらう機会を設けることが効果的です。
フォローにおける注意点として、企業側から一方的に情報を提供するだけでなく、内定者が抱える不安や疑問に耳を傾け、丁寧に解消していく双方向のコミュニケーションが求められます。
誠実な対応を続けることが、入社への安心感につながります。
ステップ7:入社後の活躍を支援し定着率を高める
採用活動の最終的な成功は、採用した人材が入社後に活躍し、組織に定着することによって測られます。
入社後の立ち上がりをスムーズにするため、オリエンテーションや研修といったオンボーディングプログラムを充実させることが重要です。
また、配属先の部署では、OJT担当者やメンターを配置し、業務面と精神面の両方から新入社員をサポートする体制を整えます。
入社後の定着率が低い場合は、採用ミスマッチや受け入れ体制、社内環境などに何らかの課題があると考えられます。
定期的な面談を通じて社員の声を聞き、組織全体の課題として改善に取り組む姿勢が求められます。
採用活動の成功確率を上げる3つの重要ポイント

採用市場の競争が激しくなる中、計画通りに採用活動を進めるだけでは、求める人材を確保することが難しくなっています。
他社との差別化を図り、候補者から選ばれる企業になるためには、戦略的な視点が欠かせません。
ここでは、採用活動の成功確率を格段に上げるために押さえておきたい3つの重要ポイントを紹介します。
自社の活動を振り返り、改善のヒントとして活用してください。
自社の強みとアピールポイントを客観的に分析
候補者から選ばれる企業になるためには、まず自社の魅力を客観的に把握し、言語化することが不可欠です。
給与や福利厚生といった待遇面はもちろん、事業の社会貢献性、独自の技術力、風通しの良い社風、成長できる環境、仕事のやりがいなど、他社にはない強みを多角的に洗い出します。
経営層だけでなく、実際に現場で働く社員にヒアリングを行い、「働きがい」や「入社して良かった点」などを集めるのも有効です。
これらの強みを求人票や面接の場で具体的に伝えることで、候補者の共感を呼び、志望度を高めることができます。
候補者体験を意識したコミュニケーションを
候補者体験とは、候補者が求人を知ってから応募、選考、内定に至るまでの一連の接点で得る体験の総称です。
迅速で丁寧なメールの返信、分かりやすい選考案内の送付、高圧的ではない面接の雰囲気作りなど、候補者の立場に立ったコミュニケーションを心掛けることが重要です。
たとえ採用に至らなかったとしても、良い候補者体験を提供できれば、企業の評判が高まり、将来的に自社の製品やサービスの顧客になる可能性もあります。
候補者一人ひとりを大切にする姿勢が、企業のブランドイメージを向上させます。
採用活動の成果を定期的に分析→改善を繰り返す
採用活動は一度計画を立てて実行したら終わりではありません。
応募数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率といった各選考段階のデータを定期的に収集・分析し、どこにボトルネックがあるのかを把握することが重要です。
例えば、応募数が目標に達していない場合は、求人媒体や募集要項の見直しが必要です。
内定承諾率が低い場合は、選考過程での魅力付けや内定後のフォローに改善の余地があるかもしれません。
データに基づいた客観的な振り返りを行い、次の採用活動に向けて改善を繰り返していくサイクルを回すことが、採用力の強化につながります。

知っておきたい採用活動の最新トレンド

労働人口の減少や働き方の多様化を背景に、企業の採用活動の手法も大きく変化しています。
従来の求人広告に頼るだけでは、優秀な人材を獲得することが困難になりつつあります。
SNSの活用や社員紹介など、より能動的で多角的なアプローチが求められています。
ここでは、採用競争を勝ち抜くために知っておきたい採用活動の最新トレンドを紹介します。
これらの新しい流れを理解し、自社の戦略に組み込むことで、採用の可能性を広げることができます。
SNSを活用したダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業から候補者に直接アプローチする攻めの採用手法です。
特に近年では、ビジネス特化型SNSなどを活用し、自社が求めるスキルや経歴を持つ人材を検索し、個別にメッセージを送る企業が増えています。
この手法の最大のメリットは、転職を積極的に考えていない「転職潜在層」にもアプローチできる点です。
企業の魅力やポジションのやりがいを直接伝えることで、候補者の興味を引きつけ、新たなキャリアの選択肢として検討してもらうきっかけを作ります。
SNSを通じて候補者の人柄や価値観に触れやすいのも特徴です。
社員紹介で質の高い人材を確保するリファラル採用
リファラル採用は、自社の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法です。
社員は会社の文化や働き方を深く理解しているため、紹介される人材は企業とのマッチ度が高く、入社後の定着率も高い傾向にあります。
また、求人広告費や人材紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。
制度を成功させるには、社員が積極的に協力したくなるような仕組み作りが重要で、紹介プロセスを簡略化したり、インセンティブ制度を設けたりするなどの工夫が求められます。
ただし、不採用時の対応など、紹介者と候補者の人間関係に配慮する手間も必要です。
自社メディアで発信するオウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングとは、自社の採用サイトやブログ、公式SNSアカウントなどを「自社メディア」と位置づけ、積極的に情報発信を行うことで採用につなげる手法です。
社員インタビューやプロジェクト紹介、働く環境の様子などをコンテンツとして発信し、求人票だけでは伝わらない企業のリアルな魅力を伝えます。
これにより、企業の文化や価値観に共感する候補者からの応募を促進し、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。
外部媒体への依存度を下げ、中長期的には採用費用を抑制できる可能性もあります。
相互理解を深めるカジュアル面談の導入
カジュアル面談は、本格的な選考に進む前に、企業と候補者がお互いの理解を深める目的で実施される面談です。
合否を判断する面接とは異なり、選考要素を排し、リラックスした雰囲気で情報交換を行います。
候補者は企業の事業内容や社風について気軽に質問でき、企業側も候補者の人柄やキャリアに対する考え方をより深く知ることができます。
候補者の応募へのハードルを下げ、自社への興味を高める効果があります。
特に、転職をまだ具体的に考えていない潜在層へのアプローチとして有効であり、ミスマッチの防止にもつながる手法です。
よくあるご質問
Q1:採用活動は何から始めるべきですか?
A1:まずは自社の事業計画を確認し、それに基づいて「いつまでに、どのような人材が、何人必要か」という採用計画を立てることから始めます。
目的を明確にすることが最初のステップです。
Q2:採用コストはどれくらいかかりますか?
A2:採用コストは、利用する採用手法によって大きく異なります。
求人広告の掲載料、人材紹介会社への成功報酬、採用管理システムの利用料などが主な費用です。
一人当たりの採用単価を算出し、予算を設定することが一般的です。
Q3:面接で候補者を見極めるポイントは?
A3:スキルや経験だけでなく、自社の企業文化に合うか(カルチャーフィット)、入社意欲は高いか、といった点も重要です。
過去の行動事例を聞く質問を通じて、その人の価値観や行動特性を見極めることが有効です。
Q4:内定辞退を防ぐ効果的な方法はありますか?
A4:内定を出した後も、定期的に連絡を取ったり、社員との懇親会を設けたりするなど、候補者との接点を持ち続けることが効果的です。
候補者の不安や疑問に寄り添い、入社への安心感を醸成します。
Q5:採用がうまくいかない場合、どうすればいいですか?
A5:まずは採用活動のどのプロセスに課題があるのかを分析します。
「応募が集まらない」「選考通過率が低い」「内定辞退が多い」など、課題に応じて求人内容や選考方法、内定者フォローなどを見直す必要があります。
まとめ
企業の採用活動は、事業計画に連動した採用計画の策定から始まり、求める人物像の具体化、採用手法の選定、募集、選考、内定者フォロー、そして入社後の定着支援まで、一連のプロセスで構成されます。
各ステップを着実に実行するとともに、自社の強みを客観的に分析し、候補者体験を向上させ、活動の成果をデータで振り返り改善を続けることが、成功の確率を高めます。
近年のトレンドも取り入れながら、自社に合った戦略的な採用活動を展開していくことが求められます。
採用の成功は、計画や戦略だけでなく、「どう伝えるか」にも大きく左右されます。
Piicでは、採用サイトやピッチ資料、動画などの採用クリエイティブを通じて、企業の魅力を“言語化・可視化”するお手伝いをしています。
自社らしさを的確に伝え、共感でつながる採用を実現しませんか?








