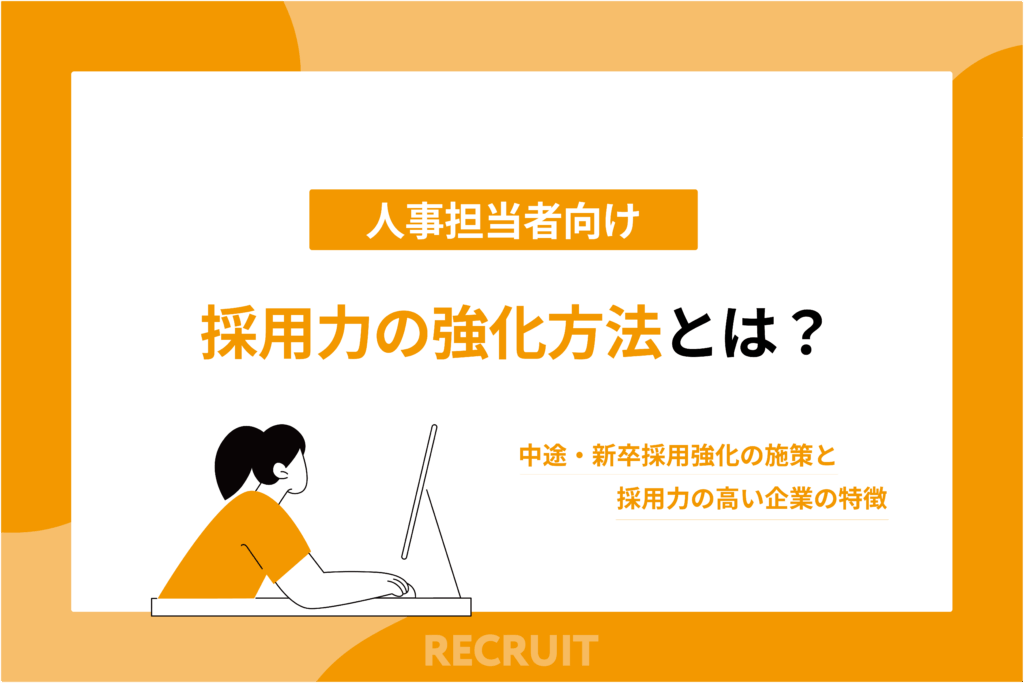
採用を強化するとは、単に求人募集の数を増やすことではありません。
自社の成長戦略に合致した優秀な人材を引きつけ、採用し、入社後も定着・活躍してもらうための一連の取り組み全体を指します。
本記事では、採用力の強化が必要な理由から、採用力が高い企業の特徴、そして明日から実践できる具体的な施策までを、新卒・中途採用それぞれの視点も交えて解説します。

Index
-
採用強化とは?企業が取り組むべき理由
-
そもそも「採用強化」が意味すること
-
なぜ今、採用強化の重要性が高まっているのか
-
あなたの会社は大丈夫?採用力の高い企業と低い企業の違い
-
【成功の秘訣】採用力が高い企業に共通する5つの特徴
-
【課題の発見】採用がうまくいかない企業に見られる4つの傾向
-
明日から始める!採用力を強化する具体的なステップ
-
【全社で取り組むべき】採用強化の基本施策5選
-
【新卒採用向け】学生に響くアプローチ方法
-
【中途採用向け】即戦力人材を獲得する戦略
-
採用成功の鍵【入社後のリテンション施策】
-
内定辞退を防ぐためのフォローアップ体制を構築する
-
新入社員が早期に活躍できるオンボーディングを充実させる
-
社員のキャリアプランを明確にし、成長を支援する
-
よくあるご質問
-
Q1:採用コストをかけずに採用力を強化する方法はありますか?
-
Q3:地方の中小企業で、なかなか応募が集まりません。
-
Q4:面接での見極めがうまくいきません。何かコツはありますか?
-
Q5:内定辞退が多くて困っています。
-
まとめ
採用強化とは?企業が取り組むべき理由

採用力とは、企業が求める人材を惹きつけ、獲得する総合的な能力のことです。
労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、企業の持続的な成長には優秀な人材の確保が不可欠です。
そのため、多くの企業が経営課題として採用強化という取り組みの重要性を認識し、その向上に努めています。
自社の魅力を高め、採用市場での競争力を維持することが、将来の発展につながります。
そもそも「採用強化」が意味すること
採用強化とは、量的な拡大だけでなく、採用活動の「質」を高めることを意味します。
具体的には、自社の事業戦略やカルチャーにマッチする人材を的確に見極め、採用のミスマッチを減らすことが重要です。
そのためには、求める人物像の解像度を上げ、選考プロセスを改善し、候補者に対して自社の魅力を正しく伝える必要があります。
採用強化を図ることは、採用活動のあらゆる側面を見直し、より戦略的に人材を獲得していくための総合的な取り組みといえます。
なぜ今、採用強化の重要性が高まっているのか
現在、多くの企業で採用強化の重要性が増しています。
その背景には、少子高齢化に伴う労働力人口の減少があり、優秀な人材の獲得競争が激化していることが挙げられます。
また、働き方の価値観が多様化し、転職が当たり前の選択肢となったことで、企業は常に人材流出のリスクにも備えなければなりません。
さらに、DX推進など事業環境の変化に対応できる専門人材の需要も高まっています。
こうした状況下で企業が成長を続けるためには、計画的で戦略的な採用活動が不可欠です。
あなたの会社は大丈夫?採用力の高い企業と低い企業の違い

採用活動の結果は、企業の採用力によって大きく左右されます。
採用力の高い企業は、優秀な人材を惹きつけて事業を成長させる好循環を生み出す一方、採用力の低い企業は人材不足に悩み、成長が鈍化する可能性があります。
両者の違いは、採用戦略の有無や候補者への向き合い方など、様々な側面に表れます。
自社の採用活動を客観的に見つめ直し、課題を特定することが、採用力強化の第一歩です。
【成功の秘訣】採用力が高い企業に共通する5つの特徴
採用力が高い企業には、いくつかの共通点が見られます。
まず、採用したい人物像が全社で具体的に共有されています。
その上で、自社の魅力を効果的に伝え、ターゲットに合った採用手法を選択できています。
また、候補者体験を重視したスムーズな選考プロセスが構築されており、採用をゴールとせず、入社後の定着と活躍まで見据えた支援体制を整えています。
これらの要素が有機的に連携することで、企業の採用力は総合的に高まります。
採用ターゲットとなる人物像が具体的に描けている
採用力が高い企業は、どのような人材を求めているのかが非常に明確です。
必要なスキルや経験はもちろんのこと、価値観や人柄、キャリア志向といったパーソナリティまで含めた具体的な人物像(ペルソナ)を設定しています。
このペルソナが社内で共有されているため、募集要項の作成から面接での評価基準まで一貫性が保たれ、採用のミスマッチが起こりにくくなります。
精度の高い見極めが可能になり、自社に本当にマッチした人材の採用につながります。
自社の魅力を効果的にアピールできている
自社の強みや働く魅力を正しく理解し、ターゲットに響く言葉で伝えられていることも成功企業の共通点です。
給与や待遇といった条件面だけでなく、事業の社会貢献性、独自の社風、社員の成長環境、ユニークな福利厚生など、他社との差別化ポイントを明確にしています。
採用ホームページやSNS、求人媒体など、様々なチャネルで一貫したメッセージを発信し、候補者の共感を呼ぶ情報訴求を行うことで、「この会社で働きたい」という動機形成を促しています。
候補者に合わせた最適な採用手法を選択している
画一的な方法に固執せず、採用したいターゲットに応じて最適な手法を柔軟に使い分けている点も特徴です。
例えば、若手層ならSNSや就活イベント、専門職ならダイレクトリクルーティングや人材紹介、というように、ターゲット人材がどこにいるのかを分析し、効果的なアプローチを選択します。
これにより、効率的に母集団を形成し、質の高い候補者と出会う確率を高めています。
常に新しい採用手法の情報収集を怠らず、自社に合った方法を模索し続けています。
スムーズで丁寧な選考プロセスを構築している
採用力の高い企業は、候補者体験を非常に重視しています。
応募から内定まで、迅速で丁寧なコミュニケーションを心がけ、候補者にストレスを感じさせません。
面接では候補者の能力や人柄を引き出すことを主眼に置き、一方的な質問ではなく対話形式で進めます。
選考プロセス全体を通じて、候補者一人ひとりに誠実に向き合う姿勢を示すことが、企業のイメージアップと入社意欲の向上につながることを理解して採用活動を行っています。
入社後の活躍まで見据えた定着支援を行っている
採用をゴールではなく、スタート地点と捉えていることも重要な特徴です。
内定者フォローに始まり、入社後のオンボーディングプログラムや研修制度を充実させることで、新しい仲間がスムーズに組織に溶け込み、早期に実力を発揮できる環境を整えています。
定期的な面談やキャリア支援を通じて、社員の長期的な成長をサポートする姿勢が、エンゲージメントを高め、人材の定着に結びつきます。
結果的に、これが企業の持続的な成長力の源泉となります。
【課題の発見】採用がうまくいかない企業に見られる4つの傾向
一方で、採用活動が難航している企業には、いくつかの共通した傾向が見受けられます。
例えば、求める人材の理想が高すぎたり、そもそも採用活動に十分なリソースを割けていなかったりするケースです。
また、人事と現場の連携不足によるミスマッチや、候補者への情報発信が不十分で自社の魅力が伝わっていないことも、採用がうまくいかない原因となります。
これらの課題を認識することが、採用活動の改善に向けた第一歩です。
求めるスキルや経験のハードルが高すぎる
特に専門性の高い職種や即戦力を求める中途の採用において、市場にほとんど存在しない完璧な経歴を持つ人材を追い求めてしまう傾向があります。
その結果、応募者が全く集まらなかったり、書類選考でほとんどの候補者を不合格にしてしまったりします。
採用要件を「必須条件」と「歓迎条件」に分け、優先順位を整理することが重要です。
また、全ての要件を満たしていなくても、ポテンシャルを評価し、入社後の育成でカバーするという視点も必要になります。
採用活動に割ける人手や時間が不足している
特に中小企業や地方の企業では、採用担当者が他の業務と兼務しているケースが多く、採用活動に十分な時間を確保できないという課題があります。
その結果、応募者への対応が遅れたり、スカウト活動が中途半端になったりして、機会損失を招いてしまいます。
候補者からの問い合わせへの返信が遅れることは、企業イメージの低下にもつながりかねません。
限られたリソースの中で成果を出すためには、業務の優先順位付けや、採用管理ツール、採用代行サービスの活用を検討することも有効です。
現場と人事の連携が取れずミスマッチが起きている
人事が主導で採用活動を進める中で、実際に人材を受け入れる現場部門とのコミュニケーションが不足しているケースがあります。
人事が「良い人材だ」と判断して採用しても、現場が求めるスキルや人物像とズレていると、入社後に本人が活躍できなかったり、早期離職につながったりするミスマッチが発生します。
採用計画の初期段階から現場の責任者を巻き込み、求める人材要件について具体的なすり合わせを徹底することが、ミスマッチ防止の鍵となります。
候補者への情報発信が不足している
求人票に記載されている情報が、業務内容や応募資格といった基本的な項目だけで、企業の魅力や社風、働きがいなどが伝わらないケースです。
候補者は、給与などの条件面だけでなく、入社後に自分がどのように働けるのかを具体的にイメージできる情報を求めています。
採用サイトやブログ、SNSなどを活用し、社員インタビューやオフィスの様子、独自の制度などを積極的に発信しないと、数ある求人の中に埋もれてしまいます。
職務経歴の書式が複雑すぎるなど、応募のハードルが高いことも原因の一つです。
明日から始める!採用力を強化する具体的なステップ
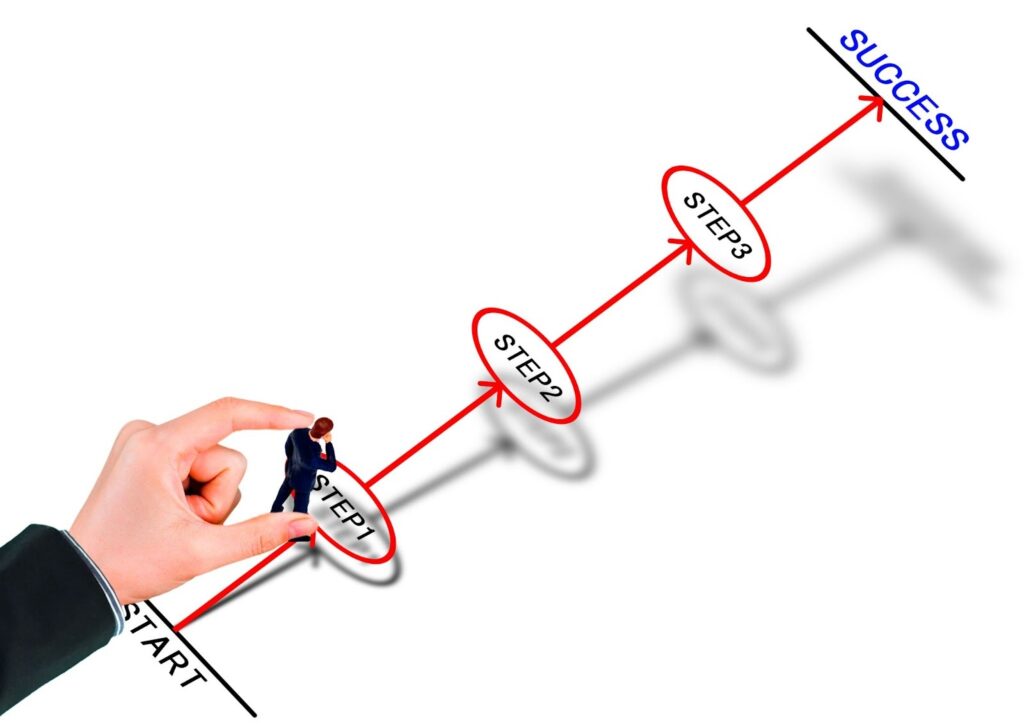
自社の採用における課題が見えてきたら、次はその解決に向けた具体的な行動に移す段階です。
採用力の強化は、一部の担当者だけでは成し遂げられません。
全社的な協力体制のもと、基本的な施策から着実に実行していくことが重要です。
ここでは、企業全体で取り組むべき基本の施策に加え、新卒・中途採用それぞれに特化したアプローチ方法を紹介します。
自社の状況に合わせて、取り入れやすい策から始めてみましょう。
【全社で取り組むべき】採用強化の基本施策5選
採用力を高めるためには、まず土台となる基本的な施策を全社で推進することが不可欠です。
具体的には、採用したい人物像と基準を明確にし、社内外に自社の魅力を発信する採用ブランディングを実践します。
同時に、働きがいのある職場環境を整備し、採用チャネルを多様化して候補者との接点を増やします。
そして、候補者体験を重視した選考プロセスへと見直す、これら5つの施策が基本となります。
これらを総合的に実行することで、採用活動の質は大きく向上します。
採用したい人物像と採用基準を明確にする
採用活動を始める前に、まず「どのような人材を、なぜ採用するのか」を明確に定義することが最も重要です。
経営層や現場部門と十分に議論を重ね、事業計画と連動した採用計画を立てます。
必要なスキルや経験だけでなく、自社の企業文化や価値観に共感してくれるかといった観点も盛り込み、具体的な人物像(ペルソナ)として言語化します。
この明確化された基準が、その後の募集、選考、最終判断の全てのプロセスにおいて、一貫した軸となります。
「ここで働きたい」と思わせる採用ブランディングを実践する
候補者から「選ばれる企業」になるための活動が採用ブランディングです。
自社のビジョンや事業の独自性、社員の働きがい、社会への貢献などを、一貫性のある魅力的なメッセージとして発信し続けます。
採用サイトのコンテンツを充実させたり、社員のリアルな声をブログやSNSで伝えたりすることで、候補者は企業文化を深く理解し、入社後の自分をイメージしやすくなります。
この取り組みは、企業のファンを増やし、応募の動機形成を強く後押しします。
働きがいのある職場環境と労働条件を整備する
優れた採用ブランディングを行っても、実態が伴わなければ意味がありません。
社員が安心して長く働ける環境を整えることが、採用力の根幹を支えます。
公正な評価制度や納得感のある給与体系、柔軟な働き方を可能にする制度(リモートワークやフレックスタイム制など)、キャリア開発を支援する研修プログラムの整備が求められます。
魅力的な職場環境は、現職社員の満足度向上だけでなく、求職者に対する強力なアピールポイントにもなります。
採用チャネルを多様化し、最適な手法を見つける
一つの採用手法に固執せず、複数のチャネルを組み合わせて活用することで、より多くの優秀な人材にアプローチできます。
従来の求人広告に加え、企業側から直接アプローチするダイレクトリクルーティング、社員の紹介で採用するリファラル採用、SNSを活用したソーシャルリクルーティングなど、手法は多様化しています。
それぞれのチャネルの特性を理解し、採用したい職種やターゲット層に合わせて最適な組み合わせを見つけ出す戦略的な視点が重要です。
候補者体験を向上させる選考プロセスへ見直す
選考過程における候補者の体験は、企業の印象を大きく左右します。
応募後の連絡を迅速に行い、面接日程を柔軟に調整するなど、候補者一人ひとりへの丁寧な対応が求められます。
面接では、候補者の能力を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝え、候補者の疑問や不安を解消する場と捉えるべきです。
こうした候補者目線の取り組みを積み重ねることが、企業の評判を高め、最終的な入社承諾率の向上に結びつきます。
【新卒採用向け】学生に響くアプローチ方法
新卒採用では、社会人経験のない学生に対して、仕事の面白さや自社の魅力をいかに具体的に伝えられるかが成功の鍵を握ります。
キャリアに対する考え方が固まっていない学生も多いため、早期から接点を持ち、企業理解を深めてもらうための工夫が求められます。
一方的な情報提供ではなく、学生が参加し、体験できるような双方向のコミュニケーションを意識したアプローチが効果的です。
仕事の魅力をリアルに伝えるインターンシップを企画する
インターンシップは、学生が企業や仕事を深く理解するための絶好の機会です。
単なる会社説明に終始するのではなく、実際の業務に近い課題に取り組んでもらったり、プロジェクトに参加してもらったりする体験型のプログラムが有効です。
現場で働く社員との座談会を設け、仕事のやりがいだけでなく、大変な部分も正直に伝えることで、学生は入社後の働き方をリアルに想像できます。
仕事の魅力の訴求と同時に、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
大学のキャリアセンターや教授との連携を深める
特に専門的な知識を持つ学生や、地方の優秀な学生を採用したい場合に有効なのが、大学との連携です。
キャリアセンターの担当者や、関連分野を専門とする教授と日頃から良好な関係を築き、自社の事業内容や求める人物像を深く理解してもらうことが重要です。
信頼関係が構築できれば、自社にマッチしそうな学生を推薦してもらえたり、学内での説明会の開催に協力してもらえたりする可能性が高まります。
地道な情報提供や訪問を続けることが、連携強化につながります。
【中途採用向け】即戦力人材を獲得する戦略
即戦力を求める中途採用では、候補者が持つスキルや経験をいかに自社で活かせるかを具体的に示すことが重要になります。
転職市場で積極的に活動している層だけでなく、現職に満足しているものの、より良い機会があれば転職を考える「転職潜在層」へのアプローチも欠かせません。
候補者のこれまでのキャリアを尊重し、正当に評価する姿勢と、入社後の活躍を具体的にイメージさせる情報提供が、採用成功の鍵を握ります。
転職潜在層にも直接アプローチできる手法を活用する
優れたスキルを持つ人材ほど、積極的に転職活動をしていない傾向があります。
こうした転職潜在層にアプローチするには、企業側から働きかける「攻め」の採用手法が有効です。
その代表的な方法が、スカウトサービスや転職SNSなどを活用したダイレクトリクルーティングです。
自社の要件に合う人材を探し出し、個別にメッセージを送ることで、公募では出会えない優秀な人材と接点を持つことができます。
自社の魅力を的確に伝え、興味を引き出すことが重要です。
これまでの経験やスキルを正当に評価する仕組みを整える
中途採用の候補者は、自身のキャリアやスキルが次の職場でどのように評価され、活かせるのかを重視しています。
そのため、選考過程では、候補者の実績を深く掘り下げてヒアリングし、その経験が自社のどの部分で貢献できるのかを具体的にフィードバックすることが有効です。
また、これまでの経験や能力を正当に処遇へ反映できるような、透明性の高い給与テーブルや等級制度を整備しておくことも、優秀な人材を引きつける上で不可欠です。
的確な見極めと評価が、候補者の信頼獲得につながります。
採用成功の鍵【入社後のリテンション施策】

採用活動の真の成功は、採用した人材が入社後に組織に定着し、能力を最大限に発揮して活躍することによって測られます。
多大なコストと時間をかけて採用した人材が早期に離職してしまうことは、企業にとって大きな損失です。
採用力には、内定辞退を防ぐ取り組みから、入社後のスムーズな立ち上がりを支援するオンボーディング、そして長期的なキャリア形成を支える仕組みづくりまで、リテンション(人材定着)の視点が不可欠です。
内定辞退を防ぐためのフォローアップ体制を構築する
内定を出してから入社までの期間は、候補者が他社と比較検討したり、入社への不安を感じたりしやすい時期です。
この期間に何のフォローもしないと、内定辞退につながるリスクが高まります。
これを防ぐためには、定期的な連絡はもちろん、内定者向けの懇親会や現場社員との面談の機会を設けるといった施策が有効です。
企業とのつながりを維持し、入社を心待ちにしているという歓迎の意を示すことで、候補者の入社意欲を高め、不安を払拭します。
新入社員が早期に活躍できるオンボーディングを充実させる
オンボーディングとは、新入社員が組織の一員としてスムーズに定着し、早期にパフォーマンスを発揮できるよう支援する一連のプロセスのことです。
入社時のオリエンテーションだけでなく、数ヶ月にわたって計画的に実施されます。
業務スキルの習得を支援するOJTはもちろん、部署の垣根を越えた交流の機会を設けたり、メンター制度を導入して精神的なサポートを行ったりすることで、新入社員の孤立を防ぎます。
充実したオンボーディングは、人材の早期戦力化と定着率向上に直結します。
社員のキャリアプランを明確にし、成長を支援する
社員が「この会社で働き続けたい」と感じるためには、自身の成長を実感できる環境が重要です。
企業は、社員一人ひとりが将来のキャリアプランを描き、その実現に向けてステップアップしていけるような仕組みを整える必要があります。
定期的な1on1ミーティングを通じて上司とキャリアについて対話する機会を設けたり、スキルアップのための研修制度や資格取得支援制度を充実させたりするなどの取り組みが考えられます。
社員の成長意欲に応えることが、エンゲージメントの向上につながります。
よくあるご質問
Q1:採用コストをかけずに採用力を強化する方法はありますか?
A1:はい、あります。まずは社員紹介制度(リファラル採用)を活性化させることや、自社のウェブサイトやSNSでの情報発信を強化することから始められます。これらは比較的低コストで実施でき、ミスマッチの少ない採用や企業の魅力発信につながります。
Q2:採用担当者が一人しかいません。何から手をつけるべきですか?
A2:まずは「採用したい人物像(ペルソナ)」を明確にすることから始めるのがおすすめです。ターゲットが定まれば、どの採用手法を選ぶべきか、どのようなメッセージでアピールすべきかが絞り込まれ、その後の活動が効率的になります。
Q3:地方の中小企業で、なかなか応募が集まりません。
A3:地域に特化した求人媒体の活用や、地元の大学・専門学校との連携強化が有効です。また、リモートワーク制度を導入して勤務地の制約をなくし、全国から応募できるようにすることも、母集団形成の有効な一手です。
Q4:面接での見極めがうまくいきません。何かコツはありますか?
A4:事前に評価項目と質問内容を決めておく「構造化面接」を導入すると、面接官による評価のブレを減らせます。また、過去の行動事実について深掘りする質問(「〇〇の時、具体的にどう行動しましたか?」など)をすることで、候補者の能力や人柄をより客観的に評価しやすくなります。
Q5:内定辞退が多くて困っています。
A5:内定から入社までの期間のフォローが重要です。定期的な連絡はもちろん、内定者懇親会や先輩社員との面談などを企画し、候補者の不安を解消し、入社へのモチベーションを高める工夫をしましょう。内定者一人ひとりに寄り添う姿勢が大切です。
まとめ
採用を強化することは、単に人材を補充する作業ではなく、企業の未来を創るための重要な経営戦略です。
そのためには、自社が求める人材を明確に定義し、その人材に響く魅力を効果的に伝え、候補者一人ひとりに誠実に向き合う姿勢が求められます。
さらに、採用活動は内定がゴールではなく、入社後の定着と活躍までを見据えた一貫した取り組みが必要です。
本記事で紹介した施策を参考に、自社の採用活動を見直し、より戦略的な採用の実現に向けた一歩を踏み出してください。
採用の戦略を「見えるカタチ」にするのが、Piicの役割です。
私たちは、企業の想いや価値観を整理し、候補者に共感を生む採用ピッチ資料や採用サイトを制作しています。
単なるデザインではなく、“誰に・何を・どう伝えるか”までを設計し、
自社らしさが伝わる採用ブランディングをサポートします。








