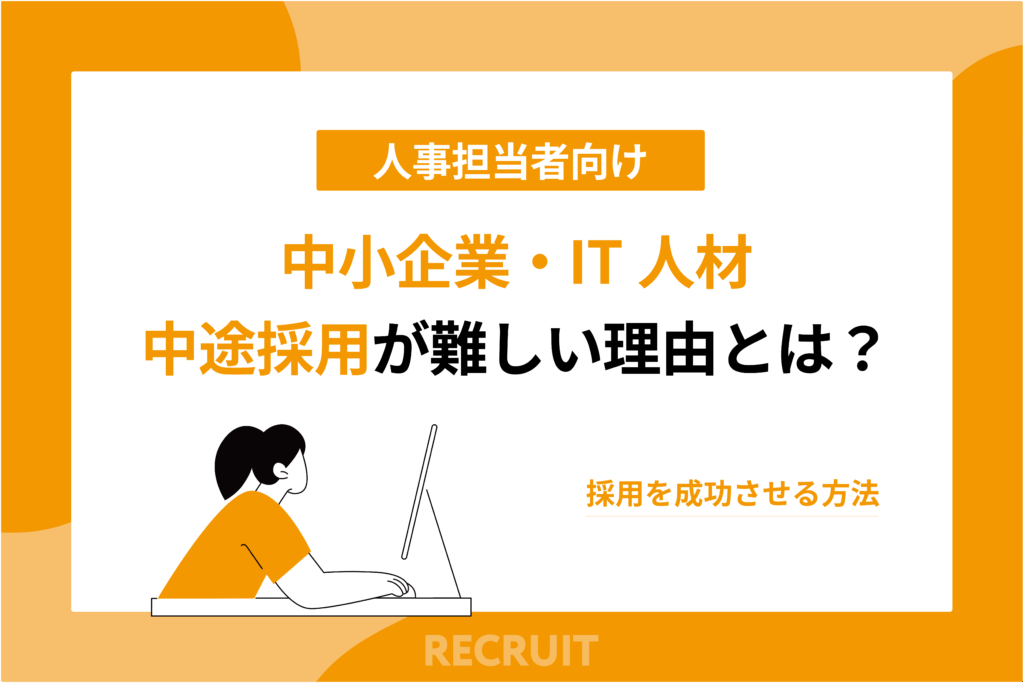
多くの企業で「採用が難しい」という声が聞かれます。
特に中小企業や専門性の高いIT人材、即戦力が求められる中途採用では、その傾向が顕著です。
採用の難しさには、社会的な構造変化といった外部要因と、企業ごとの内部的な理由が複雑に絡み合っています。
この状況を放置すれば、事業の成長に不可欠な人材を確保できず、企業の競争力低下にもつながりかねません。
まずは採用が難しくなっている理由を正しく理解し、自社に合った対策を講じることが成功への第一歩となります。

Index
-
「採用は難しい」3つの外部要因
-
少子高齢化で労働力となる人口が減っている
-
以前よりも慎重に就職先を比較検討する傾向
-
働き方の価値観が多様化し企業選びの基準が変わった
-
中小企業の採用が特に難しいとされる社内的な理由
-
大手企業に比べて会社の名前が知られていない
-
待遇や労働条件で他社との差別化ができていない
-
採用活動に十分な人手や時間をかけられない
-
採用に関する専門知識や経験が社内に蓄積されていない
-
採用プロセスごとに頻発する課題とつまずきの原因
-
【募集段階】求人情報を出しても応募者が全く集まらない
-
【選考段階】面接の日程調整や対応で候補者が離れてしまう
-
【内定段階】やっと出した内定をあっさり辞退される
-
【入社後】期待とのズレから早期に退職者が出てしまう
-
【IT・中途採用】難易度が高い採用で失敗するケース
-
専門スキルを持つ人材の需要に供給が追いついていない
-
候補者への要求が高くなりすぎている
-
入社後のキャリアプランを具体的に示せていない
-
「採用が難しい」から抜け出すための具体的な改善策
-
自社が本当に必要としている人物像を再設定する
-
会社の強みや働く魅力を求職者の目線で伝える
-
SNSやリファラル採用など新たな手法を取り入れる
-
面接官の印象を良くするためのトレーニングを実施する
-
内定者への手厚いフォローで入社までの不安を解消する
-
外部の採用代行サービスや専門家の力を借りる
-
よくあるご質問
-
Q. 採用がうまくいかない一番の原因は何ですか?
-
Q. どうすればいいですか?
-
Q. 未経験者を採用して育てる余裕がありません。
-
Q. 採用コストをかけられないのですが、何か方法はありますか?
-
Q. 面接のドタキャンや辞退が多くて困っています。
-
まとめ
「採用は難しい」3つの外部要因
多くの企業が採用活動に苦労している背景には、自社の努力だけでは変えられない社会全体の変化、すなわち外部要因が存在します。
少子高齢化による労働人口の減少、求職者が以前より慎重に就職先を比較検討する傾向、そして働き方に対する価値観の多様化が、採用を一層難しくしている大きな理由です。
これらの外部環境の変化を理解することは、現代の採用戦略を立てる上で不可欠な前提となります。
少子高齢化で労働力となる人口が減っている
日本の生産年齢人口は年々減少しており、特に企業が求める若手層の絶対数が少なくなっています。
少ない人材を多くの企業で奪い合う構図が生まれているため、採用競争は激化の一途をたどっています。
かつてのように、求人を出せば自然と応募者が集まる時代は終わりを告げました。
限られた人材の中から自社にマッチする人材を見つけ出し、採用までつなげるためには、これまで以上に戦略的なアプローチが求められます。
この人口構造の変化が、採用難の根本的な原因の一つです。
以前よりも慎重に就職先を比較検討する傾向
2025年8月の有効求人倍率は1.20倍と前月から低下しており、企業が求人を控える動きも見られます。一部地域では有効求人倍率が1.00を下回る状況も見られ、求職者にとって必ずしも選択肢が多い「売り手市場」が続いているとは限りません。このような状況は新卒採用だけでなく、中途採用市場でも同様の傾向が見られます。求職者が複数の企業から内定を得るケースも依然としてありますが、以前よりも慎重に就職先を比較検討する傾向が見られます。このような現状から、企業側は競争が激化する中で自社を選んでもらうための工夫が必要であり、選考途中での辞退や内定辞退のリスクに引き続き注意を払う必要があります。
働き方の価値観が多様化し企業選びの基準が変わった
終身雇用が当たり前ではなくなった現代では、人のキャリアに対する考え方が大きく変化しました。
給与や企業の安定性だけでなく、仕事のやりがい、スキルアップできる環境、ワークライフバランス、リモートワークの可否など、企業選びの基準は多様化しています。
特定の職種にこだわらず、自身の価値観やライフスタイルに合った働き方を実現できる企業を求める人が増えています。
企業は、こうした多様なニーズに応えられなければ、求職者から選ばれることは難しくなっています。
中小企業の採用が特に難しいとされる社内的な理由
社会全体の変化に加え、中小企業やスタートアップが採用に苦戦する背景には、企業内部に起因する理由も存在します。
大手企業と比較した場合の知名度の低さや、待遇面での見劣り、そして採用活動に割けるリソースの限界などが、採用を一層難しくしています。
これらの社内的な課題を克服することが、中小企業の採用成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。
大手企業に比べて会社の名前が知られていない
多くの求職者は、まず知名度の高い大手企業から情報を集める傾向にあります。
アクセンチュアやサイバーエージェントのような有名企業と比べると、優れた技術や魅力的な社風を持つ中小企業であっても、その名前が知られていないために、そもそも求職者の選択肢に入らないケースが少なくありません。
せっかくの魅力も、知ってもらえなければ意味がありません。
まずは自社を認知してもらい、興味を持ってもらうための工夫が不可欠です。
情報発信力の差が、応募者を集める段階で大きなハンディキャップとなっています。
待遇や労働条件で他社との差別化ができていない
給与や福利厚生、休日数といった待遇や労働条件は、求職者が企業を比較検討する上で重要な要素です。
体力のある大手企業と比較すると、中小企業はどうしても見劣りしてしまう場合があります。
求職者は複数の企業を天秤にかけるため、条件面で明確な魅力がなければ、選ばれる難易度は格段に上がります。
金銭的な条件で勝負できないのであれば、事業の将来性や独自の社内制度、働きがいの大きさなど、他の側面で他社との差別化を図り、働く魅力をアピールすることが求められます。
採用活動に十分な人手や時間をかけられない
中小企業では、人事担当者が総務や労務など他の業務と兼任していることが多く、採用活動だけに専念できるケースは稀です。
そのため、戦略立案から求人票の作成、スカウトメールの送信、面接調整、内定者フォローといった一連の業務に、十分な時間と人手をかけることができません。
結果として、候補者への対応が遅れたり、アプローチが不十分になったりして、貴重な採用機会を逃してしまうことにつながります。
採用活動の質と量が担保できないことが、採用成功を遠ざける一因となっています。
採用に関する専門知識や経験が社内に蓄積されていない
効果的な採用活動を行うには、市場のトレンドを把握し、自社に合った採用手法を選択するなど、専門的な知識やノウハウが求められます。
しかし、採用を専門に行う部署や担当者がいない企業では、過去の成功事例や失敗から学ぶ機会が少なく、ノウハウが社内に蓄積されていきません。
そのため、毎回手探りの状態で活動を進めることになり、非効率な方法を繰り返してしまうことがあります。
戦略なき採用活動は、時間とコストを浪費するだけで、望むような成果には結びつきにくいのが実情です。
採用プロセスごとに頻発する課題とつまずきの原因
採用活動は、募集、選考、内定、そして入社後フォローという一連の流れで進みます。
しかし、それぞれのプロセスには特有の課題が潜んでおり、多くの企業がつまずきの原因に気づかないまま苦戦を強いられています。
優秀な人材を採用するためには、どの段階で問題が起きているのかを正確に把握し、一つひとつ丁寧に対策を講じていくことが不可欠です。
自社の採用活動を振り返り、ボトルネックとなっている箇所を見つけ出しましょう。
【募集段階】求人情報を出しても応募者が全く集まらない
求人情報を公開しても応募が来ない場合、その原因は求人票の内容や発信方法にある可能性が高いです。
仕事内容が曖昧で働くイメージが湧かなかったり、求める人物像が不明確だったりすると、求職者は応募をためらいます。
また、ターゲットとする層が見ていない求人媒体に掲載していては、そもそも情報が届きません。
自社の魅力や仕事のやりがいを、求職者の心に響く言葉で伝えられているか、そしてターゲットに合った媒体を選べているか、募集方法の根本的な見直しが必要です。
【選考段階】面接の日程調整や対応で候補者が離れてしまう
優秀な候補者ほど、複数の企業の選考を並行して進めています。
そのため、面接の日程調整の連絡が遅い、提示される候補日が少ないといった対応は、候補者の離脱に直結します。
他社の選考がスピーディーに進む中で、待たされることは大きなストレスとなるのです。
また、面接官の態度が高圧的であったり、準備不足が透けて見えたりすると、候補者は企業への印象を悪くします。
迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけ、候補者にとって魅力的な選考体験を提供することが重要です。
【内定段階】やっと出した内定をあっさり辞退される
苦労して内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまうケースは少なくありません。
内定辞退の背景には、提示された条件への不満、競合他社との比較、あるいは企業への理解不足からくる将来への不安など、様々な理由が考えられます。
内定を出したからと安心せず、承諾期限まで気を抜かないことが肝心です。
オファー面談の機会を設け、給与や待遇について丁寧に説明したり、現場社員と話す場を設けたりするなど、候補者の疑問や不安を解消し、入社を後押しする積極的なフォローが求められます。
【入社後】期待とのズレから早期に退職者が出てしまう
採用活動のゴールは、内定を出すことではなく、採用した人材が入社後に定着し、活躍することです。
しかし、入社前に抱いていたイメージと入社後の現実にギャップがあると、早期離職につながってしまいます。
これは、選考過程で仕事の良い面ばかりを強調し、大変な部分や泥臭い業務について正直に伝えていない場合に起こりがちです。
企業のリアルな姿を包み隠さず伝えることで、候補者は納得した上で入社を決断でき、入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。
【IT・中途採用】難易度が高い採用で失敗するケース
採用市場の中でも、特に専門性が求められるIT人材や、即戦力として期待される中途採用は、難易度が高いことで知られています。
これらの領域で採用に失敗する企業には、いくつかの共通したパターンが見受けられます。
需要に対して供給が追いついていない市場の実態を理解せず、候補者への要求が高くなりすぎたり、入社後のキャリアを具体的に示せなかったりすることが、失敗の主な原因となっています。
専門スキルを持つ人材の需要に供給が追いついていない
あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、高度な専門スキルを持つエンジニアやSEといったIT人材の需要は爆発的に増加しています。
しかし、その需要に対して人材の供給は全く追いついておらず、極めて深刻な人材不足の状態です。
多くの企業が一人の優秀なIT人材を巡って激しい争奪戦を繰り広げているため、採用競争は熾烈を極めます。
このような市場環境では、旧来の採用手法に固執していては、優秀な人材と出会うことすら困難です。
候補者への要求が高くなりすぎている
「即戦力が欲しい」という思いが先行するあまり、候補者に求めるスキルや経験のハードルを、無意識のうちに高く設定してしまうことがよくあります。
開発経験はもちろん、マネジメント経験や特定のツールに関する深い知見など、全ての条件を完璧に満たす人材は、市場にほとんど存在しません。
非現実的な理想を追い求めることで、採用ターゲットが極端に狭まり、結果的に一人も採用できないという事態を招きます。
本当に必要な条件は何かを冷静に見極め、採用基準を現実的なレベルに調整することが不可欠です。
入社後のキャリアプランを具体的に示せていない
自身の成長やキャリアアップに意欲的な中途採用の候補者にとって、入社後にどのような道筋を歩めるのかは、企業選びの重要な判断基準となります。
例えば営業職の採用であっても、単に目先の業務内容を説明するだけでは魅力に欠けます。
入社後、どのようなスキルを身につけ、将来的にはどのようなポジションや役割を目指せるのか、具体的なキャリアプランを提示することが重要です。
3年後、5年後の成長した自分の姿を候補者がイメージできれば、入社への動機付けは格段に高まります。
「採用が難しい」から抜け出すための具体的な改善策
採用が難しいと現状を嘆くだけでは、事態は好転しません。
人事担当者が主体となり、これまでの採用活動を根本から見直し、具体的な改善策を実行に移すことが求められます。
自社が本当に求める人物像を明確にすることから始まり、求職者の視点に立った魅力発信、そして新たな採用手法の導入まで、取り組むべきことは多岐にわたります。
- 人物像の再設定
- 会社の強みや働く魅力を求職者目線で伝える
- 新たな採用手法を取り入れる
- 面接官トレーニングの実施
- 内定者への手厚いフォロー
- 外部の採用代行サービス等の利用
ここでは、採用難から脱却するための上記の具体的なアクションプランを紹介します。
自社が本当に必要としている人物像を再設定する
効果的な採用活動の第一歩は、どのような人材を採用するのかを明確に定義することです。
現場から挙がってくる要望をそのまま受け入れるのではなく、事業計画やチーム全体のバランスを考慮し、本当に必要なスキル、経験、価値観を改めて整理します。
特定の職種に固執せず、未経験者を採用して育成する選択肢も視野に入れると、ターゲット層が広がります。
「これだけは譲れない」という必須条件と、「あれば尚良い」という歓迎条件を切り分けることで、より現実的で効果的な母集団形成が可能になります。
会社の強みや働く魅力を求職者の目線で伝える
求職者は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、その企業で働くことでどのような経験が得られ、自身のキャリアにどうプラスになるのかを知りたいと考えています。
事業の社会貢献性、独自の企業文化、社員の成長を支える制度など、自社ならではの魅力を改めて洗い出しましょう。
そして、その魅力を「求職者の言葉」で、求人票や面接の場で具体的に伝えることが重要です。
社内では当たり前と思われていることでも、社外の求職者にとっては大きな魅力に映る可能性を秘めています。
SNSやリファラル採用など新たな手法を取り入れる
従来の求人媒体に広告を掲載して応募を待つだけの採用活動では、出会える人材に限りがあります。
企業の日常や働く社員の姿を発信するSNS採用、社員からの紹介で候補者を見つけるリファラル採用など、企業側から積極的にアプローチする「攻めの採用」へと転換することが重要です。
これらの手法は、転職をまだ具体的に考えていない潜在層にもアプローチできる上、企業の文化にマッチした人材を採用しやすいというメリットがあります。
既存のやり方に固執せず、新しいチャネルを試す柔軟な姿勢が求められます。
面接官の印象を良くするためのトレーニングを実施する
面接は企業が候補者を選ぶ場であると同時に、候補者が企業を評価する場でもあります。
面接官の何気ない言動や態度が企業のイメージを大きく左右し、候補者の入社意欲を削いでしまうことも少なくありません。
特に、普段採用に関わっていない現場社員が面接を担当する場合は注意が必要です。
人事部門が主導し、面接官向けのトレーニングを実施しましょう。
候補者の能力や価値観を引き出す質問の仕方や、自社の魅力を効果的に伝える方法を共有し、全社で選考の質を高める取り組みが不可欠です。
内定者への手厚いフォローで入社までの不安を解消する
内定通知を出してから入社日までの期間は、内定者が最も不安を感じやすい時期です。
この間にコミュニケーションが不足すると、内定ブルーに陥ったり、他社からの魅力的なオファーに心が揺らいだりして、辞退につながるリスクが高まります。
定期的に連絡を取ることはもちろん、現場社員とのオンライン懇親会を企画したり、社内報を送付したりするなど、内定者との接点を継続的に持ちましょう。
会社全体で歓迎している姿勢を示すことで、内定者の不安を解消し、入社への期待感を醸成します。
外部の採用代行サービスや専門家の力を借りる
社内のリソースやノウハウだけでは採用活動に限界を感じる場合、外部の専門家の力を借りることも有効な手段です。
採用代行(RPO)サービスなどを活用し、求人票の作成やスカウトメールの配信といったノンコア業務を委託することで、人事担当者は候補者とのコミュニケーションなど、より重要な業務に集中できます。
また、採用戦略の策定段階からコンサルティングを受けることも可能です。
コストは発生しますが、プロの知見を取り入れることで、採用活動全体の質が向上し、結果的に成功への近道となるでしょう。
よくあるご質問
Q. 採用がうまくいかない一番の原因は何ですか?
A. 一概には言えませんが、多くの場合「自社の魅力が求職者に伝わっていない」か「求める人物像が明確でない」ことが原因です。
まずはこの2点を見直すことから始めるのがおすすめです。
地方の中小企業ですが、応募が全く来ません。
Q. どうすればいいですか?
A. 地方の企業様の場合、オンラインでの採用活動が鍵となります。
Web面接を全面的に導入したり、SNSで地域の魅力と共に会社の情報を発信したりすることで、全国にいる潜在的な候補者にアプローチできます。
Q. 未経験者を採用して育てる余裕がありません。
A. 全ての業務を最初から任せる必要はありません。
まずは定型的な業務やアシスタント業務から担当してもらい、OJTを通じて育成していく計画を立ててみてはいかがでしょうか。
長期的な視点での人材投資も重要です。
Q. 採用コストをかけられないのですが、何か方法はありますか?
A. コストを抑えるなら、ハローワークの活用やリファラル採用、SNS採用が有効です。
特にリファラル採用は、社員の紹介なので入社後のミスマッチが少なく、定着しやすいというメリットもあります。
Q. 面接のドタキャンや辞退が多くて困っています。
A. 候補者とのコミュニケーション不足が原因かもしれません。
面接日程の候補を多めに提示したり、前日にリマインドメールを送ったりする工夫が効果的です。
また、応募から内定までの選考スピードを上げることも重要です。
まとめ
採用が難しいと感じる背景には、労働人口の減少や売り手市場といった社会的な要因と、知名度や採用体制といった企業が抱える内部的な理由が存在します。
特に中小企業や専門職の採用では、これらの課題がより顕著に現れます。
しかし、採用が難しい理由を正しく理解し、自社の状況に合わせて対策を講じることで、状況を改善することは可能です。
求める人物像を再定義し、自社の魅力を求職者目線で伝え、採用手法を多様化するなど、一つひとつの取り組みが採用成功へとつながります。
採用が難しい時こそ、まず見直したいのは「伝え方」です。
Piicでは、採用ピッチ資料や採用サイトなど、企業の想いや魅力を“見えるカタチ”に整えるクリエイティブを制作しています。
中小企業や専門職採用でも、限られたリソースの中で成果を出すために、本当に伝わる採用設計をご提案します。
まずは貴社の現状に合わせた最適な制作プランを一緒に考えてみませんか?








