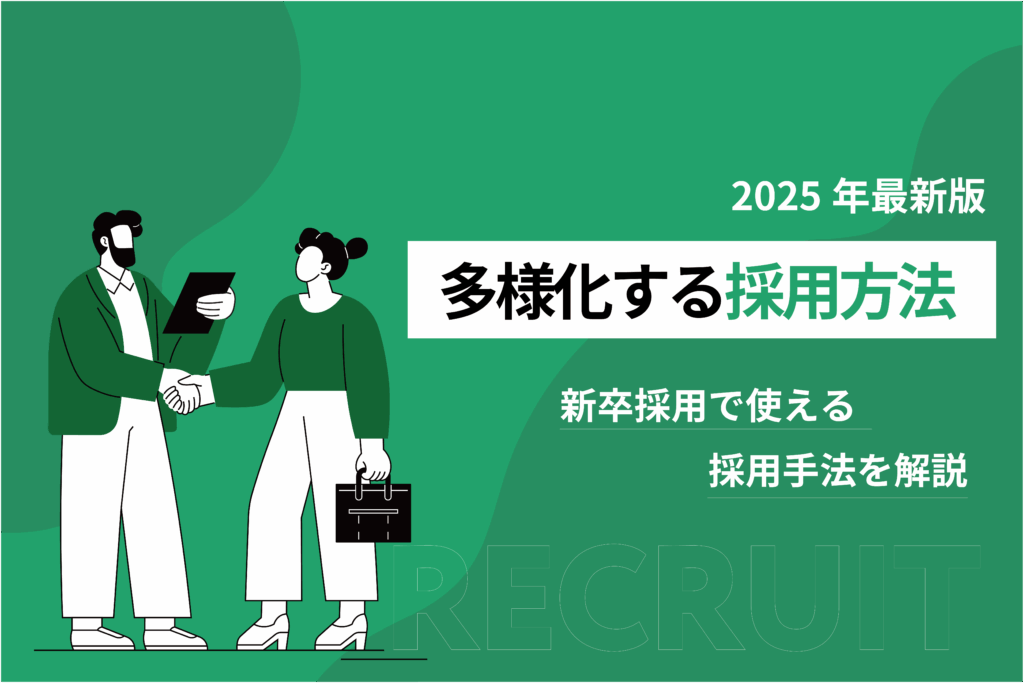
労働人口の減少や価値観の変化により、従来の手法だけでは求める人材の確保が難しくなっています。
特に新卒採用の現場では、この課題はさらに深刻です。
そこで重要となるのが、採用手法の多様化に着目することです。
自社の魅力を的確に伝え、優秀な学生と出会うためには、ナビサイトに頼るだけでなく、様々な採用手法を戦略的に組み合わせる必要があります。
この記事では、最新の新卒採用で活用できる多様な採用手法について、その背景から具体的な方法、導入のポイントまでを解説します。

Index
-
なぜ今、採用方法の多様化が求められるのか?
-
働き方の変化と求職者の価値観のシフト
-
優秀な人材を確保しにくくなった背景
-
採用方法を多様化させる3つのメリット
-
これまで出会えなかった潜在層の人材にアプローチできる
-
採用のミスマッチを減らし入社後の定着率向上が期待できる
-
独自の採用活動が企業のブランディング強化につながる
-
採用方法を多様化させる際に注意すべき2つのポイント
-
複数の選考ルートが生まれることによる管理の煩雑化
-
新しい手法の導入で採用コストが増加する可能性
-
【新卒採用向け】注目すべき最新の採用方法9選
-
Web上で候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」
-
SNSを活用して企業の魅力を発信する「ソーシャルリクルーティング」
-
社員からの紹介で信頼できる人材を獲得する「リファラル採用」
-
企業を退職した元社員を再雇用する「アルムナイ採用」
-
オンラインで開催する「Web説明会・ミートアップイベント」
-
候補者のスキルや人柄を深く知る「長期・短期インターンシップ」
-
仕事内容や社風をリアルに伝える「採用動画コンテンツ」
-
ゲームやユニークな選考を取り入れた「イベント型採用」
-
データ分析に基づいた戦略的な「データドリブン採用」
-
自社に合った採用方法を選ぶための3つのステップ
-
STEP1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確に定義する
-
STEP2:かけられる採用コストと社内工数を算出する
-
STEP3:従来の手法と新しい手法を組み合わせて試行錯誤する
-
よくあるご質問
-
Q1:採用方法を多様化したいのですが、何から始めればいいですか?
-
Q2:採用コストをあまりかけられない場合、おすすめの手法はありますか?
-
Q3:複数の採用手法を管理するコツはありますか?
-
Q4:ユニークな採用は本当に効果があるのでしょうか?
-
Q5:採用手法の多様化で、かえって応募者が混乱しませんか?
-
まとめ
なぜ今、採用方法の多様化が求められるのか?

現代の採用市場は、売り手市場の継続や働き方の価値観の変化といった要因から、大きな変革期を迎えています。
求職者はより多くの選択肢を持ち、企業は従来通りのやり方では人材獲得競争に勝ち残ることが困難になりました。
このような状況下で、企業が自社にマッチした優秀な人材を確保するためには、採用手法の多様化が不可欠な戦略となっています。
画一的なアプローチではなく、ターゲットに応じて複数の手法を使い分ける柔軟性が求められているのです。
働き方の変化と求職者の価値観のシフト
リモートワークの普及やフレックスタイム制の導入など、働き方は大きく変化しました。
それに伴い、求職者、特にZ世代と呼ばれる若年層の価値観も大きくシフトしています。
彼らは給与や待遇といった条件面だけでなく、企業のビジョンへの共感、ワークライフバランスの実現、自己成長の機会、社会貢献性などを重視する傾向にあります。
企業側は、こうした価値観の多様性を受け止め、自社のカルチャーや働き方の魅力を多角的に伝える必要があります。
画一的なメッセージではなく、個々の価値観に響くような情報発信や選考体験の提供が、採用成功の鍵を握ります。
優秀な人材を確保しにくくなった背景
終身雇用を前提とした新卒一括採用は、長らく日本企業の採用活動の主流でした。
しかし、転職が一般的になり、個人のキャリア観が多様化した現代において、その有効性は揺らいでいます。
ナビサイトに情報を掲載し、多くの学生からのエントリーを待つという従来型の採用手法では、自社のことをよく知らない層も含めた不特定多数へのアプローチとなりがちです。
その結果、本当に自社にマッチした優秀な人材を見つけ出すことが難しくなりました。
企業側から積極的にターゲットへ働きかけるなど、より戦略的な採用手法を取り入れなければ、激化する人材獲得競争の中で優位性を保つことはできません。
採用方法を多様化させる3つのメリット

採用手法の多様化は、単に母集団を増やすだけでなく、企業にとって多くの戦略的メリットをもたらします。
従来の方法では出会えなかった層にアプローチできる可能性が広がり、採用のミスマッチを防ぐことで、入社後の定着率向上にも寄与します。
さらに、自社独自の採用活動は、企業のブランディングを強化し、他社との差別化を図る上でも大きな役割を果たします。
ここでは、採用手法の多様化がもたらす具体的な3つのメリットについて詳しく見ていきます。
これまで出会えなかった潜在層の人材にアプローチできる
従来の就職ナビサイトを中心とした採用活動では、積極的に就職先を探している「顕在層」へのアプローチが中心でした。
しかし、採用チャネルを多様化させることで、まだ本格的に就職活動を開始していない、あるいは転職を具体的に考えていない優秀な「潜在層」にもアプローチできます。
例えば、ダイレクトリクルーティングやSNSを活用すれば、特定のスキルを持つ学生や、自社の事業に興味を持ちそうなコミュニティに属する人材に直接コンタクトを取ることが可能です。
複数の採用チャネルを持つことは、より幅広い候補者群との接点を生み出し、競争が激化する前に有望な人材と関係を築く機会を創出します。
採用のミスマッチを減らし入社後の定着率向上が期待できる
採用手法を多様化させ、インターンシップや社員との座談会、リファラル採用などを取り入れると、候補者は入社前に企業の文化や実際の業務内容を深く理解できます。
候補者は働く姿を具体的にイメージできるため、「こんなはずではなかった」という入社後のギャップを減らせます。
企業側も、面接だけでは分からない候補者の人柄や潜在能力を多角的に評価することが可能です。
このように、相互理解を深めるプロセスを経ることで、採用のミスマッチが大幅に減少し、結果として早期離職を防ぎ、入社後の定着率と活躍度の向上が見込めます。
独自の採用活動が企業のブランディング強化につながる
自社のビジョンやカルチャーを反映させたユニークな採用活動は、それ自体が強力な広報ツールとなり得ます。
例えば、社会課題の解決をテーマにしたワークショップ型選考や、自社製品を使ったハッカソンなどを開催すれば、SNSなどで話題となりやすく、多くの求職者の注目を集めます。
こうした取り組みは、「革新的な会社」「社会貢献意識の高い会社」といったポジティブな企業イメージを醸成し、採用ブランディングの強化に直結します。
他社とは違うユニークなアプローチは、自社のファンを増やし、理念に共感する優秀な人材を引き寄せる力となります。
採用方法を多様化させる際に注意すべき2つのポイント

採用手法の多様化は多くのメリットをもたらしますが、計画なく進めると予期せぬ課題に直面することもあります。
特に、複数の採用手法を同時に運用することによる管理の複雑化や、新しいツールの導入に伴うコストの増加は、多くの企業が直面する問題です。
これらのデメリットを事前に把握し、対策を講じておくことで、多様化のメリットを最大限に引き出すことができます。
ここでは、採用手法を多様化させる上で注意すべき2つのポイントを解説します。
複数の選考ルートが生まれることによる管理の煩雑化
採用チャネルが増えると、それぞれのチャネルから応募してくる候補者の情報や選考の進捗状況を管理することが煩雑になります。
例えば、ダイレクトリクルーティング経由の候補者とイベント経由の候補者では、評価基準や次のステップへの案内が異なる場合があり、担当者間の情報共有が不足すると、対応の遅れや評価のばらつきが生じるリスクがあります。
これを防ぐためには、全ての応募者情報を一元管理できる採用管理システム(ATS)を導入したり、各採用チャネルの運用ルールを事前に明確に定めたりするなど、管理体制を整備しておく必要があります。
新しい手法の導入で採用コストが増加する可能性
新たな採用手法を導入する際には、それに伴うコストの発生を考慮しなくてはなりません。
ダイレクトリクルーティングサービスの利用料や、SNS広告の出稿費用、採用イベントの開催費用など、直接的な金銭コストが発生します。
また、新しいツールを導入するための初期費用や、スカウトメールの文面作成、SNSコンテンツの企画・投稿といった業務にかかる人件費、つまり社内工数も増加します。
どの採用手法にどれだけの予算と人員を割り当てるのか、費用対効果を見極めながら慎重に計画を立てることが求められます。
【新卒採用向け】注目すべき最新の採用方法9選

新卒採用を取り巻く環境が変化する中で、企業は新しいアプローチを模索しています。
従来の画一的な採用手法から脱却し、自社の魅力やビジョンに共感してくれる学生と出会うためには、多様な選択肢を知ることが第一歩です。
ここでは、新卒採用の現場で特に注目を集めている、最新の採用手法を以下の9つ厳選して紹介します。
- ダイレクトリクルーティング
- ソーシャルリクルーティング
- リファラル採用
- アルムナイ採用
- Web説明会・ミートアップイベント
- 長期・短期インターンシップ
- 採用動画コンテンツ
- イベント型採用
- データドリブン採用
これらの手法は、企業側から積極的に働きかける攻めの姿勢や、候補者との相互理解を深める点に特徴があります。
Web上で候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」
ダイレクトリクルーティングは、企業が学生のプロフィールなどが登録されたデータベースを検索し、会いたいと思った候補者へ直接スカウトメールを送る採用手法です。
ナビサイトで応募を待つ「待ち」の姿勢とは対照的に、企業が主体的に動く「攻め」の採用を実現します。
特定のスキルを持つ学生や、自社の社風に合いそうな人材にピンポイントでアプローチできるため、採用の効率と精度を高められます。
候補者一人ひとりに合わせた特別なメッセージを送ることで、自社への興味を引きつけ、応募意欲を高める効果が期待できる採用手法です。
SNSを活用して企業の魅力を発信する「ソーシャルリクルーティング」
X(旧Twitter)やInstagram、FacebookといったSNSを採用チャネルとして活用する手法です。
学生が日常的に利用するプラットフォームで情報発信を行うことで、企業のリアルな姿を効果的に伝えられます。
例えば、社員のインタビュー動画やオフィスの日常風景、社内イベントの様子などを投稿することで、テキストだけでは伝わらない企業文化や働く人々の雰囲気を伝え、候補者に親近感を持ってもらえます。
ハッシュタグの活用やインフルエンサーとの連携により情報を拡散させ、これまで接点のなかった層へも自社の存在をアピールできる採用チャネルです。
社員からの紹介で信頼できる人材を獲得する「リファラル採用」
リファラル採用とは、自社の社員に友人や後輩など、企業にマッチしそうな人材を紹介してもらう採用手法です。
紹介者である社員が、企業の理念や仕事のやりがい、時には厳しさなども含めて候補者に伝えているため、入社後のミスマッチが起こりにくいという大きな利点があります。
また、求人広告費や人材紹介会社への手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も魅力です。
社員のエンゲージメントが高い企業ほど機能しやすく、信頼できるネットワークを通じて質の高い母集団を形成できる、非常に効果的な採用手法と言えます。
企業を退職した元社員を再雇用する「アルムナイ採用」
一度は自社を退職した元社員(アルムナイ)と良好な関係を継続し、再び迎え入れる採用手法です。
アルムナイは、自社の事業内容や組織文化を既に深く理解しているため、入社後すぐに活躍できる即戦力として期待できます。
さらに、他社で培った新しいスキルや知識、人脈を自社に持ち帰ってくれることで、組織の活性化にもつながります。
退職者を貴重な人的資産と捉え、多様なキャリアを応援する企業姿勢を示すことにもなり、企業のブランドイメージ向上にも貢献します。
専用のネットワークを構築し、定期的に情報交換を行うなどの取り組みが有効です。
オンラインで開催する「Web説明会・ミートアップイベント」
会社説明会や、現場社員と学生が気軽に交流できるミートアップイベントを、オンライン上で開催する採用手法です。
場所の制約を受けないため、地方在住の学生や海外に留学中の学生など、これまでアプローチが難しかった層にも参加の機会を提供できます。
企業にとっては、会場設営費や運営スタッフの交通費といったコストを削減できるメリットもあります。
チャット機能やブレイクアウトルームを活用すれば、双方向のコミュニケーションを促し、学生の疑問や不安を解消することも可能です。
時間や場所の壁を越えて、より多くの候補者と接点を持てる有効な採用手法です。
候補者のスキルや人柄を深く知る「長期・短期インターンシップ」
学生に実際の職場での業務を体験してもらうインターンシップは、新卒採用において極めて重要な手法です。
数日間の短期インターンシップでは、事業内容や社風への理解を深めてもらい、数ヶ月にわたる長期インターンシップでは、より実践的な業務を通じて、学生のスキルやポテンシャル、コミュニケーション能力などをじっくりと見極めることができます。
学生側にとっても、自身の適性を確認し、キャリアについて考える良い機会となります。
企業と学生の相互理解を促進し、入社後のミスマッチを効果的に防ぐことで、志望度の高い優秀な人材の獲得に直結します。
仕事内容や社風をリアルに伝える「採用動画コンテンツ」
企業の魅力を映像で伝える採用動画は、スマートフォンでの情報収集が当たり前になった現代の学生に有効な採用手法です。
社員の一日に密着したドキュメンタリーや、複数の社員が本音で語る座談会、オフィスの雰囲気が伝わるルームツアーなど、テキストや静止画では表現しきれないリアルな情報を届けられます。
動画は短時間で多くの情報を伝えられ、感情に訴えかける力も強いため、候補者の興味関心を引きつけ、企業への共感を醸成するのに役立ちます。
採用サイトやSNSなど、様々なプラットフォームで活用できる汎用性の高さも魅力の一つです。
ゲームやユニークな選考を取り入れた「イベント型採用」
謎解きゲームや脱出ゲーム、ハッカソンといったユニークなイベントを選考プロセスに組み込む採用手法です。
参加者は楽しみながら課題に取り組むため、リラックスした状態で本来の能力を発揮しやすくなります。
企業側は、グループワークでの協調性や、プレッシャーのかかる状況下での課題解決能力など、通常の面接では評価しにくい側面を見ることができます。
こうしたユニークな選考は話題になりやすく、SNSでの拡散も期待できるため、他社との差別化を図り、企業の先進的なイメージを打ち出すブランディング効果も見込めます。
データ分析に基づいた戦略的な「データドリブン採用」
過去の応募者の属性データや選考の通過率、入社後のパフォーマンス評価など、採用活動に関わるあらゆるデータを収集・分析し、その結果に基づいて採用戦略を立案・実行する採用手法です。
担当者の勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータを用いて、どの採用チャネルからの応募者が定着率が高いか、どのような経験を持つ人材が活躍しているかなどを明らかにします。
これにより、採用活動全体の課題を可視化し、より効果的な施策を打つことが可能になります。
PDCAサイクルを回しながら継続的にプロセスを改善していくことで、採用の精度と効率を向上させる手法です。
自社に合った採用方法を選ぶための3つのステップ

数多く存在する採用手法の中から、自社にとって最適なものを見つけ出すためには、戦略的なアプローチが欠かせません。
流行しているからという理由だけで新しい手法に飛びつくのではなく、自社の目的や状況を冷静に分析し、計画的に導入を進めることが成功への近道です。
ここでは、無数にある選択肢の中から自社に本当に合った採用手法を選び、効果的な採用活動を実現するための3つのステップを具体的に解説します。
STEP1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確に定義する
最初に行うべきは、どのような人材を求めているのかを具体的に言語化することです。
単に「優秀な学生」といった曖昧な定義ではなく、保有スキルや専門知識、価値観、性格的特徴、キャリアへの考え方まで含めた詳細な人物像(ペルソナ)を設定します。
例えば、「地方創生に関心があり、多様性を受け入れながら主体的に行動できる人材」のようにペルソナを定義すれば、その人物がどのような情報を探し、どのようなコミュニティに属しているかが見えてきます。
これにより、アプローチすべき最適な採用チャネルや伝えるべきメッセージが明確になります。
STEP2:かけられる採用コストと社内工数を算出する
次に、採用活動にどれだけのリソースを投下できるかを正確に把握します。
リソースには、求人広告の掲載料やツールの利用料といった直接的な「予算」と、採用担当者が候補者対応や面接、イベント運営などに費やす「時間(工数)」の両方が含まれます。
新しい採用手法を導入する際には、これらのコストがどの程度発生するのかを事前に見積もることが不可欠です。
限られたリソースの中で最大限の効果を出すために、どの採用手法に重点的に投資するのか、優先順位を決定します。
このステップを怠ると、活動が中途半端に終わり、成果が出ないままコストだけがかさむ結果になりかねません。
STEP3:従来の手法と新しい手法を組み合わせて試行錯誤する
求める人物像と使えるリソースが明確になったら、具体的な採用手法の組み合わせを検討し、実行に移します。
最初から一つの手法に絞り込むのではなく、従来から行っているナビサイトでの募集と、新しく始めるダイレクトリクルーティングを並行して進めるなど、複数の手法を組み合わせて試すのが効果的です。
採用手法の多様化は、実践と検証の繰り返しによって最適化されます。
各手法の応募数や選考通過率、採用決定数などのデータを継続的に測定・分析し、何がうまくいき、何が課題なのかを明らかにしながら、自社にとって最も効果的な採用手法の組み合わせを見つけ出していきます。
よくあるご質問
Q1:採用方法を多様化したいのですが、何から始めればいいですか?
A1:まずは、自社の採用における課題(例:母集団の数が足りない、内定辞退が多いなど)を洗い出し、「どのような人材を求めているのか」という人物像(ペルソナ)を明確にすることから始めましょう。その上で、設定したペルソナに最も効果的にアプローチできそうな手法を、まずは一つか二つ、小規模に試してみるのがおすすめです。
Q2:採用コストをあまりかけられない場合、おすすめの手法はありますか?
A2:低コストで始めやすい手法としては、社員の知人を紹介してもらう「リファラル採用」や、X(旧Twitter)、Instagramなどを活用する「ソーシャルリクルーティング」が挙げられます。これらは外部への支払いが発生しにくく、社内の協力体制と工夫次第で大きな効果を期待できます。
Q3:複数の採用手法を管理するコツはありますか?
A3:応募者情報や選考の進捗状況をExcelなどで個別に管理すると煩雑になりがちです。可能であれば、情報を一元管理できる採用管理システム(ATS)の導入を検討すると効率が上がります。また、各手法の主担当者を決め、定期的にチーム内で進捗を共有する会議を設けることも重要です。
Q4:ユニークな採用は本当に効果があるのでしょうか?
A4:効果はあります。ただし、奇をてらうことだけが目的になってはいけません。自社の企業文化や求める人物像と合致したユニークな選考は、他社との差別化につながり、企業のブランディングに大きく貢献します。学生の素の姿やポテンシャルを見極めやすいというメリットもあります。
Q5:採用手法の多様化で、かえって応募者が混乱しませんか?
A5:応募者が混乱しないよう、どの採用チャネルから応募しても、選考基準やプロセスに不公平が生じないように配慮することが大前提です。各チャネルで発信する企業のコアメッセージに一貫性を持たせ、選考フローを分かりやすく提示することで、応募者の不安を解消できます。
まとめ
少子化や価値観の変化が進む現代において、新卒採用の成功には採用手法の多様化が欠かせません。
ナビサイトに依存した画一的な活動から脱却し、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、SNS活用といった多様な採用手法を戦略的に組み合わせることで、これまで出会えなかった優秀な人材との接点を創出できます。
採用手法の多様化は、採用のミスマッチを減らし、企業のブランディングを強化する効果ももたらします。
自社が求める人物像を明確に定義し、利用できるリソースを把握した上で、様々な手法を試行錯誤しながら最適な組み合わせを見つけ出すことが、これからの新卒採用を勝ち抜く鍵となります。
採用活動が多様化する中で、学生が企業を知る最も重要な接点は「採用サイト」です。
就職活動中の学生のうち、約9割がエントリー前に企業サイトを確認しており、そこで得た印象が「応募するかどうか」を大きく左右しています。
Piicでは、企業の価値観やカルチャーを“伝わるカタチ”に落とし込む採用ピッチ資料・採用サイト制作を通じて、
自社にマッチした人材との出会いを生み出します。








