
採用チャネルとは、企業が求職者と出会うための経路や手段を指します。
採用手法が多様化する現代において、自社の採用戦略に合ったチャネルを選ぶことは、採用活動の成否を分ける重要な要素です。
やみくもに募集をかけるだけでは、求める人材に出会うことは難しくなっています。
この記事では、主要な採用チャネルを一覧で紹介するとともに、それぞれのメリット・デメリット、そして自社に最適なチャネルを見つけるための選び方について解説します。

Index
-
採用チャネルとは?人材獲得に欠かせないアプローチ経路を解説
-
採用活動でチャネルの選定が重要視される理由
-
【手法別】主要な採用チャネル8選を一覧で紹介
-
求人広告
-
人材紹介サービス
-
ダイレクトリクルーティング
-
オウンドメディアリクルーティング
-
リファラル採用
-
SNS採用
-
ハローワーク
-
転職フェア・採用イベント
-
自社に最適な採用チャネルを見つけるための3つのステップ
-
ステップ1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする
-
ステップ2:かけられる採用コストや工数を把握する
-
ステップ3:複数のチャネルを組み合わせて相乗効果を狙う
-
【採用課題別】おすすめの採用チャネルの選び方
-
とにかく多くの応募者を集めたい(母集団形成)
-
採用にかかるコストをできるだけ抑えたい
-
採用業務の負担を減らして効率化したい
-
自社の文化にマッチする人材と出会いたい
-
よくあるご質問
-
Q1.新卒採用と中途採用で、選ぶべきチャネルは変わりますか?
-
Q2.複数の採用チャネルを同時に使うメリットは何ですか?
-
Q3.採用チャネルの効果測定はどのように行えばよいですか?
-
Q4.地方の中小企業におすすめの採用チャネルはありますか?
-
Q5.採用チャネルを見直すタイミングはいつですか?
-
まとめ
採用チャネルとは?人材獲得に欠かせないアプローチ経路を解説

採用チャネルとは、企業が人材を募集し、採用に至るまでに利用する媒体や手法の総称です。
言い換えると「求職者とのあらゆる接点」を指し、求人サイトへの広告掲載や人材紹介会社の利用、自社の採用サイト運営などが含まれます。
かつては一部のチャネルが主流でしたが、働き方や価値観の多様化に伴い、企業と求職者の出会い方も変化しました。
現在では数多くの選択肢が存在し、それぞれに特徴があるため、自社の目的に合わせて使い分ける必要があります。
採用活動でチャネルの選定が重要視される理由
採用チャネルの選定が重要視される背景には、採用手法と求職者の価値観の多様化があります。
インターネットやSNSの普及により、求職者はさまざまな方法で企業情報を収集するようになりました。
そのため、企業側も画一的なアプローチではなく、採用したいターゲット層に合わせた情報発信が求められます。
適切なチャネルを選ばなければ、求める人材に自社の求人情報が届かず、機会損失につながりかねません。
また、チャネルごとに費用や運用工数も異なるため、自社の採用目標や予算に合わない手法を選択すると、コストが無駄になる可能性もあります。
戦略的なチャネルの選定は、採用活動の効率化と成功確率の向上に直結します。
【手法別】主要な採用チャネル8選を一覧で紹介

採用チャネルには多くの種類があり、それぞれに異なる特徴や強みがあります。
ここでは、多くの企業で活用されている代表的なチャネルを下記の8つピックアップし、その概要を一覧で紹介します。
- 求人広告
- 人材紹介サービス
- ダイレクトリクルーティング
- オウンドメディアリクルーティング
- リファラル採用
- SNS採用
- ハローワーク
- 転職フェア・採用イベント
求人広告のように広く知られた手法から、ダイレクトリクルーティングのような比較的新しいアプローチまで、その特性は様々です。
自社の採用ターゲットや課題を念頭に置きながら、それぞれのチャネルがどのようなケースで有効なのかを理解し、戦略的に選択・活用することが採用成功の鍵となります。
求人広告
求人広告は、Webサイトや雑誌といった求人媒体に自社の求人情報を掲載する、最も一般的な採用広報の手法です。
最大のメリットは、媒体の知名度を活かして、転職を考えている幅広い層の求職者に一括でアプローチできる点にあります。
新卒向けや中途向け、特定の業界・職種に特化した媒体など、種類も豊富で、ターゲットに応じて使い分けが可能です。
一方で、多くの情報の中に自社の求人が埋もれてしまうリスクや、応募者のスキルや意欲にばらつきが出やすいという側面も持ち合わせています。
そのため、ターゲットに合った媒体を選定し、候補者の心に響くような魅力的な求人原稿を作成する工夫が求められます。
人材紹介サービス
人材紹介サービスは、企業の採用要件をヒアリングした上で、人材紹介会社(エージェント)が自社に登録している候補者の中から最適な人材を推薦してくれるサービスです。
採用が決定した際に費用が発生する成功報酬型が一般的で、初期費用を抑えられます。
特に、専門性の高いスキルを持つ人材や、管理職クラスの中途採用で強みを発揮します。
エージェントが候補者のスクリーニングや日程調整などを代行してくれるため、採用担当者の工数を大幅に削減できる点も大きなメリットです。
ただし、採用決定時の成功報酬は年収の30~35%程度が相場であり、他のチャネルと比較して一人あたりの採用単価が高くなる傾向があります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側がデータベースを活用して候補者を検索し、直接スカウトメールを送ってアプローチする「攻め」の採用手法です。
転職市場には出てきていない潜在層にも接触できるため、競争率の低い優秀な人材を獲得できる可能性があります。
特に、専門スキルを持つエンジニア採用などで有効活用されています。
候補者に対して自社の魅力を直接、熱意を持って伝えられるため、入社意欲を高めやすく、ミスマッチの防止にもつながります。
その反面、候補者の選定からスカウト文面の作成、日程調整まで、採用担当者が主体的に動く必要があり、運用には相応の工数がかかります。
オウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングは、自社で運営する採用サイトやブログ、SNSなどを通じて、事業内容や企業文化、社員の働き方といった情報を発信する採用手法です。
求人広告のようなフォーマットの制約がなく、自社の魅力を自由な形で深く伝えられるため、企業の価値観に共感する候補者を集めやすいのが特徴です。
特に、企業の理念や将来性を重視する傾向にある新卒採用において、効果を発揮します。
コンテンツは企業の資産として蓄積され、中長期的なブランディングにも寄与しますが、効果が現れるまでには時間がかかります。
また、継続的なコンテンツの企画や制作にリソースを要する点も考慮しなくてはなりません。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員に友人や知人などを紹介してもらう採用手法です。
紹介者である社員が、企業の文化や仕事内容について候補者に直接説明するため、入社後のミスマッチが起こりにくいという利点があります。
企業への理解度が高い人材が集まりやすく、定着率の向上も期待できます。
また、求人広告費や紹介手数料といった外部コストがかからないため、採用単価を大幅に抑えることが可能です。
ただし、紹介してくれる社員との人間関係に配慮が必要であり、不採用時のフォローは慎重に行う必要があります。
紹介に偏りすぎると、社員層の同質化を招く可能性もあるため、他のチャネルとの併用が望ましいです。
SNS採用
SNS採用は、X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInといったソーシャルメディアを活用する採用手法です。
企業の日常や社員の様子、カルチャーなどを発信することで、まだ転職を具体的に考えていない潜在層とも自然な形で接点を築けます。
候補者とカジュアルなコミュニケーションが取りやすく、企業のリアルな雰囲気を伝えられるため、ファンを増やしながら採用につなげることが可能です。
無料で始められる手軽さも魅力ですが、成果を出すには継続的な情報発信とフォロワーとの関係構築が不可欠です。
情報が拡散しやすい分、不適切な発信による炎上リスクも伴うため、慎重な運用計画が求められます。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する公的な就職支援機関であり、企業は無料で求人情報を掲載できます。
採用コストを一切かけずに募集活動を行える点が最大のメリットです。
全国各地に拠点があるため、特に地元での採用や地域に根ざした人材を確保したい場合に有効なチャネルとなります。
幅広い年齢層や経歴を持つ求職者が利用しているため、多様な人材からの応募が期待できます。
一方で、掲載できる情報量には限りがあり、企業の魅力を詳細に伝えるのが難しい側面もあります。
また、求人の申し込みや紹介状の受け取りなどで、事業所の窓口へ出向く手間が発生する場合もあります。
転職フェア・採用イベント
転職フェアや合同企業説明会といった採用イベントは、採用意欲の高い多くの求職者と直接コミュニケーションが取れる貴重な場です。
企業の担当者が自社の魅力や事業内容を直接伝えることで、求職者の関心を引きつけ、その場で疑問や不安を解消できます。
これにより、相互理解が深まり、応募へのハードルを下げることが可能です。
Web上の情報だけでは伝わりにくい社風や働く人の雰囲気を肌で感じてもらえるため、ミスマッチの防止にもつながります。
ただし、出展には数十万円から数百万円の費用がかかるほか、ブースの設営準備や当日の運営人員の確保など、相応のコストと工数を要します。
自社に最適な採用チャネルを見つけるための3つのステップ
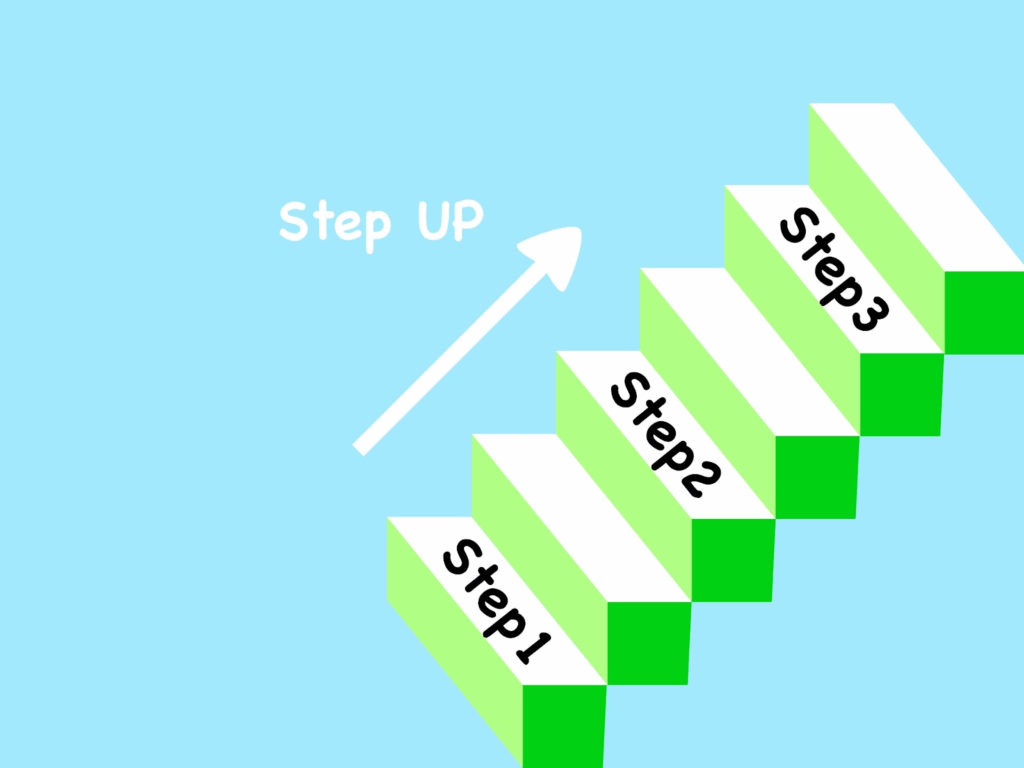
多種多様な採用チャネルの中から、自社の状況に最も合ったものを選ぶためには、計画的なアプローチが不可欠です。
流行っているから、他社が使っているからという理由だけでチャネルを選んでしまうと、期待した成果が得られない可能性があります。
ここでは、自社にとって最適な採用チャネルを戦略的に見つけ出すための、具体的な3つのステップを紹介します。
このプロセスに沿って検討を進めることで、採用活動の精度と効率を高めることができます。
ステップ1:採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする
最適な採用チャネルを選ぶための最初のステップは、どのような人材を求めているのかを具体的に定義することです。
担当業務に必要なスキルや経験といった条件だけでなく、価値観や働き方の志向性、情報収集のスタイルなどを含めた詳細な人物像(ペルソナ)を設定します。
ペルソナが明確になることで、その人物が普段どのようなメディアに接触し、どのような情報に興味を持つのかといった行動パターンを予測しやすくなります。
例えば、最新技術に敏感な若手エンジニアであれば技術ブログや専門性の高いSNS、経営幹部候補であれば人材紹介やヘッドハンティングなど、ターゲットに響きやすいチャネルの仮説を立てることが可能になります。
ステップ2:かけられる採用コストや工数を把握する
採用活動には、求人媒体への掲載料や成功報酬といった直接的な費用だけでなく、採用担当者の人件費や活動時間といった間接的なコストも考慮しなくてはなりません。
それぞれの採用チャネルは、必要となる費用や運用にかかる手間が大きく異なります。
そのため、自社が今回の採用活動にかけられる予算の上限と、担当者が割けるリソースを事前に正確に把握しておくことが重要です。
コストを最優先するならハローワークやリファラル採用が、多少費用をかけてでも業務負担を減らしたいなら人材紹介サービスが有力な選択肢となります。
予算と工数の両面から制約を洗い出すことで、実行可能なチャネルを現実的に絞り込めます。
ステップ3:複数のチャネルを組み合わせて相乗効果を狙う
一つの採用チャネルだけに頼るのではなく、複数のチャネルを戦略的に組み合わせる「採用チャネルミックス」を実践することで、採用活動全体の効果を高められます。
それぞれのチャネルが持つ強みを活かし、弱点を相互に補完し合うことが可能になるからです。
例えば、大手求人サイトで広く認知度を高めながら母集団を形成し、同時にダイレクトリクルーティングで特に会いたい優秀層へ個別にアプローチするといった使い分けが考えられます。
また、SNSで企業の魅力を発信して興味を持ってもらい、より詳細な情報が掲載されたオウンドメディアへ誘導するなど、チャネル同士を連携させることで、候補者の志望度を段階的に高める相乗効果も期待できます。
【採用課題別】おすすめの採用チャネルの選び方

採用活動における課題は、企業によって様々です。
「とにかく応募者が集まらない」「採用コストがかさむ」「内定を出しても辞退されてしまう」など、直面している問題は異なります。
ここでは、企業が抱えがちな代表的な採用課題を取り上げ、それぞれの解決に適した採用チャネルの選び方を解説します。
自社が現在どのような課題に直面しているかを明確にし、それを解決するという視点でチャネルを検討することで、より効果的な一手を見つけ出すことができるはずです。
とにかく多くの応募者を集めたい(母集団形成)
採用活動の初期段階で、まず選択肢となる候補者の数を確保したい、つまり母集団形成を優先したい場合には、広く求職者にアプローチできるチャネルが有効です。
代表的な手法として、知名度の高い大手求人サイトへの広告掲載が挙げられます。
多くの転職希望者の目に触れる機会があるため、短期間で応募者数を増やす効果が期待できます。
また、新卒採用であれば合同企業説明会、中途採用であれば大規模な転職フェアへの出展も、一度に多数の求職者と接点を持てるため母集団形成に適しています。
これらの手法は企業の認知度向上にも貢献しますが、応募者の質にばらつきが出る可能性も考慮し、その後の選考プロセスを工夫する必要があります。
採用にかかるコストをできるだけ抑えたい
採用活動にかけられる予算が限られており、コストを可能な限り抑制したい場合には、無料で利用できる、あるいは低コストで運用できるチャネルを中心に検討します。
その代表格が、無料で求人掲載が可能なハローワークです。
特に地域に根ざした人材の採用には有効な手段となります。
また、社員の人的ネットワークを活用するリファラル採用は、広告費や紹介手数料が一切かからないため、非常にコストパフォーマンスが高い手法です。
初期投資や運用工数はかかりますが、自社の採用サイトやSNSを活用したオウンドメディアリクルーティングも、中長期的に見れば外部への支払いが発生しないため、コストを抑えた採用活動の基盤となります。
採用業務の負担を減らして効率化したい
採用担当者が他の業務と兼任しているなど、リソースが限られている状況で採用業務の負担を軽減したい場合には、外部の専門家のサポートを得られるチャネルが適しています。
人材紹介サービスを利用すれば、エージェントが候補者の選定から面談の日程調整までを代行してくれるため、採用担当者は面接などのコア業務に集中することが可能です。
また、採用代行(RPO)サービスを活用し、ダイレクトリクルーティングにおけるスカウトメールの送信や応募者対応といった定型業務を外部に委託する方法もあります。
これらのサービスは費用が発生しますが、採用活動全体を効率化し、時間的なコストを削減する効果が期待できます。
自社の文化にマッチする人材と出会いたい
採用において、スキルや経験だけでなく、自社の企業文化や価値観とのマッチング(カルチャーフィット)を重視する場合、企業の魅力を深く、多角的に伝えられるチャネルが有効です。
社員インタビューや社内イベントの様子などを通じてリアルな姿を発信できるオウンドメディアリクルーティングは、企業の雰囲気に共感した候補者を集めるのに適しています。
また、社員が会社の文化を直接候補者に伝えるリファラル採用は、入社後のミスマッチが起こりにくい代表的な手法です。
スカウト型のダイレクトリクルーティングで、企業のビジョンやブログ記事に共感を示してくれそうな候補者を探し、個別にアプローチするのも効果的です。
よくあるご質問
Q1.新卒採用と中途採用で、選ぶべきチャネルは変わりますか?
A1.はい、ターゲットに応じて変える必要があります。新卒採用では就職情報サイトや合同説明会、インターンシップが主流です。一方、中途採用では人材紹介や転職サイト、ダイレクトリクルーティングなどが中心になります。それぞれのターゲットが利用する媒体を見極めることが重要です。
Q2.複数の採用チャネルを同時に使うメリットは何ですか?
A2.アプローチできる候補者の層が広がる点と、各チャネルの弱点を補い合える点がメリットです。例えば、求人広告で広く募集しつつ、人材紹介で専門職を探すといった併用が効果的です。これにより、採用機会の最大化を図れます。
Q3.採用チャネルの効果測定はどのように行えばよいですか?
A3.チャネルごとの「応募数」「書類通過率」「内定率」「採用単価」といった指標を記録し、比較分析します。どのチャネルから自社にマッチした応募が来ているか、費用対効果はどうかを定期的に評価し、予算配分を見直すことが大切です。
Q4.地方の中小企業におすすめの採用チャネルはありますか?
A4.地元の人材採用に強いハローワークや、地域に特化した求人情報誌・Web媒体が有効です。また、コストを抑えられるリファラル採用や、地域の大学や専門学校との連携を強化することも効果的な手段となり得ます。
Q5.採用チャネルを見直すタイミングはいつですか?
A5.採用目標を達成できない、応募の質が低い、採用コストが高騰している、といった課題が顕在化したときが見直しのタイミングです。また、事業計画の変更に伴い、求める人物像が変わった際にも、それに合わせてチャネル戦略を再構築する必要があります。
まとめ
採用チャネルとは、企業が求職者と出会うための多様な経路や手法を指します。
求人広告や人材紹介といった従来の手法から、ダイレクトリクルーティングやSNS採用などの新しいアプローチまで、それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットが存在します。
採用を成功させるためには、まず自社が求める人物像と、かけられるコストや工数を明確化することが不可欠です。
その上で、単一のチャネルに固執するのではなく、自社の採用課題や目的に応じて複数のチャネルを戦略的に組み合わせ、継続的に効果を測定・改善していくプロセスが求められます。
せっかくの採用チャネルも、伝える内容が弱ければ成果につながりません。
Piicは採用ピッチ資料・採用サイト・採用LPを通じて、候補者に響く採用クリエイティブを制作。
「選ばれる企業」になる採用活動を一緒に始めませんか?








