
採用活動において、応募者数や内定率といったデータを感覚的に把握している人事担当者は多いかもしれません。
しかし、それらのデータを体系的に分析することで、採用活動における課題を客観的に可視化し、具体的な改善策を導き出すことが可能です。
本記事では、採用データ分析の基本的な考え方から、収集すべきデータの種類、具体的な分析手法、そして分析結果を活かした改善アクションまでを詳しく解説します。
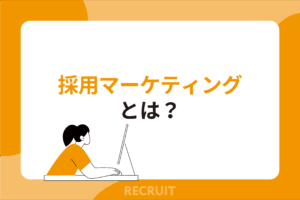
Index
-
そもそも採用データ分析とは?人事活動における重要性を解説
-
採用分析で収集・活用すべき主なデータ
-
応募者数や採用決定数など人数に関するデータ
-
求人広告費や紹介手数料などコストに関するデータ
-
応募から入社までにかかる期間など時間に関するデータ
-
【課題別】採用データ分析の具体的な手法
-
採用チャネルごとの費用対効果を可視化する
-
各選考プロセスの通過率(歩留まり率)を算出する
-
内定辞退や選考辞退の原因を特定する
-
分析結果を活かした採用活動の改善アクション例
-
最適な求人媒体や採用手法を選択する
-
候補者の離脱を防ぐために選考フローを見直す
-
入社後の定着率を高めるための施策を検討する
-
採用データ分析を成功に導くための2つのポイント
-
何のために分析するのか目的を明確にする
-
定量データと定性データの両面から分析する
-
よくあるご質問
-
Q1.データ分析には専門的な知識やツールが必要ですか?
-
Q2.どのくらいの期間のデータを集めればよいですか?
-
Q3.データの収集や管理で気をつけることは何ですか?
-
Q4.小さな会社でも採用データ分析は有効ですか?
-
Q5.分析結果がうまく採用活動に活かせません。
-
まとめ
そもそも採用データ分析とは?人事活動における重要性を解説

採用データ分析とは、応募から入社までの一連の採用活動で得られるさまざまなデータを収集・分析し、採用における課題の特定や意思決定に役立てる取り組みを指します。
従来、採用活動は担当者の経験や勘に頼る部分が大きい領域でしたが、データ分析を用いることで、客観的な根拠に基づいた戦略的な活動が可能になります。
これにより、採用プロセスの効率化、採用コストの最適化、そしてミスマッチの防止といった効果が期待でき、人事活動全体の質を向上させます。
採用分析で収集・活用すべき主なデータ

採用データ分析を始めるにあたり、どのようなデータを収集すべきかを把握することが重要です。
データは大きく「人数」「コスト」「時間」の3つのカテゴリに分類できます。
これらのデータを網羅的に収集し、それぞれの項目を掛け合わせて分析することで、採用活動全体を多角的に評価できるようになります。
まずは自社の採用活動において、どの項目が取得可能かを確認するところから始めましょう。
応募者数や採用決定数など人数に関するデータ
採用活動の成果を測る最も基本的な指標が、人数に関するデータです。
具体的には、応募者数、書類選考通過者数、各面接の通過者数、内定者数、そして最終的な採用決定数などが挙げられます。
これらの数値を時系列で追うことで、母集団形成が順調に進んでいるか、またどの選考段階で候補者が離脱しているのかを把握できます。
特に新卒採用と中途採用では、母集団の特性や選考プロセスが異なるため、それぞれ分けてデータを管理し、傾向の違いを分析することが求められます。
求人広告費や紹介手数料などコストに関するデータ
採用活動には多くのコストが発生します。
求人サイトへの広告掲載費、人材紹介会社への成功報酬、合同説明会などのイベント出展費用、採用管理システムの利用料、さらには採用担当者の人件費まで、すべてが採用コストに含まれます。
これらのデータを正確に把握することで、採用者一人あたりにかかった費用である「採用単価」を算出可能です。
チャネルごとの費用対効果を比較検討し、限られた予算をどこに投下すべきか、戦略的な判断を下すための基礎情報となります。
応募から入社までにかかる期間など時間に関するデータ
候補者の応募から入社までに要する期間も、重要な分析項目です。
具体的には、求人公開から応募が集まるまでの期間、応募から書類選考結果を通知するまでの日数、各面接間の日数、内定通知から入社承諾までの期間などが計測対象になります。
選考プロセスが長引くと、優秀な候補者が他社に流出するリスクが高まるだけでなく、候補者の入社意欲を削ぐ原因にもなりかねません。
各プロセスの所要時間を計測し、ボトルネックとなっている箇所を特定・改善することで、候補者体験の向上と採用機会の損失防止に繋がります。
【課題別】採用データ分析の具体的な手法

データを収集しただけでは意味がなく、それをどう分析するかが重要です。
ここでは、企業が抱えがちな採用課題別に、具体的なデータ分析の手法を紹介します。
自社の課題が「コストの最適化」「選考プロセスの効率化」「内定辞退の多さ」のどれに当てはまるかを考え、適切な手法を用いて現状を可視化することから始めましょう。
これにより、感覚的な問題意識が、具体的な数値に基づいた課題へと変わります。
採用チャネルごとの費用対効果を可視化する
採用コストの最適化を目指す場合、採用チャネルごとの費用対効果の分析が有効です。
まず、求人媒体A、人材紹介B、リファラル採用Cといった各チャネルに投下した総コストを算出します。
次に、それぞれのチャネル経由で何人採用できたかを明らかにします。
そして、「総コスト÷採用人数」を計算することで、チャネルごとの「採用単価」が算出されます。
この数値を比較すれば、どのチャネルが最も効率的に採用できているかが一目瞭然となり、今後の予算配分を見直す際の客観的な判断材料を得られます。
各選考プロセスの通過率(歩留まり率)を算出する
選考プロセスのどこに問題があるかを特定するには、各段階の通過率(歩留まり率)を算出する手法が役立ちます。
「書類選考通過者数÷応募者数」「一次面接通過者数÷書類選考通過者数」のように、次のステップに進んだ人数を前のステップの人数で割ることで計算できます。
これらの計算はエクセルなどの表計算ソフトでも簡単に行えます。
特定の段階で通過率が著しく低い場合、そこに何らかの課題が潜んでいる可能性が高いと判断できます。
例えば、書類選考の基準が厳しすぎる、あるいは特定の面接官の評価が辛すぎるといった仮説を立てられます。
内定辞退や選考辞退の原因を特定する
内定辞退や選考途中の辞退が多い場合は、その原因を特定する分析が必要です。
辞退した候補者に対して、可能な範囲でアンケートや電話ヒアリングを実施し、辞退理由を収集します。
収集した回答は「提示条件が他社より低かった」「面接官の印象が悪かった」「選考プロセスが長かった」などのカテゴリに分類して集計します。
この手法によって、最も多い辞退理由を突き止め、自社の採用活動における弱みを客観的に把握することが可能になります。
これにより、待遇の見直しや面接官トレーニングといった具体的な改善策の立案に繋がります。
分析結果を活かした採用活動の改善アクション例

採用データ分析の最終的な目的は、現状を把握するだけでなく、それを基に具体的な改善アクションを起こし、採用活動の成果を高めることです。
分析によって明らかになった課題に対して、どのような対策を講じることができるのか、ここでは具体的な改善アクションの例を紹介します。
データという客観的な根拠があるため、関係者への説明や協力も得やすくなり、スムーズな施策実行が期待できるでしょう。
最適な求人媒体や採用手法を選択する
採用チャネルごとの費用対効果分析の結果、採用単価が低く、かつ入社後の活躍度も高い優秀な人材が採用できているチャネルが特定できれば、そのチャネルへの予算配分を増やすという意思決定ができます。
逆に、多額の費用をかけているにもかかわらず、応募が少ない、あるいは採用に至らないチャネルは、広告の掲載内容を見直すか、場合によっては利用を停止するという判断も必要です。
データに基づいてリソースの選択と集中を行うことで、採用活動全体の効率を大幅に向上させることが可能です。
候補者の離脱を防ぐために選考フローを見直す
歩留まり率の分析によって、特定の選考段階で候補者の離脱が多いことが判明した場合、そのプロセスの見直しが急務です。
例えば、一次面接後の辞退が多ければ、面接官のスキルにばらつきがある可能性が考えられるため、面接官トレーニングを実施したり、評価基準を統一したりする対策が考えられます。
また、選考期間が長引いている場合は、人事部門が中心となって面接日程の調整方法を効率化する、オンライン面接を導入するなど、プロセス自体を短縮する工夫が求められます。
入社後の定着率を高めるための施策を検討する
採用は入社がゴールではありません。
入社した社員が定着し、活躍して初めて成功したと言えます。
そのためには、採用時のデータと入社後の人事データ(評価、離職率など)を連携させた分析が有効です。
例えば、特定の求人媒体経由で入社した社員の早期離職率が高いといった傾向が見つかれば、その媒体のターゲット層と自社が求める人物像に乖離がある可能性が示唆されます。
こうした分析を通じて採用活動の精度を高め、ミスマッチを減らすことで、長期的な組織力の強化に繋がるのです。
採用データ分析を成功に導くための2つのポイント

採用データ分析を導入したものの、うまく活用できていないというケースも少なくありません。
分析を成功させ、実際の採用活動の改善に繋げるためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。
ここでは、特に意識すべき2つのポイントについて解説します。
これらを念頭に置いて取り組むことで、データ分析の価値を最大限に引き出すことができるでしょう。
何のために分析するのか目的を明確にする
データ分析を始める前に、必ず「何のために分析するのか」という目的を明確に設定することが不可欠です。
「採用コストを前年比で15%削減する」「エンジニア職の内定承諾率を50%まで引き上げる」といったように、具体的かつ測定可能な目標を立てます。
目的がはっきりしていれば、収集すべきデータや見るべき指標、用いるべき分析手法が自ずと定まります。
目的が曖昧なまま手当たり次第にデータを眺めても、有益な知見を得ることは困難であり、データ分析そのものが目的化してしまうことを避けなければなりません。
定量データと定性データの両面から分析する
応募者数やコストといった数値で表される「定量データ」は、採用活動の全体像を客観的に把握するために重要です。
しかし、なぜそのような数値になっているのかという背景や理由を知るためには、面接での印象や辞退者アンケートの自由記述欄といった「定性データ」も併せて分析することが欠かせません。
「内定辞退率が30%」という定量データだけでは何も分かりませんが、辞退理由の定性データから「面接官の対応」に原因があると分かれば、具体的な改善策を講じられます。
データ分析では、この両輪を回していく視点が求められます。
よくあるご質問
Q1.データ分析には専門的な知識やツールが必要ですか?
A1.必ずしも専門知識や高価なツールは必要ありません。応募者数や通過率の管理といった基本的な分析であれば、多くの企業で導入されているエクセルなどの表計算ソフトで十分対応可能です。まずは手元にあるデータを使って、簡単な集計やグラフ化から始めてみることをお勧めします。
Q2.どのくらいの期間のデータを集めればよいですか?
A2.採用市場の変動や季節性を考慮するため、少なくとも1年分のデータを蓄積することが望ましいです。可能であれば、過去3年分程度のデータがあると、より精度の高い分析や将来予測が可能になります。継続的にデータを蓄積していくことが重要です。
Q3.データの収集や管理で気をつけることは何ですか?
A3.まず、候補者の氏名や連絡先などの個人情報の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。また、データの精度を保つために、部署や担当者によって入力形式が異ならないよう、事前にルールを統一しておくことが重要です。「株式会社」と「(株)」のような表記の揺れも、正確な集計を妨げる原因となります。
Q4.小さな会社でも採用データ分析は有効ですか?
A4.はい、有効です。むしろ、採用にかけられる予算や人員が限られている中小企業こそ、データ分析によって採用活動を効率化し、費用対効果を最大化させるメリットは大きいと言えます。少ないリソースを最も効果的なチャネルや施策に集中させるために、データに基づいた判断が役立ちます。
Q5.分析結果がうまく採用活動に活かせません。
A5.分析結果を現場の活動に活かすためには、分析の目的を関係者間で事前に共有しておくことが大切です。また、分析から得られた課題や改善案を、面接官などの現場担当者に分かりやすく伝え、当事者意識を持ってもらうことも重要です。分析チームと現場が連携することで、データに基づいた改善サイクルが回り始めます。
まとめ
採用データ分析は、従来の経験や勘に頼った採用から脱却し、客観的な事実に基づいて戦略的な意思決定を行うための強力な手段です。
応募者数やコスト、選考期間といったデータを収集・分析することで、採用活動における課題を可視化し、具体的な改善策を導き出すことができます。
最初から完璧を目指す必要はなく、まずはエクセルなどで管理できる範囲からスモールスタートし、継続的に取り組むことが成功の鍵です。
データ分析を活用して採用活動の質と効率を高めることは、人事部門が企業の成長に貢献する上で非常に重要な役割を担います。
採用データから見えてきた課題や傾向は、そのままにせず採用クリエイティブへ落とし込むことで成果につながります。
Piicでは、応募数・承諾率・定着率といった数値をもとに、求人票や採用サイト、採用ピッチ資料の表現を最適化。数字を“伝わるデザイン”へ変換することで、より精度の高い採用活動を実現します。








