
採用ペルソナとは、自社が求める理想の人物像を具体的に描いたものです。
効果的な採用活動には、このペルソナ設定が欠かせません。
この記事では、採用におけるペルソナの作り方を5つのステップで解説します。
具体的な項目例も紹介するので、自社の採用活動に活かすためのヒントが見つかります。
採用のミスマッチを防ぎ、効率的な採用戦略を立てるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
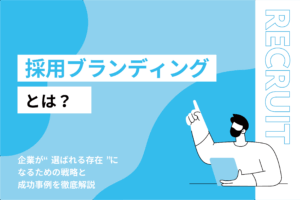
Index
-
採用ペルソナとは、自社が求める理想の人物像を具体化したもの
-
採用ペルソナと採用ターゲットは何が違う?
-
採用活動でペルソナ設定が重要視される理由
-
採用ペルソナを設定する3つのメリット
-
採用チーム内で求める人材の認識を統一できる
-
採用のミスマッチを減らし定着率を向上させる
-
採用活動の方向性が明確になり効率化が進む
-
【5ステップ】採用ペルソナの具体的な作り方
-
Step1. 経営層や現場社員へのヒアリングで必要な人材を定義する
-
Step2. 収集した情報から具体的な人物像の要素を洗い出す
-
Step3. テンプレートを活用してペルソナシートを作成する
-
Step4. 作成したペルソナを関係者と共有しフィードバックを得る
-
Step5. 採用市場の状況を考慮してペルソナを最終調整する
-
採用ペルソナに盛り込むべき具体的な項目例
-
基本プロフィール(年齢・学歴・居住地など)
-
スキル・職務経歴(保有資格・実績など)
-
価値観・志向性(仕事観・キャリアプランなど)
-
情報収集の方法(利用するSNSやWebサイトなど)
-
採用ペルソナ設計で失敗しないための4つの注意点
-
理想を詰め込みすぎて非現実的な人物像にしない
-
一度作ったら終わりではなく定期的に見直す
-
1つの職種で複数のペルソナを用意することも検討する
-
ペルソナ設定の目的を社内全体で共有する
-
作成した採用ペルソナを活かす具体的な活用シーン
-
ペルソナに響く求人票やスカウト文を作成する
-
ペルソナが見ている可能性が高い採用媒体を選定する
-
面接での質問内容や評価基準を統一する
-
よくある質問
-
Q1.ペルソナは写真や名前も決めた方がいいですか?
-
Q2.新卒採用でもペルソナは有効ですか?
-
Q3.ペルソナを作る時間がないのですが、どうすればいいですか?
-
Q4.ペルソナに合う人が全く見つからない場合はどうすればいいですか?
-
Q5.ペルソナはいくつくらい作るべきですか?
-
まとめ
採用ペルソナとは、自社が求める理想の人物像を具体化したもの

採用ペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像を、具体的な一人の人間かのように詳細に設定したものです。
その意味は、単にスキルや経験といった採用要件を並べるだけでなく、価値観やライフスタイル、性格までをリアルに描き出す点にあります。
この詳細な人物像があることで、採用チーム全体で共通認識を持ち、一貫性のある採用活動を展開できるようになります。
採用ペルソナと採用ターゲットは何が違う?
採用ペルソナと採用ターゲットは混同されがちですが、その具体性に大きな違いがあります。
採用ターゲットは、「20代の営業経験者」「首都圏在住のエンジニア」といったように、特定の条件で括られた集団を指します。
これに対して採用ペルソナは、その集団の中から一人の架空の人物を具体的に設定するものです。氏名や年齢、学歴、価値観、休日の過ごし方まで詳細に描き出すことで、その人物の思考や行動をより深く理解できます。
ターゲット設定だけでは見えてこない、個人のニーズや動機に寄り添ったアプローチが可能になる点が、ペルソナ設定の大きな特徴です。
採用活動でペルソナ設定が重要視される理由
近年の採用活動における環境は大きく変化しており、候補者の価値観も多様化しています。
このような状況で効果的な採用活動を行うためには、企業側が求める人物像を明確にするペルソナ設定が非常に重要です。
ペルソナを設定することで、自社が本当に必要としている人材の具体的なイメージが固まり、採用チーム内での認識のズレを防げます。
また、その人物像に響くメッセージは何か、どの媒体でアプローチすべきかといった戦略も立てやすくなります。
漠然とした採用活動から脱却し、一貫性のある効果的なアプローチを実現するために、ペルソナ設定は不可欠なプロセスとなっています。
採用ペルソナを設定する3つのメリット

採用ペルソナを設定することは、採用活動全体に多くのメリットをもたらします。
求める人物像が明確になることで、採用に関わる全てのメンバーが同じ方向を向いて活動できるようになります。
さらに、候補者とのミスマッチを減らし、入社後の定着率向上にも寄与するでしょう。
ここでは、採用ペルソナを設定することで得られる具体的な3つのメリットを解説し、効果的な採用戦略の立案にどう繋がるのかを明らかにします。
採用チーム内で求める人材の認識を統一できる
採用活動には、人事担当者だけでなく現場の責任者や経営層など、多くの人が関わります。
ペルソナが設定されていない場合、「コミュニケーション能力が高い人」「主体性のある人」といった抽象的な言葉の解釈が人によって異なり、評価基準にバラつきが生じる原因となります。
採用ペルソナを作成し、具体的な人物像を共有することで、チーム全員が「自社が求める人材」について同じイメージを持つことが可能です。
これにより、書類選考や面接での評価基準が統一され、判断のブレが少なくなります。
結果として、一貫性のある選考プロセスを維持でき、採用の精度向上に繋がるのです。
採用のミスマッチを減らし定着率を向上させる
採用におけるミスマッチは、スキルや経験の不足だけでなく、企業の文化や価値観との不一致によっても発生します。
採用ペルソナでは、能力面だけでなく、仕事に対する考え方やキャリアプラン、ライフスタイルといった内面的な要素まで具体的に設定します。
これにより、自社のカルチャーに本当にフィットする人物像が明確になり、選考過程で候補者の価値観を深く見極めることが可能になります。
自社の方針や働き方に共感してくれる人材を採用できる可能性が高まるため、入社後のミスマッチが減り、早期離職の防止と定着率の向上に貢献します。
採用活動の方向性が明確になり効率化が進む
採用ペルソナを設定すると、その人物がどのような情報を求めているか、普段どのような媒体に接触しているかといった行動パターンを予測しやすくなります。
例えば、特定の技術情報サイトを頻繁に閲覧するエンジニアのペルソナであれば、そのサイトに求人広告を出すといった具体的な施策が考えられます。
また、求人票のキャッチコピーやスカウトメールの文面も、ペルソナの心に響くような言葉を選ぶことが可能です。
ターゲットが明確になることで、採用活動の方向性が定まり、効果の薄い施策に時間やコストを費やす必要がなくなります。
結果的に、採用活動全体の効率化が進むのです。
【5ステップ】採用ペルソナの具体的な作り方

採用ペルソナの作り方には、効果的な作成手順が存在します。
ここでは、誰でも実践できる具体的な決め方を5つのステップに分けて解説します。
Step1. 経営層や現場社員へのヒアリングで必要な人材を定義する
Step2. 収集した情報から具体的な人物像の要素を洗い出す
Step3. テンプレートを活用してペルソナシートを作成する
Step4. 作成したペルソナを関係者と共有しフィードバックを得る
Step5. 採用市場の状況を考慮してペルソナを最終調整する
このフレームワークは、中途採用はもちろん新卒採用においても応用が可能です。
情報を収集し、具体的な人物像へと落とし込み、チームで共有するまでの一連の流れを理解することで、自社の採用活動に最適なペルソナを作成できるようになります。
まずはこのステップに沿って進めてみましょう。
Step1. 経営層や現場社員へのヒアリングで必要な人材を定義する
ペルソナ作成の第一歩は、社内関係者へのヒアリングから始まります。
まずは経営層に、事業戦略や今後のビジョンを踏まえ、どのような人材が必要かをヒアリングします。
次に、配属予定の部署で働く現場社員に、業務上必要なスキルや知識、チームで活躍できる人物の特性について具体的に聞きましょう。
特に、現役で高いパフォーマンスを発揮している社員(ハイパフォーマー)の特徴や、逆に早期離職してしまった人の傾向などを分析することで、求める人物像と避けるべき人物像の両面からヒントが得られます。
ここで集めた客観的な情報が、精度の高いペルソナを作るための土台となります。
Step2. 収集した情報から具体的な人物像の要素を洗い出す
Step1で集めたヒアリング内容をもとに、ペルソナを構成する具体的な要素を洗い出します。
この時点では、一人の人物像にまとめるのではなく、必要な情報をキーワードや箇条書きでリストアップしていくのが効率的です。
例えば、「スキル・経験」「性格・価値観」「働き方への希望」「キャリアプラン」といったカテゴリーに分けて整理するとよいでしょう。
「〇〇のツール使用経験3年以上」「チームの意見をまとめるのが得意」「新しい技術の学習に意欲的」など、具体的で客観的な事実をできるだけ多く書き出します。
この作業を通じて、求める人材に共通する要素が明確になり、後のペルソナシート作成がスムーズに進みます。
Step3. テンプレートを活用してペルソナシートを作成する
洗い出した要素を、具体的な一人の人物像としてまとめ、ペルソナシートに落とし込んでいきます。この作業には、あらかじめ項目が用意されたテンプレートを活用すると便利です。
氏名、年齢、学歴といった基本情報から、職務経歴、スキル、価値観、さらにはプライベートの過ごし方まで、各項目を埋めていきます。単に情報を羅列するのではなく、「なぜそのスキルを身につけたのか」「将来どのようなキャリアを築きたいと考えているのか」といった背景やストーリーを想像しながら記述することで、よりリアルで人間味のあるペルソナが完成します。
このシートが、今後の採用活動の羅針盤となるのです。このようなテンプレはWeb上でも入手できます。
Step4. 作成したペルソナを関係者と共有しフィードバックを得る
作成したペルソナシートは、完成したら必ず関係者と共有し、フィードバックをもらうプロセスを踏みます。
Step1でヒアリングに協力してくれた経営層や現場社員にシートを見せ、「私たちが求めているのは、まさにこういう人物です」という合意を得ることが目的です。
この共有とすり合わせを行うことで、「現場の求めるスキルが不足している」「経営層のビジョンと少し方向性が違う」といった認識のズレを修正できます。
担当者だけで完結させず、チーム全体でペルソナをブラッシュアップしていくことで、より精度の高い人物像が固まります。誰が最新版を管理するのかも決めておくと良いでしょう。
Step5. 採用市場の状況を考慮してペルソナを最終調整する
社内で合意形成ができたペルソナが、実際の採用市場に存在し、採用可能な人材であるかを確認する最終調整のステップです。
あまりに理想を高く設定しすぎると、該当する候補者がほとんどいない、あるいは競合との激しい獲得競争に巻き込まれる可能性があります。
転職サイトで似たような経歴の人物を検索してみたり、人材紹介会社に相談して市場感を確認したりするのも有効な手段です。
市場の状況を踏まえ、必要であればスキルの優先順位を見直したり、必須条件と歓迎条件を分けたりするなどの調整を行います。
社内の理想と市場の現実のバランスを取ることが、成功するペルソナ設定の鍵となります。
採用ペルソナに盛り込むべき具体的な項目例

採用ペルソナを作成する際、どのような項目を設定すればよいか迷うかもしれません。
ここでは、ペルソナシートに盛り込むべき具体的な項目例を紹介します。
基本情報からスキル、価値観、行動特性まで、多角的な視点から人物像を掘り下げるための具体例を挙げていきます。
・基本プロフィール(年齢・学歴・居住地など)
・スキル・職務経歴(保有資格・実績など)
・価値観・志向性(仕事観・キャリアプランなど)
・情報収集の方法(利用するSNSやWebサイトなど)
これらの項目を参考に、自社の採用したい職種やポジションに合わせてカスタマイズしてみてください。
基本プロフィール(年齢・学歴・居住地など)
基本プロフィールは、ペルソナの人物像にリアリティを与えるための土台となる項目です。
氏名、年齢、性別といった基本情報に加え、最終学歴や専攻、現在住んでいるエリア、家族構成などを設定します。
例えば、「都心から電車で40分圏内に、パートナーと二人暮らし」といった具体的な設定をすることで、その人物のライフスタイルや通勤に対する考え方などを想像しやすくなります。
これらの情報は、福利厚生や働き方の魅力を伝える際の参考にもなります。
ただし、これらの項目で応募者を差別することは目的ではなく、あくまで人物像を具体化するための設定である点を理解しておくことが重要です。
スキル・職務経歴(保有資格・実績など)
スキルや職務経歴は、特に中途採用のペルソナにおいて中心となる項目です。
これまでどのような業界・企業で、どのような業務に携わってきたのか、具体的な職務内容や役職、実績を詳細に記述します。
例えば、エンジニアであれば使用可能なプログラミング言語や開発環境、フレームワークの経験などが重要な要素です。
また、保有資格や語学力、マネジメント経験の有無なども明確にします。
これまでのキャリアを通じて何を成し遂げてきたのか、そして次にどのような挑戦をしたいと考えているのかをストーリーとして描くことで、自社が提供できるキャリアパスとの接続点が見えてきます。
価値観・志向性(仕事観・キャリアプランなど)
ペルソナの人物像を深く理解し、カルチャーフィットを見極めるためには、価値観や志向性の設定が欠かせません。
仕事を通じて何を実現したいのか、どのような働き方を理想としているのかといった仕事観を具体化します。例えば、「チームで協力して大きな目標を達成することにやりがいを感じる」「裁量権を持って新しいことに挑戦したい」などです。
また、5年後、10年後にどのようなキャリアを築いていたいかというキャリアプランや、性格的な特徴、強み・弱みなども設定します。
これらの内面的な要素を明確にすることで、候補者の動機や企業選びの軸を理解し、より的確なアプローチが可能になります。
情報収集の方法(利用するSNSやWebサイトなど)
設定したペルソナに自社の求人情報を届けるためには、その人物が日常的にどのような媒体で情報収集しているかを知る必要があります。
例えば、キャリアに関する情報収集のために特定の転職サイトやビジネス系SNSを頻繁にチェックしているかもしれません。あるいは、技術系の最新情報を得るために専門的なブログやニュースサイトを購読している可能性もあります。
利用するSNSの種類(X,Facebook,LinkedInなど)や、フォローしているインフルエンサー、参加しているオンラインコミュニティなども具体的に設定します。
この情報があることで、どの採用媒体に広告を出すべきか、どのサイトでスカウト活動を行うべきかといった、具体的な採用広報戦略を立てるのに役立ちます。
採用ペルソナ設計で失敗しないための4つの注意点

採用ペルソナは効果的なツールですが、設計のプロセスで注意すべき点がいくつかあります。
良かれと思って作成したペルソナが、かえって採用活動の妨げになってしまうケースも少なくありません。
ここでは、採用ペルソナ設計で失敗しないために押さえておきたい4つの注意点を解説します。
これらのポイントを意識することで、より現実的で実用的なペルソナを作成し、採用活動の成功確率を高めることができます。
理想を詰め込みすぎて非現実的な人物像にしない
ペルソナを作成する際、社内の様々な部署からの要望をすべて盛り込もうとして、結果的に非現実的な「スーパーマン」のような人物像を作り上げてしまうことがあります。
高いスキルと豊富な経験を持ち、人格的にも優れ、なおかつ自社のカルチャーに完璧にフィットする、といった理想の塊のようなペルソナは、実際の採用市場にはほとんど存在しません。
このような人物像を追い求めても、応募者が現れず採用活動が停滞するだけです。
ペルソナ設計においては、絶対に譲れない必須条件と、あれば望ましい歓迎条件を分けて考えることが重要です。
完璧を求めすぎず、採用可能な範囲での理想像を描くという視点を忘れないようにしましょう。
一度作ったら終わりではなく定期的に見直す
採用ペルソナは、一度作成したら固定化されるものではありません。
企業の事業フェーズや戦略の変化、採用市場の動向、技術の進歩など、外部環境や内部環境は常に変化しています。
例えば、半年前には最適だったペルソナが、新しい事業の立ち上げによって現状と合わなくなることも考えられます。
また、実際に採用活動を進める中で、「設定したペルソナに合致する候補者からの応募が全くない」といった事態に直面することもあります。
このような状況に応じて、ペルソナの内容を定期的に見直し、アップデートしていくことが不可欠です。
採用活動の成果を振り返りながら、柔軟にペルソナを改善していく姿勢が求められます。
1つの職種で複数のペルソナを用意することも検討する
採用したいポジションは一つでも、活躍できる人材のタイプが複数考えられる場合があります。
例えば、同じ「営業職」を募集する場合でも、未開拓の市場を切り拓く新規開拓のエースを求めるのか、既存の大口顧客との関係を深めるルートセールスのプロを求めるのかで、必要なスキルや志向性は大きく異なります。
このようなケースでは、無理に一つのペルソナにまとめるのではなく、役割に応じた複数のペルソナを用意することが有効です。
これにより、それぞれのタイプの人材に響くアプローチを使い分けることができ、より多角的な視点から優秀な人材を獲得できる可能性が広がります。
採用の目的に応じて、柔軟にペルソナの数を検討しましょう。
ペルソナ設定の目的を社内全体で共有する
採用ペルソナを作成しても、その目的や活用方法が社内で正しく理解されていなければ、効果を最大限に発揮することはできません。
「なぜペルソナを設定するのか」「このペルソナをどのように採用活動に活かしていくのか」という目的意識を、人事担当者だけでなく、面接を担当する現場社員や経営層まで含めて共有することが重要です。
目的が共有されていないと、ペルソナが単なる書類として放置されたり、「この候補者はペルソナと100%一致しないから不採用」といった硬直的な判断基準として誤用されたりする可能性があります。
ペルソナはあくまで採用の精度を高めるためのツールであることを全員で理解し、共通認識を持つことが成功の鍵です。
作成した採用ペルソナを活かす具体的な活用シーン

採用ペルソナは、作成して終わりではなく、実際の採用活動の様々な場面で活用してこそ意味があります。
採用活動は、自社の魅力を候補者に伝え、応募へと導く一種のマーケティング活動です。ペルソナという具体的な顧客像があることで、より効果的なアプローチが可能になります。
ここでは、作成したペルソナをどのように活かしていくのか、具体的な活用シーンを3つ紹介します。これらのシーンでペルソナを意識することで、採用活動の質は大きく向上するでしょう。
ペルソナに響く求人票やスカウト文を作成する
求人票やスカウトメールは、候補者が最初に企業と接点を持つ重要なツールです。採用ペルソナが設定されていれば、その人物の価値観や興味関心に合わせて、メッセージの内容を最適化できます。
例えば、新しい技術の習得に意欲的なエンジニアのペルソナであれば、「最新の開発環境でスキルアップできる」といった点を強調します。また、ワークライフバランスを重視するペルソナには、具体的な残業時間やリモートワーク制度について詳しく記載するといった工夫が可能です。
誰にでも当てはまるような一般的な文面ではなく、ペルソナという「たった一人」に向けて語りかけるように文章を作成することで、応募意欲を格段に高めることができます。
ペルソナが見ている可能性が高い採用媒体を選定する
世の中には数多くの採用媒体が存在しますが、やみくもに利用してもコストと時間が増えるだけです。
採用ペルソナで設定した「情報収集の方法」が、媒体選定の大きなヒントになります。
例えば、ペルソナが特定の業界の専門サイトを頻繁に閲覧しているのであれば、そのサイトに求人広告を掲載するのが効果的です。
また、ビジネスSNSの利用が活発なペルソナであれば、SNS広告やダイレクトスカウトが有効な手段となります。
ペルソナの行動を起点に媒体を選定することで、自社が求める人材に効率的にアプローチでき、採用コストの最適化にも繋がります。
候補者がいない場所に広告を出しても意味がない、という基本に立ち返ることが重要です。
面接での質問内容や評価基準を統一する
面接は、候補者が自社にマッチするかを判断する重要な場です。採用ペルソナは、面接官が候補者を評価する際の基準となります。
ペルソナで設定した価値観や志向性を確認するために、「仕事で困難に直面した時、どのように乗り越えましたか?」といった具体的な質問を事前に用意しておくことができます。これにより、面接官の主観や経験だけに頼った質問や評価を減らし、客観的で一貫性のある選考が実現します。
全ての面接官がペルソナという共通の物差しを持つことで、評価のブレがなくなり、自社が本当に求める人材を的確に見極めることができるようになります。
よくある質問
Q1.ペルソナは写真や名前も決めた方がいいですか?
A1.はい、決めることを推奨します。顔写真(フリー素材など)や具体的な名前を設定することで、人物像がより鮮明になり、チーム内での共通認識が深まります。架空の人物ではありますが、実在する一人の人間として扱うことが、ペルソナを効果的に活用するコツです。
Q2.新卒採用でもペルソナは有効ですか?
A2.はい、非常に有効です。職務経歴がない分、価値観やポテンシャル、学習意欲、キャリアへの考え方などを中心にペルソナを設定します。どのような学生生活を送り、どんなことに興味を持っているかを具体化することで、自社のカルチャーに合う学生を見つけやすくなります。
Q3.ペルソナを作る時間がないのですが、どうすればいいですか?
A3.全ての項目を完璧に埋めようとせず、まずは重要な項目(求めるスキル、価値観など)から簡易的に作成することから始めるのがおすすめです。現場のキーパーソン1〜2名への短時間ヒアリングだけでも、多くのヒントが得られます。時間をかけて完璧なものを作るより、まずは作って活用し、改善していくことが重要です。
Q4.ペルソナに合う人が全く見つからない場合はどうすればいいですか?
A4.まずは設定したペルソナが非現実的でないかを見直しましょう。特に必須条件が厳しすぎる可能性があります。条件を緩和したり、必須と歓迎に分けたりする調整が必要です。また、アプローチしている採用媒体がペルソナと合っていない可能性もあるため、媒体の見直しも検討します。
Q5.ペルソナはいくつくらい作るべきですか?
A5.採用する職種やポジションの数によりますが、まずは1つのポジションにつき1つのペルソナを作成するのが基本です。ただし、同じ職種でも求める役割が明確に異なる場合は、複数作成することも有効です。作りすぎると管理が煩雑になるため、多くても1職種あたり2〜3パターンに留めるのが現実的です。
まとめ
採用ペルソナとは、自社が求める理想の人物像を具体的に設定したものであり、採用活動の精度と効率を高めるためのフレームワークです。
ペルソナを設定することで、採用チーム内での認識が統一され、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。
作成にあたっては、社内ヒアリングから情報収集を始め、具体的な人物像へと落とし込み、関係者と共有して調整するという5つのステップを踏むのが効果的です。
完成したペルソナは、求人票の作成、採用媒体の選定、面接の評価基準など、採用プロセスのあらゆる場面で活用できます。
事業環境や市場の変化に合わせて定期的に見直しを行い、常に最適な状態で運用することが求められます。
また、明確なペルソナを基盤にすることで、採用ピッチ資料や採用サイトといった 採用クリエイティブの設計にも一貫性が生まれ、候補者に伝わる力が強化されます。
Piicでは、ペルソナ設計を踏まえた採用ツールの制作を通じて、より効果的な採用活動をサポートしています。








